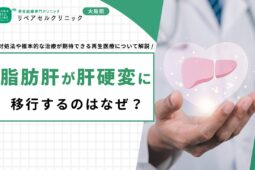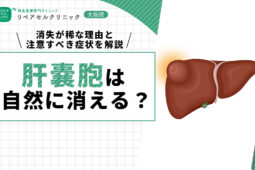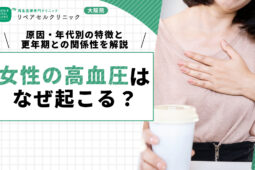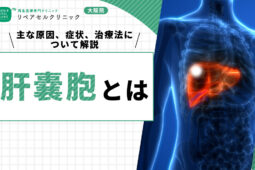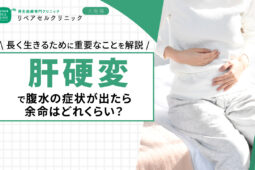- 再生治療
- 肝疾患
肝臓が痛覚を感じないのはなぜ?その理由と考えられる病気も徹底解説

「肝臓は痛みを感じない」と聞いたことはありませんか?
実際、肝臓そのものには痛覚神経がほとんど存在しないため、病気が進行しても自覚症状が乏しく、沈黙の臓器とも呼ばれます。
また、肝臓には痛覚がないため、病気の進行を見逃しやすい臓器です。
本記事では、肝臓の痛覚を感じない理由を詳しく解説します。
自覚症状がないからといって安心できないのが肝臓の病気です。
健診で肝機能の数値に異常があった方や、肝臓の不調が気になる方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
肝臓の痛覚を感じない理由|知覚神経が表面にしかなく沈黙の臓器と呼ばれている
肝臓は痛覚神経がほとんど存在せず、痛みを感じる神経は表面の被膜にのみ分布しているため、内部で障害や病変があっても痛みとして感じにくいのが特徴です。
自覚症状がないまま病気が進行し、気付いたときにはすでに重篤な状態となっている場合が多いです。
また健康診断などで確認できる以下の数値が基準値を超えている場合、肝疾患のリスクが高まります。
- AST(GOT)
- ALT(GPT)
- γ-GTP
数値が基準値を超えていると、肝細胞が壊れている可能性が高く、脂肪肝や肝炎などの疾患が疑われます。
とくにALTとγ-GTPの数値が高い場合は、飲酒や薬剤、肥満、糖尿病など生活習慣の見直しが必要です。
このように自覚症状がなくても、定期的な血液検査や超音波検査によるチェックを行い、速やかに精密検査を受けましょう。
肝臓の働き
肝臓は、私たちの健康維持に欠かせない役割を担っています。
主な働きは、以下のとおりです。
- 代謝
- 解毒
- 胆汁の生成・分泌
- 免疫機能
代謝機能では食事から摂取した糖質や脂質、タンパク質を体内で利用しやすい形に変換し、必要に応じてエネルギーとして供給します。
たとえば、ブドウ糖をグリコーゲンに変えて蓄え、血糖値が下がった時に放出することで血糖値を一定にするなどです。
さらにアルコールや薬物、アンモニアなど、体内に入った有害物質を分解・解毒し、無害な形にして体外へ排出します。
胆汁の生成・分泌も役割のひとつで、脂肪の消化や吸収に欠かせません。
胆汁の分泌が悪くなると、脂質の消化不良や腸内環境の悪化につながります。
また、肝臓にはクッパー細胞やNK細胞、T細胞などの免疫細胞が多いため、体内に侵入したウイルスや細菌、老化した細胞を処理する免疫の要です。
| クッパー細胞 | 肝臓に存在するマクロファージの一種で、異物や老廃物を貪食し、免疫応答を調節する役割を担う。肝臓の類洞に位置し、肝臓の生体防御機能に重要な役割を果たしている。 |
| NK細胞 | 体内の免疫系において重要な役割を果たすリンパ球の一種。ウイルスに感染した細胞やがん細胞を特異的に攻撃し、自然免疫の一環として迅速に反応する。 |
| T細胞 | 免疫系の中心的な役割を果たすリンパ球の一種で、骨髄で産生された後、胸腺で成熟する。主にキラーT細胞とヘルパーT細胞にわかれ、ウイルス感染細胞やがん細胞を攻撃したり、他の免疫細胞を活性化したりする機能を持つ。 |
私たちの健康バランスが保たれているのは、肝臓が正常に働いているためです。
さまざまな機能が損なわれると、体調不良や重篤な疾患につながります
主な肝臓疾患
主な肝臓疾患は、5つあります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
ウイルス性肝炎
ウイルス性肝炎は、A型、B型、C型など複数のウイルスによって引き起こされる感染症です。
| 型 | 主な症状 |
|---|---|
| A型肝炎 | ・発熱 ・全身の倦怠感 ・食欲不振 ・吐き気・嘔吐 ・黄疸(皮膚や目の白い部分が黄色くなる) ・腹痛 |
| B型肝炎 | ・倦怠感 ・食欲不振 ・吐き気・嘔吐 ・黄疸 ・腹痛 ・褐色尿(濃い色の尿) |
| C型肝炎 | ・倦怠感 ・食欲不振 ・吐き気・嘔吐 ・黄疸 ・腹痛 ・褐色尿(濃い色の尿) |
| D型肝炎 | ・発熱 ・全身倦怠感 ・食欲不振 ・黄疸 |
| E型肝炎 | ・発熱 ・倦怠感 ・悪心 ・腹痛 ・黄疸 |
特にB型とC型は慢性化しやすく、長期間炎症が続くと肝臓の線維化が進み、肝硬変や肝臓がんへと移行するリスクが高まります。
急性肝炎の場合は発熱や倦怠感、黄疸などの症状が現れる場合がありますが、慢性肝炎では自覚症状がほぼありません。
また血液検査でASTやALTの大幅な上昇がみられる場合は、ウイルス性肝炎の可能性が高まります。
近年はワクチンや抗ウイルス薬の進歩により、治療成績が向上していますが、慢性化した場合は定期的な検査と専門医の管理が欠かせません。
病気の進行を防ぐためには、早期診断と治療が必要です。
脂肪肝疾患
脂肪肝は肝細胞に中性脂肪が過剰に蓄積した状態で、日本人の成人の20~30%※が該当するとされています。
出典:脂肪肝|全国健康保険協会
脂肪肝は、以下のような生活習慣の乱れによって発症するケースが大半です。
- 運動不足
- 食べ過ぎ
- アルコールの過剰摂取
- 肥満
- 糖尿病
アルコールをあまり飲まない人でも、食生活の乱れや肥満が原因で非アルコール性脂肪肝(MASLD)を発症するケースがあります。
自覚症状はほぼ見られず、健康診断でASTやALT、γ-GTPの数値が上昇して初めて気付く方が多いです。
特に炎症と線維化を伴う非アルコール性脂肪肝炎は、放置すると肝硬変や肝がんに進行するリスクが高く、注意が必要です。
脂肪肝は初期段階では自覚症状に乏しいため、気づかないうちに進行してしまうことがあります。
進行を防ぐには、生活習慣の改善と定期的な検査による早期発見が重要です。
肝硬変
肝硬変は肝臓の正常な組織が線維化し、硬く変化した状態で、以下のような慢性的な肝障害によって引き起こされます。
- B型・C型肝炎ウイルス感染
- 長期的なアルコール過剰摂取
- 非アルコール性脂肪肝炎
- 自己免疫性肝炎などによる慢性的な肝臓の炎症や障害など
肝臓の再生能力があっても、線維化が進むと元の状態には戻りません。
初期には食欲不振や全身の倦怠感などの症状が現れる場合がありますが、進行すると黄疸や腹水、意識障害などの重篤な症状が出現します。
さらに進行すると、肝臓がんのリスクが高まるだけでなく、生命に関わる合併症を引き起こす可能性があるため注意が必要です。
現時点では、根本的な治療法は確立されておらず、進行を遅らせるための食事療法や生活習慣の改善が中心です。
肝硬変による重篤な合併症や肝臓がんへの進行を防ぐには、早期発見と適切な管理をする必要があります。
肝臓がん
肝臓がんは、肝硬変や慢性肝炎などの背景疾患がある場合に発症リスクが高まります。
日本では、肝臓がんの多くがB型・C型肝炎ウイルス感染や長期間の肝障害に起因しています。※
※出典:国立研究開発法人国立がん研究センター
初期段階では症状がほぼ見られず、進行すると腹部のしこりや痛み、黄疸、体重減少などが現れる場合があります。
主な治療法は、以下のとおりです。
| 治療法 | 特徴 |
|---|---|
| 手術 | ・肝臓がんの根治的治療法で、腫瘍を含む肝臓の一部を切除する ・肝移植も選択肢のひとつで、早期の肝がんに適応される ・手術の適応は肝機能や腫瘍の大きさや位置による |
| 抗がん剤治療 | ・がん細胞を攻撃する薬剤を使用する ・通常、手術や局所療法ができない場合に選択される ・副作用が強く出ることが多く、肝機能への影響も考慮される |
| 放射線治療 | ・高エネルギーの放射線を使用してがん細胞を破壊する ・定位放射線治療や重粒子線治療が行われる場合とがある ・健康な組織への影響を最小限に抑えられる |
治療成績を向上させるには、方法だけでなく早期発見も必要です。
定期的な画像検査や腫瘍マーカーの測定は、早い段階での発見に役立ちます。
肝臓がんは進行が速い場合もあるため、肝疾患の既往がある場合は注意が必要です。
自己免疫性肝疾患
自己免疫性肝疾患は、体の免疫システムが誤って肝細胞を攻撃することで発症します。
代表的なものには、自己免疫性肝炎や原発性胆汁性胆管炎(PBC)があります。
| 自己免疫性肝炎 | 体の免疫系が誤って自分の肝細胞を攻撃し、慢性的な炎症を引き起こす病気。主に中年以降の女性に多く見られ、倦怠感や黄疸などの症状が現れる可能性がある。 |
| 原発性胆汁性胆管炎(PBC) | 肝臓内の胆管が自己免疫反応により慢性的に炎症を起こし、胆汁の流れが妨げられる病気。主に中年以降の女性に多く、初期には無症状が多いものの、進行すると黄疸や肝硬変を引き起こす可能性がある。 |
これらは女性に多く発症し、進行すると肝硬変や肝臓がんのリスクが高まります。
症状では倦怠感やかゆみ、黄疸などがみられるものの、初期には症状が出ない場合が多いです。
血液検査で特定の自己抗体や肝機能異常がみられた場合は、専門医による診断と治療が欠かせません。
肝臓は痛みを感じないため健康診断が重要
肝臓は痛覚がほとんどないため、病気が進行しても自覚症状が現れにくいのが特徴です。
そのため、健康診断や人間ドックで肝機能異常を指摘された場合、症状がなくても再検査や精密検査を受けましょう。
血液検査では、AST、ALT、γ-GTPなどの数値が健康状態を示す指標です。
| 指標 | 上昇する疾患 | |
| AST | 肝機能障害の有無を示す指標 |
・急性肝炎 |
| ALT | 肝機能障害の有無を示す指標 | ・脂肪肝 ・慢性ウイルス性肝炎 ・肝硬変 |
| γ-GTP | 胆道系の健康状態を示す重要な指標(アルコールに敏感に反応し、胆道の障害を示す) | ・アルコール性肝障害 ・胆道系疾患 ・脂肪肝 |
これらの数値が基準値を超えている場合、脂肪肝や肝炎・肝硬変などのリスクが高まります。
診断では、腹部超音波検査や画像診断を組み合わせると、状態を正確に把握できる可能性があります。
肝臓疾患は、早期での発見と治療が欠かせません。
自覚症状がなくても定期的な健診を受けると、重篤な疾患への進行を未然に防げます。
とくに、生活習慣病や肥満、糖尿病、高血圧などのリスク因子を持つ方は、年に1回の肝機能のチェックを行いましょう。
肝臓疾患に対する治療法「再生医療」について
従来の肝臓疾患治療では、生活習慣の改善や薬物療法が基本とされてきましたが、再生医療も治療法の選択肢の一つになります。
再生医療は患者自身の脂肪から採取した幹細胞を培養し、点滴で体内に戻すことで肝臓組織の修復や再生を目指す治療法です。
幹細胞には炎症を抑えたり、線維化した組織を修復したりする働きがあり、肝硬変や重度の脂肪肝にも効果が期待されています。
特に、冷凍保存せずにその都度培養すると、生存率・活動率の高い新鮮な幹細胞を投与できる点が特徴です。
治療の安全性や効果には個人差がありますが、臨床研究が進めば、肝臓疾患治療の新たな選択肢として普及が進むでしょう。
肝臓疾患のお悩みに対する新しい治療法があります。
【まとめ】肝臓は痛覚がほとんどないので健診を受けて疾患を早期発見しよう
肝臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれるように、進行しても痛みなどの自覚症状がほとんど現れない臓器です。
そのため、病気の発見が遅れやすく、気づいたときには重症化しているケースも少なくありません。
とくに以下のような方は、健康診断の数値(AST・ALT・γ-GTP)を見逃さず、異常があれば速やかに専門医の診察や精密検査を受けることが重要です。
- 肥満、糖尿病、高血圧、脂質異常症など
- アルコールを日常的に摂取している
- 急激な体重減少が見られる
自覚症状がなくても、定期的な検診と適切な生活習慣の見直しが、肝臓病の早期発見と重症の予防につながります。
再生医療も選択肢に加えつつ、まずは自分自身のリスクを把握し、早期での発見と治療を心掛けてください。
健診結果は軽視せず、医師の指導のもとで適切な対応を行いましょう。
再生医療といった新しい治療法も選択肢として広がっています。興味のある方は以下から症例をご確認ください。
>再生医療による肝疾患の症例はこちら

監修者
渡久地 政尚
Masanao Toguchi
医師
略歴
1991年3月琉球大学 医学部 卒業
1991年4月医師免許取得
1992年沖縄協同病院 研修医
2000年癌研究会附属病院 消化器外科 勤務
2008年沖縄協同病院 内科 勤務
2012年老健施設 かりゆしの里 勤務
2013年6月医療法人美喜有会 ふたこクリニック 院長
2014年9月医療法人美喜有会 こまがわホームクリニック 院長
2017年8月医療法人美喜有会 訪問診療部 医局長
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 院長