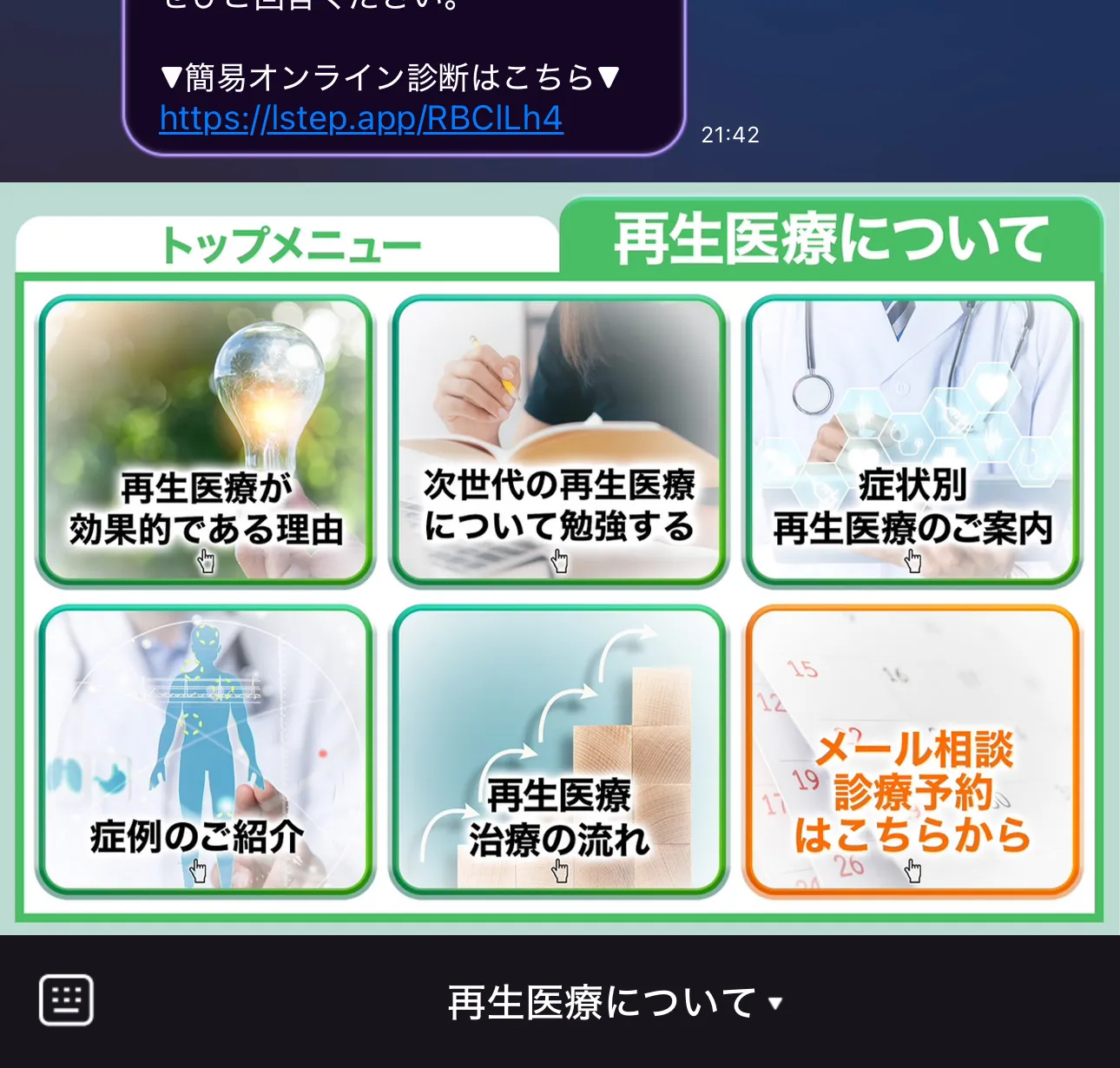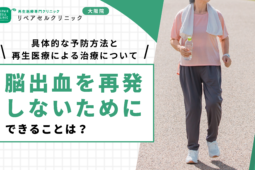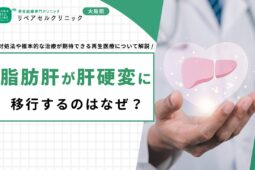サプリメントは肝臓に悪い?摂取時の注意点や正しい飲み方を解説
公開日: 2020.01.30更新日: 2025.04.28
サプリメントは健康食品の一種であり、特定の栄養成分を補給することを目的とした食品ですが、「肝臓に負担をかけてしまうのではないか」と不安を感じる方もいるのではないでしょうか。
とくに、サプリメントの摂りすぎや飲み合わせによる影響が気になる場合、どのように正しく利用すればよいのか悩む方も少なくありません。
本記事では、サプリメントの過剰摂取が肝臓に与える影響や薬剤性肝障害のリスクについて解説します。
また、肝障害に対する再生医療の可能性にも触れながら、健康的にサプリメントを活用するための知識をご紹介します。ぜひ最後までお読みください。
目次
サプリメントの摂りすぎが肝臓にダメージを与える理由
肝臓は体の中で非常に重要な役割を担っており、主に以下の働きをしています。
- 代謝
- 解毒分解
- 胆汁の生成
- エネルギーの供給
サプリメントは薬剤と同じく肝臓で解毒・分解されますが、過剰な服用で肝臓への負担が大きくなります。
実際に、薬剤によって引き起こされる「薬剤性肝障害」と呼ばれる肝臓の病気は、健康食品やサプリメントの過剰摂取によって発症した事例も報告されています。
また、アルコールの分解を補助するサプリメントを飲めば、お酒をたくさん飲んでも良いというわけではありません。
加えて、すでに肝炎や脂肪肝を患っている方は、サプリメントにより肝臓の負担が増す可能性があるため注意が必要です。
重篤な状態に陥ると、肝臓が再生しない肝硬変に進展する可能性もあります。
肝臓疾患を招く薬とその症状
実は、ほとんどのサプリメントや薬に肝臓疾患を引き起こす可能性があるため、注意が必要です。
- 解熱鎮痛剤
- 抗生物質
- 胃腸薬
- ホルモン剤
- 漢方薬
- 健康食品
発熱・倦怠感・体のかゆみ・発疹・吐き気などの症状があるときは、サプリメントや薬が肝臓に負担をかけている可能性があるので、早めに医療機関を受診しましょう。
過剰摂取すると肝臓に悪いサプリメントの成分
サプリメントは健康維持に役立つ面もありますが、過剰摂取によって肝臓に負担がかかる場合があります。
過剰摂取すると肝臓に悪いサプリメントの成分と影響は以下の通りです。
| 成分 | 肝臓への影響や注意点 |
|---|---|
| ビタミンA | 脂溶性ビタミンなので過剰に摂ると肝細胞に蓄積し、炎症や障害を誘発するケースがある |
| 鉄分 | 多量に摂取すると肝臓に蓄積し、酸化ストレスを引き起こすため肝硬変などのリスクが高まる |
| ウコン(ターメリック) | カレーなどで使われるスパイスだが、過剰摂取で肝障害につながる報告がある |
| アガリクス(キノコ類) | 免疫向上を目的に使用されるが、長期過剰摂取で肝臓に炎症が起きる可能性がある |
| プロポリス | 蜂由来の成分で抗酸化作用が期待されるが、体質や量によっては薬剤性肝障害が発生するケースがある |
| ノニ(モリンダシトリフォリア) | 健康飲料として市販されているが、過剰摂取で急性肝障害を発症した報告が存在する |
| タンパク質サプリ | 長期間にわたり高容量を摂ると肝臓が分解時に負担を受け、肝機能に悪影響を及ぼす可能性がある |
| ナイアシン、緑茶エキス | 適量なら問題ないが、過剰摂取による肝炎のリスクがあるため、サプリの上限量を守る必要がある |
サプリメントは用量や飲むタイミングを誤ると肝障害を招く恐れがあります。
安全に利用するには摂取量を守り、持病がある場合は医師に相談しましょう。
サプリメントで起こる薬剤性肝障害の症状
サプリメントの過剰摂取や成分の影響により、肝臓に炎症や障害が発生する可能性があります。
薬剤性肝障害でみられる症状は、以下の通りです。
- 疲れやすさ:慢性的な倦怠感が続くことがある
- 吐き気や嘔吐:肝臓の働きが低下することで胃腸の不調が現れる
- 黄疸:皮膚や白目が黄色くなる症状が見られる
- 食欲低下:肝機能の低下により食事が進まなくなる
- 発熱:肝臓の炎症が原因となり体温が上昇する
これらの症状が現れた場合は、早急に医療機関へ相談し、適切な検査や治療を受けることをおすすめします。
サプリメントによる肝障害は再生医療で根本的な治療に期待できる
サプリメントの影響で肝臓に障害が生じた場合の治療法の一つに、再生医療があります。
再生医療は、肝細胞の修復や再生を促進することで、従来の治療では難しい症状の改善が期待できます。
- 根本的な治療:幹細胞を用いて肝臓を正常の細胞に戻し、機能回復を目指す
- 適応範囲の広さ:慢性的な肝障害や回復が難しい症例でも改善の可能性がある
- 患者に合わせた治療:患者自身の細胞を使うため副作用のリスクが非常に少ない※
※個人差があります
再生医療による肝臓の治療をご検討の際は、ぜひ当院へご相談ください。
肝臓疾患のお悩みに対する新しい治療法があります。
肝臓疾患を防ぐ正しいサプリメントの飲み方
サプリメントにおける用法・用量は守ることは非常に重要です。
肝臓に負担をかけないためにもサプリメントの飲み方を覚えておく必要があります。
サプリメントについての理解を深め、肝臓疾患を防ぎましょう。
摂取量を守る
1日に必要な栄養素を超えないようにサプリメントを飲むことが大切です。
サプリメントをたくさん飲んだからといって効果が増幅することはありません。それどころか、サプリメントの過剰摂取は肝臓のダメージをはじめ、健康に害を及ぼす可能性があります。
必ず容量を守って飲みましょう。
飲み合わせの効果を確認する
1種類だけでなく、複数種類のサプリメントを同時に飲む方もいらっしゃるでしょう。しかし、飲み合わせはサプリメント同士の働きを邪魔してしまうこともあります。
サプリメントを複数飲む際は、一緒に飲んでも効果があるのか薬剤師に確認してみましょう。
医師に相談する
肝臓の病気を患っており、処方薬を飲んでいる場合は細心の注意を払ってサプリメントを摂取する必要があります。
処方薬と干渉しないサプリメントを選ぶ必要があるため、その場合は必ず医師に相談し、飲めるサプリメントを教えてもらいましょう。
とくに、肝硬変の場合はサプリの代謝が難しいため、必ず医師からの指導を受けてください。
サプリメントの危険な飲み合わせに注意する
サプリメント同士の組み合わせによっては、効果が減少したり副作用が発生する可能性があります。
以下は、注意が必要なサプリメント同士の組み合わせです。複数のサプリメントを飲むときはお気を付けください。
| サプリメント成分1 | サプリメント成分2 | 注意点 |
|---|---|---|
| ビタミンA | ビタミンD | 両方とも脂溶性ビタミンのため、過剰摂取で肝障害や高カルシウム血症を引き起こす可能性がある |
| 鉄分 | カルシウム | 鉄分の吸収がカルシウムによって妨げられ、鉄分不足を招く可能性がある |
| マグネシウム | カルシウム | 両者が腸内で競合し、どちらの吸収率も低下する場合がある |
| 亜鉛 | 鉄分 | 亜鉛の摂取量が多いと鉄分の吸収を阻害し、貧血を招く可能性がある |
| オメガ3脂肪酸 | ビタミンE | 両方とも血液をサラサラにする作用があり、出血時のリスクが高まる |
| クエン酸カルシウム | 亜鉛 | クエン酸カルシウムが亜鉛の吸収を妨げる可能性がある |
| ビタミンB群 | 緑茶エキス | 緑茶エキスに含まれるカテキンがビタミンB群の吸収を阻害する可能性がある |
サプリメントは適切に利用することで健康を維持できますが、飲み合わせによる影響を理解し、安全に活用しましょう。
サプリメントは摂取量に注意!肝臓が悪い場合は医師に相談しよう
サプリメントは健康維持に役立つ一方で、摂取量を守らないと肝臓に負担をかけるリスクがあります。
とくに、脂溶性ビタミンや鉄分、ウコンなど、過剰摂取により肝障害を引き起こす可能性がある成分には注意が必要です。
サプリメントの過剰摂取などにより薬剤性肝障害になってしまうと、倦怠感や吐き気、黄疸、発熱などの症状が現れます。
これらの症状を放置すると肝機能がさらに低下し、治療が難しくなる場合もあるため、早めの対応が大切です。
薬剤性肝障害などの肝臓疾患に対しては、再生医療が効果的な治療法の一つとして挙げられます。
再生医療では、幹細胞を用いて肝細胞の修復や再生を促進することで、従来の治療では改善が難しい症状の緩和が期待されています。
肝臓の疾患にお悩みの方は、再生医療を含む治療法について当院へお気軽にご相談ください。

監修者
渡久地 政尚
Masanao Toguchi
医師
略歴
1991年3月琉球大学 医学部 卒業
1991年4月医師免許取得
1992年沖縄協同病院 研修医
2000年癌研究会附属病院 消化器外科 勤務
2008年沖縄協同病院 内科 勤務
2012年老健施設 かりゆしの里 勤務
2013年6月医療法人美喜有会 ふたこクリニック 院長
2014年9月医療法人美喜有会 こまがわホームクリニック 院長
2017年8月医療法人美喜有会 訪問診療部 医局長
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 院長