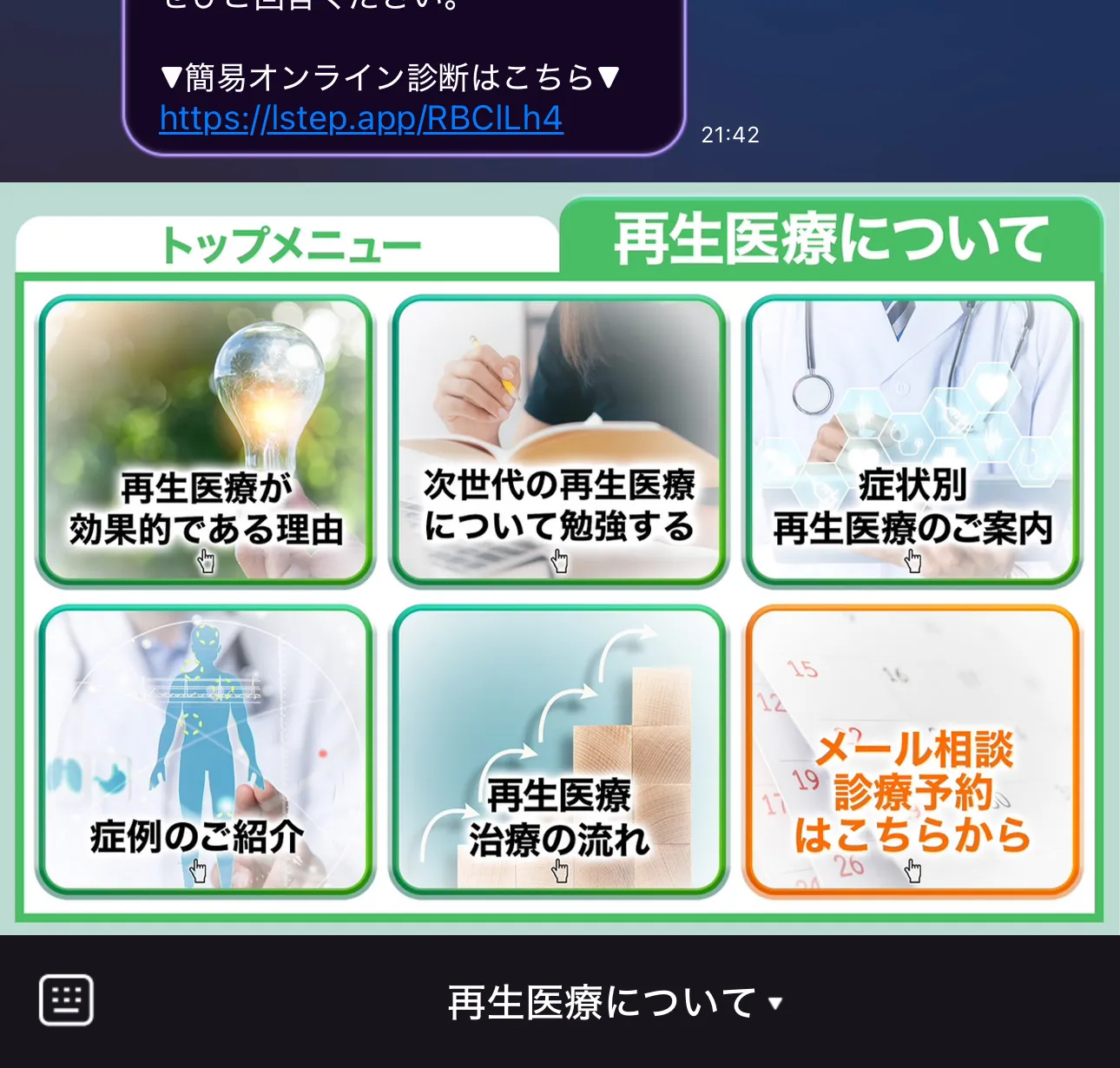RICEという医療用語の意味は?肉離れや捻挫の応急処置の基本から早期回復を目指す方法を解説
公開日: 2020.02.04更新日: 2025.05.07
スポーツ活動中の怪我は、適切な応急処置が回復の鍵を握ります。
特に肉離れや捻挫、打撲といった外傷に対して有効なのが「RICE処置」です。
しかし、RICE処置は広く知られているものの、正しい方法で実践できている人は意外と少ないのが現状です。
この記事では、RICE処置の基本から症状別の対応方法まで解説します。
スポーツからの早期復帰を目指す方に向けて、再生医療についても紹介します。ぜひ最後までご覧ください。
目次
医療におけるRICE処置とはスポーツでよく起こるケガの応急処置のこと
RICE処置とは、次の4つの頭文字を取った応急処置法です。
これはスポーツで起きやすい肉離れ、捻挫、打撲などさまざまな外傷に対して効果的な初期対応として確立されています。
RICE処置は怪我の症状悪化を防ぎ、治癒を促進する重要な役割を果たします。
R(Rest):安静
怪我をした部位を無理に動かさず、負荷をかけないようにします。
完全に動かさないというわけではなく、痛みが出ない範囲で負荷を軽減することが目的です。
必要に応じて松葉杖や添え木、テーピングなどを使用して患部を保護しましょう。
I(Ice):冷却
受傷した部位を氷やアイスパックで冷やします。
冷やすことで血管を収縮させ、内出血や腫れ、炎症を抑制し、痛みを和らげる効果があります。
直接皮膚に氷を当てると凍傷のリスクがあるため、タオルで包むなどして15〜20分ほど冷やし、その後は間隔を空けて繰り返すと効果的です。
C(Compression):圧迫
弾性包帯やテーピングで患部を適度に圧迫することで、これにより内出血や腫れを最小限に抑えられます。
圧迫が強すぎると血流障害を起こす恐れがあるため、患部の先端(指先など)の色や感覚を定期的に確認し、しびれや変色がある場合は一度緩めましょう。
E(Elevation):挙上
怪我をした部位を心臓よりも高い位置に保ちます。
これにより重力の作用で静脈還流(血液が心臓に戻る流れ)が促進され、腫れの軽減につながります。
クッションや枕を使って患部を高く保つことで、血流改善と腫れの軽減が期待できます。特に足首や膝など下肢の怪我では効果的です。
適切なRICE処置を主なスポーツ外傷ごとに解説
スポーツ外傷の種類によって、RICE処置の重点ポイントや効果的なアプローチが異なります。
ここでは、代表的な3つのスポーツ外傷に対する適切なRICE処置について解説します。
- 肉離れ
- 捻挫
- 打撲
スポーツでのケガに備えて、それぞれのRICE処置について見ていきましょう。
肉離れ
肉離れは、筋肉が急激に引き伸ばされることで筋線維が断裂する怪我です。
肉離れに対するRICE処置では、特に受傷直後の圧迫が重要です。
筋肉内の出血によるしこり形成を防ぐため、弾性包帯での適切な圧迫を心がけましょう。
アイシングは間隔を空けながら24〜48時間継続し、この期間は患部の安静を保ちます。
症状が改善しない場合や悪化する場合は、より重度の損傷の可能性があるため早めに医療機関を受診してください。
捻挫
捻挫は関節を支える靭帯が損傷する怪我です。
捻挫の特徴は顕著な腫れと内出血であり、これが関節の動きを制限し回復を遅らせる原因となります。
このため、RICE処置では早期からのアイシングと圧迫を重視します。
弾性包帯やテーピングで適切に圧迫し、腫れを最小限に抑えることが重要です。
立てない、歩けないなどの重い症状の場合は、重度の靭帯損傷の可能性があるため医療機関を受診しましょう。
打撲
打撲は外部からの衝撃で組織が損傷する怪我で、内出血を伴うことが特徴です。
打撲に対するRICE処置では、特に受傷直後のアイシングが効果的です。
衝撃を受けた直後から冷却することで、血管収縮を促し内出血の範囲を最小限に抑えることができます。
軽度の打撲であれば、数日で青あざの色が変化し始め、徐々に消失していきます。
2〜3日経っても痛みが改善しない場合や打撲部位の痛みが強まる場合は、骨折や深部組織の損傷の可能性があるため、医療機関の受診をおすすめします。
RICE処置はあくまで応急処置!医療機関を受診する基準
RICE処置は怪我の初期対応として効果的ですが、あくまでも応急処置であり、原因の根本的な治療にはなりません。
適切な処置を行った後も症状が改善しない場合は、専門医による診断・治療が必要です。
以下のような症状がある場合は、早急に医療機関を受診しましょう。
- 強い痛みが24〜48時間経過しても軽減しない
- 腫れや内出血が広範囲に広がっている
- 関節の動きが著しく制限されている
- 患部に変形や異常な動きがある
- 立てない、歩けないなど日常生活に支障がある
- 捻挫を繰り返す、または同じ部位を何度も痛める場合
特に「立てない」「歩けない」といった症状がある場合は、重度の靭帯損傷や骨折の可能性があります。
早期の診断と治療が後遺症を防ぎ、早期回復につながります。
スポーツへの早期復帰を目指すなら「再生医療」を検討しよう
スポーツ選手にとって、怪我からの早期回復と競技復帰は非常に重要な課題です。
競技への早期復帰を目指す方は、「再生医療」による治療もご検討ください。
当院「リペアセルクリニック」では、患者さま自身の幹細胞を用いて損傷部位にアプローチする「幹細胞治療」を提供しております。
入院や手術は不要で、治療は患者さまから米粒2~3粒ほどの脂肪を採取後、培養した幹細胞を患部に投与するだけです。
軟骨損傷や靭帯損傷、肉離れなどのスポーツ外傷でお悩みの方は、ぜひ当院「リペアセルクリニック」へご相談ください。
スポーツ外傷は⼿術しなくても治療できる時代です。
RICE処置に関してよくある質問
RICE処置に関してよくある質問を紹介します。
ケガに備えてRICE処置への疑問を解消しておきましょう。
RICE処置の順番は?
RICE処置の理想的な順番は、以下の通りです。
- Rest:安静
- Compression:圧迫
- Ice:冷却
- Elevation:挙上
注意したいのが、実施する順番はRICEではなく、RCIEの順になる点です。
圧迫してから冷やすことで、冷却効果がより患部に伝わりやすくなります。
ただし、怪我の状況によっては順番を変える場合もあります。
例えば出血が著しい場合は、先に圧迫と挙上を行い出血をコントロールし、その後に冷却することもあります。
重要なのは、各要素をバランスよく組み合わせて行うことです。
最新のRICE処置と呼ばれるPOLICE処置とは?
近年、従来のRICE処置を発展させた「POLICE処置」が注目されています。
POLICEは次の頭文字をとったものです。
- Protection(保護)
- Optimal Loading(最適な負荷)
- Ice(冷却)
- Compression(圧迫)
- Elevation(挙上)
大きなの違いは、従来のRICE処置の「Rest(安静)」が「Protection(保護)」と「Optimal Loading(最適な負荷)」に置き換えられた点です。
完全な安静よりも、損傷組織を保護しながら適切な負荷をかけることで、より効果的な組織修復が促進されるという考え方に基づいています。
例えば、足首捻挫の場合、完全に動かさないのではなく、痛みのない範囲で足首を動かす運動を行います。
適切な負荷により関節の可動域を維持し、筋力低下を防げるのです。
ただし、最適な負荷のかけ方は怪我の種類や程度によって異なるため、医師や理学療法士など専門家の指導のもとで行うことが重要です。
【まとめ】RICE処置は外傷に対する応急処置!痛みが引かなければ医療機関へ
RICE処置は、スポーツ活動中に起こりやすい肉離れ、捻挫、打撲などの外傷に対する効果的な応急処置法です。
Rest(安静)、Ice(冷却)、Compression(圧迫)、Elevation(挙上)の4つのステップを適切に行うことで、内出血や腫れを抑え、痛みを軽減し、回復を早められます。
ただし、RICE処置はあくまでも応急処置です。
症状が改善しない場合や、「立てない」「歩けない」といった症状がある場合は、速やかに医療機関を受診することが重要です。
また、スポーツへの早期復帰を目指す場合は、再生医療などの新しい治療法を検討することも選択肢の一つです。
幹細胞治療やPRP療法などは、入院や手術を必要としないため、競技への早期復帰が目指せます。
再生医療をご検討の際は、当院「リペアセルクリニック」へご相談ください。

監修者
坂本 貞範
Sadanori Sakamoto
医療法人美喜有会 理事長
「できなくなったことを、再びできるように。」
人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの
お手伝いができれば幸甚の至りでございます。
略歴
1997年3月関西医科大学 医学部卒
1997年4月医師免許取得
1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務
1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務
1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務
1999年2月国立大阪南病院 勤務
2000年3月野上病院 勤務
2003年3月大野記念病院 勤務
2005年5月さかもとクリニック 開設
2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任
2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設
2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設