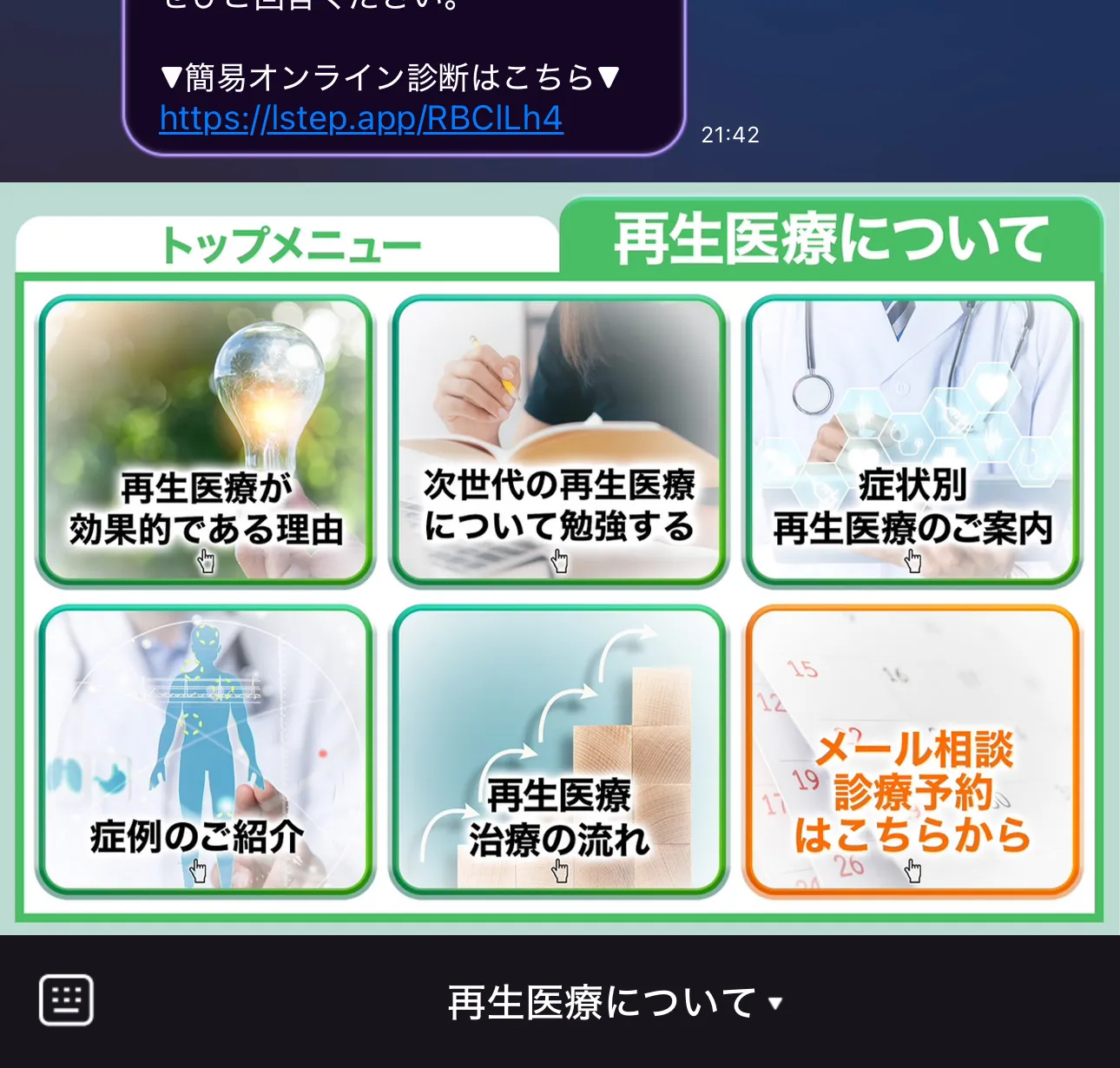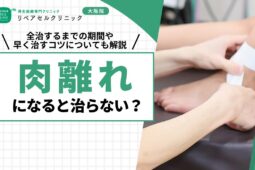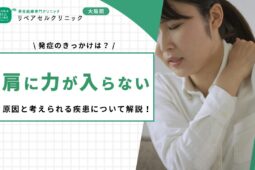肝硬変の人が食べてはいけないものとは?避けるべき食品と正しい食事管理を解説
公開日: 2020.02.05更新日: 2025.06.02
「食事で何に気をつければよいのか」「これまで楽しんでいた食事はできなくなるのか」
肝硬変と診断されたときに、このような不安を感じられる方は少なくありません。
とくに外食時や家族との食事の場で、何を選べばよいのか悩まれることも多いでしょう。
この記事では、肝硬変の方が避けるべき食品・飲み物のリストと、その理由を詳しく解説します。
また、腹水やむくみ、肝性脳症、食道静脈瘤といった症状別の食事制限についても紹介し、肝機能をサポートするために積極的に摂りたい栄養素もご案内します。
正しい知識を身につけて、肝硬変による制限の中でもなるべく美味しく楽しい食生活を続けましょう。
目次
肝硬変の人が食べてはいけない・避けるべき食品・飲み物を紹介
肝硬変の人が食べてはいけない・避けるべき食品・飲み物は、以下の通りです。
| 分類 | 避けるべき食品・飲み物 | 理由 |
|---|---|---|
| アルコール | ビール、ワイン、日本酒、焼酎など全てのアルコール飲料 | 肝臓での分解負担が大きく、肝細胞にダメージを与える |
| 塩分の多い食品 | インスタント食品、漬物、梅干し、加工食品、かまぼこ、ソーセージなど | 腹水やむくみを悪化させる |
| 刺激物・硬い食品 | 香辛料の多いカレー、コーヒー、せんべい、ナッツ、骨のある魚、フランスパンなど | 食道静脈瘤が破裂するリスクがある |
| 高タンパク食品 | 過剰な肉類、卵類、乳製品など | アンモニアが体内に蓄積し肝性脳症のリスクが高まる |
| 生もの | 刺身、寿司、生牡蠣など | 食中毒リスクが高く、肝機能低下により感染症にかかりやすい |
| 加工食品 | 缶詰、レトルト食品、スナック菓子など | 防腐剤や添加物が多く含まれ、肝臓に負担をかける |
| 高脂肪食品 | フライドポテト、揚げ物、脂身の多い肉など | 消化不良を起こし、肝臓に負担をかける |
| 糖分の多い食品 | お菓子、砂糖を多く含む食品、清涼飲料水など | 脂肪肝を助長し、肝機能をさらに低下させる |
肝硬変の方は、これらの食品・飲み物を避けるか、摂取量を注意深く管理する必要があります。
病状や合併症の種類によって制限内容は異なりますので、上記はあくまで参考にして医師の指導に従いましょう。
肝硬変の症状別にみる避けるべき食事
肝硬変の症状別にみる避けるべき食事を紹介します。
肝硬変が進行すると、さまざまな合併症が現れることがあります。症状によって食事制限の内容も変わってきますので、自分の症状に合わせた食事管理が重要です。ここでは代表的な症状別に、とくに注意すべき食事内容を解説します。
腹水・浮腫(むくみ)がある場合
腹水や全身のむくみがある場合は、体内の水分バランスが崩れている状態です。
この症状がある方は、塩分摂取量を1日5〜7g(※)に制限する必要があります。
※参照:日本消化器病学会・日本肝臓学会「肝硬変診療ガイドライン 2020(改訂第 3 版)」2020年発行
- 醤油、味噌、塩などの調味料を減らす
- 加工食品、インスタント食品、漬物などの高塩分食品を避ける
- だしを効かせた薄味料理を心がける
- 医師の指示があれば水分制限・タンパク質制限も行う
腹水・むくみがある場合は、塩分を控えるだけでなく、水分やタンパク質も適量に抑える必要があるケースもあります。
医師や栄養士と相談しながら、塩分と水分、タンパク質の摂取量を調整しましょう。
肝性脳症がある場合
肝性脳症は、肝機能の低下によって血液中のアンモニア濃度が上昇し、脳機能に影響を及ぼす状態です。
アンモニアの主な発生源は食事から摂取するタンパク質なので、この症状がある方はタンパク質の摂取量に注意が必要です。
- タンパク質の摂取量を制限する(医師の指示に従う)
- 動物性タンパク質(肉、魚、卵、乳製品など)の摂取をとくに控える
- 植物性タンパク質(豆腐、納豆など)を中心に摂る
- 便秘を防ぐために食物繊維を適量摂取する
- 医師の指示があればBCAA(分岐鎖アミノ酸)製剤を利用する
肝性脳症の症状がある場合は、医師の指示のもとで適切なタンパク質制限を行いましょう。
しかしタンパク質が不足すると栄養状態が悪化する恐れもあるため、自己判断での過度な制限は避けてください。
食道静脈瘤がある場合
食道静脈瘤は食道の血管が瘤状に膨らんだ状態で、破裂すると命に関わる出血を引き起こす危険があります。
この症状がある方は食事の内容と食べ方に注意が必要です。
- 硬い食品(せんべい、ナッツ、固いパンなど)を避ける
- 刺激物(香辛料、酸味の強い食品、熱い食べ物など)を控える
- 柔らかく調理した食品を選ぶ(茶碗蒸し、うどん、お粥など)
- 小さく切って、よく噛んでゆっくり食べる
- アルコールは絶対に避ける
食道静脈瘤がある場合は、食道を傷つけるのを防ぐため、やわらかい食品を中心によく噛んで食べましょう。
大きな塊を飲み込まないように注意してください。
肝硬変の人が積極的に取りたい栄養素と食品
肝硬変の人が積極的に取りたい栄養素とその食品を以下にまとめました。
| 栄養素 | 目的・効果 | 主な食品例 |
|---|---|---|
| 分岐鎖アミノ酸(BCAA) | 筋肉量の維持、代謝の補助 | BCAA製剤(リーバクトなど)、大豆製品、乳製品 |
| 良質なたんぱく質(適量) | 肝機能の維持、体力の回復 | 豆腐、納豆、白身魚、鶏ささみ、牛乳 |
| ビタミンB群 | エネルギー代謝、神経機能の維持 | 玄米、卵、大豆、緑黄色野菜 |
| ビタミンC・E(抗酸化ビタミン) | 肝細胞の保護、酸化ストレスの軽減 | ブロッコリー、パプリカ、キウイ、ほうれん草 |
| 食物繊維 | 便通改善、腸内環境の整備 | 野菜(煮物など)、きのこ、海藻 |
| エネルギー源(糖質・脂質) | エネルギー確保、低栄養の予防 | ごはん、うどん、植物油、間食(ゼリーなど) |
これらの栄養素や食品は、医師や管理栄養士の指導の下で、病状に応じて適切に取り入れることが大切です。
バランスよくこれらの栄養素を取り入れることで、肝硬変による栄養障害を予防・改善しやすくなります。
肝硬変の人が食事で気を付けること
肝硬変になると、肝機能の低下によって栄養の吸収・代謝バランスが崩れやすくなるため、日々の食事管理が病状の進行抑制や合併症の予防の効果につながる可能性があります。
以下のポイントに注意しましょう。
- 塩分(ナトリウム)の制限
- 適切なたんぱく質の摂取
- 十分なエネルギー補給
- 禁酒
食事療法は、医師・管理栄養士の指導のもとで個々の病状や体格に応じて調整することが重要です。
自己判断で制限しすぎると、かえって体調を崩す恐れもあるため注意しましょう。
【まとめ】肝硬変で食べてはいけないものを正しく理解し、食生活を改善しよう
肝硬変の方の食事管理は、病状の進行を抑える重要な治療の一つです。
アルコール類は完全に避け、症状に応じて塩分や動物性タンパク質の摂取量を調整する必要があります。
腹水・むくみがある方は塩分制限を、肝性脳症の方はタンパク質制限を、食道静脈瘤の方は刺激物や硬い食品を避けるなど、合併症に応じた食事調整が重要です。
また、良質なタンパク質やビタミン、食物繊維などを適切に摂取し、栄養バランスを整えることも大切です。
自己判断せず、医師や管理栄養士と相談しながら、症状や病状に合わせた食事療法を継続することで、肝硬変と上手に付き合っていきましょう。
なお、当院「リペアセルクリニック」では、肝臓の疾患に対する再生医療を提供しております。
再生医療の詳細については、以下よりお気軽にお問い合わせください。

監修者
岩井 俊賢
Toshinobu Iwai
医師