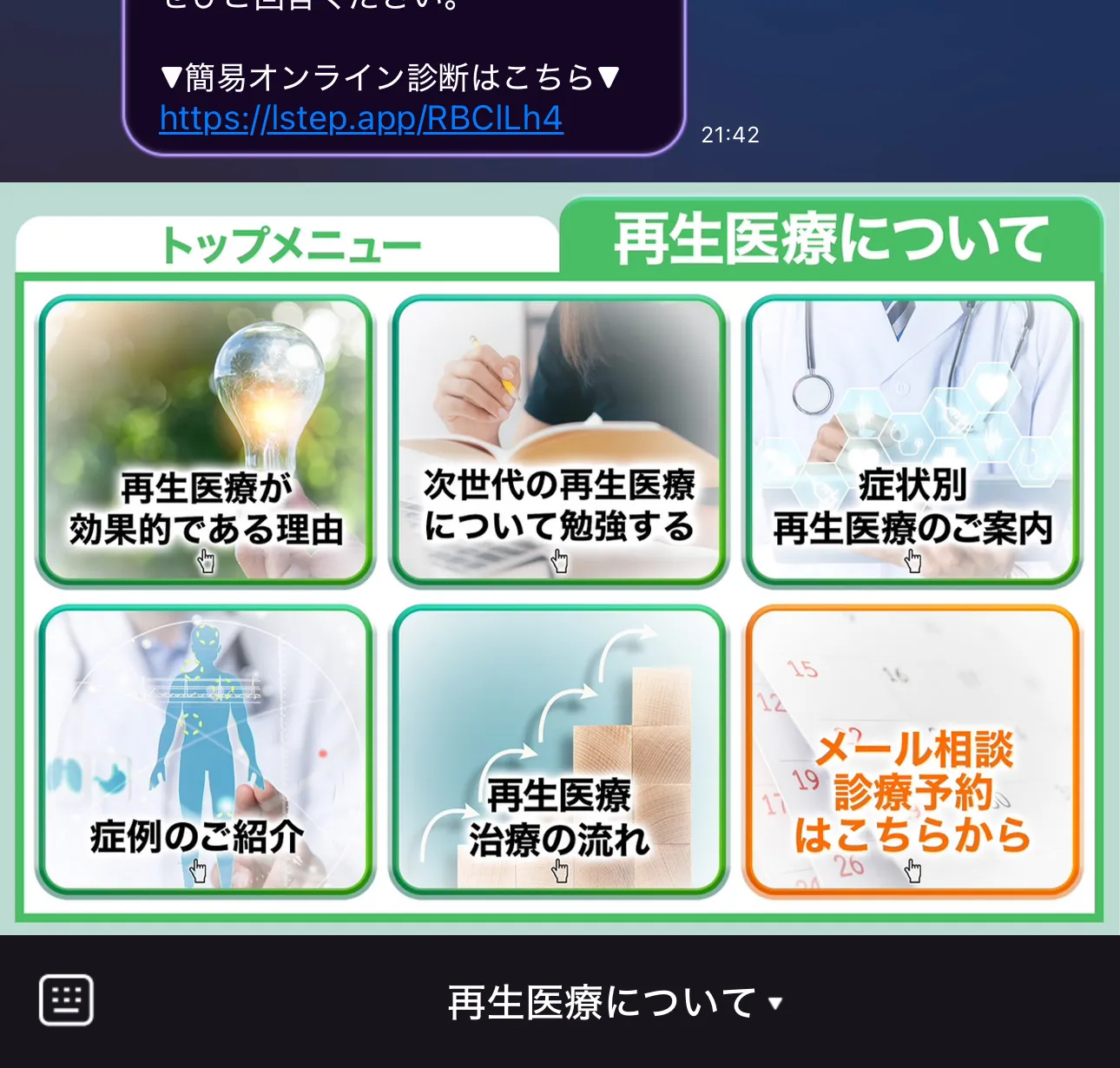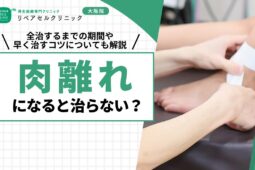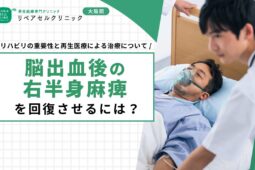肝臓が悪いと言われたら | どのような症状が出るか解説!
公開日: 2020.02.02肝臓が悪いと顔や体に変化がありますが、初期症状が曖昧で気づきにくいため注意が必要です。
肝臓の病気は進行すると、肝硬変や肝臓がんなどの重篤な病気になる可能性があるため、早く症状に気づけるかどうかが大切です。
そこで本記事では、肝臓が悪いとどんな症状が出るのか解説します。最後までご覧いただき肝疾患の早期発見・早期治療を目指しましょう。
|
この記事を読むとわかること |
目次
肝臓が悪いと顔や体に出る症状

肝臓が悪いと顔や体に出る症状は、以下のとおりです。
|
肝臓が悪いと顔や体に出る症状
|
肝臓は沈黙の臓器と呼ばれ、初期段階では症状に気づきにくいのが特徴です。症状に気づいたころには重症化している可能性もあるため、どんな症状が出現するのか知っておきましょう。
黄疸と皮膚のかゆみ
肝臓が悪いと、黄疸や皮膚のかゆみが現れる場合があります。黄疸とは、皮膚や眼の白い部分が黄色くなる症状です。
肝臓の機能が低下し、ビリルビンと言われる黄色い色素を正常に処理できなくなると、黄疸の症状が現れます。皮膚のかゆみも肝臓の異常を示す症状で、ビリルビンや胆汁酸が体内に蓄積されて生じます。
視力の低下と目の疲れ
肝臓が悪くなると、視力の低下や目の疲れなどの症状が現れることがあります。
肝臓の機能低下による間接的な影響で、健康な血液が十分に供給されなくなり、視界がぼやけたりかすんだりする症状が出現します。
ドライアイの症状も肝臓の異常を示すサインの場合があるため、目に違和感があるときは注意が必要です。
からだのむくみと腹水
肝臓の働きが鈍ると、からだがむくんだり腹水が溜まったりする場合があります。体内の水分量が増える原因は、肝機能の悪化により正常に血液を処理できなくなり、血液や体液が滞るためです。
一般的に足や顔がむくみやすく、症状が進行すると大量の腹水が溜まる場合もあります。
全身倦怠感と疲労感
肝臓が悪いと、全身倦怠感や疲労感が強く現れます。肝機能の悪化により全身倦怠感や疲労感が出現する理由は、肝臓が担う代謝の機能が乱れ、疲労物質が蓄積するためです。
日常生活動作で疲れたり、何も動いていないのに倦怠感があったりする場合は、早めに医師へ相談しましょう。
吐血と意識障害
肝臓病が重篤化すると、吐血や意識障害が現れる場合があります。吐血が起こる原因は、肝臓の異常によって消化管の血管が破れやすくなるためです。
意識障害が現れる理由は、体内に蓄積した毒素が脳に影響を及ぼすためです。肝臓には代謝や解毒作用などの働きがあり、正常に機能しなければ毒素が蓄積します。
肝疾患が重篤化する前に、体の異変に気づいたらすぐ医療機関を受診しましょう。
食欲低下と消化不良
肝臓が悪化すると、食欲低下や消化不良が起こります。
食べ物の消化には、肝臓から分泌される胆汁が必要です。肝臓の働きが鈍り、胆汁の分泌量が低下すると、食べ物の消化が困難になります。
消化不良の場合は、食欲がなくなったり嘔気を感じたりします。
受診の重要性
肝臓の疾患が疑われる症状がみられる場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
肝臓の異常はウイルス感染や自己免疫異常、薬の副作用など、さまざまな原因で引き起こされます。血液検査や画像診断で肝臓の状態を知り、医師の治療を受ける必要があります。
知っておくべき肝臓の病気の種類
知っておくべき肝臓の病気は、以下のとおりです。
- 肝炎
- 脂肪肝
- 非アルコール性脂肪性肝炎
- アルコール性肝障害
- 肝硬変
肝臓の病気を早期に発見し、スムーズに治療を受けられるよう、疾患別の症状を確認しましょう。
肝炎
肝炎は主に肝炎ウイルスの感染により発症する病気で、感染以外の発症要因にはアルコールや薬物などがあります。
急激に症状が出現する急性肝炎は、A型・B型・E型ウイルスが原因の場合が大半です。一方で、慢性的に症状が進行する慢性肝炎は、B型・C型ウイルスを要因とする場合が多いと言われています。
肝炎になると、以下の症状が現れる場合があります。
- 全身倦怠感
- 食欲不振
- 皮膚のかゆみ、黄疸
- 発熱、頭痛
- 嘔気、嘔吐
- 褐色尿
症状には個人差があるため、違和感や不安があるときは迷わず医師にご相談ください。
脂肪肝
知っておくべき肝臓の病気の1つに、脂肪肝があります。脂肪肝とは、肝臓に過剰な脂肪が蓄積された状態です。
脂肪肝は主に、中性脂肪が肝細胞内に多く蓄積し起こります。脂肪肝が悪化すると、肝炎や肝硬変、肝がんなどの深刻な病気に進展するリスクがあります。
脂肪肝は、乱れた生活習慣が原因で起こる場合が大半です。過剰な飲酒や肥満なども脂肪肝のリスクを高めるため、自身の生活習慣を見直しましょう。
非アルコール性脂肪性肝炎
知っておくべき肝臓の病気に、非アルコール性脂肪性肝炎があります。
非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)は、肥満や糖尿病などの生活習慣病に関連して発症する肝炎です。肝臓に異常に蓄積した脂肪が炎症を引き起こし、疲労感や腹部の不快感などの症状が現れます。
NASHは、肝硬変や肝臓がんなどの深刻な疾患を合併する恐れがあります。合併症を予防するためには、不規則な生活習慣の改善や早期治療が重要です。NASHの治療法は、食事療法や運動療法、薬物療法などです。治療効果が得られず症状が悪化した際は、肝移植を行う場合もあります。
医師と相談し自身に合った治療を受け、症状の改善を目指しましょう。
NASHは初期段階で症状に気づくのが難しいため、定期的な健康診断や肝機能モニタリングが早期発見・早期治療の鍵となります。
アルコール性肝障害
知っておくべき肝臓の病気に、アルコール性肝障害があります。アルコール性肝障害とは、多量のアルコールを長期間にわたり摂取し、肝臓が損傷を受ける疾患の総称です。
多量飲酒によりアルコール代謝の過程で生成される有害物質が肝細胞を傷つけ、炎症を引き起こします。肝臓が炎症を起こすと、肝機能が低下し、以下の症状が現れます。
- 全身倦怠感
- 食欲不振
- 体重減少
- 黄疸(皮膚や目が黄色くなる)
- 腹水、浮腫(むくみ)
アルコール性肝障害は、以下3つの状態に分けられます。
| 進行度 | アルコール性脂肪肝(初期) | アルコール性肝炎(中期) | アルコール性肝硬変(末期) |
| 状態 | 肝臓に脂肪が蓄積している状態 | 肝臓に炎症が生じ、肝細胞が破壊された状態 | 肝臓の組織が線維化し硬くなり、正常な機能が失われた状態 |
アルコール性肝障害を予防するためには、飲酒量を適度に抑えることが最も重要です。厚生労働省の「健康日本21(アルコール)」によると、適度な飲酒量は1日平均純アルコールで約20gで、具体例は以下のとおりです。
| お酒の種類 | 純アルコール量 |
| ビール中瓶1本(500ml) | 20g |
| 清酒1合(180ml) | 22g |
| ウイスキー(60ml) | 20g |
| 焼酎35度1/2合(90ml) | 25g |
| ワイン2杯(240ml) | 24g |
飲酒の頻度や量を減らすと、肝臓への負担が軽減され、肝障害のリスクが低下します。治療する際はアルコールを完全に断ち、肝臓の損傷部位を回復させるとともに、栄養療法や薬物療法を行います。
アルコール性肝障害は、生活習慣の見直しで予防できる疾患です。健康的な飲酒習慣を心がけたり、定期的に健康診断を受けたりし、早期発見・早期治療を目指しましょう。
肝硬変
慢性肝炎が長期化すると、肝臓の組織が線維化し硬くなり、肝硬変になります。肝臓は再生力が高い臓器ですが、肝硬変になると肝機能を元の状態に戻すのが難しくなるため、早期発見・早期治療が重要です。
肝硬変の主な症状は以下のとおりです。
- 足がむくむ
- 腹水がたまる
- 黄疸が出る
- 腹部静脈が盛り上がる
- 意識障害が起こる
初期の肝硬変は、症状に気づきにくいのが特徴です。健康診断で異常を指摘されたら、症状がなくても病院を受診しましょう。
自己免疫性肝疾患
自己免疫性肝疾患とは、自己免疫反応が原因で肝臓が障害される病気の総称です。主に自己免疫性肝炎、原発性胆汁性肝硬変、原発性硬化性胆管炎の3つがあります。
| 自己免疫性肝炎(AIH) | 原発性胆汁性肝硬変(PBC) | 原発性硬化性胆管炎(PSC) |
|
50歳から60歳代の中年以降の女性 ※若い女性や小児でも発症する場合あり |
中年以降の女性に多い ※50歳代が最も多い |
20歳代と60歳代 |
| 自己免疫反応により肝細胞が攻撃され慢性肝炎を引き起こす | 細い胆管が慢性的な炎症により破壊され、肝臓に胆汁が停滞して、肝臓の細胞が障害される | 臓内外の胆管が障害され胆汁の停滞が起こり、肝臓に炎症を引き起こす |
自己免疫性肝疾患は、発症メカニズムが完全に解明されておらず、遺伝的要因や環境要因が関与していると考えられています。
肝臓が悪いとどんな症状が出る?セルフチェック項目
肝臓が悪いと出現する症状が現れていないか、以下の表でセルフチェックをしてみましょう。
| チェックポイント | 理由 |
| 顔や体の皮膚が黄色い | 黄色い色素のビリルビンが正常に処理されず体内に蓄積されるため |
| 白目が黄色く濁っている | |
| 鼻の頭に赤みを帯びている | 肝臓が正常に機能せずホルモン異常が起き、クモ状血管腫が増えるため |
| 手の平に赤みを帯びている | 肝臓が正常に機能せず、血管拡張作用のあるエストロゲンが処理されなくなるため |
セルフチェックの項目に当てはまる場合は、肝臓が悪くなっている可能性を考え、早めに医療機関を受診するのが得策です。症状には個人差があるため、セルフチェックだけで病気の発症の有無を判断しないよう注意しましょう。
肝臓が悪い場合は、栄養療法や薬物療法で治療を行うのが一般的ですが、再生治療も選択肢の1つです。肝機能の改善を目指すために、自身に合った治療法を医師と相談したうえで検討しましょう。
定期的な血液検査で肝臓の数値をチェックしよう
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、病気が進行しても自覚症状が現れにくい特徴があります。そのため、肝臓の不調を早期に発見するためにも、健康診断などで定期的な血液検査を行いましょう。
血液検査では、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTPなどの数値を確認し、肝臓の状態を把握します。
肝機能に異常がある場合、数値の変化として現れることが多く、脂肪肝や肝炎、肝硬変といった疾患の兆候を早期に見つけられます。
早期治療ができるよう、定期的に健康診断を受け、血液検査で肝臓の数値を確認しましょう。
予防や生活習慣の改善も大切
肝臓の病気を予防するためには、生活習慣の改善も大切です。以下の3つの生活習慣を参考に、自身の日常生活を振り返りましょう。
- 食事のバランスを整える
- 適度な運動を行う
- 休肝日をつくる
肝臓の病気は、生活習慣と密接に関わっています。肝臓が悪くならないよう、改善できる生活習慣から見直すことが大切です。
食事のバランスを整える
肝機能を向上させるためには、食事のバランスが重要です。主食・主菜・副菜を揃えた食事を心がけると、バランスの良い食事になります。
炭水化物はエネルギー源となり、日常の活動を支えます。タンパク質は、筋肉や臓器の修復・成長に必要不可欠です。ビタミンやミネラルは、体の機能を正常に保つために大切です。
家で健康的な食事を心がけていても、外食時に栄養バランスが崩れる場合があるため注意してください。
たとえば、ラーメンやカレーライスなどの単品料理は、主食と主菜は満たしますが、副菜が不足します。サラダや野菜スープなどを追加し、副菜も摂取できるよう工夫しましょう。
適度な運動を行う
肝機能の改善や健康維持には、適度な有酸素運動が非常に効果的です。適度な運動を行うと、肝臓に蓄積した脂肪の減少が期待できます。
有酸素運動とは、ウォーキングやジョギングなどです。有酸素運動を毎日30分以上行い、肝機能の改善や筋肉量の維持を目指しましょう。
筋肉は糖質代謝やアンモニア代謝をつかさどり、肝臓の機能を補完する役割があります。肝臓病患者にとって筋肉の維持は、肝臓の負担を軽減し、肝機能の向上につながるため大切です。
また、有酸素運動はストレスの軽減にも効果があります。通勤や日常生活にウォーキングを取り入れると心身の健康に良い影響を与えます。
休肝日をつくる
肝臓が悪くならないよう休肝日をつくりましょう。休肝日(きゅうかんび)は、週に1日以上飲酒しない日を設け、肝臓を休めることを目的としています。
習慣的な飲酒は依存性を高め、飲酒量が増加する危険性があります。休肝日を設け、飲酒総量を減少させると、肝障害を予防できる可能性があります。
肝臓の症状に気づいたら早めに医療機関を受診しよう
肝臓の症状に気づいたら早めに医療機関を受診しましょう。
肝臓は沈黙の臓器と言われ、悪くなっても症状の自覚が難しく、発見が遅れやすいのが特徴です。肝機能の悪化でどんな症状が出るのか事前に知っておくと、病気の早期発見が可能です。
肝臓が悪くなった場合の治療法には、栄養療法や薬物療法、再生医療などがあります。医師と相談し、自身に合った治療法の選択が大切です。
体に異変を感じたらすぐに医療機関を受診し検査を受けるのが大切です。定期的に健康診断や受診に行き、早期発見・早期治療を目指しましょう。

監修者
渡久地 政尚
Masanao Toguchi
医師
略歴
1991年3月琉球大学 医学部 卒業
1991年4月医師免許取得
1992年沖縄協同病院 研修医
2000年癌研究会附属病院 消化器外科 勤務
2008年沖縄協同病院 内科 勤務
2012年老健施設 かりゆしの里 勤務
2013年6月医療法人美喜有会 ふたこクリニック 院長
2014年9月医療法人美喜有会 こまがわホームクリニック 院長
2017年8月医療法人美喜有会 訪問診療部 医局長
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 院長