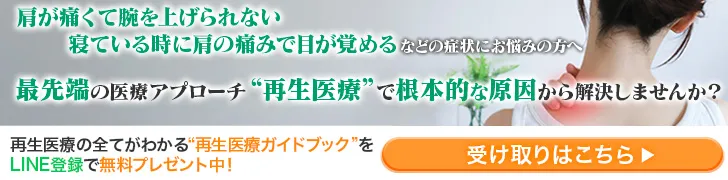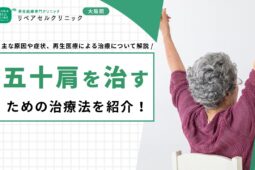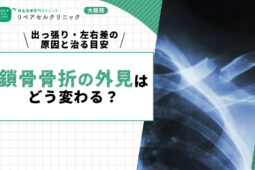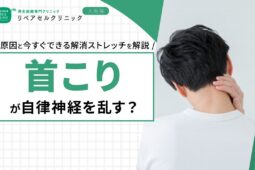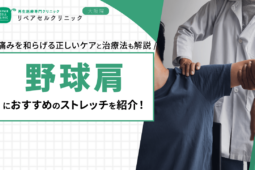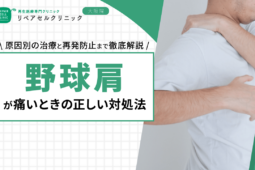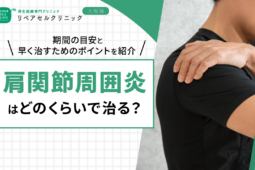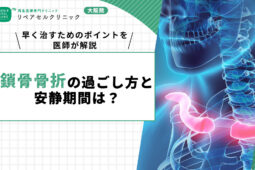- 再生治療
- 腱板損傷
- 肩
肩に力が入らない原因とケガ・病気について解説!発症のきっかけは?
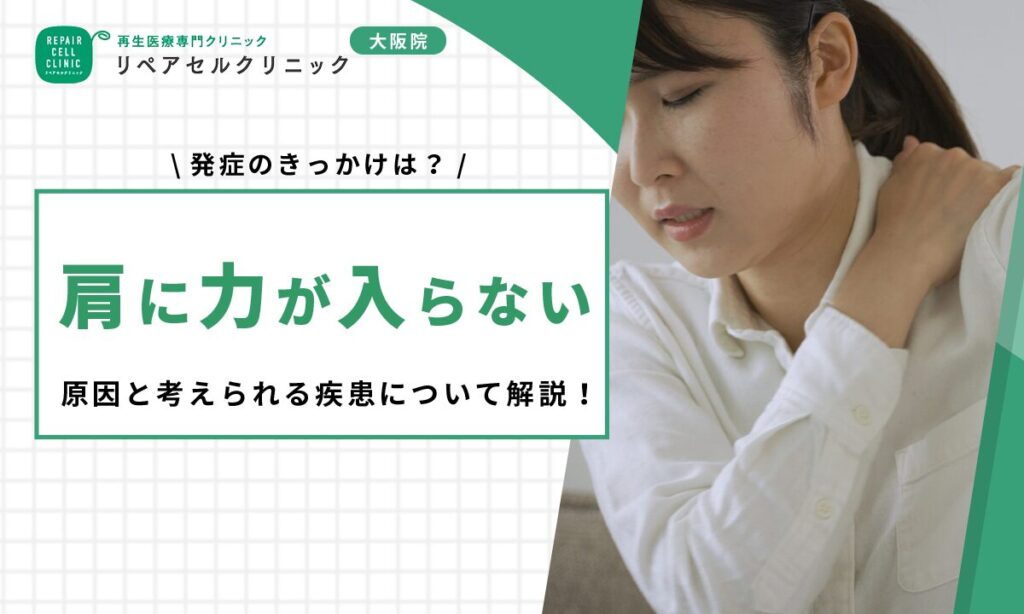
肩に力が入らず、医療機関で受診しても改善が見られないまま、強い痛みや機能障害に悩む方も多いかと思います。
肩の痛みは日常生活においても不便なことも多いため、早く治したいという焦りもあるでしょう。
この記事では、肩に力が入らない原因と、ケガや病気について解説していきます。
投薬治療やリハビリテーション療法でも改善が見られない場合、手術療法を行う可能性があります。
肩の痛みを早く治したい方は、再生医療も選択肢の一つです。
以下のページでは、当院の再生医療によって肩の痛みが改善した症例を紹介しているため、併せて参考にしてください。
>再生医療による肩関節の症例はこちら
目次
肩に力が入らない原因
肩に力が入らなくなる原因は、主に以下の内容が考えられます。
- 肩の使いすぎ
- 事故による負傷
- 転倒
- 腱板組織の損傷や断裂
肩に力が入らない症状は、日常生活からスポーツまで幅広い場面で発生する可能性があります。過度な肩の使用により筋肉や腱に疲労が蓄積し、炎症や微細な損傷が生じることで筋力低下が起こるものです。
外傷性の原因では、転倒時に肩を直接打撲したり、手をついて転倒した際の衝撃が肩関節に伝わることで組織が損傷します。とくに肩関節を安定させるのに重要な腱板が損傷・断裂すると、肩を挙上する動作に必要な筋力が発揮できず、力が入らない状態となるのです。
これらの原因により生じる症状の程度や治療方針は、損傷の範囲や患者の年齢、活動レベルによって大きく異なります。そのため、適切な診断と治療が重要です。
肩に力が入らない原因となるケガ・病気
肩に力が入らない原因となるケガや病気は以下のとおりです。
| 疾患名 | 症状・特徴 |
| 肩腱板損傷 |
|
| 肩腱板断裂 |
|
| 肩関節周囲炎(五十肩) |
|
| 変形性肩関節症 |
|
| 石灰沈着性腱板炎 |
|
| 反復性肩関節脱臼 |
|
それぞれのケガや病気について詳しく解説していきます。
肩腱板損傷
| 原因 | 症状 | 治療法 |
| 外傷・加齢 | 肩の痛みと可動域制限 | 保存療法・手術療法・再生医療 |
肩腱板損傷は、スポーツによる肩の酷使、外傷、加齢などが原因で発症します。
発症のメカニズムは主に2つあります。
1つ目は、スポーツや重労働で肩を繰り返し使うことで腱板に負担がかかり損傷するケースです。
2つ目は、加齢により肩甲骨の突起部分(肩峰)に骨のとげ(骨棘)ができるケースです。腕を動かすたびに腱板とこすれ合って炎症を起こし、徐々に腱板が擦り切れていきます。
どちらも腱板という肩の動きに重要な組織が傷つくことで、肩の痛みや力の入らない症状が現れます。
肩腱板断裂
| 原因 | 症状 | 治療法 |
| 外傷・加齢 | 肩の痛みと可動域制限 | 保存療法・手術療法・再生医療 |
肩腱板断裂は肩を強く打った、肩をぶつけたなどの外傷や、加齢により自然に腱板が切れてしまうことがあります。
四十肩、五十肩と勘違いされやすいので、痛みが長引く場合は病院に行って詳しい検査をしましょう。
肩関節周囲炎(五十肩)
| 原因 | 症状 | 治療法 |
| 加齢・運動不足・糖尿病 | 肩の痛みと可動域制限 | 薬物療法・リハビリ・手術療法・再生医療 |
肩関節周囲炎は、一般的に五十肩と呼ばれる疾患で、肩関節の滑膜や関節包に炎症が起き、肩が硬くなることが特徴です。
加齢が主な原因とされていますが、運動不足や糖尿病などの基礎疾患が原因で発症することもあります。
変形性肩関節症
| 原因 | 症状 | 治療法 |
| 加齢・関節リウマチ | 肩の痛みと可動域制限 | 薬物療法・リハビリ・手術療法・再生医療 |
変形性肩関節症は、肩関節の軟骨がすり減って骨が変形し、痛みや可動域制限が引き起こされる疾患です。
変形性肩関節症は肩の酷使や加齢、軟骨や周囲の組織の損傷によって発症しますが、肩を動かすときにゴリゴリとこすれるような音が出るのも特徴のひとつです。
石灰沈着性腱板炎
| 原因 | 症状 | 治療法 |
| 腱板へのリン酸カルシウムの沈着 | 激しい肩の痛み、可動域制限 | 保存療法・体外衝撃波療法・手術療法・再生医療 |
石灰沈着性腱板炎は、肩の腱板にカルシウムの結晶である石灰が沈着する原因不明の疾患です。
石灰沈着性腱板炎には急性期と慢性期があり、急性期では激しい痛みで肩を動かすことも困難となります。慢性期では肩を動かした際の痛みやひっかかりなどの症状が出るのが特徴です。
反復性肩関節脱臼
| 原因 | 症状 | 治療法 |
| 初回脱臼時の損傷 | 肩の痛みと可動域制限、肩の不安定感 | 保存療法・手術療法 |
一度脱臼すると再発を繰り返しやすくなる疾患が、反復性肩関節脱臼です。
ラグビーやアメフトなどの激しいスポーツや転倒時に初回脱臼が起こり、その後は寝返りや軽い動作でも再び脱臼してしまうのが特徴です。
とくに10代の若年層は関節や軟部組織の柔軟性が高いことが原因で、脱臼を繰り返すこともあります。
肩に力が入らないケガ・病気の予防策
肩に力が入らない状態を防ぐためにできる予防策を紹介します。
- スポーツの前に準備運動をする
- 適度に休憩を取る
- 正しい歩き方で転倒を防止する
スポーツの前に準備運動をして肩周りの筋肉を十分にほぐし、関節の可動域を広げることで急激な負荷による損傷を予防できます。
また、運動中や仕事中は定期的な休憩を取り、同じ動作の繰り返しによる肩の使いすぎを防ぐことが大切です。
高齢者や運動習慣のない方は、段差での転倒や滑りやすい場所での事故に注意し、肩の外傷を防ぐよう心がけましょう。
肩に力が入らないケガ・病気の主な治療法
肩に力が入らない症状に対する治療法は、主に以下の4つです。
これらの治療法は単独で行う場合もあれば、症状に応じて組み合わせて実施することもあります。
投薬治療
投薬治療では、関節内注射や消炎鎮痛剤などの内服が行われます。
また、トリガーポイント注射と呼ばれる、痛みがある部位に局所的に行う注射を検討される場合もあります。
筋肉が緊張しているケースでは筋弛緩剤が処方されますが、筋弛緩剤は副作用が出る場合がありますので注意が必要です。
薬物療法は痛みや炎症を抑える効果がありますが、主に症状の軽減を目的とした治療法です。根本的な回復には、他の治療法との組み合わせが必要になるケースが多くあります。
リハビリテーション療法
リハビリテーション療法では、次のような取り組みで肩に力が入らない症状の改善を目指します。
- 肩の可動域を広げる運動
- 肩関節の安定性を向上させるための筋力トレーニング
- 日常生活での肩の動かし方の指導
これらのトレーニングで肩の筋力を高め、日常的な負荷に耐えられる肩を作ります。
肩のトレーニングでは、かける負荷と運動量が重要です。無理なトレーニングを行うと効果が減ってしまうほか、症状が悪化する可能性があります。
専門家の指導の下、適切なリハビリを続けましょう。
手術療法
投薬治療やリハビリテーション療法の効果が感じられなかった方や、症状が重い方には手術療法が検討されます。
症状の程度によって、関節鏡手術や直視下手術などの方法が選ばれます。
関節鏡手術は体に小さな穴を開けて手術する方法で、身体への負担が少ないのが特徴です。
一方、直視下手術は皮膚を大きく切開して直接患部を確認しながら行う手術で、複雑な損傷や大規模な修復が必要な場合に選択されます。
再生医療
肩の痛みの治療には再生医療という選択肢もあります。
再生医療の幹細胞治療は、患者さま自身の幹細胞を培養し、損傷した患部に投与する治療法です。
入院・手術が不要なため、手術後の再発リスクを軽減したいという方には、再生医療が適している場合があります。
当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、簡易オンライン診断を行っております。気になる肩の症状がある方は、お気軽にお試しください。
肩に力が入らないときはすぐに医療機関を受診しよう
肩に力が入らない原因は、肩の使いすぎや外傷、腱板損傷など多岐にわたり、肩腱板断裂や五十肩などさまざまな疾患が関与している可能性があります。
症状が現れた際は早期の医療機関受診が重要です。
肩の痛みの治療としては、再生医療も選択肢の一つです。
再生医療なら手術が必要ないため「肩の痛みを治したいけど手術は避けたい」とお考えの方でも、適している可能性があります。
当院「リペアセルクリニック」では、肩の痛みにお悩みの方からのご相談を承っております。気になる症状がある場合は、お気軽にお問い合わせください。

監修者
坂本 貞範
Sadanori Sakamoto
医療法人美喜有会 理事長
「できなくなったことを、再びできるように。」
人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの
お手伝いができれば幸甚の至りでございます。
略歴
1997年3月関西医科大学 医学部卒
1997年4月医師免許取得
1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務
1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務
1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務
1999年2月国立大阪南病院 勤務
2000年3月野上病院 勤務
2003年3月大野記念病院 勤務
2005年5月さかもとクリニック 開設
2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任
2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設
2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設