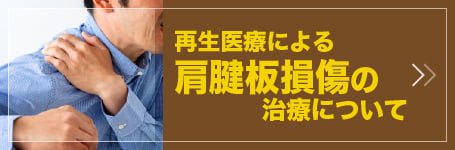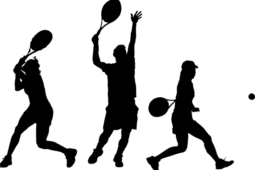肩腱板損傷にサポーターは有効?それとも使わないほうが良い?
目次
肩腱板損傷にサポーターは有効?それとも使わないほうが良い?
肩腱板損傷で肩に痛みがあったり、腕が上がらなかったりすることで悩んでいる人のなかにはサポーターをつけることで対策をしている人もいると思いますし、これからサポーターをつけようかなと考えている人もいるでしょう。
そこで今回は、肩腱板損傷にサポーターをつけることは有効か、使用してもいいのかどうかについて解説します。

肩腱板損傷でサポーターを使うことはあまりおススメできません
肩腱板損傷になると、思うように腕や肩を動かすことができません。無理に動かそうとすると痛みが生じますからつらいですよね。
そこで、サポーターを使用する人が多いのですが、肩腱板損傷でサポーターをつけることは、あまりおススメできません。その理由について、以下で詳しく解説します。

サポーターで肩腱板損傷の症状を和らげることは可能です
サポーターを付けることで、必要以上に関節や筋肉が動くことを防いで損傷部分への負担が分散されますし、サポーターをつけることで関節を動かしやすくする効果も期待できます。
ですから、肩が思うように動かせなかったり、痛みがあったりするけれど、仕事や作業などでどうしても動かす必要があるという時にサポーターを使用するのは有効といえるでしょう。
肩腱板損傷はサポーターで治ることはない
肩腱板損傷にサポーターを使用すると、一時的に痛みが軽減され、動かしやすくなる効果が期待できます。しかし、サポーターを付けたからといって肩腱板損傷自体が治るわけではありません。
サポーターを使用することで症状が楽になるからと無理をしてしまうと、損傷している部分が断裂するなど、症状が悪化してしまう可能性があります。
サポーターの常時使用は控えるべき!
サポーターを使用することで肩腱板損傷の症状が和らぐのであれば、常時使用したいと考える人もいると思います。
しかし、サポーターを常時使用してしまうと、肩の筋肉や関節が使われなくなることで硬くなってしまう、筋力が低下するなどの問題も出てきます。
周辺の筋肉や関節が硬くなってしまうと、損傷部分にさらに大きな負担がかかって症状が悪化してしまうので、周辺の筋肉や関節は適度に動かしておく必要があります。
このような理由から、サポーターは補助的な役割として使用し、常時使用は控えたほうが良いです。
まとめ・肩腱板損傷にサポーターは有効?それとも使わないほうが良い?
肩腱板損傷にサポーターは有効かどうかについて解説しました。
サポーターは肩腱板損傷の症状を和らげる効果が期待できます。しかし、常時使用していると逆に症状を悪化させてしまうこともありますから、使用の仕方については十分気を付けてくださいね。
監修:リペアセルクリニック大阪院
| こちらも併せてご参照ください 目次1 肩腱板損傷はテーピングで痛みが和らぐものの注意が必要1.1 肩腱板損傷にテーピングをして症状を和らげることは「可能」です!1.2 肩腱板損傷にテーピングをしても治るわけではありません1.3 肩腱板損傷でのテーピン […]
|