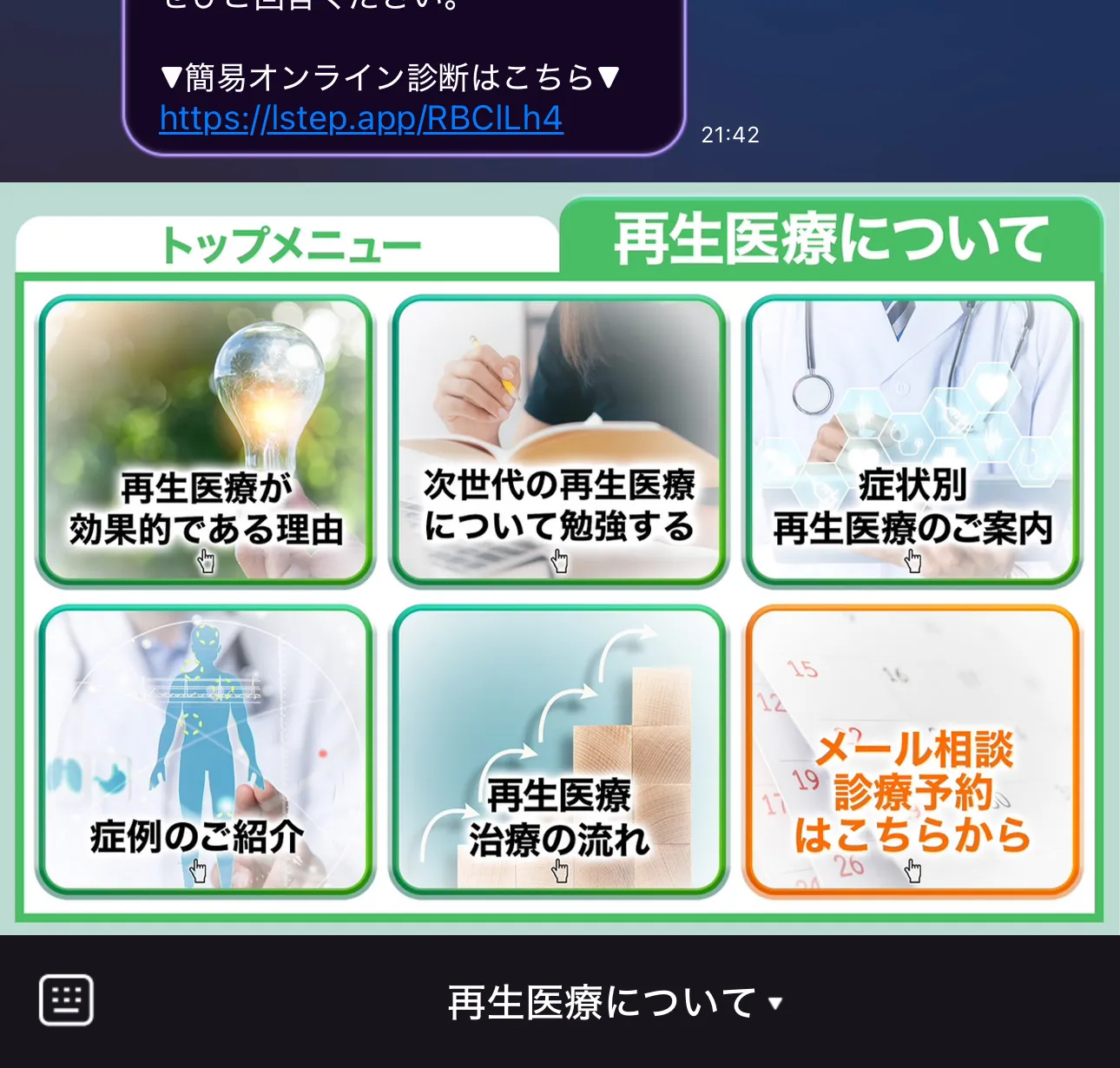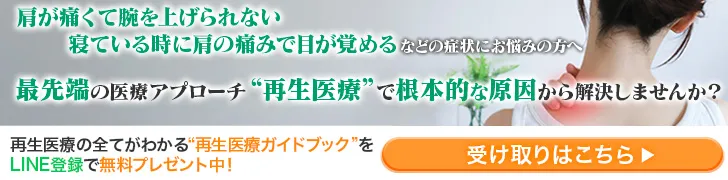インピンジメント症候群の手術後の痛みと回復期間について紹介
公開日: 2019.05.08更新日: 2025.06.30
インピンジメント症候群の手術後に、痛みが残る・動きが戻らないと不安を感じている方もいらっしゃるかと思います。
結論、インピンジメント症候群の手術後には一定期間の痛みと機能制限がみられるのが通常です。
術後の肩の痛みや違和感は回復過程において、一般的に起こりうる症状です。
本記事では、術後の回復期間や経過についてわかりやすく解説します。
回復を早めるためのポイントについても紹介していくので、安心して日々を過ごすためにぜひ参考にしてみてください。
また当院リペアセルクリニックの公式LINEでは、インピンジメント症候群の手術後の症状に不安を持つ方に向けて、再生医療の症例や治療内容を紹介しています。
従来の治療方法で改善が見られなかった方や、先進医療での治療を検討したい方はぜひご確認ください。
目次
インピンジメント症候群の手術後の痛みと回復期間について
インピンジメント症候群の手術後には、一定期間の痛みと機能制限がみられるケースが多いです。
術後も肩の痛みや違和感を感じることで不安を抱くことが多いですが、それらは回復過程において一般的に起こりうる症状です。
特に術後1〜3ヶ月の期間には、関節周囲の組織が修復過程にあるため、痛みや可動域の制限が持続することが多くみられます。
インピンジメント症候群とは、肩関節周辺の腱板や滑液包が肩峰(けんぽう)などの骨性構造に衝突(インピンジ)することで、炎症や損傷を引き起こす状態です。
手術の目的は、肩峰下に存在する摩擦を取り除き、滑らかな動作を回復することにありますが、術後の回復には個人差があり、焦らず段階的にリハビリを進めることが重要です。
インピンジメント症候群の術後の経過の進み方の例
インピンジメント症候群の術後の経過の進み方の例は、以下の通りです。
下記では経過について詳しく紹介していくので、ぜひ参考にしてみてください。
術後1ヶ月以内
術後1ヶ月以内は、炎症を抑えながら痛みの管理を行う時期です。
この時期には、肩の固定やアイシング、消炎鎮痛剤の使用が推奨されることが多く、日常生活においても無理のない範囲での動作に制限されます。
- 主な目的:痛みの緩和と炎症の抑制
- リハビリ内容:軽度の振り子運動や可動域維持のための運動
急性期のリハビリは炎症を悪化させないことが最優先であり、痛みのケアを行うことが重要です。
術後1~3ヶ月
術後1〜3ヶ月は、肩関節の可動域を少しずつ広げていく時期です。
この時期になると痛みが徐々に軽減される一方で、動かすことでの不快感が残る場合があります。
- 主な目的:可動域の改善
- リハビリ内容:自動運動(自ら動かす運動)や軽負荷の筋力トレーニング
この時期は理学療法士による個別対応が推奨されており、この段階での取り組みが中長期的な回復に大きく影響するとされています。
術後3〜6ヶ月
この時期は、社会復帰やスポーツ再開を視野に入れた応用的な訓練を開始するフェーズです。
肩関節の安定性と機能性を向上させることで、日常生活への影響を最小限に抑えます。
- 主な目的:機能的動作の改善と復帰準備
- リハビリ内容:抵抗運動・動作訓練(荷物を持つ・上げ下げなど)
この時期でも痛みが残る場合には、リハビリ内容の見直しや医師の再診が必要になることがあります。
回復を早めるためのポイント
回復を早めるためには、医療機関でのリハビリだけでなく、自宅でのセルフケアも重要です。
以下は、回復を促進する具体的なポイントとなります。
- 毎日一定時間の自主リハビリ(軽いストレッチや振り子運動)を継続する
- 睡眠と栄養の質を高め、筋肉と組織の修復を促進する
- 痛みが増す場合は無理をせず、すぐに医師や理学療法士に相談する
回復には、生活習慣や心理面も含めた総合的な取り組みが求められます。
また心理的な不安を抱えやすい術後には、信頼できる医師に相談すると、安心感を得られメンタルケアにも繋がります。
再発防止のための再生医療という選択について
再発を防ぐための手段として、再生医療は近年注目を集めている選択肢です。
再生医療とは、損傷した組織の修復や再構築を目指す医療技術であり、主に細胞治療・遺伝子治療・組織工学の3つのアプローチがあります。
中でも整形外科領域では、自己脂肪由来幹細胞を用いた細胞治療が実用化されつつあります。
リペアセルクリニックが提供している治療法では、患者自身の脂肪から抽出した幹細胞を体内に再注入することで、炎症の抑制や組織の再生を促進します。
これにより、術後に残る慢性痛・可動域制限・筋力低下などに対し、従来のリハビリや薬物療法とは異なるアプローチで効果が期待されます。
手術を再度行うことなく、回復を促進・再発を予防できる可能性があるので、ぜひ再生医療を検討してみてください。
手術をしない新しい治療「再生医療」を提供しております。
インピンジメント症候群の手術後は回復を早めるセルフケアが重要
インピンジメント症候群の手術後の回復には、患者自身の積極的なケアが欠かせません
日常生活の中でできるセルフケアは、術後の経過を良好に保つために重要な役割を果たします。
【回復を早めるセルフケア】
- リハビリ運動を無理のない範囲で毎日継続する
- 日常動作の中で肩を冷やさない・過度な負荷を避ける
- ストレスや不安を軽減するため、必要に応じてカウンセリングを利用する
上記の取り組みとあわせて、回復の質を高めたい方には再生医療の活用も選択肢となります。
特に、リペアセルクリニックが提供する幹細胞治療は、術後の慢性痛や可動域の改善を目指す方にとって注目すべき手段です。
リペアセルクリニックでは、患者自身の脂肪から抽出された幹細胞を用い、患部の炎症軽減と組織修復を促進します。
また医師による丁寧なカウンセリングと、術後の回復状況に応じた個別対応により、「自分に合ったケアを受けたい」方にとって、信頼できる選択肢となります。
再生医療と日常的なセルフケアを組み合わせることで、術後の生活をより前向きで快適なものにしていくことが可能です。
インピンジメント症候群の手術後の痛みや違和感に不安を感じている方は、ぜひリペアセルクリニックの無料カウンセリングを検討してみてください。

監修者
坂本 貞範
Sadanori Sakamoto
医療法人美喜有会 理事長
「できなくなったことを、再びできるように。」
人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの
お手伝いができれば幸甚の至りでございます。
略歴
1997年3月関西医科大学 医学部卒
1997年4月医師免許取得
1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務
1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務
1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務
1999年2月国立大阪南病院 勤務
2000年3月野上病院 勤務
2003年3月大野記念病院 勤務
2005年5月さかもとクリニック 開設
2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任
2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設
2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設