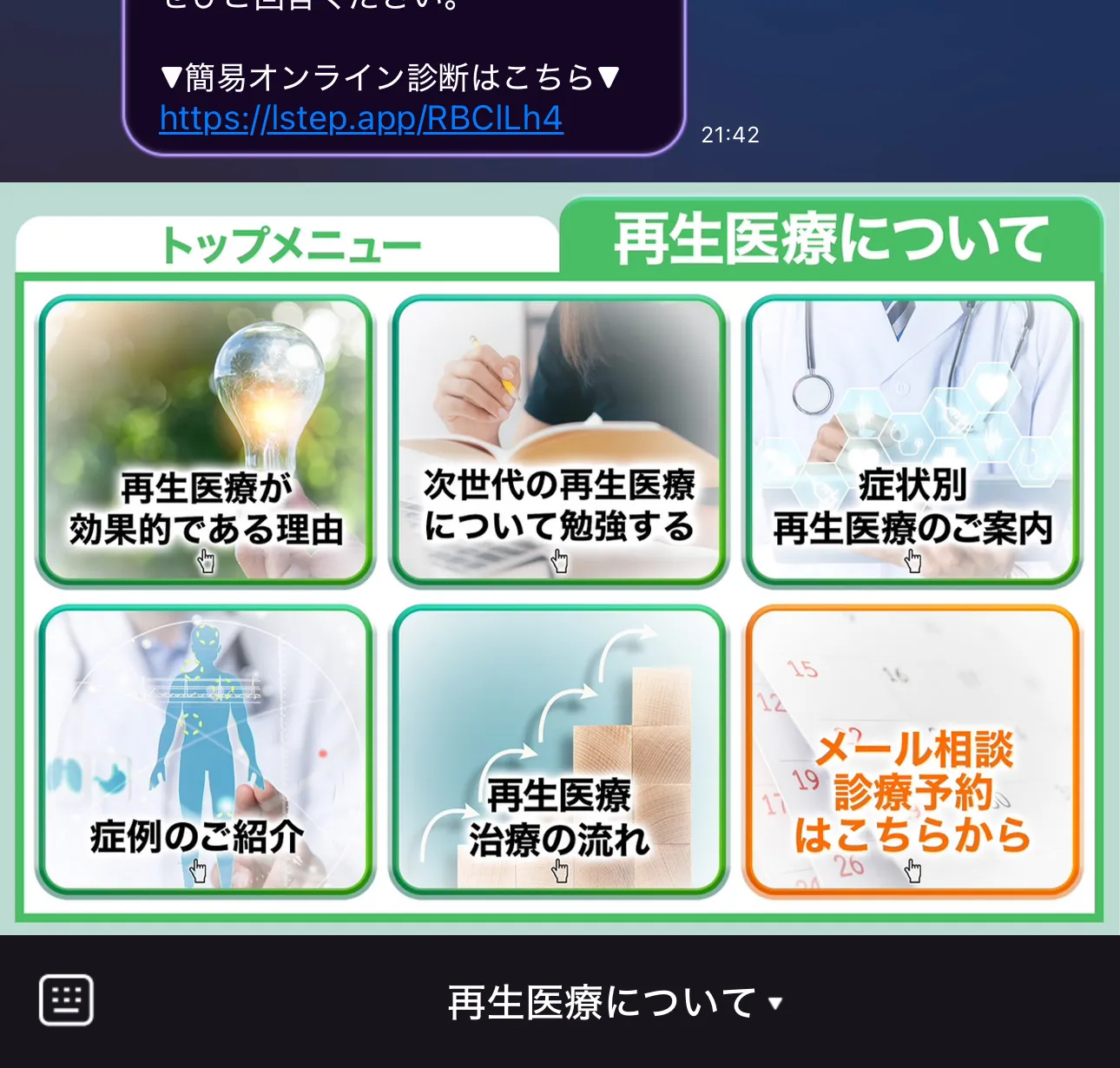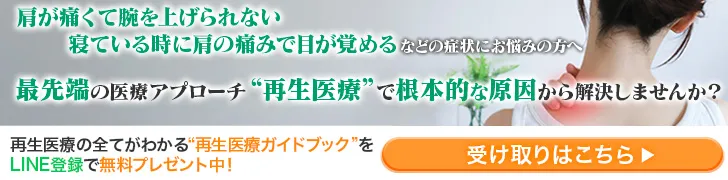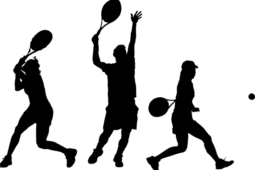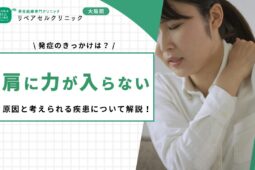腱板損傷の原因とは?対策法についても医師が解説
公開日: 2020.02.19更新日: 2025.06.02
「肩を動かすと痛い」「夜になるとズキズキして眠れない」といった、肩の不調が続いている場合、腱板損傷が原因かもしれません。
腱板損傷は40代以降に発症しやすいとされており、日常の些細な動作や加齢による変化でも引き起こされることがあります。
しかし「肩の痛みの原因って何があるの?」「腱板損傷ってどんな症状?」「どうすれば予防できるの?」と、疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、腱板損傷の主な原因だけでなく、症状が進行する前に早期発見・予防につなげる方法も解説しています。
腱板損傷は放置すると腱板断裂に進行するリスクもあり、日常生活に大きな支障をきたす恐れがあります。
「もしかして自分も腱板損傷かも」と感じている方は、ぜひ本記事を参考に、早期発見と適切な対処を行いましょう。
目次
腱板損傷の原因とは|使いすぎ(オーバーユース)に注意が必要
腱板損傷は、以下のような原因によって引き起こされます。
腱板損傷の詳細については、以下の記事でも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
加齢性変化(年齢)
腱板損傷の原因のひとつが、加齢による腱の変性(老化)です。
腱板は、肩甲骨と上腕骨をつなぐ4つの筋肉(棘上筋・棘下筋・小円筋・肩甲下筋)から構成されており、肩の安定性とスムーズな動作を支える重要な組織です。
しかし年齢を重ねると、以下のような組織の変化が起こります。
- コラーゲン繊維の弾力性が低下
- 血流が悪化し、栄養や酸素の供給が不十分に
- 腱自体がもろくなり、損傷しやすくなる
その状態で肩を使い続けると、日常の動作や軽い作業でも腱に小さな損傷が蓄積し、やがて断裂につながることがあります。
また腱板は40代から少しずつ傷みやすくなり、加齢とともに誰にでも腱板損傷を起こる可能性(※)があるので注意しましょう。
※参照:MSDマニュアル「肩腱板損傷」
初期の段階では「肩に違和感がある」「少し痛む」といった症状にとどまることもありますが、進行すると夜間痛や腕の可動制限など、日常生活に支障をきたすケースも少なくありません。
加齢に伴う腱板の劣化の場合は、日頃からストレッチや適度な運動を心がけることで、ある程度予防が期待できます。
外傷性(転倒・打撲・事故など)
腱板損傷は加齢や使いすぎだけでなく、転倒・打撲・交通事故などの外傷が原因で突然発症するケースもあります。
このような外傷性の腱板損傷は、発症直後から痛みが強く、腕が上がらない・力が入らないといった症状が急激に現れるのが特徴です。
また以下のような状態が見られる場合は、早めに整形外科を受診し、身体診察・MRIなどで状態を確認することが大切です。
- 安静にしていても痛みが引かない
- 内出血や腫れがある
- 肩の動きに明らかな制限がある
外傷をきっかけにした腱板損傷は早期発見と早期治療が重要になるので、自己判断せずに速やかに医療機関へ受診しましょう。
オーバーユース(繰り返しの動作・スポーツ)
腱板損傷は、肩の使いすぎ(オーバーユース)によっても生じることがあります。
オーバーユースによる腱板損傷のリスクが高い動作・場面としては、以下のようなものが挙げられます。
- 野球やソフトボールの投球動作
- テニス・バドミントンなどのサーブやスマッシュ動作
- 重量物を頭上に持ち上げる動作
- 水泳のクロールなど、腕を頭より上に繰り返し動かす運動
※参照:MSDマニュアル「肩腱板損傷」
特にテニス、野球、水泳などの肩を頭より高く挙げた状態に保ったまま負荷をかけるため、腱板に強いストレスがかかります。
症状は、初めは軽い違和感や筋肉の張り程度であることが多いですが、そのまま使い続けると腱板断裂に進行するリスクもあるため、注意が必要です。
腱板損傷を防ぐための方法
腱板損傷を予防するために、日常生活の中で以下のような対策を意識してみましょう。
- 肩のストレッチ
- 適度な筋力トレーニング
- 同じ動作の繰り返しを避ける
腱板周囲の筋肉や関節が硬くなると、肩の動きに無理がかかり損傷のリスクが高まるのでストレッチで肩甲骨や肩関節の可動域を広げるようにしましょう。
また長時間の作業や肩に負担のかかるフォームに注意し、痛みが出たら無理に動かさず、休むことも大切です。
少し痛むだけだからと放置すると、炎症が進行して断裂に至るリスクもあります。
軽い痛みや動かしにくさを感じたら、整形外科を早めに受診し、画像検査(MRIやエコー)などで状態を確認しましょう。
腱板損傷に有効なトレーニング方法については、以下の記事でご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
【まとめ】腱板損傷の原因を知って早期発見・予防につなげよう
腱板損傷は、加齢による腱の変性(老化)・転倒や打撲などの外傷・肩の使いすぎなど、複数の要因が重なって発症します。
特に40代以降は腱板の組織が弱くなりやすく、日常の些細な動作でも損傷を起こすリスクがあります。
発症を防ぐためには、以下の点を意識しましょう。
- 肩の柔軟性を保つストレッチを取り入れる
- 適度な筋力トレーニングを行う
- 肩に違和感があれば早めに状態を確認する
肩の不調をそのままにしておくと、腱板断裂や痛みが強くなる・腕が上がらなくなるなど、日常生活に影響が出ることもあります。
気になる症状があれば、無理せず整形外科を受診し、早めに対処しましょう。
また当院(リペアセル)では症例などの情報に関する詳細についてLINEでも解説していますので、肩に違和感を感じている方は、ぜひ参考にしてください。

監修者
坂本 貞範
Sadanori Sakamoto
医療法人美喜有会 理事長
「できなくなったことを、再びできるように。」
人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの
お手伝いができれば幸甚の至りでございます。
略歴
1997年3月関西医科大学 医学部卒
1997年4月医師免許取得
1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務
1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務
1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務
1999年2月国立大阪南病院 勤務
2000年3月野上病院 勤務
2003年3月大野記念病院 勤務
2005年5月さかもとクリニック 開設
2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任
2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設
2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設