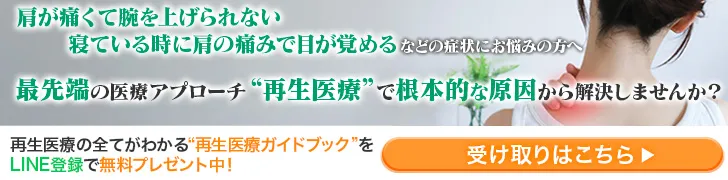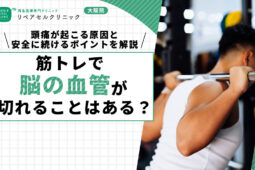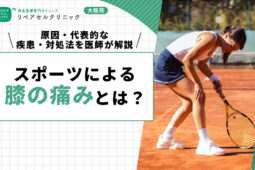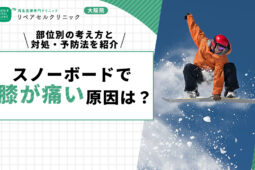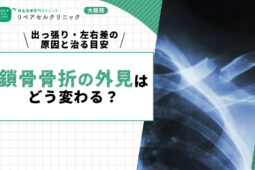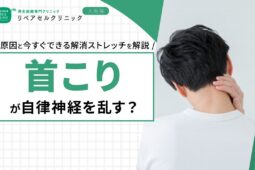- 肩
- スポーツ医療
野球選手に多い肩腱板損傷について解説!原因や治療法まで紹介

「投球時に肩が痛い」「肩腱板損傷と診断されたけど、本当に野球を続けられるのか」といった不安を抱えている野球選手の方も多いのではないでしょうか。
肩腱板損傷は、特に投手や外野手など肩を酷使するポジションの選手にとって避けて通れないケガの一つです。
しかし、正しい知識と適切な治療を受けることで、選手として再びマウンドやフィールドに立つことが可能です。
この記事では、野球選手の肩腱板損傷について、その原因から最新の治療法まで分かりやすく解説します。
野球をプレーしていて、現在肩の痛みで悩んでいる・肩腱板損傷と診断された方は、痛みを気にせずに競技を楽しむためにも、ぜひ参考にしてください。
目次
肩腱板損傷とは?野球選手に多い理由とその影響
肩腱板損傷とは、肩の動きを支える筋肉と腱(腱板)が傷ついた状態で、肩の痛みや運動障害を引き起こすケガです。
野球選手に肩腱板損傷が多い理由は、投球動作の特殊性と繰り返しの負荷にあります。
投球時には肩関節が極端な位置まで動かされ、腱板に大きな負担がかかるのが理由です。
肩腱板損傷により投球時の痛み、球速低下、制球力の悪化などが現れますが、早期の適切な対処により競技復帰の可能性を高められます。
野球選手が肩腱板損傷を予防するために取り入れるべきトレーニングとセルフケア
肩腱板損傷を予防するには、日常的なトレーニングとケアが何より重要です。
トレーニングとセルフケア方法として、以下をご紹介します。
これらの予防法を継続的に実践することで、肩腱板損傷のリスクを大幅に軽減できます。
肩甲骨周辺の強化・可動域アップ
肩甲骨周辺の筋肉を強化し、可動域を広げるストレッチを2つご紹介します。
肩甲骨はがしストレッチ
- 両手を肩の高さで前に伸ばし、手のひらを合わせる
- 息を吸いながら、両腕を大きく後ろに引く
- 肩甲骨を背骨から引き離すように意識する
- 息を吐きながら、ゆっくりと元の姿勢に戻る
- これを10回程度繰り返す
肩甲骨を背骨から引き離すように動かすストレッチです。
デスクワークなどで固まりがちな肩甲骨周りの筋肉をほぐし、柔軟性を高めます。
チューブローイング
- 床に座り、足を軽く伸ばす
- ゴムチューブを足の裏に引っ掛け、両端を握る
- 背筋を伸ばし、胸を張った状態を保つ
- 肘を曲げながら、チューブを身体の後ろに引く
- 肩甲骨を背骨に寄せるように意識する
- 10~15回を3セット行う
ゴムチューブを使って肩甲骨を内側に引き寄せる筋肉を鍛えるトレーニングです。
投球時の肩甲骨の安定性向上が期待できます。
フォーム改善と投球制限
正しい投球フォームの習得と適切な投球制限は、肩腱板損傷予防の基本です。
以下のポイントを意識して、投球フォームを見直しましょう。
- 肩甲骨を寄せて胸を張る姿勢を保つ
- 下半身の力を上半身に伝える動作を意識する
- 腕の振りは肩甲骨の動きと連動させる
- リリース後は自然な腕の振り下ろしを行う
腕だけでなく全身を使った投球動作を心がけることで、肩への負担を分散できます。
また適切な投球制限としては、以下の通りです。
| 年齢 | 1日の投球数目安 |
|---|---|
| 小学生 | 50球以下 |
| 中学生 | 70球以下 |
| 高校生 | 100球以下 |
年齢や体力に応じた投球数の管理は、オーバーユースによる肩腱板損傷を防ぐためにも欠かせませんので必ず守りましょう。
アイシング・ストレッチをしっかり行う
練習後は以下のようにアイシング・ストレッチをしっかり行いましょう。
- 投球直後から30分以内に開始する
- 氷嚢やアイスパックを肩に当てる
- 15~20分間継続する
- 皮膚を保護するタオルを間に挟む
- 血行が悪くなりすぎないよう注意する
投球後のアイシングは、肩関節の炎症を抑制し、腱板の回復を促進するため、適切な時間と方法で行うことが重要です。
また、肩関節と腱板の柔軟性を維持するため、肩甲骨はがしストレッチなどを日常的に行いましょう。
テーピングやサポーターの使用をする場合は、以下の記事をご覧ください。
肩腱板損傷の治療法
現在は以下の治療法があるため、肩腱板損傷の診断を受けても、決して諦める必要はありません。
治療法の選択は症状の程度や個人の状況によって決まりますが、どの方法でも多くの選手が競技復帰を果たしています。各治療法について詳しく見ていきましょう。
保存療法
保存療法は、手術を行わずに肩腱板損傷を治療する方法です。
保存療法では主に以下の3つのアプローチが組み合わせて行われます。
- 安静
- 薬物療法
- リハビリテーション
まず、損傷した腱板の回復を促すため、投球動作を一時的に中止しつつ、完全な安静ではなく日常生活に支障のない範囲での活動を継続しましょう。
次に、痛みや炎症を抑えるために主に消炎鎮痛薬による薬物治療が行われ、症状に応じて内服薬や外用薬が選択されます。
理学療法士の指導のもと、筋力強化・可動域訓練・投球動作の再習得などを含む段階的なリハビリテーションが実施され、競技復帰に向けて計画的に進められるのです。
手術
保存療法で改善が見られない場合や、肩腱板の完全断裂がある場合には手術が検討されます。
現在の主流は関節鏡視下手術と呼ばれる、切開が小さく体の負担が少ない手術です。
カメラを使って関節内を確認しながら、損傷した腱板を修復します。
復帰までの期間目安は以下のとおりです。
| 復帰期間の目安 | 活動内容 |
|---|---|
| 手術後6週間 | 固定期間、基本的な日常生活動作 |
| 3~6ヶ月 | 可動域訓練、筋力トレーニング |
| 6~9ヶ月 | 段階的な投球動作の再開 |
| 9~12ヶ月 | 競技復帰 |
手術後のスポーツ復帰には時間を要しますが、段階的なリハビリテーションにより、多くの選手が元のレベルまで回復できます。
再生医療
肩腱板の手術には、感染症や痛みの増加、運動制限の悪化などのリスクが伴います。
そこで手術を避けたい方に向けた新しい治療選択肢として注目されているのが、再生医療です。
再生医療の一つ、幹細胞治療では、患者さまの幹細胞を採取・培養して、患部に注射します。
幹細胞は体内の様々な種類の細胞に変化する能力があり、損傷部位に投与すると、必要とされる特定の細胞の種類へと変化するのが特徴です。
手術せずに野球に復帰したいという方は、選択肢の一つとして再生医療もご検討ください。
肩腱板損傷に対する再生医療についての詳細は、以下で解説していますのでぜひご覧ください。
肩の痛みは⼿術しなくても治療できる時代です。
【まとめ】野球を続けるためには肩腱板損傷は放置せずに早期治療を
肩腱板損傷の治療法選択は、損傷の程度、年齢、競技レベル、個人の希望など様々な要因を総合的に考慮して決定されます。
手術後の競技復帰には、以下の期間がおおよその目安とされています。
|
復帰期間の目安 |
活動内容 |
|---|---|
|
手術後6週間 |
固定期間、基本的な日常生活動作 |
|
3~6ヶ月 |
可動域訓練、筋力トレーニング |
|
6~9ヶ月 |
段階的な投球動作の再開 |
|
9~12ヶ月 |
競技復帰 |
貴重な競技生活を無駄にしないためにも、手術を避けたいという方は再生医療も一つの選択肢としてご検討ください。
幹細胞治療は、患者さまご自身の幹細胞を採取・培養し、損傷部位に注射することで、手術を行わずに自然な回復を促す治療法です。
身体への負担も比較的少なく、競技復帰を目指すことが期待できます。
治療法については、当院(リペアセルクリニック)の公式LINEでも詳細を解説していますので、ぜひ参考にして前向きに治療に取り組み、再び野球を楽しめる日を目指しましょう。

監修者
坂本 貞範
Sadanori Sakamoto
医療法人美喜有会 理事長
「できなくなったことを、再びできるように。」
人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの
お手伝いができれば幸甚の至りでございます。
略歴
1997年3月関西医科大学 医学部卒
1997年4月医師免許取得
1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務
1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務
1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務
1999年2月国立大阪南病院 勤務
2000年3月野上病院 勤務
2003年3月大野記念病院 勤務
2005年5月さかもとクリニック 開設
2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任
2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設
2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設