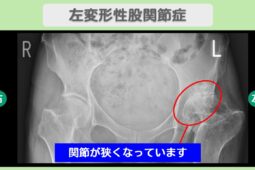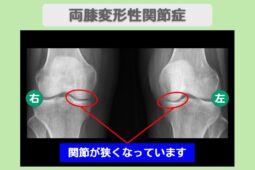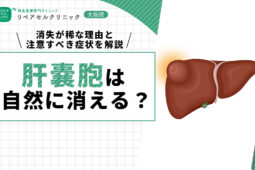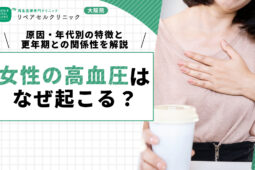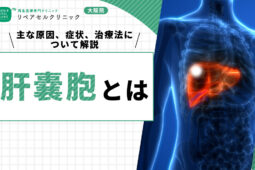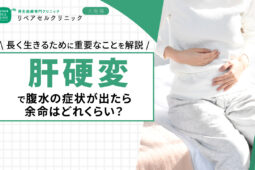- 幹細胞治療
- 肝疾患
- 再生治療
肝臓機能回復はどのくらいかかる?期間や改善を目指す方法も紹介

「健康診断で肝機能の数値が悪いと言われた」「疲れやすくて肝臓が心配」という不安を抱えている方にとって、肝臓機能が回復するまでの期間についてが気になるポイントではないでしょうか。
結論から言えば、肝臓機能の回復にどのくらいかかるかは症状や状態、原因によって異なります。
脂肪肝、アルコール性肝炎、薬物性肝障害、慢性肝炎など、肝機能低下の原因はさまざまで、それぞれに適した対処が必要です。
さらに肝臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれ、症状が表に出にくいため、気づいたときにはすでに機能が低下していたというケースも少なくありません。
放置してしまうと、慢性化や肝硬変、さらには肝がんへと進行するリスクもあるため、早期の対応が重要です。
この記事では肝臓機能が回復するまでの期間や改善を目指す方法まで紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。
「どれくらいで治るのか」「今の状態は放っておいても大丈夫なのか」と気になっている方は、ぜひ参考にしてください。
また肝臓の状態を改善を目指すなら、再生医療も選択肢の一つになります。
詳しい症例や治療法については、当院(リペアセルクリニック)の公式LINEでも紹介していますので、一度ご確認ください。
目次
肝臓機能はどのくらいで回復する?【原因別の期間目安】
肝臓機能は症状や原因によって回復期間が異なります。
症状によっては回復ではなく、症状の進行を抑制することが目的となる場合もあります。
原因別に回復期間の目安をチェックしましょう。
脂肪肝|生活習慣改善で約1〜3ヶ月が目安
脂肪肝の肝臓機能回復までの期間は、生活習慣を改善することで、約1~3ヶ月が目安とされています。
生活習慣の改善は、日常生活においてバランスのとれた食事、適度な運動、禁酒、十分な休養と睡眠が必要です。
とくに肥満は脂肪肝の主要な原因の一つであるため、適切な体重管理が不可欠です。
ただし、急激な減量は肝機能を悪化させる可能性があるため、医師の指導のもとで段階的に行いましょう。
脂肪肝の改善の程度や期間には個人差があるため、定期的な血液検査により肝機能の変化を確認しながら治療を進めることをおすすめします。
アルコール性肝炎・肝障害|禁酒後2週間〜1ヶ月
アルコール性肝炎や肝障害の回復期間について、軽度の症状であれば禁酒後約2週間〜1ヶ月で血液検査数値が正常化する場合があります。
アルコール性肝炎や肝障害の回復には、完全な禁酒が最も重要です。
軽度の場合は、禁酒の継続により2週間〜1ヶ月で肝機能検査値の改善がみられる場合があります。
一方、重度の肝障害では回復により長期間を要し、完全な回復が困難なこともあります。
禁酒の継続が困難な場合は、アルコール依存症の専門治療も検討しましょう。
薬物性肝障害|中止後、数週間から数か月程度
薬物性肝障害は、服用している薬物を中止してから数週間から数カ月程度で改善がみられます。
服用している薬の種類や服用期間、肝臓障害の度合いによって回復期間は異なるため注意が必要です。
代表的な薬の種類は、解熱消炎鎮痛薬、抗がん剤、抗真菌薬(水虫や真菌症の飲み薬)、漢方薬などがあります。
薬物性肝障害は発症のパターンが複数あり、服用量に比例して起こる場合(用量依存性)と、少量でも特定の体質の人に起こる場合(特異体質性)があります。
そのため、薬物による肝障害が疑われる場合は、服用している薬剤の種類や量に関わらず、速やかに処方医に相談し適切な対応を受けてください。
ウイルス性肝炎・肝硬変|回復ではなく進行抑制が目的
ウイルス性肝炎や肝硬変は発症すると回復することが難しくなるため、回復ではなく進行抑制が目的となります。
肝臓に負担をかける不規則な食生活や過度な飲酒、肥満体質などは症状が悪化する可能性があるため、早期改善が必要です。
抗ウイルス薬でウイルスの増殖を抑える治療法や、ウイルスの排除が難しい場合は内服薬や注射により進行を抑えます。
抗ウイルス薬によりウイルスの排除や増殖抑制を目指す治療を行いますが、完全排除が困難な場合には内服薬や注射薬により病気の進行を抑制します。
アルコール性肝硬変|回復ではなく延命管理が中心
アルコール性肝炎や肝障害は回復する見込みがありますが、アルコール性肝硬変は回復が困難となるため、延命管理が中心となります。
アルコール性肝硬変を発症すると、元の状態に戻ることはほとんどありません。
肝硬変の進行を大幅に遅らせるには、禁酒を徹底することが重要です。
また、栄養状態の改善や、腹水・黄疸といった肝硬変の合併症の管理も必要となります。
定期的な検査により肝がんの早期発見にも努め、可能な限り良好な生活を送ることを目指します。
肝機能回復に有効とされる基本的な治療法
肝機能回復に有効とされる基本的な治療法は以下のとおりです。
まずは生活習慣の改善が重要ですが、薬物療法や再生医療も詳しく解説していきますので、参考にしてください。
まずは生活習慣の改善|禁酒・食事・運動が基本
治療を行う前に、まずは禁酒、食生活の見直し、適度な運動が基本となります。
- バランスの取れた食事
- ビタミンやミネラルの摂取
- 食物繊維の摂取
- 禁酒
- 適度な運動
- 十分な睡眠
- ストレス管理
肝機能障害の原因が脂肪肝であれば、ビタミンやミネラルを豊富に含んだ食事や食物繊維の摂取、適度な運動が必要です。
アルコール性肝炎であれば、禁酒・断酒、ウイルス性肝炎では飲み薬で治療を行います。
薬剤性の肝機能障害であれば、原因となっている薬やサプリメントを中止することで改善する可能性があります。
薬物療法
肝機能回復に有効とされる治療法として薬物療法があります。
肝庇護薬を用いた薬物療法の目的は、肝細胞の保護や肝機能の改善、肝炎の進行抑制です。
肝庇護薬には主にウルソデオキシコール酸やグリチルリチン製剤などの医薬品があり、補助的にオルニチンやシリマリンなどのサプリメントが用いられることもあります。
ほかにも、ウイルスを攻撃するインターフェロンやウイルスの増殖を抑える核酸アナログ製剤といった杭ウイルス療法もあります。
再生医療
肝機能回復には、再生医療という選択肢もあります。
再生医療の幹細胞治療では、患者さま自身の血液から幹細胞を採取し、培養後に点滴をします。
自己由来の幹細胞を使用するため、拒絶反応やアレルギーのリスクが低いのが特徴です。
詳しい症例や治療法についてはLINEでも紹介していますので、以下リンクよりご覧ください。/p>
【まとめ】肝機能の回復期間は原因と重症度によって変わる!原因に応じた対応をしよう
肝機能障害の治療法と回復期間は、原因や重症度によって大きく異なります。
軽度であれば禁酒や食事療法などの生活習慣改善により改善が期待できますが、進行した場合には薬物療法も併用します。
ただし、肝硬変まで進行すると元の状態に戻るのが難しくなるため、早期発見、早期治療が重要です。
肝機能障害には、薬物療法の他に再生医療という選択肢もあります。
以下のページでは、当院の再生医療によって、脂肪肝や肝硬変の改善が見られた症例を公開しています。
>再生医療による肝疾患の症例はこちら
肝機能に不安がある方や、現在の治療法について相談したい方は当院「リペアセルクリニック」のLINEまたは電話相談をご利用ください。

監修者
渡久地 政尚
Masanao Toguchi
医師
略歴
1991年3月琉球大学 医学部 卒業
1991年4月医師免許取得
1992年沖縄協同病院 研修医
2000年癌研究会附属病院 消化器外科 勤務
2008年沖縄協同病院 内科 勤務
2012年老健施設 かりゆしの里 勤務
2013年6月医療法人美喜有会 ふたこクリニック 院長
2014年9月医療法人美喜有会 こまがわホームクリニック 院長
2017年8月医療法人美喜有会 訪問診療部 医局長
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 院長