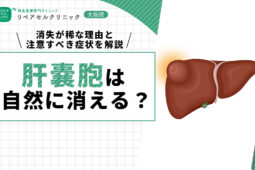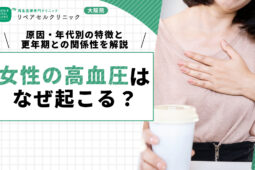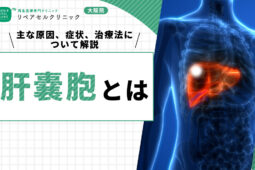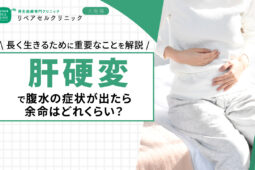- 再生治療
- 肝疾患
- 幹細胞治療
脂肪肝に効果的な対策方法とは?診断される数値の目安も解説

脂肪肝は肝臓に中性脂肪が過剰に蓄積した状態で、放置すると肝炎・肝硬変・肝がんへと進行するリスクもあります。
しかし、食事・運動・生活習慣を見直して対策することで、十分に改善が期待できます。
この記事では、肝脂肪に対する対策方法を解説しています。
脂肪肝と診断される数値の目安も紹介していますので、ご自身の数値や生活に不安のある方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
脂肪肝の対策法を紹介!食事・運動・生活習慣の改善が大切
脂肪肝については、以下のような対策法があります。
これらの対策を習慣づけることで、脂肪肝の発症リスクを抑えられる可能性があるため、参考にしてください。
【食事改善】糖質・脂質の摂り方を見直し、バランスの良い食事へ
脂肪肝は肝細胞に脂肪が異常に多く蓄積した状態で、脂質の大部分は中性脂肪のため、糖質や脂質など日常的に摂取する食事の見直しが必要です。
お菓子やジュースなどは糖質が多く、特に砂糖は消化・吸収がされやすいため、中性脂肪として肝臓にたまりやすくなります。
野菜や海藻類、キノコ類などの食物繊維は、腸からの糖質や脂質の吸収を遅らせる働きがあるため、積極的に摂取することが大切です。
また、納豆や牛乳、若鶏のささみなど、良質なたんぱく質を含む食品も摂取することで、バランスの良い食事を心がけましょう。
食事方法については以下の動画でも解説していますので、ぜひ参考にしてください。
【運動習慣】有酸素運動と筋トレなどの運動を無理なく続ける
脂肪肝対策として、ウォーキングや自転車など有酸素運動や、筋トレなど、日常的に運動習慣を身につけることも大切です。
有酸素運動は体内の中性脂肪を燃焼するため、肝臓の脂肪が減りやすくなります。
また、筋肉を増やすことは基礎代謝が上がることで、脂肪が燃焼しやすくなります。
スクワットや腕立て伏せ、腹筋運動など、無理のない範囲内で継続することが大切です。
【生活習慣】禁酒・節酒と睡眠・ストレス管理も大切
食事の見直しや、継続的な運動習慣も重要ですが、お酒の過剰摂取や睡眠不足、ストレスなども脂肪肝のリスクが高くなります。
お酒の過剰摂取はアルコールを分解する過程で肝臓の働きが低下することにより、脂肪が溜まりやすくなります。
また、不眠症や睡眠の質が下がる睡眠時無呼吸症候群は脂肪肝のリスクが高くなる可能性があるため、注意が必要です。
食事の見直しや運動を習慣づけ、健康な身体を作り上げることで、ストレスの軽減にもつながります。
さらに、禁酒や節酒などお酒の量を見直すことも、脂肪肝を含む生活習慣病の予防・改善に効果的です。
脂肪肝と診断される数値の目安を正しく理解しよう
脂肪肝と診断された方や健康診断の結果を見て不安に思っている方は、血液検査の数値を正しく理解することが大切です。
健康診断(血液検査)の結果が手元にある場合は、リストに掲載されている項目の中から「AST」「ALT」という項目を探してください。
- AST(GOT):基準値7~38IU/L
- ALT(GPT):基準値4~44IU/L
上記の数値を越えている場合、疑われる病気の1つとして「脂肪肝」が挙げられます。
ただし、数値の上昇はウイルス性肝炎や肝硬変、薬剤性肝障害など他の肝疾患の可能性もあるため、自己判断せず医師の診断を受けることが重要です。
また、脂肪肝とは直接関係しない数値ですが「BMI(体格指数)」という数値も重要な指標の一つです。
自分の数値を把握するためにも、以下の計算式を使って、現在のBMIを一度チェックしてみましょう。
- BMI = 体重(kg) ÷ 身長(m)²
一般的に、BMIが25以上の場合は「肥満」※と判定され、脂肪肝のリスクが高まるといわれています。
※参照:J-Stage「肥満と炎症」
脂肪肝が進行した場合は、再生医療も治療の選択肢の一つ
脂肪肝の状態をそのままにすると、「肝硬変」や「肝臓がん」といった状態に進行する可能性があり、場合によっては命に関わることもあります。
しかし、近年では再生医療という選択肢があり、再生医療は「幹細胞」を利用することで、脂肪が原因による肝機能低下の改善が期待できます。
治療効果には個人差がありますが、機能が低下した肝臓の回復を目指せるという点で、再生医療は検討に値する選択肢の一つと言えるでしょう。
【まとめ】脂肪肝は早めの対策が大切!まずは医師に相談して自分に合った治療法を始めよう
脂肪肝は血液検査の数値を参考にできますが、自覚症状は目立つものではなく、気づかないうちに症状が大きく進行している可能性があります。
定期的に健康診断を受けて、肝臓の数値を確認して、数値が気になる方は医師に相談するなど、早めの対策を行うことが大切です。
近年では、再生医療という治療法が選択肢としてあります。再生医療は自身の幹細胞を用いて肝臓機能を改善を目指し、再生を目指す治療法で、副作用や身体への負担も軽減される可能性があります。
自分に合った治療法を見つけるためにも、まずは医師に相談し、脂肪肝の症例や再生医療の詳細について知識を深めておきましょう。
以下のページでは、当院の再生医療によって脂肪肝や肝硬変の改善が見られた症例を公開していますので、併せて参考にしてください。
>再生医療による肝疾患の症例はこちら
肝臓疾患のお悩みに対する新しい治療法があります。

監修者
渡久地 政尚
Masanao Toguchi
医師
略歴
1991年3月琉球大学 医学部 卒業
1991年4月医師免許取得
1992年沖縄協同病院 研修医
2000年癌研究会附属病院 消化器外科 勤務
2008年沖縄協同病院 内科 勤務
2012年老健施設 かりゆしの里 勤務
2013年6月医療法人美喜有会 ふたこクリニック 院長
2014年9月医療法人美喜有会 こまがわホームクリニック 院長
2017年8月医療法人美喜有会 訪問診療部 医局長
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 院長