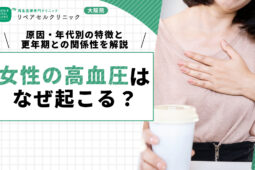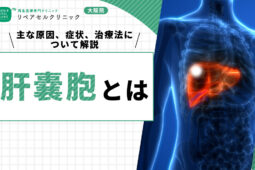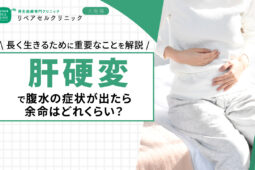- 再生治療
- 肝疾患
肝臓の数値が高いとどんな症状が出る?肝疾患と生活習慣の改善について解説

「肝臓の数値が高いときはどんな症状が出る?」
健康診断で肝臓の数値が高いことが判明するとどのような症状が出るのか、病気ではないか不安な方も多いのではないでしょうか。
本記事では、肝臓の数値が高いときに現れる症状や考えられる疾患について、わかりやすく解説します。
また、当院リペアセルクリニックの公式LINEでは、肝硬変をはじめとする肝臓疾患を患っている方向けに先端医療である再生医療に関する情報を配信しています。
従来の治療では治らないといわれている肝硬変の改善にも期待できる治療法なので、ぜひご参考ください。
目次
肝臓の数値が高いと現れる症状
肝臓の数値が高いときには、以下の症状が現れます。
- 倦怠感
- 浮腫(むくみ)
- 食欲不振
- 吐き気
- 発熱
- 皮膚のかゆみ
- 黄疸(皮膚や目の白い部分が黄色くなる)
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるほど症状が現れにくいため、初期段階ではこれらの症状を自覚できず、血液検査を受けて初めて数値の異常に気付くケースがほとんどです。
上記の症状が現れている場合は、肝疾患がある程度進行している可能性があるため、速やかに医療機関を受診しましょう。
健康診断でチェックされる肝臓の数値と基準値
健康診断では、肝臓の状態を把握するために以下の検査項目がチェックされます。
| 検査項目 | 基準値 | 異常値の意味 |
|---|---|---|
| AST(GOT) | 10〜30 U/L | 高値:肝細胞の損傷 |
| ALT(GPT) | 男性:10~42 U/L 女性:7~23 U/L |
高値:肝細胞の損傷 |
| γ-GTP(ガンマGTP) | 男性:13~64 U/L 女性:9~34 U/L |
高値:アルコール性肝障害、胆道系疾患 |
| 総ビリルビン | 0.4~1.5 mg/dL | 高値:肝機能低下、胆道閉塞 |
| アルブミン | 4.1~5.1 g/dL | 低値:肝機能低下、栄養不良 |
| 総蛋白 | 6.6~8.1 g/dL | 低値:肝機能低下、栄養不良 |
※出典:日本臨床検査医学会
AST、ALT、γ-GTP、総ビリルビンは肝機能に異常があると、数値が高くなります。
一方、アルブミンと総蛋白は数値が低くなることで問題となる項目です。
これらが低下している場合は肝臓の合成機能が低下しており、肝機能がかなり悪化している可能性があるため注意が必要です。
肝臓の数値が高いときに疑われる疾患
肝臓の数値が高いときには、以下の疾患が疑われます。
| 検査項目 | 疑われる肝臓疾患 |
|---|---|
| AST(GOT):高値 | 急性肝炎、慢性肝炎、肝硬変、脂肪肝、アルコール性肝障害、薬物性肝障害 |
| ALT(GPT):高値 | 急性肝炎、慢性肝炎、脂肪肝、アルコール性肝障害、薬物性肝障害 |
| γ-GTP:高値 | アルコール性肝障害、脂肪肝、薬物性肝障害 |
| 総ビリルビン:高値 | 急性肝炎、肝硬変 |
| アルブミン:低値 | 肝硬変、慢性肝疾患 |
| 総蛋白:低値 | 肝硬変、慢性肝疾患 |
血液検査で異常値が出た項目を上記の表と照らし合わせ、疑われる疾患を確認してください。
詳しい診断については医療機関での受診をおすすめします。
ここからは、肝臓の数値が高いときに疑われる以下の疾患について解説します。
急性肝炎
急性肝炎はウイルス感染や免疫異常、薬の副作用などが原因で起こる炎症です。
ほとんどは自然に治りますが、1~2%ほどは重症化して急性肝不全になることがあります。
血液検査が有効なので、早めの検査がおすすめです。
慢性肝疾患
肝臓の炎症が6カ月以上続いている状態を、慢性肝疾患といいます。
慢性肝疾患の多くがB型肝炎とC型肝炎で、肝硬変や肝がんなどの重大な肝臓疾患につながる可能性があります。
早期に発見して、肝硬変や肝がんへと進行する前に治療を始めましょう。
脂肪肝
脂肪肝とは肝臓の肝細胞に中性脂肪がたまっている状態のことで、飲み過ぎや運動不足、肥満や糖尿病が原因で起こります。
お酒の飲み過ぎが原因とイメージされがちですが、お酒を全く飲まない人でも発症のリスクは否定できません。
疲労感や肩こりなどを感じることがありますが、自覚症状がほとんどなく、進行すると肝硬変や肝がんのリスクが高まるため注意が必要です。
自己免疫性肝炎
自己免疫性肝炎は、免疫システムが自分の肝細胞を攻撃してしまうことで起こる慢性肝炎です。
40~60代の女性に多く見られ、疲労感や関節痛、皮膚の発疹などの症状が現れることがあります。
血液検査では肝機能異常とともに、自己抗体(抗核抗体、抗平滑筋抗体など)が検出されます。
早期診断・治療により肝硬変への進行を防ぐことが可能で、免疫抑制剤による治療が有効です。
アルコール性肝障害
アルコール性肝障害は、長期間の過度な飲酒が原因で起こる肝臓の病気です。
アルコール性脂肪肝から始まり、アルコール性肝炎、そして肝硬変へと進行する可能性があります。
初期は自覚症状がほとんどありませんが、進行すると倦怠感や食欲不振、黄疸などの症状が現れます。
禁酒により改善が期待できるため、早期発見と適切な治療が重要です。
非アルコール性肝障害
非アルコール性肝障害は、お酒を飲まない、または少量しか飲まない人に起こる肝臓の病気です。
肥満や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病が主な原因で、非アルコール性脂肪肝(NAFLD)から非アルコール性脂肪肝炎(NASH)へと進行することがあります。
生活習慣の改善、とくに食事療法と運動療法が治療の基本となります。
放置すると肝硬変や肝がんに進行するリスクがあるため、定期的な検査と管理が必要です。
肝硬変
肝硬変は、ウイルスや過剰なアルコール摂取などさまざまな原因で肝炎を発症し、肝臓が線維化して起こります。
肝障害が進行して肝細胞が破壊されると、身体が肝細胞を修復しようとする働きによって、コラーゲンである線維が増えるのです。
肝臓に線維が広がる状態を線維化といいます。
初期には自覚症状がほとんど見られませんが、徐々に黄疸やかゆみ、腹水や膨満感などの症状が出てきます。
肝がん
肝がんは、肝臓にできる悪性腫瘍で、慢性肝炎や肝硬変から進行して発症することが多い病気です。
B型・C型肝炎ウイルス感染、アルコール性肝障害、非アルコール性脂肪肝炎などが主な原因となります。
初期はほとんど症状がありませんが、進行すると腹部の痛みや膨満感、体重減少、黄疸などが現れます。
早期発見・早期治療が重要なため、肝疾患のある方は定期的な画像検査と腫瘍マーカー(AFP)の測定が必要です。
肝臓の数値が高いときに行う検査
血液検査で肝臓の数値が高いときは、肝臓の状態をより詳しく調べるために以下の画像検査や精密検査を行います。
| 検査名 | 検査内容・特徴 |
|---|---|
| 腹部超音波検査(エコー検査) | 肝臓の大きさや形、脂肪肝の有無、腫瘍の存在などを確認。痛みがなく短時間で検査可能 |
| 腹部MRI検査 | 肝臓の詳細な構造や血管の状態、小さな病変まで高精度で検出。造影剤使用でより詳細な診断が可能 |
| 腹部CT検査 | 肝臓の形態や内部構造を立体的に観察。腫瘍の大きさや位置、他臓器への影響を詳しく調査 |
| 肝生検 | 肝臓の一部を採取して顕微鏡で詳しく調査。肝炎の程度や肝硬変の進行度、腫瘍の性質を正確に診断 |
| FibroScan(フィブロスキャン) | 肝臓の硬さを測定し肝線維化の程度を評価。肝硬変の進行度を非侵襲的に把握 |
これらの検査により肝臓の数値が高い原因を特定し、適切な治療方針を決定します。
肝臓の数値が高いときは食事・飲酒・運動習慣を改善しましょう
肝臓の数値が高い場合、まず取り組むべきなのが生活習慣の改善です。
とくに以下の3つの習慣の見直しは、肝機能の改善に直接的な効果があります。
初期段階であれば、これらの対処法によって数値の正常化が期待できるため、継続的に実践することが重要です。
症状が進行する前に、日常生活を見直して肝臓への負担を軽減しましょう。
食生活を改善する
肝臓の数値を改善するには、栄養バランスの取れた食事を1日3回規則正しく摂ることが基本です。
脂肪分の多い食事や糖質の過剰摂取は肝臓に負担をかけるため、野菜や魚類を中心とした食事に切り替えましょう。
とくに揚げ物や甘い物の摂り過ぎには注意し、食物繊維が豊富な野菜や海藻類を取り入れると、肝機能の改善効果が期待できます。
アルコール摂取を控える・禁酒する
血液検査で肝機能異常を示す数値が高い場合、重要なのがアルコール摂取を控えることです。
とくに初期段階の場合には効果が得られやすく、約1カ月アルコール摂取を控えれば、肝機能数値が基準範囲に改善※していきます。
※出典:金沢医科大学
しかし、症状が進行して肝硬変を発症してしまうと、禁酒しても肝機能が正常に戻らなくなる可能性があります。
そのため、肝臓の数値異常が指摘されたら、できるだけ早めに完全な禁酒を始めましょう。
運動習慣を取り入れる
適度な運動は肝機能の改善に非常に有効で、とくに有酸素運動がおすすめです。
ウォーキングやジョギング、水泳などの運動を週3〜4回、30分程度行うことで脂肪肝の改善効果が期待できます。
今まで運動習慣がなかった方は、エレベーターの代わりに階段を使う、一駅手前で降りて歩くなど、日常生活に取り入れやすいことから始めましょう。
肝臓疾患に対しては再生医療も選択肢の一つ
肝臓の数値が高く肝機能障害になった場合、再生医療による治療も選択肢の一つです。
再生医療とは、さまざまな組織に変化する幹細胞を用いて、損傷した肝臓を修復・再生させる医療技術のことです。
従来の治療では治らないといわれている肝硬変の改善につながる治療法として注目されています。
患者さまの細胞のみを使用するため、拒絶反応やアレルギーなどの副作用が少ない点も強みの一つです。
「肝臓の数値が高いのを改善したい」という方は、再生医療による治療を検討してみましょう。
肝臓疾患のお悩みに対する新しい治療法があります。
肝臓の数値が高いと肝機能障害の可能性あり!早めに医療機関を受診しよう
肝臓の数値が高いと肝機能障害の可能性があるため、早期に医療機関を受診しましょう。
肝炎や脂肪肝といった肝臓の病気は、自覚症状がないことが多く、健康診断や人間ドックで気づくことがほとんどです。
知らぬ間に肝臓疾患が進行し、肝硬変になってしまうと従来の治療では治せないといわれています。
しかし、近年の治療では、肝硬変をはじめとする肝疾患に対して再生医療による治療が注目されています。
以下のページでは、実際に当院リペアセルクリニックで再生医療を受け、肝疾患が改善された患者さまの症例を紹介しているので、ぜひご覧ください。
「肝疾患を早く治したい」「再生医療について詳しく知りたい」という方は、ぜひ当院リペアセルクリニックへお問い合わせください。

監修者
渡久地 政尚
Masanao Toguchi
医師
略歴
1991年3月琉球大学 医学部 卒業
1991年4月医師免許取得
1992年沖縄協同病院 研修医
2000年癌研究会附属病院 消化器外科 勤務
2008年沖縄協同病院 内科 勤務
2012年老健施設 かりゆしの里 勤務
2013年6月医療法人美喜有会 ふたこクリニック 院長
2014年9月医療法人美喜有会 こまがわホームクリニック 院長
2017年8月医療法人美喜有会 訪問診療部 医局長
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 院長