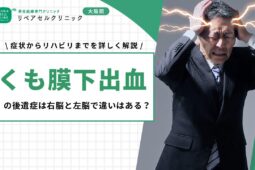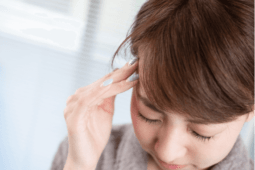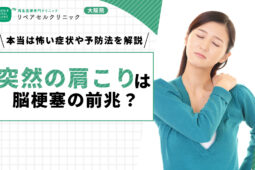- 脳卒中
- 脳梗塞
脳卒中(脳梗塞)は倒れてからよりも発症後の時間が重要!初期治療の詳細や倒れた時にやるべきことも解説

脳卒中は発症後どれだけ早く初期治療を受けられるかで、その後の回復に大きな影響を与えます。
本記事では「脳卒中発症後の初期治療の重要性」について詳しく解説します。
脳卒中の発症後はできるだけ早い対応が求められるため、自分や家族が倒れた時にすぐ対応できるようにしましょう。
機能回復に重要なリハビリや再生医療による治療方法についても解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
脳卒中(脳梗塞)は倒れてからの時間より発症後の時間が重要
脳卒中には「脳梗塞」「脳出血」「くも膜下出血」の3種類があり、これらを発症してしまった場合は、一刻も早く治療を受ける必要があります。
特に「脳梗塞」は、発症からの時間がその後の回復に大きな影響を与えます。
重要なのは倒れた時間ではなく、最初に症状が現れた時刻です。
頭痛やしびれなど、軽微な症状が出始めた時点が発症時間となります。
救急車を呼ぶ際も、「何時頃から症状が出始めたか」を正確に伝えられるよう、時間を記録しておくことが大切です。
脳卒中を疑ったら可能な限り早く専門医を受診しましょう。
脳の障害は発症後、時間が経つほど症状が大きくなり後遺症も重度になる可能性が高いです。
また脳梗塞では、発症してから4.5時間以内に行えるt-PA点滴治療、8時間以内の患者さんのみに行える特殊な治療の血管内治療があります。
脳梗塞になると、脳に血液を送る血管が詰まり、脳に血液が流れなくなることで脳の神経細胞が死んでしまいます。
しかし、脳梗塞の発症から4.5時間以内なら、血栓を溶かすt-PA治療が行えます。
t-PA治療は、血管内の血栓を溶かすことで詰まった脳血管を再開通させ、脳細胞への血流を回復させます。
発症から治療開始までの時間が遅くなるほど脳の神経細胞が死滅するリスクが上がるため、早急に治療を受ける必要があります。
脳出血は発症後1~6時間で出血が止まるが早期受診が必要
脳出血(脳内出血)は発症から1〜6時間程度で出血が止まりますが、意識障害など重症になる可能性があるため、早期受診しましょう。
脳出血とは、脳内の血管が破れて脳内に出血する病気のことです。
出血した血液が固まって血腫となり脳を圧迫することで吐き気や意識障害などを引き起こします。
脳出血を発症してから6時間以上経過しても、意識障害などの重度な症状が出ない場合は手術せずに様子をみることが多いです。
しかし、発症後に意識障害まで悪化してしまうと命に関わる可能性があります。
早期受診することで症状が悪化した時に病院ですぐ対応できるようにすることが重要です。
くも膜下出血を発症した場合は早急に救急車を呼ぶ
くも膜下出血を発症した場合は、できる限り早く医療機関へ搬送できるよう救急車を呼びましょう。
脳の血管が破裂したことで、脳の表面を覆っているくも膜と軟膜の間にある「くも膜下腔」に出血が起こる病気のことです。
くも膜下出血の原因でもっとも多い脳動脈瘤が破裂してしまうと、24時間以内に再破裂する可能性があります。
再破裂して出血すると死亡率は約50%といわれており、初期治療では再出血の予防が重要になります。
主な初期症状は「突然の激しい頭痛」「嘔吐」「意識障害」などがあり、一時的に症状が治ることもあるため、異変を感じたらすぐに医療機関へ相談しましょう。
4.5時間経過後も初期治療は重要!諦めずにすぐ病院へ
脳梗塞の治療は発症から4.5時間以内のt-PA静注療法が有効ですが、それを過ぎても諦める必要はありません。6時間以内なら血管内治療など、まだできることがあるのです。
発症時刻が不明でも、MRI検査で判断できればt-PA静注療法を検討できる場合もあります。
さらに、脳卒中専門病棟での治療と早期リハビリで、4.5時間を過ぎても良好な効果が期待できます。
大切なのは、できるだけ早く専門的な治療を始めること。脳梗塞の疑いがあれば、躊躇せずに救急車で専門病院へ行きましょう。
諦めずに治療を受けることが、その後の回復と生活の質を大きく左右します。
急性脳卒中のガイドライン/FASTで脳卒中(脳梗塞)か判断

急性脳卒中を診断する際には、「FAST」と呼ばれるガイドラインが使用されます。FASTは、脳梗塞を早期発見するためにチェックするポイントの頭文字を合わせたものです。
|
FACE:顔 |
うまく笑顔が作れますか? 片側の顔だけが歪んでいたり、ひきつっていないか、顔の麻痺状態をチェックしましょう。 |
|
ARMS:腕 |
腕を上げたままキープできますか? 両腕をゆっくりと上げ下ろししてみて、腕の麻痺が起きていないかどうかをチェックします。もしも両腕を前に上げた際に、片腕だけが脱力して腕が上げられなければ要注意です。 |
|
SPEECH:話 |
短い文がいつも通り話せますか? 簡単な問いかけ(例えば本人の名前や今日の日付など)をしてみて、正しい返答があるかどうかをチェックしましょう。 |
|
TIME:時間 |
発症時刻を確認。 脳梗塞の場合、発症してからの時間によって治療内容が変わります。発症後3〜4.5時間以内であれば、薬物により血栓を溶かす治療が可能となることがあります。 |
周りにいる人が突然倒れたり、自分でおかしいなと思ったら、上記の4点を確認して、速やかに救急車を呼びましょう
症状が消えても油断できない一過性脳虚血発作(TIA)について
脳梗塞は突然襲ってきます。夜中のトイレ、朝の起床時、日中の活動中など、発症のタイミングははっきりしているケースがほとんどです。
ところが、最初の症状が徐々に和らいで消えてしまうことがあります。これを「一過性脳虚血発作(TIA)」と呼びます。
一過性脳虚血発作(TIA)は、脳梗塞の前触れとして、同じような症状が一時的に現れる現象です。数分から数十分、長くても24時間以内に症状が消えます。
症状が一時的でも、一過性脳虚血発作(TIA)を経験した人は、再び脳卒中に襲われる危険性が非常に高いため油断は禁物です。
もし一過性脳虚血発作(TIA)かもしれないと思ったら、一刻も早く医療機関を受診しましょう。
脳卒中で自分や家族が倒れた時にやるべきこと
脳卒中で自分や家族が倒れた時にやるべきことや、対応のポイントを解説します。
脳卒中で倒れるほどの症状が出ている場合は、時間との戦いです。
後遺症のリスクを抑え、回復する確率を少しでも上げるために、できるだけ早く医療機関を受診して初期治療を受けましょう。
意識があるとき
とにかく周囲に助けを求め、できるだけ動かずその場で横になることが原則です。周囲の人は、マットや毛布の上に患者さんを乗せて、広いところに移動して寝かせましょう。
これは脳への血流を保つこと、血圧上昇による出血の悪化や、再出血を予防するためです。横になれる場所が近くになくても、自分で立って歩くべきではありません。
なぜなら脳の血管が詰まって症状が出ている時には、歩くことで脳への血流が悪くなり、脳の障害がひどくなる恐れがあるからです。
意識がないとき
こちらからの呼びかけや、体をゆすっても反応がまったくない、一時的に目を開けてもまたすぐに閉じて眠り込んでしまう。
さらに目は開いていても応答が曖昧な場合は、周囲の人が慎重に機敏に対応しなくてはなりません。
意識がないときの対応ポイント
倒れたまま意識がない時は救急車が到着するまで、以下のポイントを意識して対処しましょう。
|
1.適切な場所への移動 |
|
|
2.気道の確保と誤飲の防止 |
|
|
3.環境調節 |
|
脳卒中発症後すぐに生命の危険があるのは、重症のくも膜下出血を除けばほとんどありません。落ち着いて上記の3点をすぐに実行してください。
救急車を呼ぶ
脳卒中が疑われる時は、一刻も早く専門医の受診が必要になります。通院治療中のかかりつけ医がいる場合は、専門の医療機関を紹介してもらうのが良いでしょう。
すぐに連絡がつかない場合は、直ちに119番に電話し、救急車を呼びましょう。受診予定の病院には、あらかじめかかりつけ医や救急隊から連絡し、搬送予定の患者の病状を説明した上で受け入れ可能か確かめておけば無駄な時間を省いて搬送できます。
重症の場合ではもちろんですが、軽症と思われる時も救急車を利用してください。
これは一刻も早く救急搬送するためであり、また搬送の途中で急に容体が悪化することも十分あり得るからです。
もしも救急車が他の現場へ出動中などで到着に時間がかかる時は、患者さんに横向きに寝てもらって、家族や周囲の人が車を運転し、病院へ運んでください。
ただし、患者さん本人が運転したために大事故を起こした例や、手遅れになるほど病状が悪化した例もあるため、患者さんが自分で運転して病院へ向かうのは絶対にやめましょう。
脳卒中(脳梗塞)で倒れたらどんな後遺症が残る?
脳卒中、特に脳梗塞は治療後も様々な後遺症が残ることがあります。
主な後遺症とその症状は以下の通りです。
| 後遺症 | 主な症状 |
|---|---|
| 運動麻痺 | 片側の上下肢が動かなくなる |
| 感覚障害 | 触覚や痛覚が鈍くなったり、過敏になったりする |
| 目の障害 | 視野狭窄、複視、半盲などの症状が長期間残ることも |
| 構音障害 | 呂律が回りにくくなる |
| 嚥下障害 | 飲み込みにくくなる |
| 高次脳機能障害 | 記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、病識欠落など多岐にわたる |
| 失語症 | 言葉が出にくくなったり、理解できなくなったりする |
| 半側空間無視 | 外界の半側(主に左)に注意が向かなくなる |
| 自発性障害 | 自ら進んで動作や会話ができなくなる |
脳梗塞の後遺症は、日常生活に大きな影響を与える可能性があります。脳梗塞になった場合は、このような後遺症についても理解しておくことが重要です。
脳卒中(脳梗塞)の後遺症に対する治療
脳卒中(脳梗塞)の後遺症は、患者さんの日常生活に大きな影響を与えます。
しかし、適切なリハビリテーションと治療により、後遺症の改善が可能です。
- 理学療法
- 作業療法
- 感覚統合訓練
- 認知リハビリテーション
- 薬物治療
など
リハビリテーションは、急性期、回復期、維持期に分けて行われ、それぞれの時期に応じた適切なアプローチが重要です。
後遺症からの回復には時間がかかりますが、粘り強いリハビリテーションを続けることで、多くの患者さんが自立した生活を取り戻すことができます。
リハビリや治療に関して、詳しくは以下の記事をご覧ください。
脳卒中(脳梗塞)の回復には早期のリハビリが重要
脳卒中の治療後は、さまざまな後遺症が残ってしまう可能性があり、機能回復のために早期のリハビリが重要です。
一般的に脳卒中の発症から6ヶ月後までは、ダメージを受けた脳の神経ネットワークが再構築すると考えられているため、後遺症が回復する見込みがあります。
そのため、発症から6ヶ月後までの「回復期」と呼ばれる期間にリハビリを積極的に行いましょう。
脳梗塞の後遺症に効果的なリハビリ内容について詳細が知りたい方は、以下をご参考ください。
脳卒中(脳梗塞)の治療法としての選択肢「再生医療」
脳卒中(脳梗塞)の治療法としては、脳梗塞や脳出血に対する効果が認められてきている再生医療という選択肢もあります。
再生医療では、主に幹細胞治療とPRP療法の2つを行います。
- 幹細胞治療:患者さま自身から採取した幹細胞を培養して投与。ご自身の幹細胞を利用するため副作用などリスクが少ないのが特徴です。
- PRP療法:患者さま自身の血液から抽出した多血小板血漿(PRP)を患部に注射します。こちらもご自身の血液を利用するため副作用などリスクは少ない治療方法です。
特に幹細胞治療は脳神経細胞の修復および再生と、脳の血管を新しく再生させるという2つの大きな作用があり、脳卒中の再発予防にも効果的です。
>>当院で再生医療を受けられた方の症例はこちら
特に以下のような方が治療対象になります。
- うまく話せない
- 痺れや麻痺をなんとかしたい
- もうこれ以上の機能の回復が見込めないと診断を受けた方
- リハビリの効果を高めたい
- 脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)の再発を予防したい
再生医療について興味がある方は、ぜひ当院「リペアセルクリニック」へご相談ください。
脳卒中のお悩みに対する新しい治療法があります。
【まとめ】脳卒中の発症後は時間との戦い!その時に取るべき行動や知っておきたいこと
早期発見や早期治療がその後の予後に大きく関わります。
運動麻痺、感覚障害、高次脳機能障害など、患者さんの日常生活に大きな影響を与える後遺症に対して、適切なリハビリテーションが重要です。
脳卒中の後遺症からの回復には時間がかかりますが、あきらめずに継続的なリハビリテーションに取り組むことで症状の改善が目指せます。
また自分が脳卒中の危険因子に当てはまる場合は、再発予防のためにも生活習慣を見直し、検診を受けるように心がけましょう。
現在既に脳卒中後の後遺症で悩んでいる方は、後遺症の改善・再発予防として再生医療もご検討ください。
脳卒中の症状の多くはリハビリを重ねていけば改善が見込めるものの、慢性期を過ぎてしまった場合はリハビリ効果が低くなっていきます。
そうしたケースに対して、後遺症の回復効果が期待できるのが再生治療です。
- 身体の機能(後遺症)回復
- 脳卒中のリハビリ効果を高める
- 脳卒中の再発予防
脳卒中の治療法でお悩みの方は、ぜひ当院「リペアセルクリニック」で行っている無料相談をご利用ください。
以下の動画では、実際に当院リペアセルクリニックで再生医療を受け、脳梗塞の後遺症が改善された患者様の症例を紹介しています。
併せて参考にしてください。

監修者
圓尾 知之
Tomoyuki Maruo
医師
略歴
2002年3月京都府立医科大学 医学部 医学科 卒業
2002年4月医師免許取得
2002年4月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2002年6月関西労災病院 脳神経外科 勤務
2003年6月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2003年12月大阪母子医療センター 脳神経外科 勤務
2004年6月大阪労災病院 脳神経外科 勤務
2005年11月大手前病院 脳神経外科 勤務
2007年12月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2012年3月大阪大学大学院 医学系研究科 修了(医学博士)
2012年4月大阪大学医学部 脳神経外科 特任助教
2014年4月大手前病院 脳神経外科 部長