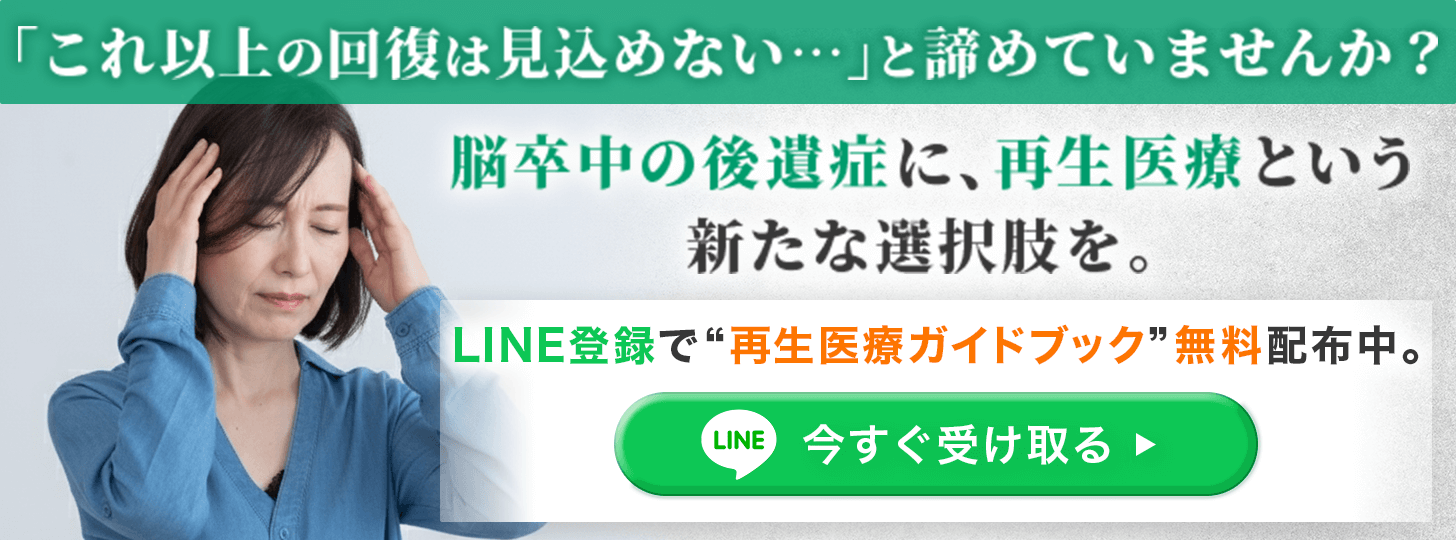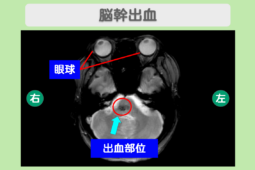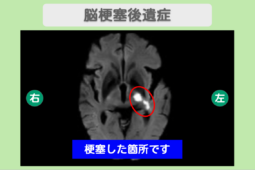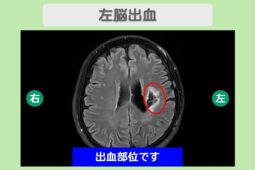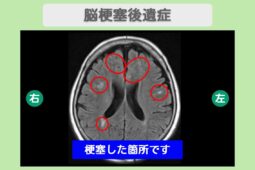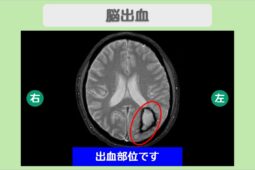- 脳卒中
くも膜下出血になった家族に対してできることは?回復過程や入院期間も紹介

くも膜下出血は後遺症が出ることが多く、本人はもとより、家族もつらい思いをすることが少なくありません。
家族(患者)の幸せを願い懸命に看病することはとても素晴らしいことです。そのため、「家族である自分たちができることは何か」と考えをめぐらせる方もいらっしゃるでしょう。
そこで本記事では、くも膜下出血になってしまった家族に対して、残された家族ができることについて紹介します。
お悩みの方はぜひ最後までご覧ください。
目次
くも膜下出血になった家族に対してできること
くも膜下出血を発症した家族のためにできることはいくつかあります。
|
家族にできることまとめ
|
再発防止や日常生活のサポートなど、具体的な行動について紹介していきます。
再発した場合の早期発見
くも膜下出血は、治療後も再発する可能性がある病です。そのため家族だからできる重要なことは、再発した場合の早期発見です。
くも膜下出血は早期発見が非常に大切です。そのためには本人だけでなく、周りの家族も変調にいち早く気づけるかがその後のカギを握ります。
|
早急に医療機関を受診すべきケース
|
日頃から再発を意識して、注意深く観察する習慣を身につけましょう。また、医療機関を受診した際に、調子の良し悪しを詳細に医師へ伝えることでその後の治療に役立ちます。
顔や手足に麻痺がみられる・呂律が回っていない・こちらが言っていることを理解できていないなどの症状が見られた場合は、早急に医療機関を受診しましょう。
介護保険など支援サービスの申請
くも膜下出血を発症した場合、働けない分の給料を保証してくれたり保険範囲内の医療費が一部払い戻されたりする制度などが使用できる場合があります。また、介護保険制度を活用すれば、必要な介護サービスを受けられます。
くも膜下出血を発症した方が利用できるサービスを下記にまとめました。
|
くも膜下出血を発症した方が利用できるサービス
|
くも膜下出血を発症した本人がひとりで申請するのは難しい場合は、家族が申請をサポートしましょう。
高額療養費制度
高額療養費制度とは、1日から月末までに支払った医療費が自己負担額を超えた場合、払い戻される制度です。
医療費は保険診療の範囲内なので、くも膜下出血による診療代や検査料が対象です。一方で、差額のベッド代や先進医療の費用、食事代は対象ではありません。
自動で払い戻しはされないので、申請が必要です。国民健康保険の場合は各市区町村の窓口に問い合わせてみてください。
介護保険
介護保険とは、介護が必要な方にサービスを提供する制度で、訪問介護や福祉用具の貸与、施設の入所などさまざまです。
くも膜下出血による後遺症で介護が必要な場合は40歳から利用できます。しかし、利用には介護保険の申請や介護度の認定が必要で、認定のないまま介護サービスを利用すると全額が自己負担となります。
介護保険の申請からサービスの開始まで時間がかかる場合があるため、早めの申請がおすすめです。
傷病手当金
病床手当金とは、くも膜下出血による入院や治療で働けない場合、月給のおよそ2/3程度の金額を保証してくれる制度です。支給には4つの条件がありすべてに当てはまっている方が対象です。
傷病手当を受けられる条件を下記にまとめました。
|
傷病手当を受けられる条件
|
該当している方は、加入している保険組合や協会けんぽから申請書を取り寄せておきましょう。
障害年金
障害年金は、くも膜下出血による後遺症によって労働や日常の生活が制限される場合に国から支給されます。受給に障碍者手帳の有無は問いませんが、書類による審査が必要です。
障害年金は2種類あり、くも膜下出血の発症で初めて診療を受けたときに加入していた年金によって請求できる障害年金が異なります。
|
障害年金の種類
|
申請の際は、近くの年金事務所に問い合わせてみましょう。
自立支援医療制度
くも膜下出血による後遺症で怒りっぽくなったり、ぼんやりしてしまったりする高次脳機能障害にお悩みの方は自立支援医療制度を活用してみましょう。
自立支援医療制度とは、高次機能障害を治療するための医療費が1割の負担まで軽減される制度です。通院の際の診療や薬代、往診、訪問看護などが対象です。
申請の際は、市区町村の障害福祉課に問い合わせてみましょう。
転倒防止のための工夫
くも膜下出血に関して家族ができることに転倒防止の工夫が挙げられます。くも膜下出血は麻痺などの後遺症が残り、転びやすくなるケースが多いため、なんらかの工夫を講じる必要があります。
|
主な転倒防止策
|
玄関や部屋、廊下の境目に段差がある場合は、段差をなくす・手すりを設置するなど、歩くための障害を極力なくしましょう。
また、床や浴槽、マットが置いてある場所など、滑りやすくなっていないか確認することも大切です。また、床や廊下での物の置きっぱなしに気をつけましょう。
くわえて、足元が見にくい場所にライトを設置する工夫も有効です。
食事や喫煙・飲酒などの管理
くも膜下出血の危険因子(原因)を取り除くことも家族にできることのひとつです。くも膜下出血は脳動脈瘤の破裂が主な原因ですが、その危険因子となるのが高血圧や喫煙、飲酒などです。
喫煙や飲酒は自制するのが難しいため、家族のサポートを必要とします。また、高血圧の対策として脂肪や塩分を控えた食事の提供も大切です。
定期的な会話
くも膜下出血後の家族間の定期的な会話は身体的な回復だけでなく、精神的な健康を維持する上で重要です。
患者は不安や孤独感を抱きやすい状態にあるため、家族との対話が心の支えになります。日々の出来事や患者の気持ちについて、ゆっくりと話し合う時間を設けましょう。
認知機能の維持や改善にも会話は効果的です。また、会話を通じて患者の状態の変化にいち早く気づくことができます。
【ご家族向け】寝たきりのくも膜下出血患者に関する知識
寝たきりになったくも膜下出血患者の家族として、適切なケアを提供するためには、病状や回復過程に関する正しい知識が不可欠です。
|
寝たきりのくも膜下出血患者に関する知識 |
ここではくも膜下出血の回復過程や入院期間、予後について解説します。
くも膜下出血の回復過程
くも膜下出血からの回復期間は個人差が大きく、一様ではありませんが全治までに6カ月以上かかるとされています。
一般的には、急性期・回復期・生活期と3つの段階を経ていきます。
| 段階 | 発症からの期間 | 過程 |
|---|---|---|
| 急性期 | 発症後約2週間 | 生命の危機管理が最優先され集中的に治療 |
| 回復期 | 2週間〜3カ月 | 集中的なリハビリテーション |
| 生活期 | 3カ月以降 | 定期的な通院によるリハビリテーション |
上記の過程で、患者はさまざまな症状(頭痛・めまい・認知機能の低下など)を経験する可能性があります。家族は、医療チームと密に連携し、患者の状態に応じたケアの提供が重要です。
くも膜下出血の平均入院期間
くも膜下出血の平均入院期間は、患者の状態や治療方法によって大きく異なります。
一般的には、軽症例で1〜2カ月、中等症から重症例では3〜6カ月程度の入院が必要となることが多いです。
| 症状レベル | 入院期間(目安) |
|---|---|
| 軽症 | 1〜2カ月 |
| 中等症〜重症 | 3〜6カ月 |
ただし、これはあくまで平均的な目安であり、個々の患者の回復状況によって大きく変動します。
また、入院中は定期的な面会や病室の環境整備(写真や好みの物の配置など)を通じた家族間の寄り添いが大切です。患者の回復意欲を高めることにもつながります。
くも膜下出血になった方の平均余命
くも膜下出血になった方の平均余命は、年齢・合併症・治療内容などにより個人差が大きいため確実なことは一概に言えないものの、生存率に関しては以下のようになります。
-
発症後1年の生存率: 約80%※1
-
発症後5年の生存率: 約55%※2
※1:参考文献における1年以内の致死率(男性19.5%、女性19.3%)から算出(生存率 = 1 – 致死率)
※2:参考文献:「脳卒中患者の生命予後と死因の5年間にわたる観察研究: 栃木県の調査結果とアメリカの報告との比較」
くも膜下出血は特徴として発症直後は死亡のリスクが非常に高い傾向にあるだけでなく、再出血や血管攣縮といった合併症のリスクが伴うため、5年後の生存率は約55%となっています。
しかし、適切な治療と発症後のケアによって予後を改善できる可能性もあります。
とくに急性期治療はもちろんのこと、その後のリハビリテーションや生活習慣の改善は、再発予防や後遺症の軽減につながるでしょう。
くも膜下出血後の余命や生存率について不安を感じる方は多いと思いますが、医師としっかりと相談したうえで、状況に合った治療計画やケアプランを立てることが大切です。
くも膜下出血の後遺症を改善するためにできる再生医療
くも膜下出血の発症後、後遺症なく元通りの生活ができる人は約33.5%※(内訳 全く症候がない:19.8% / 症候あるが明らかな障害はない:13.7%)です。
※出典:日本脳卒中データバンク報告書2023
後遺症を少しでも改善したいとお考えの方は、再生医療を検討してみましょう。
当院では再生医療を取り扱っていて、後遺症が改善する効果が期待できます。
実際にくも膜下出血の後遺症に対して再生医療を受けられた患者様の症例もご紹介していますので、参考にしてみてください。
神経や血管などに変化できる性質のある幹細胞を自身の体から採取し、点滴にて体に送り込む治療方法です。
くも膜下出血の治療は早ければ早いほど良い結果が出る傾向にありますが、時間が経っている方についても効果が期待できますので、興味のある方はお気軽にお問い合わせください。
脳卒中のお悩みに対する新しい治療法があります。
くも膜下出血患者に対して大切なのは家族の思いやり
くも膜下出血になってしまった患者に対して家族にできることは、まずは思いやり、そして行動観察・生活環境の改善・飲食の管理などたくさんあります。
|
大切な家族をしっかりとサポートし、精神面でも支えになれるようにしましょう。
また、脳をはじめとするさまざまな治療で注目を集めている再生医療は、くも膜下出血の再発予防に効果的です。
家族の後遺症に悩んでいたり、再発を恐れている場合は、再生医療による治療も検討してみましょう。

監修者
圓尾 知之
Tomoyuki Maruo
医師
略歴
2002年3月京都府立医科大学 医学部 医学科 卒業
2002年4月医師免許取得
2002年4月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2002年6月関西労災病院 脳神経外科 勤務
2003年6月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2003年12月大阪母子医療センター 脳神経外科 勤務
2004年6月大阪労災病院 脳神経外科 勤務
2005年11月大手前病院 脳神経外科 勤務
2007年12月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2012年3月大阪大学大学院 医学系研究科 修了(医学博士)
2012年4月大阪大学医学部 脳神経外科 特任助教
2014年4月大手前病院 脳神経外科 部長