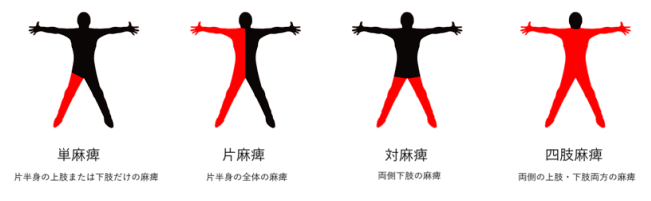- 脳卒中
- 脳梗塞
くも膜下出血の後遺症は右脳と左脳で違いはある?症状からリハビリまでを詳しく解説
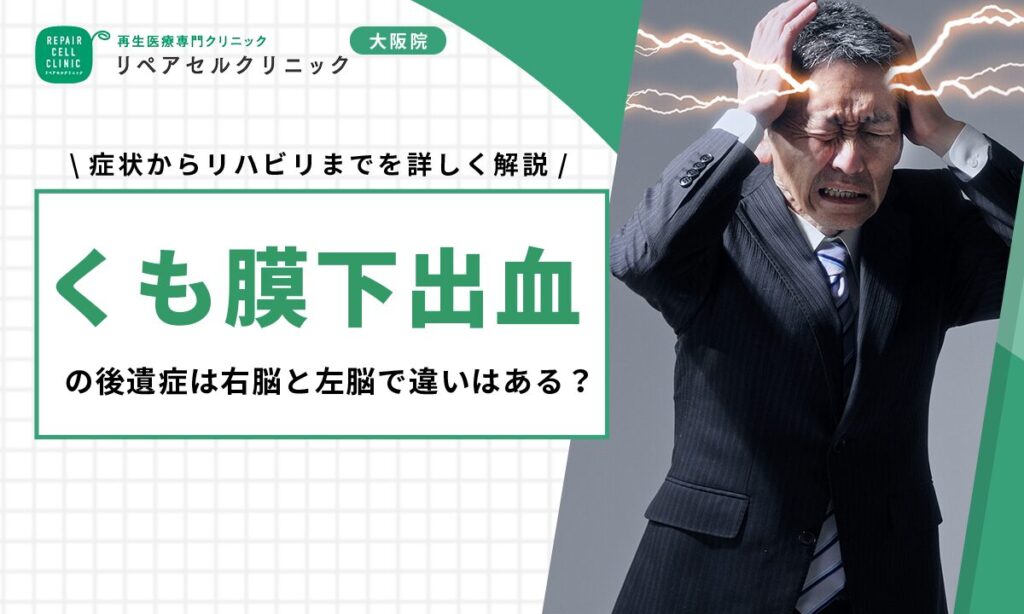
くも膜下出血は、半身麻痺や運動や言語などの神経障害など、多くの後遺症が残る可能性があります。
くも膜下出血の原因は、髄膜という脳の組織の内側にある軟膜と、中間にあるくも膜のすき間にあるくも膜下腔の出血です。
この記事ではくも膜下出血による右脳と左脳の後遺症の違いや、症状からリハビリまで詳しく解説します。
目次
くも膜下出血の後遺症は右脳と左脳で異なる?
くも膜下出血の後遺症は、半身麻痺の場合、右脳では左半身に、左脳では右半身に麻痺症状が出ます。
これは運動機能の中枢は、右脳と左脳の両方にあり、右脳は左半身の運動機能に、左脳は右半身の運動機能につながっているためです。
また、運動機能だけでなく、視覚なども同じ機能のため、右脳と左脳とでは現れる後遺症に左右の違いがあります。
くも膜下出血の後遺症
くも膜下出血の後遺症は、出血した部位や出血量、発症後から治療までの時間などによって、症状や後遺症に違いがあります。
出血量が多い場合や治療が遅れた場合は、脳血管攣縮による脳梗塞などを発症し、その結果として高次脳機能障害や運動障害などの後遺症が残ることがあります。
くも膜下出血の主な症状には次のような後遺症があります。
- 高次機能障害
- 運動障害
- 言語障害
- 感覚障害
- 視野障害
- 嚥下障害
- 排尿障害
- 感情障害
それぞれの症状について解説していきます。
高次脳機能障害
くも膜下出血の後遺症による神経症状に、高次脳機能障害があります。
高次脳機能障害は、脳の損傷による認知障害全般を指していて、失語・失行・失認や、記憶障害、注意障害、遂行機能障害などの症状が含まれます。
また、高次機能障害は外見では判断しにくいことや、本人が認識していないなどの特徴があります。
運動障害
くも膜下出血の後遺症による神経症状は、運動障害です。脳の運動に関わる部位がダメージを受けると、身体を思い通りに動かせなくなります。
運動障害の1つである麻痺は、症状の程度や出現する部位によって名称が決まっています。
痙縮
不全麻痺
完全麻痺
不随意運動
運動失調
|
単麻痺
片麻痺
対麻痺
四肢麻痺
|
くも膜下出血の発症部位の反対側に運動障害が現れることを「半身麻痺」といいます。障害部位と反対側に麻痺が起こる理由は、脳からの指令を全身に伝達する神経が首のあたりで交差しているためです。
|
言語障害
くも膜下出血の後遺症による神経症状に、言語障害があります。言語障害は、構音障害(運動障害性構音障害)と失語症に分けられます。
脳の障害部位により、うまく話せない理由が異なるため注意が必要です。
構音障害(運動障害性構音障害)
くも膜下出血の後遺症による言語障害に、構音障害(こうおんしょうがい)があります。
構音障害は声が出にくかったり、呂律が回らなかったりする言語障害です。
構音障害が起こると、口や舌などの発声・発語器官がうまく機能しなくなってしまいます。
失語症
くも膜下出血の後遺症の1つに、失語症があります。
失語症とは、脳の言語中枢が障害されて考えている言葉とは異なる言葉が出たり、聞いた単語を理解できなくなったりする症状です。
失語症の患者さんは、”言葉がわからない国に、突然放り出されたような状態”となります。
相手の言葉を理解できず、自分の思いも上手に伝えられないためコミュニケーションにストレスを感じやすいのが特徴です。
感覚障害
くも膜下出血の後遺症に感覚障害があります。感覚神経の異常反応によって視覚・聴覚などの知覚に異常が生じたり、鈍くなったりする障害です。
半身の感覚が麻痺したり手足がしびれたりすると、痛覚や温度感覚などが鈍くなる感覚障害が現れる場合があります。
視野障害
くも膜下出血の後遺症に、視野障害があります。視野障害のひとつ「Terson(テルソン)症候群」は、くも膜下出血に伴う眼内出血が原因です。
主に硝子体と呼ばれる部位に出血することで知られています。
症状としては、目のかすみや浮遊物がみえるなどがありますが、さらに悪化すると視力の低下など日常生活に支障を来す場合があります。
嚥下障害
くも膜下出血を発症すると、嚥下障害(えんげしょうがい)が起こる可能性があります。嚥下障害は、食べ物の飲み込みが上手にできなくなる症状です。
嚥下(飲み込み)障害には、窒息や誤嚥性肺炎のリスクもあるため注意が必要です。
排尿障害
くも膜下出血により排尿に関わる神経が障害されると、排尿をコントロールできなくなる症状が現れます。
排尿障害の症状例は、以下のとおりです。
|
排泄に関する症状はデリケートな内容であるため、周囲の人に伝えられずにストレスを感じる場合もあります。
感情障害
くも膜下出血の後遺症に、感情障害があります。感情障害で出現する症状は、以下のとおりです。
|
また、気分障害の一種である「うつ病」になる場合もあります。うつ病は気持ちの落ち込みが長く続き、心の持ちようや精神力をコントロールできなくなる病気です。
うつ病の主な症状は、抑うつ気分や不安感、焦燥感(しょうそうかん:焦りやイライラ感)、不眠、食欲低下などです。
くも膜下出血の後遺症により、日常生活に支障をきたすショックがうつ病の原因になります。
くも膜下出血の後遺症に対するリハビリ
くも膜下出血の後遺症に対するリハビリは、「急性期」「回復期」「維持期」の3段階に分けられます。
症状や障害の程度に応じて、理学療法(基本動作)、作業療法(日常生活動作)、言語聴覚療法(コミュニケーション機能)を組み合わせてリハビリを実施します。
急性期リハビリテーション
くも膜下出血の急性期リハビリテーションは、発症からおよそ1~2カ月以内※ とされています。
※出典:厚生労働省「脳卒中に関する留意事項」
発症直後はベットから起き上がれない状態となることが多いため、麻痺した側の手足の関節が固まってしまうことや、麻痺していない筋力が低下する可能性があります。
そのため、急性期では手足を動かしたり、筋力をつけるなど、ベットサイドで簡単にできるリハビリを行います。
回復期リハビリテーション
くも膜下出血の回復期リハビリテーションは、発症からおよそ3~6ヵ月とされています。
主に、立ち上がりや歩く動作のほか、箸の練習から着替えなど、日常生活における動作を中心に行われます。
回復期で行われるリハビリは、歩行といった日常生活の確立を目標として実施されます。また、機能が低下している部分の回復も重要です。
維持期リハビリテーション
くも膜下出血の維持期リハビリテーションは、発症から6ヵ月以降とされています。
回復期で行ってきたリハビリの継続や、取り戻した身体機能の維持など日常生活の自立と社会生活への復帰を目指す段階です。
つまり、維持期ではくも膜下出血によって、後遺症として残った機能障害の改善だけでなく、生活の質の向上を目的としています。
くも膜下出血の後遺症改善のための選択肢「再生医療」について
近年、くも膜下出血だけでなく脳出血や脳梗塞などにおいて、新たな治療の選択肢として再生医療があります。
くも膜下出血を含む脳卒中に対する治療として、再生医療の幹細胞治療が行われています。
以下の動画では、実際に再生医療の治療を受け、くも膜下出血の後遺症が改善した患者さまの症例を紹介しているため、併せて参考にしてください。
>>その他のくも膜下出血を含む脳卒中に対する再生医療の症例はこちら
再生医療について詳しい情報をご希望の方は、当院「リペアセルクリニック」にご相談ください。
無料のメール相談やオンラインカウンセリングを承っております。
脳卒中のお悩みに対する新しい治療法があります。
【まとめ】くも膜下出血の後遺症は早期リハビリと適切な治療が重要
くも膜下出血による後遺症は、神経症状など個人によって差があります。
しかし、急性期から維持期まで、適切なリハビリを行うことにより低下した身体機能を回復させ、日常生活への支障を軽減することができます。
くも膜下出血に対する治療法としては、再生医療も選択肢の一つとして挙げられます。再生医療は、患者様自身の幹細胞を採取・培養し、体内の損傷した部位に投与する治療法です。
くも膜下出血による後遺症にお悩みの方は、ぜひ当院「リペアセルクリニック」へ一度ご相談ください。

監修者
圓尾 知之
Tomoyuki Maruo
医師
略歴
2002年3月京都府立医科大学 医学部 医学科 卒業
2002年4月医師免許取得
2002年4月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2002年6月関西労災病院 脳神経外科 勤務
2003年6月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2003年12月大阪母子医療センター 脳神経外科 勤務
2004年6月大阪労災病院 脳神経外科 勤務
2005年11月大手前病院 脳神経外科 勤務
2007年12月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2012年3月大阪大学大学院 医学系研究科 修了(医学博士)
2012年4月大阪大学医学部 脳神経外科 特任助教
2014年4月大手前病院 脳神経外科 部長