- 脳梗塞
- 脳卒中
- 頭部
脳梗塞後の言語障害は治る?リハビリや回復率、家族ができるサポートについて解説

脳梗塞の後遺症による言語障害で「言葉がうまく話せない」「思ったことを伝えられない」といった症状にお悩みの方は多いです。
言語障害には、失語症や構音障害などの症状があり、回復のスピードは個人差があります。
本記事では、脳梗塞後に起こる言語障害から回復する割合や期間、回復率を高める方法について詳しく解説します。
また、近年の治療では、今まで損傷して元に戻らないといわれていた脳細胞が改善する可能性があるとして再生医療が注目されています。
損傷を受けた脳細胞の修復を促すことで再発リスクを抑えるとともに、言語障害をはじめとする後遺症の緩和にもつながる治療法です。
当院リペアセルクリニックの公式LINEでは、再生医療の治療に関する情報を配信しています。
「言語障害がなかなか改善しない」「再生医療について詳しく知りたい」という方は、ぜひ当院リペアセルクリニックまでご相談ください。
▼脳梗塞の後遺症治療に注目
>>公式LINE限定の再生医療に関する情報を見てみる
目次
脳梗塞後の言語障害は治る可能性がある
脳梗塞による言語障害は、適切なリハビリテーションによって改善が期待できます。
医療技術の進歩により脳血管障害による死亡率は減少しており、若い患者の約7割※が発症直後からリハビリを受けることで症状が改善し職場復帰が可能です。
※出典:厚生労働省「脳卒中に関する留意事項」
復職率は発症から3〜6か月後、または1年〜1年半後に上昇し、最終的には50〜60%に達します。
経過は急性期、回復期、生活期に分かれ、患者は治療状況や職場への配慮を医療機関と相談する必要があります。
脳梗塞による失語症の回復率
脳梗塞後に失語症がみられた患者さまの約74%の方が、発症から6ヶ月後に症状が改善している※と報告されています。
※出典:PubMed
発症から6ヶ月までの「回復期」と呼ばれる期間に適切なリハビリテーションを行うことで、失語症の改善が期待できることがわかるでしょう。
また、発症6ヶ月以降でも回復期ほどではないものの失語症が改善する傾向があります。
失語症にお悩みの方は、諦めずに適切なリハビリテーションを継続することが重要です。
脳梗塞後の言語障害でみられる症状とメカニズム
脳梗塞後の言語障害でみられる症状と発症のメカニズムについて解説します。
それぞれの症状について詳しく解説していきます。
失語症
失語症は、脳梗塞などにより脳の言語機能が損なわれ、読む・書く・話す・聞く能力に影響を及ぼす症状です。
脳梗塞によって大脳の言語をつかさどる領域が損傷することで、言語機能に大きな影響を与えます。
回復には年齢や損傷部位、健康状態などが関わりますが、継続的な言語訓練によって大幅な改善が期待できます。
リハビリの内容としては、口や舌の運動、ジェスチャーを交えた会話、書字の訓練などがあります。
症状や進行具合に応じてリハビリ内容が調整され、患者さまにあったプランを作成します。
構音障害
構音障害は、脳梗塞によって脳幹や脳幹につながる神経線維が損傷することで、唇や舌が麻痺して言葉を発音しづらくなる症状です。
言葉を発音しづらくなるだけのため、失語症を合併していない場合は、聞く能力や文字を読み書きする能力に影響はありません。
治療法としては「外科的介入」「発音補助装置の利用」「構音訓練」の3つがあり、患者の症状に応じて選択されます。
外科手術では発音機能を改善し、補助装置を使用して発声を補助します。
また、言語聴覚士がリハビリテーションを通じて舌や口の運動機能を高め、呼吸・発声・音読の向上を目指します。
早期のリハビリテーションが回復において重要な役割を果たすため、少しでも違和感を感じたら速やかに医療機関を受診しましょう。
脳梗塞後の言語障害に対するリハビリテーション
脳梗塞発症後の言語障害のリハビリについては、意識状態など症状が安定し始めた頃から適切な対処が必要となります。
言語能力が維持・向上し続けるためには、主に発症からおよそ1~2カ月以内の急性期、約3〜6ヶ月の回復期、自宅へ戻ってからの生活期と、それぞれのリハビリを行うことが重要です。
また、急性期・回復期においては、医療保険が適用される病院でのリハビリが行われますが、適用期間については基本的に脳梗塞は150日、高次機能障害を伴う重篤の場合は180日と定められていて、その後介護保険が適用される生活期へと移行していきます。
この3段階のリハビリをどのように行っていくのかをそれぞれ詳しく紹介していきます。
急性期のリハビリテーション
急性期のリハビリでは、言語聴覚士が中心となり、口の動きの練習など患者の発話に合わせた言語機能回復訓練を行うことにより、発話意欲を高めていくことが重要となります。
また、挨拶など実用的なコミュニケーションが最も重要で、毎回顔を合わせるたびに挨拶を行い、時間帯で違う挨拶が返ってきても決して否定しないことが大切です。
患者だけでなく、ご家族の方もコミュニケーション方法をしっかり習得して、患者の言語機能の変化を追跡していくと同時に、患者が安心してリハビリに取り組んでいける環境づくりも、急性期では重要となります。
回復期・維持期のリハビリテーション
回復期のリハビリは失語症と構音障害により違いがありますが、基本的にはどちらも発話や読み書き、言葉の理解などを中心とした訓練を行うことが重要です。
リハビリでは、言語聴覚士が回復に向けたプランを作成しますが、患者本人の意欲を高めるためには、家族のサポートが何より重要です。そのサポートがリハビリの効果をさらに向上させます。
脳梗塞のリハビリ期間は病院などにより違いはありますが、原則発症から6ヵ月が経過した段階で生活期へと移行します。基本的には回復期で行ってきたリハビリは継続しながら、社会活動への参加なども行います。
脳梗塞後の言語障害に対して家族ができるサポート
脳梗塞後の言語障害のリハビリでは、主に言語聴覚士が行いますが、日常生活の中でご家族がサポートすることも重要です。
以下では、それぞれのサポート内容について詳しく解説していきます。
あいさつや日常会話のコミュニケーションを大切にする
「おはよう」や「いただきます」といった簡単なあいさつなど、日常的に会話の機会を増やしていくことが大切です。
重度の失語症の場合でも、家族が発音した言葉を真似て言うことが可能なので、日常会話のミュニケーションは積極的に行いましょう。
また、難しい質問などは控えて、患者さまが「はい」「いいえ」で答えられる簡単な質問も効果的です。
日記や手帳など読み書きを一緒に行う
日記や手帳にその日の出来事や今後の予定を書くなどの読み書きの練習を一緒に行うことが重要です。
文章を書くのが難しい場合は「名前」「生年月日」「住所」などの簡単な文字から書いてみるのが良いです。
書ける文字が増えてきたら、徐々に長い文章や申込書などを患者さまが自分で記入できることを目標にしてみましょう。
思考能力は低下していないことを理解する
患者さまが言語障害によって会話や読み書きが難しい場合でも、思考能力は低下していないことを理解することが重要です。
例えば、失語症によって言葉をうまく話せなくなった患者さまに対して、小さな子供に接するような態度をとってしまうケースがあります。
患者さまの自尊心が傷ついてしまうことも少なくないため、患者さまの症状を理解して寄り添う気持ちを持ちましょう。
脳梗塞後の言語障害にお悩みなら再生医療も選択肢の一つ
脳梗塞後の言語障害にお悩みの方は、再生医療による治療も選択肢の一つです。
今まで損傷した脳細胞や神経は元に戻らないといわれていましたが、再生医療によって改善する可能性があるとして注目されています。
損傷を受けた脳細胞の修復を促すことで再発リスクを抑えるとともに、言語障害をはじめとする後遺症の緩和にもつながります。
再生医療による治療は、開始時期が早いほど高い治療成績をもたらします。
また、当院リペアセルクリニックの公式LINEでは、脳梗塞の言語障害の改善が期待できる再生医療に関する情報を配信中です。
「言語障害のリハビリを頑張っても改善がみられない」「患者さまの言語障害を早く治してあげたい」という方は、ぜひ再生医療について知っておきましょう。
▼脳梗塞の後遺症治療に注目
>>公式LINE限定の再生医療に関する情報を見てみる
脳梗塞後の言語障害は適切なリハビリで回復を目指せる
脳梗塞による言語障害は、適切なリハビリを行うことで日常生活への影響を軽減し、言語機能を改善できる可能性があります。
また、言語障害のリハビリは患者さま本人だけでなく、ご家族の理解やサポートが重要です。
症状について理解し、患者さまの気持ちに寄り添って日常生活をサポートしましょう。
当院リペアセルクリニックでは、脳梗塞による後遺症の改善が期待できる再生医療をご提供しています。
「言語障害がなかなか改善しない」「再生医療について詳しく知りたい」という方は、ぜひ当院リペアセルクリニックまでご相談ください。
また以下の動画でも、実際の症例を紹介していますので、ぜひご確認ください。
現在、公式LINEでも再生医療に関する情報を配信しているため、まずはお手持ちのスマホから確認してみてくださいね。
▼脳梗塞の後遺症治療に注目
>>公式LINE限定の再生医療に関する情報を見てみる

監修者
圓尾 知之
Tomoyuki Maruo
医師
略歴
2002年3月京都府立医科大学 医学部 医学科 卒業
2002年4月医師免許取得
2002年4月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2002年6月関西労災病院 脳神経外科 勤務
2003年6月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2003年12月大阪母子医療センター 脳神経外科 勤務
2004年6月大阪労災病院 脳神経外科 勤務
2005年11月大手前病院 脳神経外科 勤務
2007年12月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2012年3月大阪大学大学院 医学系研究科 修了(医学博士)
2012年4月大阪大学医学部 脳神経外科 特任助教
2014年4月大手前病院 脳神経外科 部長
あわせて読みたいトピックス
-

脳卒中における二木の予後予測とは|回復期リハビリテーションの重要性と注意点を解説
-
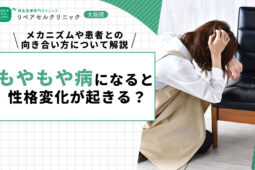
もやもや病になると性格変化が起きる?メカニズムや患者との向き合い方について解説
-

くも膜下出血は後遺症がなくても再発するリスクがある!注意点を解説
-

橋梗塞の症状とリハビリの進め方|具体的なプログラムとポイントについて解説
-

脳出血の看護ケア|在宅でも家族ができることや注意点・ポイントについて解説
-

脳出血の入院期間|年齢別・重症度別の違い、入院費用について解説【医師監修】
-

高次脳機能障害の回復事例を紹介!経過や治療・リハビリが大切な理由も解説
-

高次脳機能障害患者の家族が抱えるストレスとは?つらさの理由と無理をしない接し方を紹介
















