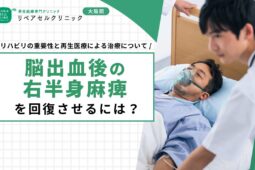- 幹細胞治療
肝硬変の合併症と治療法について詳しく紹介!|適切な治療方法についても医師が徹底解説

肝硬変と診断されて「今後どのような合併症が起こるのか」「どのような治療法があるのか」と不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
肝硬変は肝臓が線維化して硬くなる疾患であり、進行すると様々な合併症を引き起こす可能性があります。
本記事では、肝硬変で起こりやすい合併症とその治療法について詳しく解説します。
元の状態に戻すのが難しいといわれている肝硬変に対しての新たな治療法である再生医療についてもご紹介します。
また、当院の公式LINEでは肝硬変の根本的な治療が期待できる再生医療の症例を公開しているため、ぜひご覧ください。
目次
肝硬変の合併症を紹介
肝硬変が進行すると、肝機能の低下などにより以下の合併症が現れるリスクがあります。
これらの合併症は患者さまの生活の質を下げるだけでなく、命に関わる可能性もあるため、早期の発見と適切な治療が重要です。
腹水
腹水は、肝硬変でも多く見られる合併症の一つです。
主に以下の症状があります。
- 腹部の膨満感(お腹が張って重い・苦しい感覚)
- 呼吸困難
肝硬変により血中のアルブミンが低下し、肝臓に血液を送る門脈の圧力が高くなるのが原因です。
治療では減塩食(1日7g以下)から始まり、利尿薬の内服、アルブミン点滴投与、腹水濃縮再静注療法(CART)などが行われます。
呼吸困難や腹部膨満感が強い場合は、応急処置として腹水穿刺排液(溜まった腹水を抜く処置)も実施されます。
肝性脳症
肝性脳症は、肝機能低下によりアンモニアなどの毒素が蓄積し、脳機能が低下する状態です。
主に以下の症状があります。
- 軽度の昼夜逆転症状(体内時計が正しく機能せず生活リズムが崩れる)
- 羽ばたき振戦(手が羽ばたくように震える症状)
- 意識消失
治療方法としては、たんぱく質の適量摂取や便秘の改善のための栄養療法、血中のアンモニア濃度をコントロールするための薬物療法が行われます。
食道静脈瘤
食道静脈瘤は、肝臓への血管の圧力が高くなることで食道や胃の静脈が拡張し、瘤(こぶ)状になった状態です。
主に以下の症状があります。
- 基本的には無症状(内視鏡検査でしか発見できない)
- 破裂時には吐血や下血がみられ生命に危険が及ぶ
一度破裂すると消化管の中に大出血を起こし、吐血や下血がみられ、命に危険が及ぶこともあります。
内視鏡検査で赤い斑点(Red Color Sign)が見られた場合は破裂の危険が高いため、予防的治療が必要です。
治療法には、内視鏡を用いて静脈瘤を縛る内視鏡的結紮術(けっさつじゅつ)や、薬で固める食道静脈瘤硬化療法があり、患者さまの状態に応じて選択されます。
肝腎症候群
肝腎症候群は、肝硬変により体内の血液量が低下し、腎臓への血流が悪くなって腎機能障害が起こった状態です。
主に以下の症状があります。
- 尿量の減少
- 腹水の悪化
- 血中クレアチニン値の上昇
肝硬変の患者さまが肝腎症候群を診断するには、腎臓が上手く機能しているかの基準となる血中クレアチニンを定期的に検査することが重要です。
肝腎症候群の治療では、血液製剤のアルブミン投与や血圧を上げる薬の使用、重症例では肝移植が検討されます。
肝肺症候群
肝肺症候群は、肝硬変が原因で肺の細い動脈が拡張されることで、血中の酸素濃度が低くなった状態です。
主に以下の症状があります。
- 座位や立位での息苦しさ(横になると改善する場合がある)
- ばち指(指が太鼓のばちのように膨れる)
- 呼吸困難
肝硬変により肺の血管に異常が生じ、肺内の血液量が増えることで血液中の酸素が十分に取り込めなくなります。
特徴的なのは、座ったり立ったりしたときに息苦しさを感じ、横になると改善することです。
治療には主に酸素投与を行いますが、原因となる肝臓の機能を元に戻すことができないため、根本的な治療につながるのは肝移植のみとなります。
肺高血圧症
肺高血圧症は、肝硬変により血液の流れが変化し、肺の血管の圧力が高くなった状態です。
主に以下の症状があります。
- 息苦しさ
- 足のむくみ
- 動悸
- 失神
治療では、肺の血管を広げる薬(マシテンタンなど)が使用され、症状の改善や進行を遅らせる効果が期待できます。
特発性細菌性腹膜炎
特発性細菌性腹膜炎は、お腹にたまった水(腹水)に細菌が感染した状態で、肝不全への進行が懸念される合併症です。
主に以下の症状があります。
- 腹部不快感
- 発熱
- 腹水の増加
肝硬変の方は感染症にかかりやすく、通常の検査では見つけにくいため、腹水の検査で診断します。
早期発見が重要なため、定期的な検査が必要です。
特発性細菌性腹膜炎と診断された場合は、抗生物質の点滴で治療を行います。
肝臓がん
肝臓がんは、肝硬変の患者さまに高い頻度で発症する重篤な合併症の一つです。
主に以下の症状があります。
- 初期は無症状
- 疲労感
- 体重減少
- 腹部の違和感
肝硬変と診断された方は、定期的な腹部エコーなどの画像検査で経過観察を行うことが重要です。
血液検査も参考になりますが、最終的な診断には組織を取って調べる生体検査が必要です。
治療法はがんの大きさ・数・肝硬変の程度により決定されます。
早期発見により治療選択肢が広がるため、定期的な検査受診が不可欠です。
白血球減少症
白血球減少症は、肝硬変によって脾臓(ひぞう)が腫れて大きくなり、その中に白血球が捕えられてしまうことで起こる合併症です。
主に以下の症状があります。
- 発熱
- 感染症の症状が頻繁に起こる
白血球が減ると感染症にかかりやすくなるため、手洗いやうがい、予防接種などで感染症を防ぐことが重要です。
重度の場合は脾臓の手術が検討されることもあります。
皮膚のかゆみ
皮膚のかゆみは、肝硬変を含む肝疾患で生活の質を大きく低下させる症状の一つです。
主に以下の特徴があります。
- 皮膚の強いかゆみ
- 黄疸と併せて現れることが多い
- 抗ヒスタミン薬が効かない
皮膚のかゆみが起こるのは、肝機能低下による胆汁処理能力の低下が原因です。
症状は肝機能の改善とともに軽減されることがあり、スキンケアや適切な保湿も症状緩和に役立ちます。
また、抗ヒスタミン薬では効果が不十分な場合、ナルフラフィンという薬がかゆみに効くことがあります。
早期発見と適切な治療により症状の悪化を防ぐことができるため、異変を感じたら早めに医療機関を受診しましょう。
肝硬変の合併症に対する治療法
肝硬変の合併症に対する治療は、それぞれの症状に応じた以下の対症療法が中心です。
治療法は主にこれらの3つに分けられ、患者さまの状態や合併症の種類に応じて組み合わせて実施されます。
食事療法
食事療法は合併症の種類に応じて食事内容を調整することが必要です。
| 症状・合併症 | 食事のポイント |
|---|---|
| 腹水・むくみの場合 | 塩分制限(5~7g/日)が最も重要で、適度な水分制限も行う |
| 食道静脈瘤の場合 | 刺激物や硬い食物を避け、よく噛んでゆっくり食べる |
| 肝性脳症の場合 | たんぱく質を適度に摂取し、食物繊維を多く摂る |
| 糖尿病合併の場合 | 一度に大量に食べることを避け、砂糖や果物を控えめにする |
肝機能が保たれている場合は一般的な食事で問題ありませんが、肝機能が低下している場合は分割食(1日3~5回)や就寝前軽食(200kcal程度)が推奨されます。
また、分岐鎖アミノ酸(BCAA)製剤による栄養補充も重要です。
薬物療法
薬物療法は各合併症の症状緩和と進行抑制を目的として実施され、患者さまの症状に応じて以下のように適切な薬剤が選択されます。
| 症状・合併症 | 食事のポイント |
|---|---|
| 肝性脳症 | ラクツロース、分岐鎖アミノ酸製剤、リファマイシン系抗菌薬、亜鉛製剤、カルニチン製剤 |
| 腹水 | フロセミド、スピロノラクトン、トルバプタンなどの利尿薬 |
| 皮膚のかゆみ | ナルフラフィン塩酸塩 |
| こむら返り | 芍薬甘草湯、カルニチン、BCAA、亜鉛製剤 |
| 血小板減少 | アバトロンボパグ、ルストロンボパグ |
| 肺高血圧症 | マシテンタンなどの肺動脈拡張薬 |
それぞれの薬剤には副作用もあるため、医師の指導のもとで適切に使用します。
肝移植
肝移植は肝硬変が進行し、他の治療法が効果を示さない場合の最終的な治療選択肢です。
肝移植には生体肝移植と脳死肝移植の2種類があります。
| 症状・合併症 | 食事のポイント |
|---|---|
| 生体肝移植 | 健康なドナー(主に家族)の肝臓の一部を移植する方法で、待機時間が短いメリットがある |
| 脳死肝移植 | 脳死状態の方からの肝臓提供で、肝臓全体を移植できるが待機時間が長くなる可能性がある |
肝移植後は拒絶反応を防ぐため免疫抑制剤の生涯服用が必要です。また、感染症リスクの増加などの副作用もあります。
すべての肝硬変患者さまが移植を受けられるわけではなく、年齢、全身状態、他の臓器の機能などを総合的に評価して適応が判断されます。
手術自体にも全身麻酔による合併症や周囲臓器損傷のリスクが伴うため、慎重な検討が必要です。
肝硬変の合併症の治療法には再生医療も選択肢の一つ
一般的に、肝硬変で線維化した肝臓が元に戻ることは難しいとされています。
しかし、肝硬変および合併症に対して再生医療という新しい治療選択肢があることをご存じでしょうか。
肝臓疾患に対する再生医療では、点滴投与(静脈注射)により多様な細胞に分化する能力を持つ幹細胞を弱った肝臓に届けます。
また、入院を伴う大きな手術を必要としない点滴による治療のため、身体への負担が少ないという利点もあります。
食事を含む生活習慣の改善と合わせて再生医療による治療も検討しましょう。
再生医療について詳細は、以下をご覧ください。
手術をしない新しい治療「再生医療」を提供しております。
肝硬変の合併症に応じて適切な治療を受けることが重要
肝硬変の合併症は多岐にわたり、それぞれに応じた適切な治療法があります。
早期発見と早期治療により、症状の悪化を防ぎ生活の質を維持することが可能です。
食事療法では合併症の種類に応じた栄養管理が重要で、薬物療法では症状緩和と進行抑制を目的とした治療が行われます。
重篤な場合は肝移植も選択肢となりますが、すべての患者さまが適応となるわけではありません。
また、肝硬変および合併症に対しては、再生医療という新しい治療法もあります。
当院リペアセルクリニックでは患者様一人一人に合わせた独自の再生医療で、体に負担を少なく症状が改善することが可能です。
以下では、当院の再生医療によって脂肪肝や肝硬変の改善が見られた症例を公開していますので、併せて参考にしてください。
>再生医療による肝疾患の症例はこちら
肝硬変の合併症でお困りの方は、一人で悩まずぜひ一度当院へご相談してみてください。

監修者
岩井 俊賢
Toshinobu Iwai
医師