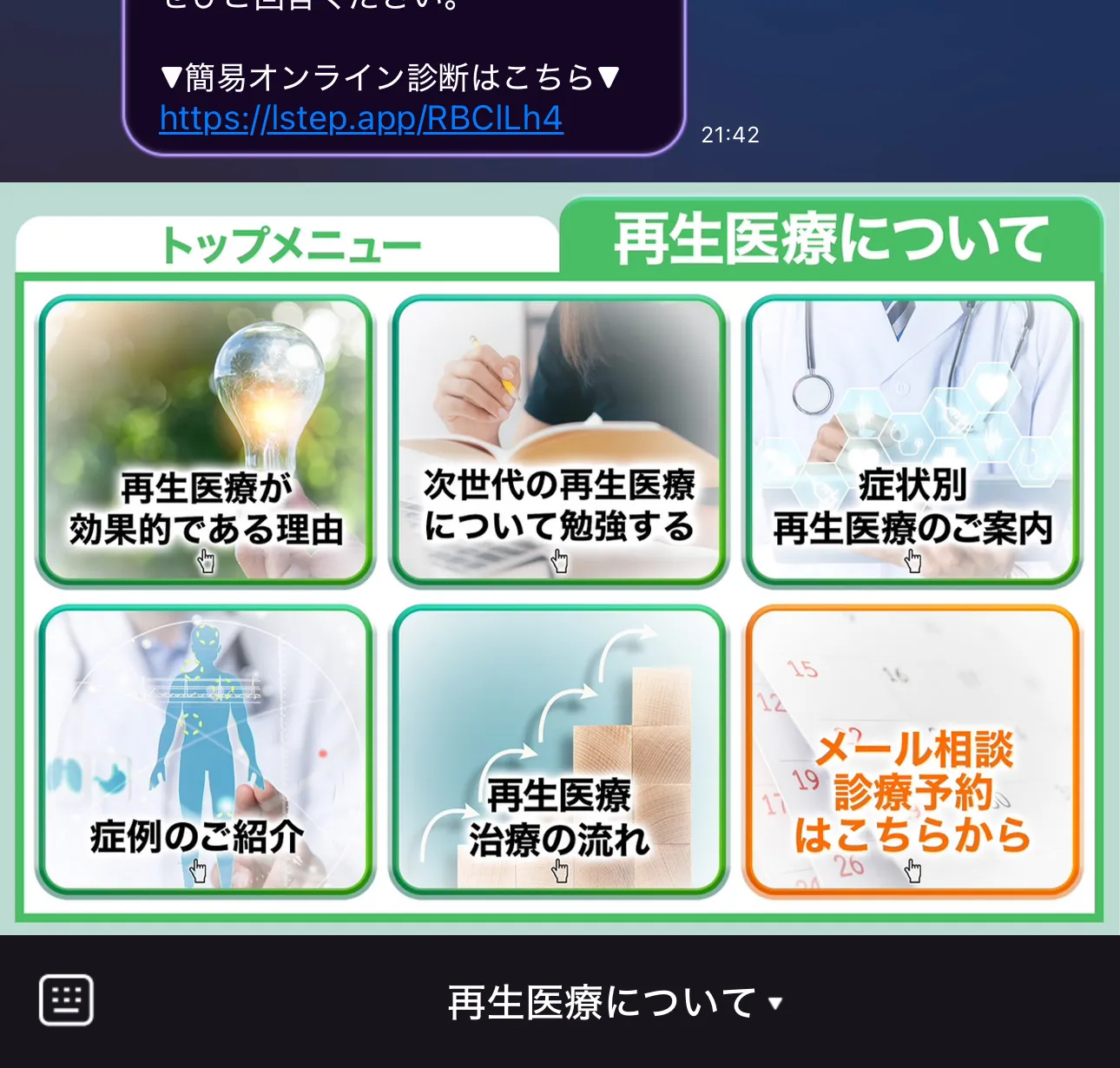半月板損傷を手術するデメリットとは?手術を回避する治療法も解説
公開日: 2020.02.29更新日: 2025.06.30
現在、半月板損傷と診断されて手術をすすめられている方や、すでに保存療法(投薬・リハビリ)を受けているものの、なかなか改善を感じられない方の中には、「このまま今の治療を続けて本当にいいのか?」「もっと自分に合った方法があるのでは?」と疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
実際、半月板損傷の治療では手術療法が選択されることが多い一方で、手術には一定のデメリットやリスクも伴います。
手術に対して不安を感じたり、慎重に判断したいという方も少なくないでしょう。
本記事では、半月板損傷の手術のデメリット・メリットについて詳しく解説します。
また、当院(リペアセルクリニック)の公式LINEでは手術以外の治療法も紹介していますので、ぜひ参考にしてご自身の症状やライフスタイルに合った治療法を選びましょう。
目次
半月板損傷における手術のデメリット
半月板損傷における手術のデメリットは、主に以下4つあります。
それぞれのリスクについて、詳しく解説します。
また半月板損傷を手術せずに放置するリスクについては、以下の記事でも解説していますので参考にしてください。
感染症にかかるリスクが上がる
半月板損傷の手術を受けると、感染症にかかるリスクがあります。
内視鏡(関節鏡)手術の場合で細菌感染する可能性は1%以下※となっています。
※参考:さいたま市「半月板損傷について」
しかし、ごくまれに感染症にかかると、傷口の化膿や関節に膿がたまるなどの症状が発生します。
感染を予防するために、手術後に抗生物質が投与されるケースがあるのです。
感染症に対しては適切な対策が講じられているため、過度に心配する必要はありませんが、術後の体調や傷口の状態には注意を払うことが大切です。
知覚神経を傷つける可能性がある
手術中に、皮膚の表面にある知覚神経を傷つける可能性があります。
ごくまれなケースですが、万が一神経が傷ついた場合、皮膚の感覚が鈍くなり、熱いものや鋭利なものに触れても気づきにくくなるため、二次的なケガのリスクが高まるおそれがあります。
このような知覚神経の損傷は、頻度は高くないものの、半月板手術における注意すべきリスクの一つです。
術後の違和感に気づいた場合は、早めに医師に相談しましょう。
仕事復帰までの期間が長くなる
半月板損傷の手術後は、再断裂を防ぐために慎重かつ継続的なリハビリが必要で長期にわたります。
手術後にリハビリを十分にせず無理に動かすと、再断裂のリスクが高まるので、仕事に復帰するうえでリハビリが重要です。
復帰までの期間は、以下のように異なります。
手術後にリハビリを十分にせず無理に動かすと、再断裂のリスクが高まるので、仕事復帰のタイミングにも注意が必要です。
仕事への復帰時期は、焦らずに回復を目指し、主治医と相談しながらリハビリの進捗を見て判断しましょう。
変形性膝関節症のリスクが高まる可能性がある
半月板の一部またはすべてを切除すると痛みや腫れは改善されますが、膝のクッション性が低下し将来的な変形性膝関節症のリスクが上がります。
そのため、近年では可能な限り半月板を温存する方向が主流であり、切除術(部分・全切除)ではなく、半月板縫合術が優先されるケースが増えています。
手術を受ける際は、将来的なリスクも考慮しながら医師と相談することが大切です。
また、半月板損傷の手術には他に以下のような後遺症の可能性があります。
- 静脈血栓塞栓症(肺血栓塞栓症)
- しびれ
術後の経過は個人差が大きいため、不安な症状が現れた場合は、自己判断せずに早めに医療機関に相談することが大切です。
半月板損傷に対して手術を行うメリット
半月板損傷に対して手術を行うメリットは、主に以下の3つがあります。
- 痛みの緩和
- 可動域の改善
- 変形性膝関節症のリスクを減らす
手術にはリスクも伴いますが、症状の進行を防ぎ、日常生活やスポーツ活動への早期復帰を目指せます。
また手術を行うことで、半月板損傷による痛みを緩和できる可能性があります。
損傷部位によっては膝の可動域が制限されることがありますが、手術によって関節内の動きがスムーズになり、可動域の回復が見込まれます。
半月板が傷ついたまま放置されると膝関節の軟骨がすり減り、やがて変形性膝関節症へ進行するリスクが高まります。
適切なタイミングで手術を行うことで、膝関節全体の機能を保ち、長期的な関節の健康を守ることが可能です。
半月板損傷の手術方法
半月板損傷に効果的な手術は、主に3つあります。
それぞれの手術について、詳しく解説していきます。
半月板損傷の治療法に関しては以下の動画(3:12~)でも解説していますので、併せて参考にしてください。
縫合術
| メリット |
|
| デメリット |
|
縫合術は、損傷した軟骨を縫い合わせる方法です。
膝のふた近くに穴を開け、関節鏡や器材を挿入して患部を縫合します。
切除術
切除術は、半月板の損傷した箇所を切り取る手術方法です。損傷部位の縫合が困難な場合は切除術が検討されます。
| メリット |
|
| デメリット |
|
縫合術と同じように、膝のふた付近に穴を開け、関節鏡を挿入して手術を行います。
専用のハサミを用いて患部の一部またはすべてを切除します。
再生医療も選択肢のひとつ
変形性膝関節症の手術として、再生医療も効果的です。
再生医療は患者さま自身の幹細胞を利用するため、拒否反応のリスクが低い手術です。また、リハビリ期間の短縮が期待できるため、早期に仕事へ復帰できる可能性があります。
長期の入院ができない方や人工関節の手術に抵抗がある方は、再生医療をご検討ください。
膝の痛みは⼿術しなくても治療できる時代です。
半月板損傷の手術に関するよくある質問
半月板損傷の手術に関する質問を紹介します。
3つの質問について、詳しく回答します。
半月板損傷で手術した場合の入院期間はどのくらいですか?
縫合術は10~14日、切除術は2~4日程度※の入院が一般的です。
※国立大学法人信州大学「半月板損傷の治療について」
切除術よりも縫合術の方が入院期間が長いケースが多いです。退院した後、しばらくは杖を使って歩行します。
退院後も、しばらく痛みが続く可能性があります。
術後は膝に負担がかかる動作は控えましょう。
半月板損傷の手術費用はどのくらいかかりますか?
半月板損傷の手術費用は、手術の種類・入院日数・自己負担割合などによって変動します。
一般的に3割負担の方の場合、平均的な費用の目安は以下のとおりです。
半月板縫合術:約10~20万円
半月板切除術:約7~15万円
たとえば、70歳以上で3割負担の方が9日間入院した場合、トータルで約9万円程度かかるケースもあります。
また、縫合術よりも切除術のほうが入院期間が短く、結果的に費用が抑えられる傾向がありますが、これは症状や病院の方針によっても異なります。
詳しい費用を確認したい方は、手術を受ける予定の医療機関に直接問い合わせてみましょう。
手術をせずに半月板損傷を治す方法はありますか?
再生医療は、手術をせずに損傷した半月板を治療することが可能です。
再生医療では、自身の細胞から採取して培養した幹細胞を膝に注射します。自分自身の細胞を使用するため、アレルギーなどの反応が少ない点、手術を避けられる点で身体への負担を抑えた治療法と言えます。
また、手術よりも治療期間が短くなるメリットがあります。
半月板損傷の手術を行った10年後はどうなっていますか?
臨床報告によると、一般の方の約30%、スポーツ選手のうち約70%が変形性膝関節症を発症しています。
半月板はひざのクッションの役割をしているため、切除することによって軟骨がすり減ってしまい、変形性膝関節症の原因になります。
とくに、半月板切除術は変形性膝関節症の発症率が高いと言えます。
半月板損傷手術のデメリットを回避できる再生医療を検討しよう
半月板損傷手術は、痛みや腫れを取り除く効果が期待できる反面、以下のようなデメリットがあります。
- 感染症にかかるリスクが上がる
- 知覚神経を傷つける可能性がある
- 仕事復帰までの期間が長くなる
- 変形性膝関節症のリスクが高まる可能性がある
半月板損傷の手術を受けた患者さまの10年後の臨床報告では、一般の方の約30%が変形性膝関節症を発症するなど、手術には大きなリスクが伴います。
しかし、将来的な変形性膝関節症のリスクや感染症にかかる危険性があるので、放置せずに治療を行いましょう。
ただし半月板損傷の手術を受けた患者さまの10年後の臨床報告では、一般の方の約30%が変形性膝関節症を発症するなど、手術には大きなリスクが伴います。
手術に不安がある方、すぐに会社やスポーツに復帰したい方は、再生医療をご検討ください。再生医療は手術しないため入院の必要がなく、リハビリ期間の短縮も期待できる治療法です。
詳しい治療法や症例については、当院(リペアセルクリニック)の公式LINEでも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

監修者
坂本 貞範
Sadanori Sakamoto
医療法人美喜有会 理事長
「できなくなったことを、再びできるように。」
人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの
お手伝いができれば幸甚の至りでございます。
略歴
1997年3月関西医科大学 医学部卒
1997年4月医師免許取得
1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務
1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務
1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務
1999年2月国立大阪南病院 勤務
2000年3月野上病院 勤務
2003年3月大野記念病院 勤務
2005年5月さかもとクリニック 開設
2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任
2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設
2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設