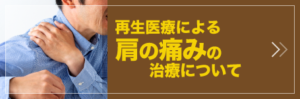石灰沈着性腱板炎は、どれくらい痛みが続くのか?
目次
石灰沈着性腱板炎は、どれくらい痛みが続くのか?
石灰沈着性腱板炎は痛みや関節が動かせないといったつらい症状が出ます。
寝ている時に突然強い痛みに襲われることもあるので、痛みが続くと寝不足にもなってしまいます。なので、石灰沈着性腱板炎の痛みが生じると、いつまで続くのだろうと不安になる人も多いのではないでしょうか。
そこで、ここでは、石灰沈着性腱板炎の痛みの原因やどれくらいの期間痛みが続くのかについて紹介します。

石灰沈着性腱板炎で痛みが続く原因
石灰沈着性腱板炎の痛みは、石灰が沈着することによる腱板の炎症によるものです。
沈着する石灰はリン酸カルシウム結晶で、なぜリン酸カルシウムが沈着してしまうのかは解明されていません。
また、石灰が付着しても必ず痛みが生じるわけではないので、症状が出ていない人のなかにも石灰が沈着している人はたくさんいます。
沈着した石灰が硬くなって膨らんでしまうこともありますが、そうなると痛みが増してきますし、腱板を破って関節の周囲にある滑液包へ出てしまうと強烈な痛みが生じます。
石灰沈着性腱板炎の痛みが続く期間
石灰沈着性腱板炎には3つの型(急性型、亜急性型、慢性型)があり、この型によって痛みが続く期間が異なります。
急性型
急性型は発症してから1週間から4週間に炎症によって強い痛みが生じるタイプです。
沈着する石灰はミルク状です。そして、体内で一部吸収されることもあり、自然に消滅することもあります。
石灰が消滅し炎症も治まれば痛みも生じなくなるのですが、多くの場合、残存します。
亜急性型
亜急性型は1ヶ月から半年くらい痛みが続くタイプです。
急性型のような症状が出たり、症状が治まったりするのを繰り返すのが特徴です。
慢性型
慢性型は6ヶ月以上痛みが続くタイプです。
関節をたくさん動かしたら痛くなったり、腕を挙げると痛くなったりするのが特徴です。
石灰沈着性腱板炎の運動療法と温熱療法
石灰沈着性腱板炎には3つの型があって、痛みが続く期間や痛みの特徴も異なるので、医療機関ではそれぞれの症状に合った治療がおこなわれます。
治療によって痛みが続く状態が終われば、入浴やホットパックなどによる温熱療法や運動療法などのリハビリで強張ってしまった関節周囲の筋肉をほぐしていきます。
まとめ・石灰沈着性腱板炎はどれくらい痛みが続くのか?
石灰沈着性腱板炎の痛みが続く原因やどれくらいの期間痛みが続くのかなどについて紹介しました。
多くの場合では、1週間から4週間くらい安静にしておくことで自然に症状が治まることが期待できますが、悪化して慢性的に痛みが続いたり、関節が動かせなくなったりすることもあります。
早期治療をすれば、早期回復が期待できますし、負担の少ない治療で済ませることができるので、できるだけ早めに医療機関を受診することをおすすめします。
監修:リペアセルクリニック大阪院
| こちらも併せてご参照ください 目次1 石灰沈着性腱板炎の治療には手術が必要なのか?1.1 石灰沈着性腱板炎の手術が検討されるケース1.2 石灰沈着性腱板炎の手術内容1.3 入院期間と術後について2 まとめ・石灰沈着性腱板炎の治療には手術が必要なのか? […]
|