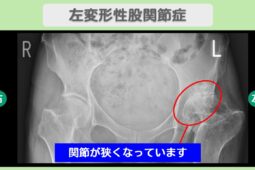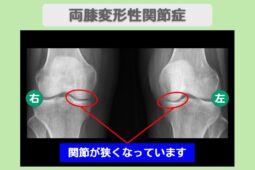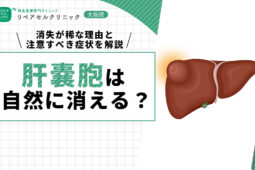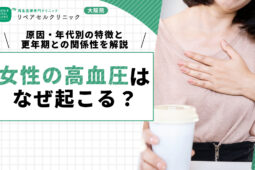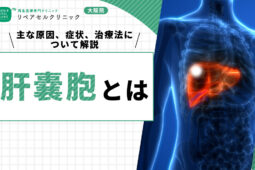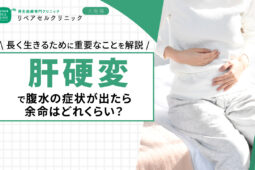- 免疫細胞療法
- 肝疾患
- 再生治療
アルコール性肝硬変は治るのか?回復の可能性と治療法について解説【医師監修】

「アルコール性肝硬変は治るのだろうか」「完治は難しいと聞くけれど、進行を止める方法はあるのか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
アルコール性肝硬変とは、長期間の飲酒により肝臓の細胞が硬く変化し、正常な肝機能が失われていく病気です。
進行すると肝機能が大きく低下し、腹水や意識障害などの重い症状を引き起こす可能性があります。
日常的にお酒を飲む習慣がある方にとって、アルコール性肝硬変は決して他人事ではありません。
この記事では、アルコール性肝硬変の完治の可能性や、進行を抑えるための治療法、早期発見のポイントを詳しく解説します。
肝硬変の症状や治療選択肢を正しく理解することで、適切な対処ができるようになります。
不安を感じている方は、ぜひ最後まで読んで今後の治療方針を考える参考にしてください。
また、現在リペアセルクリニックでは肝硬変の治療法の一つである「再生医療」に関する情報をLINEで発信しているので、ぜひご登録ください。
目次
【結論】アルコール性肝硬変の完治は難しい
アルコール性肝硬変まで進行してしまうと、元の健康な肝臓に戻る(完治する)ケースはほとんどありません。
※参照:全国健康保険協会
ただし、病状の悪化を抑えつつ、ある程度の肝機能を維持しながら日常生活を送ることは可能です。
アルコール性肝硬変の進行を抑制するためには、禁酒が重要です。アルコール依存症になっている場合は、専門医に相談し、早期に治療を開始しましょう。
また、併せて生活習慣の改善も大切です。脂質や塩分を抑え、タンパク質豊富な食事を心がけてください。
肝硬変になる前の脂肪肝の場合は、禁酒や生活習慣の改善が期待できます。
肝臓における生活習慣の見直し方法などについては、以下の記事でも解説していますので、ぜひ参考にしてください。
アルコール性肝硬変の治療法
アルコール性肝硬変の治療法について、進行を抑え症状を緩和するための方法として以下の4つがあります。
これらの治療法を適切に組み合わせることで、肝硬変の進行を遅らせ、生活の質を維持できます。
断酒と食生活の改善
アルコール性肝硬変の治療でとくに重要なのは、完全な断酒です。
お酒を飲み続けると肝臓の炎症が進み、回復が難しくなるため、肝臓を守るために飲酒を完全にやめることが大切です。
アルコール依存により断酒が難しい場合は、精神科や心療内科の専門医による治療も有効な選択肢となります。
また、断酒以外にも食生活の改善が肝臓の回復を助けます。
具体的には、以下のような食事を心がけましょう。
- タンパク質が豊富な食品(肉、魚、大豆製品など)を積極的に摂る
- ビタミン類を多く含む食材(野菜、果物など)を取り入れる
- 脂肪分の多い食事や糖分の過剰摂取は控える
- 塩分は1日5~7gに制限する
食生活の改善は、無理のない範囲で継続することが大切です。
薬物療法
アルコール性肝硬変では、症状を緩和するためにビタミン剤やアミノ酸製剤による薬物療法が行われます。
これらの薬は肝臓の保護や症状の緩和を目的としています。
また、アルコール依存症がある場合は、断酒を補助するために抗酒薬や抗不安薬などが用いられることがあります。
これらの薬は精神的な症状を和らげ、断酒の継続を助けます。
ただし、薬物療法は症状を和らげるための対症療法であり、肝硬変が根本的に治るわけではないため注意が必要です。
肝移植
肝臓の機能が著しく低下している場合や肝硬変の根本的な治療法として、肝移植が検討されます。
肝移植とは、機能を失った肝臓を健康な肝臓に置き換える手術で、重症の肝硬変患者にとって、生命を救う可能性のある治療法となります。
ただし、肝移植にはドナー(提供者)の確保や手術のリスク、術後の免疫抑制剤の継続的な服用など、さまざまな課題があります。
また、移植後も断酒を継続しなければ、新しい肝臓も同じように傷ついてしまいます。
肝移植は最終的な治療手段として位置づけられており、医師との十分な相談が必要です。
再生医療
肝硬変をはじめとする肝臓疾患に対する治療法には、再生医療という選択肢もあります。
再生医療は、さまざまな細胞に変化する「分化能」という能力を持つ幹細胞を活かし、肝硬変の改善が期待できる治療法です。
治療は点滴によって幹細胞を投与するだけで、手術は必要ありません。
また、ご自身の細胞を使用するため、拒否反応のリスクが低いのが特徴です。
しかし、先端医療のため保険適用外となり、治療費用が高い傾向がある点は留意しましょう。
当院リペアセルクリニックで行っている肝臓疾患に対する再生医療については、以下のページを併せてご覧ください。
肝臓疾患のお悩みに対する新しい治療法があります。
アルコール性肝硬変になる前の肝疾患に注意
アルコール性肝硬変は、突然発症する病気ではありません。
長期間の飲酒を続けることで肝臓は徐々にダメージを受け、段階を経て進行していきます。
重症化を防ぐには、以下の各段階で適切な対応を取ることが大切です。
| 病気の段階 | 特徴と症状 |
|---|---|
| アルコール性脂肪肝(初期) |
|
| アルコール性肝炎 |
|
| アルコール性肝硬変(末期) |
|
初期のアルコール性脂肪肝は、目立った症状がないのが特徴です。
そのため、多くの方が気づかないうちに病気が進行してしまいます。
禁酒や節酒を行わずにお酒を飲み続けると、アルコール性肝炎や肝硬変を発症する可能性が高まります。
また、多量の飲酒によって肝臓の病気が進行すると、肝がんを発症するリスクも高くなります。
早い段階で生活習慣を見直すことが、将来の重大な病気を防ぐことにつながります。
アルコール性肝硬変を早期発見するために重要な検査
アルコール性肝硬変を早期に発見するために重要な検査は、以下の2つです。
検査を定期的に受けることで、肝臓の異常を早く見つけられます。
肝生検
肝生検は、肝臓の一部を採取して組織を詳しく調べる検査です。
この検査により、炎症の進行度や肝臓の硬さ(線維化)の程度を正確に把握できます。
肝硬変の進行具合を診断する際にも用いられます。
検査は局所麻酔を行い、細い針を肝臓に刺して組織を採取します。
肝生検は肝臓の状態を詳しく知るために有効な方法であり、治療方針を決める上で重要な情報を得られます。
血液検査
肝臓の異常は自覚症状が出にくいため、血液検査による早期発見が重要です。
AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTPといった酵素の数値は、肝機能の状態を把握する基本的な指標となります。
| 検査項目 | 説明 |
|---|---|
| AST(GOT) | 肝細胞に含まれる酵素で、肝臓にダメージがあると血液中に漏れ出して数値が上昇します。 |
| ALT(GPT) | 肝臓に特化した酵素で、肝細胞が破壊されると血液中に漏れ出し、数値が高くなります。肝炎などの診断に役立ちます。 |
| γ-GTP | 胆道から分泌される酵素で、肝臓の解毒機能に深く関わっています。過度な飲酒や肝硬変、肝臓がん、胆石、胆管がんなどが原因で数値が高くなる可能性があります。 |
これらの数値が高い場合、肝臓や胆道に何らかの異常がある可能性があります。
また、服用している薬の副作用によっても数値が上がるケースがあるため、医師に相談して薬の量を調整するなどの対応が必要です。
定期的に健康診断を受け、これらの数値をチェックすることで肝臓の病気を早期に発見できます。
アルコール性肝硬変の末期症状
アルコール性肝硬変が重症化すると、以下のようなさまざまな症状や合併症を引き起こします。
| 腹水 |
|
| 肝性脳症 |
|
| 食道静脈瘤 |
|
それぞれの合併症の対処法について詳しく紹介します。
腹水
腹水の対処法は、主に3つあります。
- 食事療法
- 利尿剤
- 腹水穿刺
腹水の発生・悪化を防ぐためには、食塩摂取量の制限が基本です。
塩分は体内に水分を保持する性質があり、過剰摂取すると腹水の悪化につながるため、塩分の摂取は1日に5~7g※にしましょう。
※参照:日本消化器病学会・日本肝臓学会「肝硬変診療ガイドライン 2020(改訂第 3 版)」2020年発行
また、腹水を体外へ排出するために、利尿剤(尿量を増やす薬)が処方されることがあり、体内に余分な水分が蓄積するのを防ぎます。
腹水が大量にたまり、腹部膨満や呼吸困難、食欲不振などの症状が強く現れる場合には、腹水穿刺(ふくすいせんし)という処置が行われます。
このように腹水は単なる症状ではなく、肝硬変の機能が低下した段階に入っているサインです。
進行を防ぐには断酒・栄養管理や、内科的・外科的治療などを組み合わせて全体的に病態のコントロールをする必要があります。
肝性脳症
肝性脳症とは、肝機能の低下により体内の有害物質(アンモニアなど)が解毒されずに脳へ到達し、意識障害や神経精神症状を引き起こす合併症です。
治療の基本は、主に以下の通りです。
- 誘因の除去
- 栄養療法
- 薬物療法
肝性脳症は、以下のような特定の誘因をきっかけに急激に悪化することが多いため、まずはそれらを的確に見つけ出し、排除することが最優先です。
- 便秘
- タンパク質の過剰摂取
- 消化管出血
- 感染症
- 脱水・電解質異常
- 利尿薬の過剰投与
※参照:J-Stage「日本内科学会雑誌第111巻第1号」
かつてはタンパク質制限が推奨されていましたが、現在は過度な制限は予後を悪化させるとされ、適正なタンパク質摂取の維持が重要とされています。
また、薬物療法では腸内アンモニアの生成・吸収を抑えることを目的とした治療が中心になります。
肝性脳症は肝硬変が進行しているサインであり、放置すると昏睡や死亡に至ることもある重大な状態です。
しかし、誘因の早期除去・適切な栄養と薬物管理により、再発予防が期待できます。
ただし、自己判断での食事制限はリスクも大きいため、医療機関と連携しながら治療を継続しましょう。
食道静脈瘤
食道静脈瘤は、肝硬変によって肝臓内の血流が悪くなり、門脈圧(門脈内の血圧)が上昇することで、食道の静脈が異常に膨らんだ状態です。
破裂すると大量吐血や消化管出血を引き起こし、命の危険が伴う深刻な状態になります。
破裂を未然に防ぐ、あるいは破裂後の止血を行うために、主に以下の2つの内視鏡的治療が用いられます。
- 食道静脈瘤硬化療法(EIS)
- 内視鏡的静脈瘤結紮術(EVL)
食道静脈瘤硬化療法(EIS)は、内視鏡を使って食道静脈瘤に硬化剤(血管を固める薬)を注入し、静脈瘤を閉塞させる方法です。
瘤そのものに直接作用するため、再発リスクが比較的低いとされていますが、処置の際の合併症や身体への負担がやや大きいという側面もあります。
一方で、内視鏡的静脈瘤結紮術(EVL)は内視鏡で静脈瘤を確認し、ゴムバンドで結紮(縛る)することで血流を遮断し、壊死・脱落させることで瘤を除去する治療法です。
患者の病態や静脈瘤の状態に応じて治療方法が異なるため、専門医と相談しながら治療方針を決定します。
アルコール性肝硬変の根治を目指すなら再生医療をご検討ください
アルコール性肝硬変は、完治は困難ですが進行の抑制は可能です。
断酒や食生活の見直し、運動習慣をつけると肝機能の改善が期待できます。
アルコール性肝硬変は、合併症を引き起こすリスクも高まるため、普段から断酒やバランスの良い食生活を送ることが大切です。
肝硬変を予防するため、普段から体調に気を配り、定期的に検査を受けましょう。
また、アルコール性肝硬変の治療法として、再生医療の選択肢もあります。
再生医療は、さまざまな細胞に変化する「分化能」という能力を持つ幹細胞を活かし、肝硬変の改善が期待できる治療法です。
患者さまの細胞や血液を利用した治療法のため、拒否反応などのリスクが低い点も特徴です。
アルコール性肝硬変でお悩みの方は、再生医療専門クリニックである当院「リペアセルクリニック」にご相談ください。

監修者
渡久地 政尚
Masanao Toguchi
医師
略歴
1991年3月琉球大学 医学部 卒業
1991年4月医師免許取得
1992年沖縄協同病院 研修医
2000年癌研究会附属病院 消化器外科 勤務
2008年沖縄協同病院 内科 勤務
2012年老健施設 かりゆしの里 勤務
2013年6月医療法人美喜有会 ふたこクリニック 院長
2014年9月医療法人美喜有会 こまがわホームクリニック 院長
2017年8月医療法人美喜有会 訪問診療部 医局長
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 院長