- 脳梗塞
- 脳卒中
- 頭部
脳梗塞後に食べてはいけないもの|再発予防のための食事療法について解説【医師監修】

脳梗塞の再発予防において、食事管理は重要な対策の一つです。
なぜなら、脳梗塞の再発の引き金となる高血圧や脂質異常症、糖尿病といった生活習慣病は、毎日の食事内容と密接に関連しているからです。
しかし「食事で何に気をつければいいのか」「具体的に食べてはいけないものは何なのか」と、日々の食生活について悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、脳梗塞の再発リスクを高めてしまう「食べてはいけないもの」について詳しく解説します。
正しい食生活を理解し、毎日の習慣を見直すことが、再発を防ぐための一歩となります。
また、近年の脳梗塞の再発予防策として「再生医療」という選択肢が注目されています。
再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて、損傷した血管や脳細胞の再生・修復を促す医療技術です。
脳梗塞の再発への不安がある方や、後遺症の改善を諦めたくない方は、ぜひ当院リペアセルクリニックにご相談ください。
目次
脳梗塞後に食べてはいけないもの一覧
脳梗塞の再発を予防するためには、食生活の改善が重要です。
とくに、動脈硬化や高血圧、脂質異常症といった脳梗塞の再発リスクを高める要因を悪化させる食品は、日常の食事から避けるか、厳しく制限する必要があります。
脳梗塞後に食べてはいけないものは、以下のとおりです。
これらの食品がなぜ脳梗塞の再発リスクとなるのか、具体的に解説していきます。
脂肪分が多い食品
脂肪分の多い食品の中でも、「飽和脂肪酸」や「トランス脂肪酸」を多く含むものは、避けるべきです。
これらは血液中の悪玉(LDL)コレステロールを増やし、血管の壁にプラークを蓄積させ、動脈硬化を促進させてしまうためです。
飽和脂肪酸を多く含む食品例
- 肉の脂身(バラ肉、ロース肉の脂身など)
- バター、ラード、生クリーム
- 加工肉(ソーセージ、ベーコン)
など
トランス脂肪酸を多く含む食品例
- マーガリン、ショートニング
- ケーキ、クッキー、スナック菓子
- ファストフード、揚げ物
など
後述する塩分の多い食品やアルコールとともに摂取する機会が多いため、意識して避ける必要があります。
塩分の多い食品
塩分の多い食品は、脳梗塞の危険因子である高血圧を直接招くため、厳しく制限する必要があります。
高血圧は血管に常に高い圧力をかけ、血管を傷つけ、動脈硬化を進行させる原因となります。
塩分を多く含む食品例
- 加工食品(ハム、ソーセージ、ちくわ、かまぼこ)
- インスタント食品(カップラーメン、インスタント味噌汁)
- 漬物、梅干し、佃煮
- 干物
- スナック菓子、せんべい
など
とくに、カップラーメンなどのインスタント食品の汁は塩分が多いため、飲み干さないようにしましょう。
糖分の多い食品
ジュースやお菓子、菓子パンなど、砂糖を多く含む糖分の多い食品も控えるべきです。
これらは食後の血糖値を急激に上昇させるだけでなく、過剰な糖質は中性脂肪として蓄積されやすいためです。
糖分を多く含む食品例
- 清涼飲料水、ジュース、加糖のコーヒー・紅茶
- ケーキ、クッキー、饅頭などの菓子類
- アイスクリーム
- 菓子パン、デニッシュパン
など
血糖値の乱高下(血糖値スパイク)や肥満は、血管に負担をかけ、動脈硬化のリスクを高めます。
高GI炭水化物
白米や食パン、うどんなど、精製された炭水化物(高GI食品)の摂取量にも注意が必要です。
これらは糖分の多い食品と同様に、摂取すると体内で速やかに糖に分解され、食後の血糖値を急激に上昇させます。
主な高GI炭水化物の例
- 白米
- 食パン、菓子パン
- うどん、そうめん
- じゃがいも
など
主食を摂る場合は、玄米や雑穀米、全粒粉パン、そばといった血糖値の上昇が緩やかな「低GI食品」に置き換えることが推奨されます。
アルコール
アルコールの過剰な摂取は、脳梗塞の再発リスクを高めるため、原則として控えるべきです。
過度な飲酒は、脳梗塞の原因となる「高血圧」「脂質異常症」「糖尿病」を悪化させる要因となります。
また、降圧剤や血液をサラサラにする薬(抗血小板薬、抗凝固薬)を服用中の方は、アルコールが薬の効果に影響を与える可能性もあります。
主治医から許可が出ている場合でも、示された適量を厳守することが不可欠です。
【再発防止につながる】脳梗塞後に食べた方が良いもの
脳梗塞の再発予防には、「食べてはいけないもの」を避けるだけでなく、動脈硬化や高血圧を防ぎ、血液の状態を良好に保つ栄養素を含む食品を積極的に摂ることが重要です。
再発予防のために日々の食事で積極的に取り入れたい食品群は、以下のとおりです。
- 野菜類・果物類
- 青魚(サバ、イワシ、アジなど)
- 大豆製品・海藻類・きのこ類
- 低GI炭水化物(玄米、全粒粉パンなど)
- 良質な油(オリーブオイル、亜麻仁油など)
など
これらの食品群はどれも重要ですが、再発予防において、とくに重要なのが「野菜・果物」と「青魚」です。
野菜や果物には、血圧を下げる働きのあるカリウムが豊富に含まれており、高血圧の原因となる体内の余分なナトリウム(塩分)を排出するのを助けてくれます。
また、豊富な食物繊維がコレステロールの吸収や血糖値の急上昇を抑える役割も果たします。
青魚は血液をサラサラにする効果が期待できるEPAやDHAという良質な脂質(n-3系脂肪酸)を含みます。
これらに加え、食物繊維が豊富な大豆製品や海藻類、血糖値の上昇が緩やかな玄米、悪玉コレステロールを減らすオリーブオイルなどをバランス良く組み合わせることが重要です。
ただし、腎機能が低下している方や特定の薬を服用中の方は、カリウムの摂取制限が必要な場合もあるため、必ず主治医や管理栄養士に相談しましょう。
脳梗塞の再発防止のための食事療法とは
脳梗塞の再発予防における食事療法は、血管や血液を健康に保つための栄養素をバランス良く摂取する積極的な取り組みです。
再発防止のために日々の食事で意識すべきポイントは、以下のとおりです。
以下では、それぞれの具体的な実践方法について解説します。
バランスよく食べる
食事療法の基本は、「主食・主菜・副菜」をそろえ、多様な栄養素を過不足なく摂ることです。
特定の食品に偏るのではなく、野菜、魚、肉(赤身)、大豆製品、海藻類などをバランスよく取り入れましょう。
バランスの悪い食事は、脂質異常症や糖尿病などのリスクを高め、動脈硬化を促進させる原因となるため注意が必要です。
食物繊維の多い食品を選ぶ
食物繊維の多い食品を取り入れるのも、脳梗塞の再発予防につながります。
野菜、きのこ類、海藻類、玄米などに含まれる水溶性食物繊維は、コレステロールの吸収を抑え、血糖値の急上昇を防ぐ重要な役割を果たします。
これらは余分な脂質や糖を体外に排出するのを助けます。
また、満腹感を得やすいため、カロリーの過剰摂取を防ぎ、肥満予防にもつながります。
良質なタンパク質を摂る
筋肉や血管を丈夫に保つために、良質なタンパク質を適量摂ることが重要です。
ただし、肉類に偏ると飽和脂肪酸(悪い脂)も多く摂りがちになるため注意しましょう。
肉の脂身は避け、赤身を選んだり、EPAやDHAが豊富な青魚、あるいは豆腐・納豆などの大豆製品、卵などからバランスよく摂取することを心がけましょう。
こまめに水分補給する
脳梗塞の再発予防において、血液がドロドロになるのを防ぐための水分補給は非常に重要です。
体内の水分が不足すると血液の粘度が上がり、血栓(血の塊)ができやすくなります。
とくに起床時や入浴後、運動後は水分が不足しやすいため、喉が渇く前にこまめに水や白湯、麦茶などで水分を補給する習慣をつけましょう。
カリウムを積極的に摂る
カリウムは、高血圧の原因となるナトリウム(塩分)を体外に排出する働きがあるため、積極的に摂取したい栄養素です。
ほうれん草など葉物野菜、かぼちゃ、バナナやキウイなどの果物、海藻類に多く含まれています。
ただし、腎機能に問題がある方や特定の薬を服用している方は、カリウムの摂取制限が必要な場合がありますので、必ず主治医に相談してください。
脂質・塩分・糖分の過剰摂取を避ける
「食べてはいけないもの」とも共通しますが、食事療法の根幹として過剰摂取を避ける意識が重要です。
飽和脂肪酸やトランス脂肪酸(脂質)、塩分、砂糖(糖分)は、それぞれ脂質異常症、高血圧、糖尿病や肥満のリスクを高め、動脈硬化を直接的に進行させます。
普段の食事から、脂質・塩分・糖分の過剰摂取をいかに減らしていくかが再発予防の鍵となります。
脳梗塞の再発リスクについて食事で注意すべきこと
脳梗塞の再発予防では、食べるものだけでなく、食生活全体を見直すことが不可欠です。
本章では、食事に関して注意すべき3つの重要なポイントを解説します。
肥満や脱水は再発リスクを高める直接的な要因であり、後遺症としての嚥下障害も食事の安全に直結します。
以下では、それぞれの注意点について詳しく解説していきます。
食べ過ぎによる肥満・体重増加を防ぐ
食べ過ぎによる肥満や体重増加は、脳梗塞の危険因子である高血圧、糖尿病、脂質異常症を悪化させるため、避ける必要があります。
肥満は万病のもとと言われ、特に血管への負担を増大させます。
食事は「腹八分目」を心がけ、主食・主菜・副菜のバランスを整えることが重要です。
とくに夜遅い時間の食事や、お菓子・ジュースなどの間食は中性脂肪として蓄積されやすいため、摂取量や時間帯にも注意しましょう。
脱水症状にならないように水分を摂取する
体内の水分が不足すると血液の粘度が上がり、血栓(血の塊)ができやすくなるため、こまめな水分補給は脳梗塞の再発予防に重要です。
とくに高齢者は喉の渇きを感じにくくなるため、意識的な水分摂取が求められます。
起床時、入浴前後、運動中やその前後、就寝前など、タイミングを決めてコップ一杯の水や白湯、麦茶などを飲む習慣をつけると良いでしょう。
ただし、心臓や腎臓に疾患がある場合は水分摂取量に制限が必要なこともあるため、必ず主治医の指示に従ってください。
嚥下障害がある場合は誤嚥に注意する
脳梗塞の後遺症で嚥下障害(飲み込む力が低下すること)がある場合、食べ物や飲み物が誤って気管に入る「誤嚥(ごえん)」に注意が必要です。
誤嚥は、窒息や「誤嚥性肺炎」という命に関わる深刻な肺炎を引き起こす原因となります。
食事中にむせる、咳き込む、食べた後に声がかすれるといった症状が見られる場合は、すぐに主治医やリハビリテーション科の医師、言語聴覚士に相談してください。
食材を細かく刻んだり、とろみをつけたりするなど、本人の飲み込む力に合わせた「嚥下調整食」の導入を検討する必要があります。
脳梗塞の再発リスクを抑えるには食事以外にも再生医療をご検討ください
脳梗塞の再発リスクを抑えるためには、脳梗塞の引き金となる高血圧や脂質異常症、糖尿病といった生活習慣病を徹底して管理することが重要です。
そのためにも、食事管理によって血管や血液の状態を良好に保つ「守り」の対策は、脳梗塞の再発予防に不可欠です。
本記事で紹介した「食べてはいけないもの(脂質・塩分・糖分の多い食品)」を避け、「食べた方が良いもの(野菜・青魚など)」を積極的に取り入れる食事療法を実施しましょう。
しかし、長年の生活習慣によって進行した動脈硬化や、脳梗塞によってダメージを受けた脳の機能は、食事療法だけでは改善しません。
そうした課題に対し、近年では「再生医療」という選択肢が注目されています。
再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて、傷ついた血管や神経組織の修復を促したり、炎症を抑えたりすることで、失われた機能の回復や動脈硬化の根本的な改善を目指す治療法です。
脳梗塞の再発への不安がある方や、後遺症の改善を諦めたくない方は、ぜひ当院リペアセルクリニックにご相談ください。

監修者
圓尾 知之
Tomoyuki Maruo
医師
略歴
2002年3月京都府立医科大学 医学部 医学科 卒業
2002年4月医師免許取得
2002年4月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2002年6月関西労災病院 脳神経外科 勤務
2003年6月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2003年12月大阪母子医療センター 脳神経外科 勤務
2004年6月大阪労災病院 脳神経外科 勤務
2005年11月大手前病院 脳神経外科 勤務
2007年12月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2012年3月大阪大学大学院 医学系研究科 修了(医学博士)
2012年4月大阪大学医学部 脳神経外科 特任助教
2014年4月大手前病院 脳神経外科 部長
あわせて読みたいトピックス
-

脳卒中における二木の予後予測とは|回復期リハビリテーションの重要性と注意点を解説
-
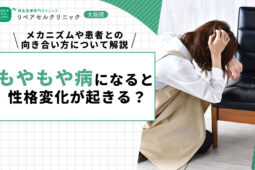
もやもや病になると性格変化が起きる?メカニズムや患者との向き合い方について解説
-

くも膜下出血は後遺症がなくても再発するリスクがある!注意点を解説
-

橋梗塞の症状とリハビリの進め方|具体的なプログラムとポイントについて解説
-

脳出血の看護ケア|在宅でも家族ができることや注意点・ポイントについて解説
-

脳出血の入院期間|年齢別・重症度別の違い、入院費用について解説【医師監修】
-

高次脳機能障害の回復事例を紹介!経過や治療・リハビリが大切な理由も解説
-

高次脳機能障害患者の家族が抱えるストレスとは?つらさの理由と無理をしない接し方を紹介

















