- 脳梗塞
- 脳卒中
- 頭部
脳梗塞の再発リスク|再発率が高いのはなぜ?再発予防のための対処法【医師監修】

脳梗塞は、突然の発症だけでなく再発するリスクが高い病気です。
一度発症すると、「また起こったらどうしよう」「再発を防ぐには何をすればいいのか」といった不安や疑問を抱える方も多いでしょう。
本記事では、脳梗塞の再発リスクや具体的な予防策について詳しく解説します。
- 脳梗塞の再発リスクとは
- 脳梗塞を再発すると後遺症が重くなるリスク
- 脳梗塞の再発リスクを高めないための対策
- 脳梗塞の再発予防には再生医療という選択肢
脳梗塞を再発すると一度目より後遺症が重くなる傾向があり、生活の質に大きな影響を及ぼすことが懸念されます。
近年の治療では、脳梗塞の後遺症改善や予防法の一つとして、先端医療である再生医療が注目されています。
以下の動画では、実際に当院リペアセルクリニックで再生医療を受け、脳梗塞の後遺症が改善された患者様の症例を紹介しています。
併せて参考にしてください。
目次
脳梗塞の再発リスク|再発率に関するデータ
脳梗塞は一度発症すると、再発するリスクが高い疾患です。
再発を重ねると後遺症が重くなる傾向があるため、正しい知識をもって予防に取り組む必要があります。
本章では、以下の点について解説します。
具体的なデータを確認し、予防の重要性について理解を深めましょう。
脳梗塞の再発率は約50%
脳梗塞は再発しやすい疾患として有名ですが、発症から10年以内に約50%の方が再発すると報告されています。
主な原因である高血圧や動脈硬化などの生活習慣病は、一度の治療で完治するわけではなく、継続した管理をしないと血管の状態が再び悪化するためです。
脳梗塞の累積再発率について、以下のようなデータが示されています。
| 期間 | 脳卒中(脳梗塞を含む)累積再発率 |
|---|---|
| 5年以内 | 約35% |
| 10年以内 | 約50% |
※出典:PubMed
再発を繰り返すごとに後遺症が重くなる傾向もあるため、発症直後から継続的に再発予防に取り組むことが重要です。
再発リスクを高める危険因子
再発率の数字からも分かるように、脳梗塞は長期的に再発リスクが続く病気です。
以下のような項目は危険因子と呼ばれ、再発を高める要因とされています。
| 再発リスクを高める危険因子 | 内容 |
|---|---|
| 高血圧 | 血管にかかる負担が増大し、動脈硬化が進行する |
| 糖尿病 | 血糖値のコントロール不良が血管のダメージを悪化させる |
| 脂質異常症 | 血中の脂質バランスが崩れ、血管の詰まりが起こりやすくなる |
| 喫煙 | 血管の収縮や血液の粘度が高まり、血流障害を引き起こす |
| 心房細動 | 不規則な心拍により血液の流れが乱れ、血栓が形成されやすくなる |
これらの危険因子に注意して日常生活を送ることが、再発予防のカギとなります。
脳梗塞の再発リスクが高い理由は?
脳梗塞の再発リスクが高い理由は、脳梗塞を引き起こした根本原因が治療後も残り続けるためです。
脳梗塞の治療によって脳の症状が改善・緩和された場合でも、脳梗塞の原因となった高血圧など危険因子が治るわけではありません。
高血圧などの脳梗塞の危険因子を改善しない限り、再び脳梗塞が起こる可能性があります。
そのため、再発を防ぐには脳梗塞の治療だけでなく、背景にある危険因子を生涯にわたって管理し続ける「二次予防」が必要です。
脳梗塞の再発リスクを高めないための対策
脳梗塞は、生活習慣や健康状態の見直しといった適切な予防によって、再発リスクを低下させることができます。
とくに生活習慣や健康状態の見直しが予防のカギです
以下では、脳梗塞予防のための具体的な方法を詳しく解説します。
生活習慣病を改善する
脳梗塞の再発予防の基本は、原因となる高血圧や糖尿病といった生活習慣病を適切に管理することです。
生活習慣病は血管に負担をかけ、動脈硬化を進行させるため、放置すると再び脳梗塞を引き起こすリスクが高まります。
医師の指導のもと、薬物療法を継続するとともに、以下の数値を目標に生活習慣を改善していく必要があります。
| 管理項目 | 目標値の目安 |
|---|---|
| 血圧 | 135/85mmHg未満 |
| 糖尿病 | HbA1c:7.0%未満 |
| 脂質異常症 | LDLコレステロール:120mg/dL未満 |
目標を達成するため、減塩や適度な運動を心がけ、処方された薬は自己判断で中断しないようにしてください。
定期的な通院で体の状態を確認し、治療を継続することが再発予防につながります。
血栓を予防する
脳梗塞を予防するためには、血栓の形成を防ぐ抗血栓療法が有効です。
抗血栓療法は脳梗塞に効果的な方法の一つとして広く用いられています。
血液をサラサラにする抗血栓薬の服用により、血液中の血小板の働きを抑えて血管内で血栓ができにくい状態を維持します。
さらに、血栓がすでに形成されている場合や高度な動脈硬化がある場合には、外科的治療も選択肢の一つです。
例えば、動脈の詰まりを取り除く手術や、血流を確保する治療などがあります。
食生活を改善する
脳梗塞の再発リスクを高めないためには、食生活の改善が重要です。
食生活の改善をするうえでポイントとなるのが塩分と脂質で、塩分は1日6g未満に抑え、高脂質の食事は控えましょう。
大量のアルコール摂取は脳梗塞の再発リスクが高まるため、お酒の飲みすぎには十分注意してください。
また、体内の水分が不足すると血栓ができやすくなるため、こまめな水分補給を心がけることも大切です。
以下の動画では、脳梗塞を含む脳卒中のリスクを下げる食生活について解説しているので、ぜひ参考にしてください。
適度に運動をする
日常的に体を動かし、血流を促進することが脳梗塞の再発リスクを抑える対策の一つです。
- ウォーキング
- 軽いジョギング
- 水中歩行
- 階段の使用
- 徒歩での移動
- 家事
- ガーデニング
ウォーキングや軽いジョギングなど有酸素運動や、水中歩行など軽いリハビリを日常生活に取り入れることで、血流の改善や心肺機能の向上が期待されます。
また、日常生活では階段を使用することや、徒歩で移動するなど、自然な形での運動量を確保することで、生活習慣を改善できます。
日常的に体を動かして、血流を促進することで再発リスクを予防できるため、適度な運動により血管や心臓の健康を保ち、脳梗塞や高血圧のリスクを減らしましょう。
睡眠の質を高める
睡眠の質を高めることも脳梗塞の再発リスクを高めない重要な対策の一つです。
良質な睡眠は血圧を安定させるため、脳への負担を減らすことができます。
睡眠の質を高めるためには、就寝前のスマホ操作を控えることや、簡単なストレッチを行うことも重要です。
ストレスを発散する
心身のストレスを上手に発散することも、脳梗塞の再発予防には欠かせません。
ストレスは交感神経を刺激し、血圧が上昇するだけでなく、過食や喫煙といった生活習慣の乱れにもつながり、再発リスクを高めるからです。
心と体の緊張をほぐし、再発リスクを遠ざけるために、以下のような方法を日常に取り入れましょう。
おすすめのストレス発散方法
- ウォーキングなどの有酸素運動
- ぬるめのお湯での入浴
- 規則正しい生活で睡眠の質を高める
- 家族や友人との会話を楽しむ
飲酒・喫煙はかえって体に負担をかけ、再発リスクを高めます。
健康的な方法でストレスを管理し、穏やかな毎日を過ごすことが再発予防の助けとなります。
定期健診を受ける
定期健診は脳梗塞の危険因子を早期に発見し、適切な対応を取るために欠かせない予防策です。
とくに、脳梗塞の主なリスクである高血圧・糖尿病・脂質異常症は、自覚症状がないまま進行することが多いため、定期的な検査によるチェックが必要です。
健診では、血圧や血糖値、コレステロール値の測定に加えて、心電図や頸動脈エコー検査などにより隠れたリスクを見つけられます。
定期健診を通じて危険因子を早期に発見し、脳梗塞の発症や再発を未然に防ぎましょう。
脳梗塞の再発予防につながるリハビリテーション
脳梗塞を発症した後のリハビリテーションは、失われた機能を取り戻すためだけでなく、再発を予防するうえでも必要なステップです。
体を動かす習慣を身につけることで、血圧や血糖値の安定につながり、再発リスクを減らすことにつながります。
本章では、以下の点について解説します。
リハビリテーションがなぜ再発予防に必要なのか、具体的な内容についてそれぞれ見ていきましょう。
リハビリテーションの重要性
リハビリテーションの目的は、ただ手足の動きを回復させるだけでなく、体全体の健康状態を向上させ、再発の引き金となる要素を減らすことにあります。
以下のような再発予防効果が期待できます。
リハビリテーションの重要性
- 運動習慣が身につき、血圧や血糖値が安定する
- 寝たきりによる血栓や誤嚥性肺炎などを防ぐ
- 転倒などを防ぎ、安全に活動できる範囲が広がる
発症直後の急性期から退院後の生活期まで、一貫してリハビリに取り組むことで、再発しにくい体と生活習慣を作り上げることが重要です。
リハビリテーション内容
リハビリテーション内容は、発症後の時期によって目的が異なり、段階的に進められます。
脳梗塞後のリハビリテーション内容は、以下のとおりです。
| 時期 | 主な目的 | リハビリ内容の例 |
|---|---|---|
| 急性期(発症直後) | 合併症の予防、寝たきりの防止 | ベッド上での関節運動、座位訓練 |
| 回復期(状態安定後) | 日常生活動作の再獲得、在宅復帰 | 歩行訓練、食事や着替えの練習、言語訓練 |
| 維持期(退院後) | 機能の維持、再発予防の習慣化 | 通所リハビリ、自宅での自主トレーニング |
それぞれの時期で、患者さまの全身状態に合わせた専門的なプログラムが組まれます。
また、リハビリテーションは入院中の病院だけで完結するものではありません。
退院後も通所サービスや訪問リハビリなどを活用し、リハビリテーションを生活の一部として続けることが大切です。
脳梗塞の再発予防には再生医療をご検討ください
再生医療による幹細胞療法は、脳梗塞の再発予防と後遺症の改善に期待ができる治療法です。
幹細胞治療は、患者さま自身の脂肪組織から採取した幹細胞を培養し、体内に戻すことで損傷した組織の修復や再生を促進する治療法です。
さらに幹細胞には抗炎症作用があり、脳内の炎症を抑制して再発リスクの低減が期待できます。
当院リペアセルクリニックでは、脳梗塞を含む脳卒中に対する再生医療の症例が多くございます。
例えば、50代の女性が脳梗塞と脳出血を経験し、右半身麻痺や言語障害などの後遺症に悩まされていましたが、幹細胞治療を3回受けた結果、症状改善がみられたケースがあります。
>症例の紹介ページはこちら
再生医療は脳梗塞の再発予防だけでなく、後遺症の改善にも効果が期待できます。
再生医療による治療をご検討の際は、ぜひ当院へご相談ください。
脳卒中のお悩みに対する新しい治療法があります。
脳梗塞の再発リスクに関するよくある質問
ここでは、脳梗塞の再発リスクに関するよくある質問に回答していきます。
それぞれの疑問を解消し、今後の対策を明確にしていきましょう。
脳梗塞を再発しやすい人は?
脳梗塞を再発しやすい方には、生活習慣や治療への取り組み方において共通する特徴が見られます。
注意が必要な方の特徴は、以下のとおりです。
| 分類 | 再発リスクが高い方の特徴 |
|---|---|
| 生活習慣・行動 | ・喫煙や多量の飲酒を続けている ・塩分の多い食事が中心 ・運動不足が続いている ・医師から処方された薬を自己判断でやめてしまう ・定期的な通院や検査を怠っている |
| 身体的な特徴・病気 | ・高血圧、糖尿病、脂質異常症の管理が不十分 ・心房細動(不整脈の一種)がある ・肥満の状態にある |
脳梗塞の根本的な原因である危険因子を放置していると、再発のリスクは常に高い状態が続きます。
ご自身の生活や体の状態が上記に当てはまる場合は、生活習慣の改善や適切な治療を受けましょう。
脳梗塞を再発したらどうなる?
脳梗塞を再発すると、初回の発症時よりも後遺症が重くなる可能性があります。
一度ダメージを受けた脳に、新たな損傷が加わることで症状が悪化したり、後遺症の種類が増えたりするためです。
具体的には、以下のような状態になる場合があります。
脳梗塞の再発を繰り返すリスクの例
- 初回発症時よりも症状が悪化し、日常生活の自立が難しくなる
- 高次脳機能の低下が進行して会話や判断力に支障をきたし、介護が必要となる
- 後遺症の種類が増える
上記のように、脳梗塞の再発は患者さまご本人とご家族の負担を増大させます。
後遺症を悪化させないためにも、日々の再発予防が何よりも大切です。
脳梗塞の再発サインは?
脳梗塞の再発を早期に発見するには、「FAST(ファスト)」と呼ばれるサインを覚えておくことが役立ちます。
これは、脳梗塞の典型的な初期症状の頭文字をとったものです。
| FAST | 症状 |
|---|---|
| Face(顔のゆがみ) | 顔の片側だけが下がる、笑ったときに片方の口角が上がらない |
| Arm(腕の麻痺) | 腕が上がらない、力が入らない |
| Speech(言葉の不明瞭さ) | 言葉がうまく出てこない、話している内容が不明瞭になる |
| Time(時間) | 迅速に医療機関へ連絡し、治療を開始する時間を確保するのが重要 |
これらのサインが1つでも見られた場合は、ためらわずに救急車を要請してください。
脳梗塞の治療は時間との勝負です。発症から4.5時間以内であれば、血栓を溶かす効果的な治療を受けられる可能性※があります。
※参照:国立循環器病研究センター「4.5時間を過ぎても、専門的な脳梗塞救急治療が重要です」
以下の動画では、脳梗塞の前兆である危険サインについて解説しているので、合わせて参考にしてください。
脳梗塞の再発リスクを抑えるには生活習慣の改善が重要
脳梗塞の再発予防には、危険因子を管理して生活習慣を見直すことが重要です。
高血圧や糖尿病、脂質異常症といった危険因子をコントロールし、適度な運動や減塩を意識した食生活を取り入れて再発リスクを減らしましょう。また、喫煙や多量飲酒を控えるのも効果的です。
さらに、再発のサインであるFAST(顔のゆがみ、腕の麻痺、言葉の不明瞭さ、時間の重要性)を理解し、早期に対応するのが後遺症を抑えるカギとなります。
定期健診を受け、自分の健康状態を常に把握しておくことも忘れてはなりません。
これらの取り組みに加え、再生医療は脳梗塞の再発予防や後遺症の改善に新たな選択肢を提供します。
幹細胞治療は、損傷した神経の修復や再生を促し、脳細胞の損傷が改善されることで再発リスクを軽減する効果が期待されています。
予防と治療の両面で効果が期待できる再生医療をぜひご検討ください。

監修者
圓尾 知之
Tomoyuki Maruo
医師
略歴
2002年3月京都府立医科大学 医学部 医学科 卒業
2002年4月医師免許取得
2002年4月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2002年6月関西労災病院 脳神経外科 勤務
2003年6月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2003年12月大阪母子医療センター 脳神経外科 勤務
2004年6月大阪労災病院 脳神経外科 勤務
2005年11月大手前病院 脳神経外科 勤務
2007年12月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2012年3月大阪大学大学院 医学系研究科 修了(医学博士)
2012年4月大阪大学医学部 脳神経外科 特任助教
2014年4月大手前病院 脳神経外科 部長
あわせて読みたいトピックス
-

脳卒中における二木の予後予測とは|回復期リハビリテーションの重要性と注意点を解説
-
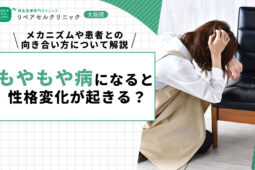
もやもや病になると性格変化が起きる?メカニズムや患者との向き合い方について解説
-

くも膜下出血は後遺症がなくても再発するリスクがある!注意点を解説
-

橋梗塞の症状とリハビリの進め方|具体的なプログラムとポイントについて解説
-

脳出血の看護ケア|在宅でも家族ができることや注意点・ポイントについて解説
-

脳出血の入院期間|年齢別・重症度別の違い、入院費用について解説【医師監修】
-

高次脳機能障害の回復事例を紹介!経過や治療・リハビリが大切な理由も解説
-

高次脳機能障害患者の家族が抱えるストレスとは?つらさの理由と無理をしない接し方を紹介

















