- 脳梗塞
- 脳卒中
- 頭部
脳梗塞退院後の生活で注意すべきことは?リハビリや支援制度について紹介

「脳梗塞退院後の生活が不安」
「退院後に注意すべきことは?」
「退院後の支援制度やお金のことを知りたい」
脳梗塞を発症するとさまざまな後遺症がみられる場合があるので、退院後の生活について上記のような不安を抱えている患者さまやご家族は多いのではないでしょうか。
この記事では、脳梗塞退院後の注意点やリハビリの内容、支援制度について解説します。
注意すべきことや必要な手続きを把握して、安心して退院後の生活をはじめられるようにしましょう。
目次
脳梗塞退院後の生活で注意すべきこと
脳梗塞退院後の生活で注意すべきことを、以下4つで解説します。
脳梗塞は再発しやすい病気で、発症10年後の再発率は49.7%※とされており、つまり脳梗塞発症後10年の間に半数の方が脳梗塞を再発しています。
※引用:日本人における脳卒中の10年間の累積再発率
特に食事やお酒・たばこについて心当たりがある方は、生活習慣の見直しが重要です。
一つずつみていきましょう。
食事内容の見直し
脳梗塞退院後の生活では、食事内容の見直しが重要です。
脳梗塞の主な原因は動脈硬化です。動脈硬化は血管の内部にコレステロールなどがたまって血流が悪くなる症状を指し、高血圧や糖尿病などにより引き起こされます。
そのため、高血圧や糖尿病を避ける食事を摂ることは、脳梗塞の再発リスクの低減と同様の効果があります。
脳梗塞の再発を防ぐ具体的な食事内容の例を下記にまとめました。
- 塩分を1日6g未満※にする
※引用:高血圧の予防のためにも食塩制限を―日本高血圧学会減塩委員会よりの提言 - 脂っこいものやインスタント食品を控える
- 魚介類やナッツを食べる
- 野菜やキノコなど食物繊維が含まれるものを食べる
基礎疾患や症状によって異なるので、適切な摂取量は医師に相談してみましょう。
お酒とたばこは控える
脳梗塞退院後は、お酒とたばこを控えましょう。
お酒とたばこによる脳梗塞のリスクを下記にまとめました。
- お酒・・・利尿作用による脱水で血液が濃縮される
- タバコ・・ニコチンによって血圧が上がったり血管を収縮させたりする働きで血栓ができやすくなる
お酒は利尿作用があり、脱水状態を引き起こすと血液も濃縮されるので、脳梗塞再発のリスクが高まります。
しかし、脳の血液が安定する2~3カ月以降は少量なら可能と考えられている※ため、お酒を飲みたいと思う方は、適切な飲酒量を医師に相談してみてください。
※出典:シミズ病院・大宮KENKOU情報局「脳梗塞後のお酒の飲み方は」
たばこに含まれるニコチンは血圧を上げたり血液を収縮させたりする働きがあるため、血栓ができやすくなります。
血栓が脳の血管で詰まってしまうと、脳梗塞が再発する可能性が高まるのでたばこを吸うのは避けましょう。
適度な運動を取り入れる
脳梗塞後の生活では、適度な運動を取り入れてみましょう。
運動は、血管を健康な状態にしたり、筋力を維持したりする効果が期待できます。
適度な運動は脳梗塞の発症予防や再発防止にも効果的で、例えば毎日30分以上の有酸素運動※は動脈硬化の予防に有用です。
※引用:日本動脈硬化学会
過度な運動は心肺機能に負担をかけるため、軽めのウォーキングや水泳などを1日30分程度、できる範囲から始めてみましょう。
定期検診の重要性
脳梗塞の退院後は定期健診に通い、数値の悪化や再発の早期発見がないかチェックしましょう。
定期健診の主な内容を下記にまとめました。
- 月に1回程度の定期健診(血圧測定、血液検査、診察)
- 年に1回の画像検査(CT、MRIやエコーなど)
血圧計を使用して自宅で血圧をチェックするのも健康を意識できるきっかけになるので、試してみてください。
脳梗塞退院後で後遺症がある場合におけるリハビリテーション
脳梗塞の退院後、後遺症がみられる場合は自宅や施設でリハビリを受ける必要があります。
リハビリの種類や目的を紹介します。
順番にみていきましょう。
リハビリの種類と目的
脳梗塞退院後のリハビリは、主に理学療法、作業療法、言語聴覚療法に分けられています。
主なリハビリの種類と内容を下記にまとめました。
| リハビリの種類 | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 理学療法 |
|
|
| 作業療法 |
|
|
| 言語聴覚療法 |
|
|
その他に、脳の働きを活性化させる目的で、微弱な電流や電磁石を使用して脳を刺激するリハビリもあります。
自宅でできるリハビリ
病院や施設での専門スタッフとのリハビリ時間が限られているため、自宅や日常生活の中で自主的にリハビリに取り組むことが重要です。
自宅でできるリハビリを下記にまとめましたので、参考にしてみてください。
- 単語や文章の書き取りや音読
- ジグソーパズルや数独
- 麻痺側の手で物を握る、つまむ、たたむなどの練習
脳梗塞後は疲れやすかったり集中力が切れやすかったりするので、無理のない範囲で行いましょう。
ただし自己流のリハビリは、場合によっては症状を悪化させることもあるため、言語聴覚士・理学療法士・作業療法士などの専門家に相談しつつトレーニングメニューを決めてください。
専門施設でのリハビリ
脳梗塞後の退院後は、施設に入所したり外来を利用してリハビリを継続しましょう。
退院後に何もしないでいると、入院中のリハビリで回復した機能が低下してしまう可能性があります。
主な施設を下記にまとめました。
- 病院の外来
- 訪問リハビリ
- デイサービス
- 介護保険施設
- リハビリ専門施設
一般的な病院や介護施設は現状を維持するリハビリが目的になりがちですが、リハビリ専門の施設だと機能の改善に積極的なプランを作成してくれます。
個々の能力に寄り添ったリハビリを受けたいとお考えの方は検討してみてください。
脳梗塞患者の家族や介護者ができるサポート
脳梗塞の退院後の生活でご家族や介護者ができるサポートを紹介します。
詳しく解説していくので、ぜひ参考にしてください。
日常生活のサポート
脳梗塞の退院後の生活では、家族や介護者による日常生活のサポートが重要です。
患者の機能状態によりますが、自宅の環境の整備や食事の補助、介護保険の申請が必要な場合があるためです。
具体的には手すりやスロープの改修をしたり、握りやすいスプーンを用意したりして患者本人ができるかぎり自分の力で日常生活が送れるようにしましょう。
精神的サポートも大切
多くの脳梗塞の患者は、機能の回復具合や脳梗塞の再発について悩みや不安を抱えているため、精神的なサポートも大切になります。
また、退院してしまうと周りに相談できる相手や一緒にリハビリに励む仲間がいなくなるので、リハビリに対する意欲を維持し続けるのが難しくなりがちです。
患者の家族や介護者は、リハビリを継続するためにも声かけや傾聴による精神的なサポートが求められます。
介護者の負担を軽減する方法も重要
患者の家族や介護者も患者の回復の状態を心配したり、動作が心許ないために目を離せなかったりとさまざまな不安をお持ちでしょう。
患者の家族や介護者の不安を解決する方法の一例をご紹介します。
- 家族や友人など身近な人に話を聞いてもらう
- ケアマネージャーに相談する
- SNSなどの脳梗塞の家族のコミュニティに参加する
- 患者本人にデイサービスやショートステイなどの介護サービスを利用してもらい、自分の時間を作る
- 再生医療を受ける
当院でも扱っている再生医療とは、わかりやすく言うと自然治癒能力(再生する力)を活かした最先端の医療です。
当院では脳梗塞を含む脳卒中の患者さまに対しては、自己脂肪由来の幹細胞治療を提供しており、脳梗塞による後遺症の根本的な治療や再発の予防が期待できます。
再生医療(幹細胞)治療については早ければ早いだけ良い結果が出る傾向にあるため、脳梗塞後の早期回復に興味がある方は、ぜひ当院へご相談ください。
脳卒中のお悩みに対する新しい治療法があります。
脳梗塞患者が退院後に利用できる支援制度やサービス
脳梗塞患者が退院後に利用できる支援制度やサービスを紹介します。
実際の症状や支援制度・サービスの条件を照らしあわせて、利用できるかどうかをチェックしてみましょう。
高額療養費制度
高額療養費制度とは、月の初めから終わりまでの間に自己限度額を超えて保険適用の治療を受けた際、超過した金額が払い戻される制度です。
脳梗塞による保険適用の範囲は診察料、検査料、投薬料、入院料などです。先進医療費や差額のベッド代、食事代は対象外なので注意しましょう。
自己限度額は年齢や所得によって異なり、70歳以上で住民税非課税世帯の方が入院や外来を利用した際は1カ月あたり15,000円~24,600円です。
1.病院の領収書を控えて、保険適用の領収書をまとめておく
2.患者本人の自己限度額を確認する
3.月初から月末までの保険適用の支払いが限度額を超過している場合は、医療保険に申請書を提出する
申請書の提出先は加入している医療保険によって異なりますが、国民健康保険の場合は各市町村の窓口です。
介護保険
食事や排せつ、入浴に介護が必要な場合は介護保険制度を利用しましょう。
介護保険制度とは介護が必要な度合いに応じて介護サービスを受けられる仕組み※を指し、利用には介護度の認定を受ける必要があります。
※引用:厚生労働省老健局「介護保険制度の概要」
介護サービスは施設に入所する居住系サービスと自宅にいながら支援を受ける在宅系サービスに分けられます。
主なサービスを下記にまとめました。
- 特別養護老人ホームや老人保健施設への入所
- 通所介護(デイサービス)
- 訪問介護(ホームヘルパー)
- 福祉用具貸与
- 訪問介護
施設への入所から在宅での家事のサポートや福祉用具の貸与まで、幅広いサービスがあります。
介護保険の対象者
介護保険制度を利用できる対象者をみていきましょう。
結論から述べると、脳梗塞によって介護や支援が必要な方は40歳以上から介護保険制度を受けられます。
介護保険の被保険者は2種類あり、第1号被保険者と第2号被保険者に分けられます。
具体的な内容を下記にまとめました。
- 第1号被保険者・・・65歳以上で介護や支援が必要な方
- 第2号被保険者・・・40歳から64歳で、介護や支援が必要な状態の原因が特定疾病による方(脳梗塞含む)
脳梗塞は特定疾病に含まれるので、40歳以上の方であれば介護保険制度を利用できると言えます。
要介護・要支援認定の申請
要介護、要支援認定の申請方法を紹介します。
介護保険制度の対象者であっても申請して介護認定を受けないと、全額が自費負担となってしまいます。
申請方法を下記にまとめました。
1.1号の方は介護保険被保険者証、2号の方は医療保険の被保険者証など必要な書類を準備する
2.1を持って市役所の介護保険課の窓口に行く
3.市区町村の職員が自宅を訪問し、要介護認定の調査や判定
4.介護度の認定結果が届く
5.ケアマネージャーに依頼して、利用するサービスを決める
6.サービスの利用
認定には時間がかかる場合があるので、退院後の生活をスムーズにするためにも早めの申請を心がけましょう。
傷病手当金
傷病手当金は、病気やケガで会社を休んだときに受けられる制度で、月給の2/3程度の金額が支給されます。
支給には条件が4つあり、すべて満たしている必要があります。
具体的な内容を下記にまとめました。
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業
- 仕事に就けない
- 仕事を休んだ日から連続して3日間休んで待機した後、4日目以降の仕事に就けなかった場合
- 休業した期間について給与の支払いがない
※引用:全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
入院が必要なほどの脳梗塞がおこると、長期の治療やリハビリが必要です。給料の全額支給は難しいですが、利用できる制度は活用しましょう。
障害年金
障害年金とは脳梗塞を含む病気やケガなどで障害の状態になった際に生活を支える目的で支払われます。
公的年金に加入し保険料を支払っていて、障害の状態が一定の状態にある方が対象です。
支給の申請をする際は、年金事務所や年金相談センターに問い合わせてみましょう。
脳梗塞の後遺症でお困りの方は再生医療の選択肢もあります
脳梗塞の後遺症でお困りの方や、早期回復を目指す方には再生医療も一つの手です。
再生医療とは、脳卒中(脳梗塞・脳出血)後に失われた脳の神経細胞を修復したり、血管を再生させる効果が期待できる治療法です。
当院では、患者さま自身の細胞から幹細胞を採取し、培養させたうえで体内に投与します。
幹細胞とは、神経や血管などに変化する能力があり、損傷箇所に到達して修復を促進します。
>>脳梗塞を含む脳卒中に対する再生医療の症例はこちら
脳梗塞の再生医療による治療は結果に個人差がありますが、早ければ早いほど良い結果が出ているので、治療を迷われている方はお気軽にご相談ください。
以下の動画では、実際に当院リペアセルクリニックで再生医療を受け、脳梗塞の後遺症が改善された患者様の症例を紹介しています。
併せて参考にしてください。
脳卒中のお悩みに対する新しい治療法があります。
脳梗塞退院後の生活でよくある質問
脳梗塞退院後の生活でよくある質問をまとめました。
不明な点を少しでも解消して退院後の生活をイメージしてみましょう。
脳梗塞で後遺症が無い確率は?
厚生労働省※1の調査によると、18-65歳の脳梗塞患者の約21.7%※2が、発症から3ヶ月後に完全回復することが調査で判明しています。
※1出典:厚生労働省「脳卒中患者(18-65歳)の予後」
※2計算式:スコア0(まったく症状がない)患者数344人÷総患者数1,584人
厚生労働省の調査に基づく、18-65歳の脳梗塞患者の発症3ヶ月後の状態と割合については以下の通りです。
|
症状の程度(mRSスコア) |
割合 |
|
まったく症状がない(mRS 0) |
21.7% |
|
症状はあるが日常生活に支障なし(mRS 1) |
29.7% |
|
軽度の障害があるが自立(mRS 2) |
17.8% |
|
中等度の障害、歩行に介助必要(mRS 3) |
6.2% |
|
日常生活に介助が必要(mRS 4) |
11.5% |
|
重度の障害、常時介護が必要(mRS 5) |
5.7% |
|
死亡(mRS 6) |
7.4% |
後遺症の程度は早期の治療開始とリハビリテーションの取り組みによって大きく変わるため、発症後の迅速な対応が極めて重要と言えます。
また、退院時には大きな後遺症がなくとも、身体に違和感を感じたらすぐに医療機関を受診しましょう。
左右どちらかのしびれや脱力感などがみられたら、軽度の脳梗塞を起こしている可能性があります。
脳梗塞が再発しやすいのはどんな人?
脳梗塞が再発しやすい方を下記にまとめました。
- タバコを吸っている
- 塩分の摂取量が多い
- 肥満
- 高血圧、糖尿病、心臓病などを持っている
- 運動不足
生活習慣を見直し、定期的に検査を受けて再発を防ぎましょう。
脳梗塞の再発防止のために避けるべき食品は?
脳梗塞の再発リスクが高まる食品は以下の通りです。
- アルコール類・・・ビール、日本酒、ワインなど
- 加工食品・・・・・炭酸飲料、アイスクリーム、シリアル、フライドポテトなど
- 動物性脂肪・・・・肉の脂身、ベーコン、卵、生クリーム、チーズ、チョコレートなど
食物繊維や不飽和脂肪酸が摂れる野菜、魚類、海藻を積極的に食事に摂り入れてみましょう。
脳梗塞退院後の生活についてのまとめ
脳梗塞の退院後の生活では、生活習慣を見直したり定期的な検査を受けることで再発を防止しましょう。
また、後遺症によってはリハビリを継続し、必要なサービスを活用して機能が低下しないようにするのも重要です。
脳梗塞の後遺症にお悩みの方は、再生医療による治療もおすすめです。
当院では、再生医療による脳梗塞の治療も取り扱っているので、後遺症についてご不安やお悩みがある場合はお気軽にお問い合わせください。

監修者
圓尾 知之
Tomoyuki Maruo
医師
略歴
2002年3月京都府立医科大学 医学部 医学科 卒業
2002年4月医師免許取得
2002年4月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2002年6月関西労災病院 脳神経外科 勤務
2003年6月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2003年12月大阪母子医療センター 脳神経外科 勤務
2004年6月大阪労災病院 脳神経外科 勤務
2005年11月大手前病院 脳神経外科 勤務
2007年12月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2012年3月大阪大学大学院 医学系研究科 修了(医学博士)
2012年4月大阪大学医学部 脳神経外科 特任助教
2014年4月大手前病院 脳神経外科 部長
あわせて読みたいトピックス
-

脳卒中における二木の予後予測とは|回復期リハビリテーションの重要性と注意点を解説
-
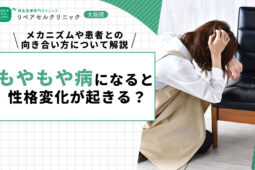
もやもや病になると性格変化が起きる?メカニズムや患者との向き合い方について解説
-

くも膜下出血は後遺症がなくても再発するリスクがある!注意点を解説
-

橋梗塞の症状とリハビリの進め方|具体的なプログラムとポイントについて解説
-

脳出血の看護ケア|在宅でも家族ができることや注意点・ポイントについて解説
-

脳出血の入院期間|年齢別・重症度別の違い、入院費用について解説【医師監修】
-

高次脳機能障害の回復事例を紹介!経過や治療・リハビリが大切な理由も解説
-

高次脳機能障害患者の家族が抱えるストレスとは?つらさの理由と無理をしない接し方を紹介


















