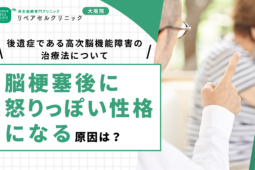- 脳梗塞
- 脳卒中
- 頭部
脳梗塞の看護計画とケアのポイント|退院後に家族ができることを解説
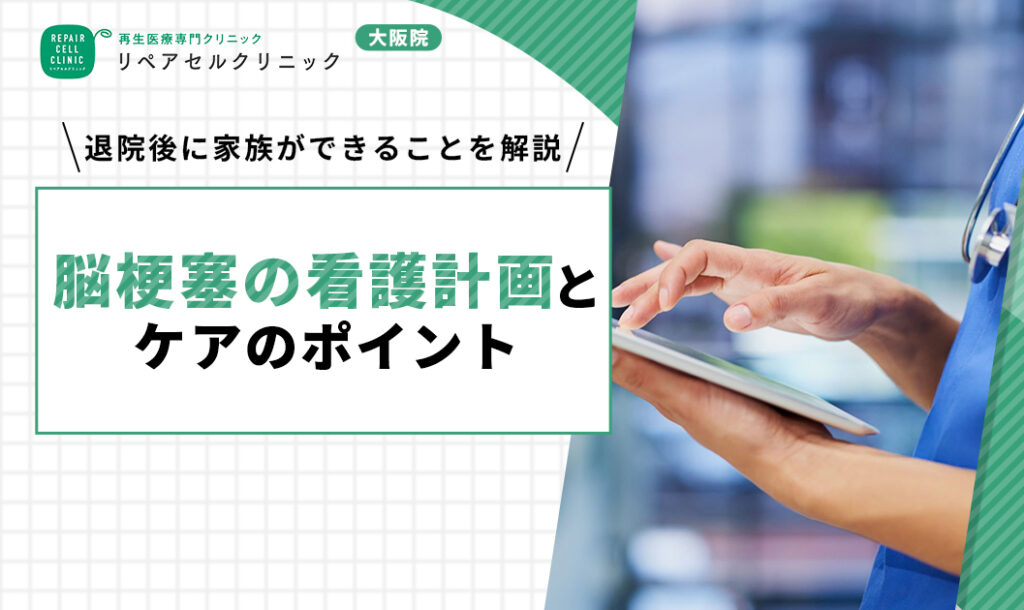
脳梗塞は突然発症し、適切な治療を受けないと重篤な後遺症が残る可能性がある疾患です。
脳梗塞を発症したご家族の看護について、どのようにサポートすればよいか悩まれている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、脳梗塞の病期ごとの看護計画や、ご家族が退院後にできる具体的なサポート方法を解説します。
脳梗塞の看護で困っている方は、ぜひ最後まで読んで適切な対処法を見つけましょう。
また、現在リペアセルクリニックでは脳梗塞の後遺症改善や再発予防の選択肢「再生医療」に関する情報をLINEで発信しております。
脳梗塞の後遺症に関する改善症例も紹介しておりますので、ぜひ登録してください。
目次
脳梗塞の看護計画とケアのポイント
脳梗塞の看護は、発症からの時期によって治療方針や看護内容が異なります。
医療機関では、発症直後と3つの病期に分けられ、それぞれの段階で適切な治療とケアを行われます。
各段階での看護内容を理解することで、ご家族として患者さまがどのような状況にあるのかを把握できます。
発症直後
脳梗塞の発症直後は、生命に関わる最も危険な時期です。
脳の血管が詰まると、脳細胞に酸素や栄養が届かなくなり、時間とともに細胞が壊死していきます。
後遺症を減らすためにも、一刻も早く血流を再開させる治療を始めることが重要です。
脳梗塞の発症直後に医療機関で行われる主な治療は、以下の2つです。
| 治療法 | 内容 |
|---|---|
| t-PA療法 | 発症から4.5時間以内であれば、血栓を溶かす薬を点滴で投与します。 |
| 血栓回収療法 | カテーテルという細い管を血管に入れて、直接血栓を取り除きます。原則として発症から8時間以内、状態によっては24時間以内まで可能です。 |
この時期は、意識の状態、呼吸、血圧、脈拍などを常に確認しながら、症状の変化に注意深く対応します。
食べ物や飲み物が誤って気管に入らないよう、飲み込む力を確認してから食事を開始します。
急性期
急性期は全身の状態が安定しておらず、まだ症状が変化する可能性がある段階(1~2週間が目安)です。
医療機関では、状態が急に悪くなるリスクに注意しながら、全身の管理を行います。
医療スタッフが重点的に確認する項目は、以下のとおりです。
- 意識の状態(呼びかけに反応するか、会話ができるか)
- 呼吸の様子
- 血圧の変動
- 体温
- 手足の動き
- 皮膚の状態
この時期に注意すべきは、廃用症候群の予防です。
廃用症候群とは、筋肉が弱くなる、関節が固まる、肺炎や床ずれが起きやすくなる、といった身体機能の低下を指します。
これを防ぐため、医師の許可が出れば発症から48時間以内にリハビリを開始します。
回復期
発症後2週間から6ヶ月目までの期間を指す回復期は、全身状態が安定し、日常生活の動作を取り戻すための積極的なリハビリを行う時期です。
歩行訓練、手足の運動、言語訓練、飲み込みの訓練など、患者さまの状態に合わせたリハビリを毎日行います。
看護では、リハビリをサポートしながら以下の点を重点的に管理します。
- 食事の飲み込みの確認と栄養状態の管理
- 床ずれの予防と皮膚の清潔保持
- 排泄機能の回復支援
- 手足の麻痺や感覚障害の観察
- 心理的なサポート(不安や落ち込みへの対応)
適切なリハビリと看護により、多くの患者さまが日常生活動作の改善を実感できる時期です。
慢性期
慢性期は、退院に向けた準備を本格的に進める時期です。
患者さまの健康管理を続けながら、以下の点を重視した看護を行います。
- 退院後の日常生活をどう送るかの支援
- ご家族への説明とアドバイス
- 不安や心配に対する心のケア
わからないことや気になることがあれば、遠慮せずに医師や看護師に相談してください。
また、脳梗塞は再発しやすい病気のため、血圧の管理や生活習慣の改善などの再発防止対策を行うことも重要です。
脳梗塞の患者さまを看護するときに家族ができること
脳梗塞の患者さまが退院した後、ご家族が自宅でできる具体的な看護方法を紹介します。
これらのサポートを適切に行うことで、患者さまの回復を促し、ご家族の負担も軽減できます。
日常生活のサポート
退院後の日常生活では、すべてを代わりにやってしまうと回復が遅れる可能性があるため、できることは患者さま自身に行ってもらうことが大切です。
主なサポート内容は、以下のとおりです。
| サポート項目 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 食事 | ・食べ物を小さく切る、とろみをつける ・姿勢を正してゆっくり食べてもらう ・誤嚥防止のため食事中は目を離さない |
| 入浴 | ・手すりの使用、転倒に注意 ・麻痺側を優しく洗い、皮膚状態を確認 ・必要に応じて訪問入浴サービスを利用 |
| 排泄 | ・トイレで排泄できる環境を整える ・ポータブルトイレの設置を検討 ・尊厳を守りながらサポート |
| リハビリ | ・病院で教わった運動を継続 ・無理のない範囲で毎日続ける |
| 心理面 | ・話を聞いて共感する ・小さな回復も一緒に喜ぶ |
生活環境の整備
自宅での生活を安全で快適にするためには、生活環境の整備が必要です。
とくに転倒防止のためにできる工夫として、以下があります。
- 床に物を置かない
- 廊下やトイレ・浴室に手すりを設置する
- 照明を明るくして夜間も足元が見えるようにする
- 段差をなくす、滑りにくいスリッパや靴を使う
- カーペットを固定する
介護保険を利用すれば、住宅改修費用や介護用品の補助を受けられる場合があります。
ケアマネージャーや自治体の窓口に相談してください。
専門家に頼ることも検討
ご家族だけで看護を続けることは、身体的にも精神的にも大きな負担になります。
以下のような専門家に頼ることは決して悪いことではなく、むしろ患者さまとご家族の両方にとって良い選択です。
| サービス | 内容 |
|---|---|
| ソーシャルワーカー | 退院後の生活や介護サービス、介護保険の申請方法など幅広い相談が可能 |
| 訪問看護 | 看護師が自宅を訪問し、健康状態の確認や医療処置、薬の管理を実施 |
| 訪問リハビリ | 理学療法士や作業療法士が自宅でリハビリを指導 |
| デイサービス | 日中、施設で食事や入浴、リハビリなどを受けられ、交流の機会にもなる |
一人で抱え込まず、専門家やサービスを上手に活用しましょう。
脳梗塞の看護についてよくある質問
脳梗塞の看護についてよくある質問を紹介します。
患者さまやご家族が抱える疑問を解消し、適切なケアにお役立てください。
脳梗塞の看護の役割は?
脳梗塞の看護の役割は、患者さまの生命を守り、合併症を予防し、機能回復を支援することです。
具体的には、意識状態や呼吸、血圧などの全身状態を管理し、異常があれば迅速に対応します。
患者さまやご家族の不安に寄り添い、前向きな気持ちを保てるような心理的なケアも重要な役割です。
脳梗塞の看護における観察項目は?
脳梗塞の看護における主な観察項目は、以下のとおりです。
- 意識の状態(目を開けるか、反応があるか、話せるか)
- 呼吸の状態(息苦しさがないか、呼吸のリズムは正常か)
- 血圧と脈拍(血圧が高すぎたり低すぎたりしていないか)
- 体温(発熱していないか)
- 手足の動き(麻痺の程度、筋力の変化)
- 言葉の状態(言葉が出るか、理解できるか)
- 飲み込む力(食事や水分を安全に摂取できるか)
- 排尿・排便の状態
- 皮膚の状態(床ずれができていないか)
- 精神状態(不安や落ち込みがないか)
これらの項目を定期的に確認することで、症状の変化を早期に発見し、適切な対応ができます。
脳梗塞の看護で困ったことは専門家に相談することが大切
脳梗塞の看護は、病期によって治療方針やケアのポイントが異なります。
発症直後から急性期、回復期、慢性期と段階を追って、医療スタッフが適切な治療とケアを行います。
退院後は、ご家族が日常生活のサポート、生活環境の整備、専門家への相談などを通じて患者さまを支えることが大切です。
しかし、すべてを一人で抱え込む必要はありません。
訪問看護やデイサービスなどのサービスを活用し、専門家に頼ることも大切な選択です。
また、脳梗塞の後遺症改善や再発予防の選択肢として、再生医療をご検討ください。
再生医療は、患者さま自身の細胞を使って損傷した組織を再生させる医療技術で、脳梗塞のリハビリとの併用が可能です。
当院「リペアセルクリニック」では、患者さまの状態にあわせて治療方針を提案いたします。
リハビリ以外の治療法をお探しの方は、当院リペアセルクリニックにご相談ください。
>当院の再生医療による脳梗塞の症例はこちら

監修者
圓尾 知之
Tomoyuki Maruo
医師
略歴
2002年3月京都府立医科大学 医学部 医学科 卒業
2002年4月医師免許取得
2002年4月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2002年6月関西労災病院 脳神経外科 勤務
2003年6月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2003年12月大阪母子医療センター 脳神経外科 勤務
2004年6月大阪労災病院 脳神経外科 勤務
2005年11月大手前病院 脳神経外科 勤務
2007年12月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2012年3月大阪大学大学院 医学系研究科 修了(医学博士)
2012年4月大阪大学医学部 脳神経外科 特任助教
2014年4月大手前病院 脳神経外科 部長
あわせて読みたいトピックス
-

脳卒中における二木の予後予測とは|回復期リハビリテーションの重要性と注意点を解説
-
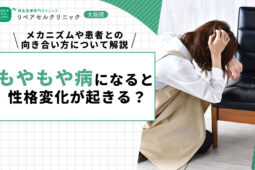
もやもや病になると性格変化が起きる?メカニズムや患者との向き合い方について解説
-

くも膜下出血は後遺症がなくても再発するリスクがある!注意点を解説
-

橋梗塞の症状とリハビリの進め方|具体的なプログラムとポイントについて解説
-

脳出血の看護ケア|在宅でも家族ができることや注意点・ポイントについて解説
-

脳出血の入院期間|年齢別・重症度別の違い、入院費用について解説【医師監修】
-

高次脳機能障害の回復事例を紹介!経過や治療・リハビリが大切な理由も解説
-

高次脳機能障害患者の家族が抱えるストレスとは?つらさの理由と無理をしない接し方を紹介