変形性膝関節症の手術のタイミングは?決める判断基準や手術前に確認すべきことを解説
公開日: 2020.06.28更新日: 2025.06.02
変形性膝関節症の手術は、いつ受けるべきなのか、そのタイミングについて多くの患者さまが悩まれるポイントです。
痛みがあっても日常生活をなんとか送れている場合や、保存療法である程度の効果を感じている場合は、とくに判断が難しいものです。
本記事では、変形性膝関節症の手術のタイミングを判断するための3つの重要な基準と、手術前に確認すべきことを詳しく解説します。
また、当院リペアセルクリニックの公式LINEでは、変形性膝関節症を手術せずに治療できる可能性がある再生医療に関する情報を公開しています。
「手術をせずに治療したい」という方は、手術のタイミングを決める前に再生医療とはどのような治療かご覧ください。
目次
変形性膝関節症の手術のタイミングを決める判断基準
変形性膝関節症の治療では、まず保存療法から始めるのが一般的ですが、手術を検討するべきタイミングは個人の症状や状態によって異なります。
主な判断基準には以下の3つがあります。
これらの基準は互いに関連しており、どれか一つだけでなく、複数の要素を総合的に判断することが重要です。
保存療法で改善が見られない
変形性膝関節症の治療では、まず保存療法(薬物療法、理学療法、装具療法など)から始めるのが一般的です。
しかし、保存療法を6ヶ月程度継続しても痛みや炎症の症状に改善が見られない場合は、手術を検討するタイミングと言えます。
また、保存療法は症状を緩和することはできても根本的な治療ではありません。
十分な効果が得られない場合や、症状の再発を繰り返す場合には、より積極的な治療法として手術が選択肢となります。
医師と相談しながら、症状の経過と治療効果を評価することが大切です。
日常生活に支障が出ている
変形性膝関節症の痛みが日常生活に明らかな支障をきたしている場合は、手術を検討する重要な判断基準となります。
たとえば、歩行困難、階段の昇り降りができない、長時間立っていられない、夜間痛で睡眠が妨げられるなどの症状がある場合です。
これらの症状は生活の質を著しく低下させるだけでなく、膝関節の軟骨がさらに損傷し、骨自体にも悪影響を及ぼしている可能性があります。
症状が悪化する前に専門医に相談することをおすすめします。
進行度がグレード3以上
変形性膝関節症の進行度は、レントゲン画像に基づいて「グレード0〜4」の5段階で評価されます。
グレード3は関節の隙間が明らかに狭くなり、骨棘(こつきょく:骨の端に形成される突起)が顕著に見られる状態です。
この段階になると、軟骨のほとんどが摩耗しており、医師から手術を提案されるケースが増えます。
グレード4になると骨と骨が直接ぶつかる状態となり、痛みがさらに強くなります。
ただし、グレードのみで判断せず、痛みの程度や日常生活への影響も含めて総合的に判断することが重要です。
変形性膝関節症の手術前に確認すべきこと
変形性膝関節症の手術を受ける決断をされた場合、手術に向けて準備を進める前に、いくつかの重要な確認事項があります。
とくに以下の2点については、手術を受ける前に確認しておきましょう。
これらは手術の種類や個人の状態によって大きく異なるため、自分の場合はどうなのか、具体的に確認しておくことが重要です。
それぞれの項目について詳しく見ていきましょう。
術後の日常生活への影響
変形性膝関節症の手術を検討する際は、術後の日常生活にどのような影響があるのかを事前に確認しておきましょう。
手術の種類や個人の状態によって回復期間や制限は異なりますが、一般的には以下のような点に注意が必要です。
| 日常生活への影響 | 詳細 |
|---|---|
| 体重管理 | 体重の増加は膝への負担が増えるため注意 |
| 感染症対策 | 人工関節は感染に弱いため、手洗い・うがいの徹底や歯科疾患や水虫などの早期治療が必要 |
| 深く曲げる動作の制限 | 正座などの膝を深く曲げる動作は避ける |
| 負担が大きい運動の回避 | ウォーキングや水泳などの低負荷の運動を選ぶ |
| 靴の選択 | ヒールが低く幅広い、安定した靴を履く |
| リハビリ期間の確保 | 術後1〜2ヶ月程度の継続的なリハビリが必要 |
これらの生活上の配慮を理解し、術後の生活環境を整えておくことで回復をスムーズに進め、人工関節の寿命を延ばせます。
合併症の可能性
どのような手術にも合併症のリスクは存在するため、変形性膝関節症の手術を受ける前に、起こりうる合併症について理解しておくことが大切です。
主に以下のような合併症が考えられます。
- 傷口の感染
- 血栓症(深部静脈血栓症や肺塞栓症)
- 神経や血管の損傷
- 関節の硬直(拘縮)
とくに人工関節置換術では、人工関節のゆるみや脱臼、摩耗、アレルギー反応といった特有の合併症も考えられます。
年齢や持病によってもリスクは変わるため、個人の状態に応じた詳しい説明を医師から受け、メリットとリスクを十分に比較検討することが重要です。
変形性膝関節症の手術のメリット・デメリット
変形性膝関節症の手術を検討する際には、以下のメリットとデメリットの両方を理解してから判断することが大切です。
手術には患者さまの状態を大きく改善する可能性がある一方で、リスクや回復期間の問題もあります。
ここではメリットとデメリットの両方を詳しく解説します。
手術のメリット
変形性膝関節症の手術には、症状や生活の質を大きく改善する以下のようなメリットがあります。
| 手術のメリット | 詳細 |
|---|---|
| 痛みの大幅な緩和 | 傷んだ軟骨や骨を除去することで大幅な痛みの軽減が期待できる |
| 関節機能の回復 | 変形した関節が修復または置換され、膝の動きが改善する |
| 姿勢の改善 | 膝の変形が矯正され姿勢が良くなり、他の関節への過剰な負担が軽減される |
| 生活の質の向上 | 痛みの軽減と可動域の改善により、生活の質が全体的に向上する |
| 長期的な安定 | 人工関節置換術では、適切なケアを行えば10年以上安定した状態が維持できる |
手術によって得られるこれらのメリットは、保存療法では得られない効果です。
手術のデメリット
一方で、手術には以下のようなデメリットやリスクも存在します。
| 手術のデメリット | 詳細 |
|---|---|
| 感染症リスク | 傷口から細菌が入り込み感染症を引き起こす可能性がある |
| 回復期間の長さ | 腫れや痛みがあり、リハビリが必要で、日常生活への完全復帰までには数ヶ月かかることがある |
| 人工関節の摩耗と緩み | 人工関節置換術では、時間の経過とともに緩みや摩耗が生じ、再手術が必要になる場合がある |
| 活動制限の必要性 | 人工関節置換術後は、激しいスポーツや膝を深く曲げる動作を避けるなど、一定の活動制限が生じる |
| 合併症の可能性 | 血栓症や神経損傷など、手術に伴う合併症のリスクがある |
これらのデメリットを理解した上で、自分の症状や生活スタイル、年齢などを考慮し、医師と十分に相談して手術を検討することが重要です。
変形性膝関節症の手術のタイミングによくある質問
変形性膝関節症の手術を検討する際に、多くの患者さまが抱える疑問にお答えします。
手術のタイミングだけでなく、入院期間や成功率、さらには手術以外の選択肢について、専門的な観点から解説します。
変形性膝関節症の手術後の入院期間は?
人工関節全置換術の場合は通常2〜3週間程度の入院が必要です。
一方、関節鏡手術など負担の少ない手術では1週間程度、部分置換術では10日〜2週間程度が一般的です。
高齢の方や合併症がある場合はさらに長くなることもあります。
退院後も外来でのリハビリテーションが継続的に必要となるため、全体の治療期間を考慮した準備が大切です。
変形性膝関節症の手術の成功率は?
変形性膝関節症の手術の成功率は90%以上です。
手術を受けた患者さまは痛みの軽減と機能改善を実感できるケースが多いです。
とくに人工関節置換術は確立された手術法で、適切な症例選択と術後ケアがなされれば良好な結果が期待できます。
ただし「成功」の定義は患者さまごとに異なり、完全な痛みの消失を期待する方もいれば、日常生活の改善を重視する方もいます。
年齢や活動レベル、関節の状態なども成功率に影響するため、事前に医師と十分に相談し、納得した上で手術を受けることが大切です。
変形膝関節症を手術しないで治す方法はある?
変形性膝関節症を手術せずに治療する方法として、再生医療が注目されています。
再生医療では、主な治療法として幹細胞治療とPRP(多血小板血漿)療法があり、どちらも体への負担が小さいのが特徴です。
- 幹細胞治療:患者さまから採取・培養した幹細胞を患部に注入
- PRP療法:患者さまの血液から採取し濃縮した、成長因子を含む液体を膝関節内に注入
手術をせずに変形性膝関節症の治療する方法をお探しの方は、当院「リペアセルクリニック」へお気軽にお問い合わせください。
再生医療についての詳細は、以下のページでご確認いただけます。
膝の痛みは⼿術しなくても治療できる時代です。
変形性膝関節症の手術のタイミングは3つの判断基準から医師と相談しよう
変形性膝関節症の手術のタイミングは、以下の3つの判断基準を総合的に考慮して決めることが重要です。
- 保存療法で改善が見られない
- 日常生活に支障が出ている
- 進行度がグレード3以上
手術には痛みの緩和や機能回復といった大きなメリットがある一方、回復期間や合併症などのデメリットもあります。
手術前には、術後の生活への影響や合併症の可能性をしっかり理解しておきましょう。
また、手術以外の選択肢として再生医療も注目されています。
ご自身の症状やライフスタイルに合わせて、医師と十分に相談した上で治療法を選択することをおすすめします。

監修者
坂本 貞範
Sadanori Sakamoto
医療法人美喜有会 理事長
「できなくなったことを、再びできるように。」
人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの
お手伝いができれば幸甚の至りでございます。
略歴
1997年3月関西医科大学 医学部卒
1997年4月医師免許取得
1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務
1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務
1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務
1999年2月国立大阪南病院 勤務
2000年3月野上病院 勤務
2003年3月大野記念病院 勤務
2005年5月さかもとクリニック 開設
2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任
2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設
2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設
あわせて読みたいトピックス
-

頬の面積が広い原因とは?原因や対策・治療法も解説
-

鷲足炎のつらい痛みにおすすめのサポーターはソフトタイプ!選び方や種類について解説
-

高齢者の変形性膝関節症手術の種類や特徴について紹介!リスクや治療法の選び方も解説
-

膝の関節リウマチの初期症状は?セルフチェックリストや痛みの対処法について医師が解説
-

鵞足炎の痛みはマッサージで改善できる?痛みを改善して治療する方法を解説
-
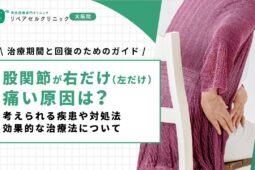
股関節が右だけ(左だけ)痛い原因は?考えられる疾患や対処法、効果的な治療法について
-

変形性股関節症が治った症例はある?損傷した関節軟骨を修復する再生医療について解説
-

変形性膝関節症は水泳で平泳ぎできる?膝に負担をかけない泳法を解説【医師監修】





















