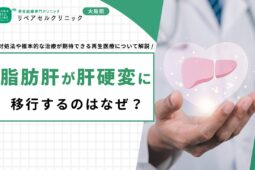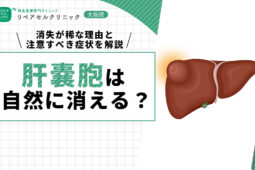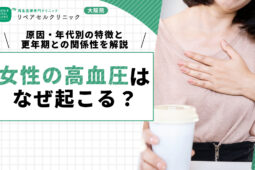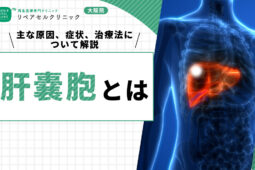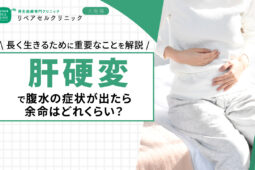- 再生治療
- 肝疾患
- 幹細胞治療
肝硬変を治すには|症状・原因や根治を目指せる治療法について解説【医師監修】

「肝硬変は治る病気なのか」
「肝硬変にはどのような治療法があるのか」
肝硬変と診断され、上記のようなお悩みや不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
今までは一度肝硬変になると完治させることは難しいと言われていましたが、医療技術の進歩により治療選択肢が広がりつつあります。
本記事では、従来の治療法から先端医療である再生医療まで、肝硬変を治すためのさまざまな治療法を紹介します。
肝硬変の治療方法について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
なお、肝硬変を手術や入院なしで治したい方は、先端医療である再生医療による治療も選択肢の一つです。
以下では、実際に当院を利用した患者様の肝硬変に対する再生医療の症例を紹介しているため、併せて参考にしてください。
>再生医療による肝硬変の症例はこちら
当院リペアセルクリニックの公式LINEでは、「再生医療ではどのような治療を行うのか」「再生医療で治療した症例」を無料で配信しています。
「肝硬変を手術や入院なしで治したい」という方は、ぜひ公式LINEをチェックしてみてください。
目次
肝硬変とは|知っておきたい基礎知識
はじめに、肝硬変の症状や治療方針、原因などの基礎知識について解説します。
肝硬変は原因や症状によって治療方針が大きく異なるため、症状や原因についてよく理解しておきましょう。
肝硬変の症状と治療方針
肝硬変の症状や治療方針は、進行度によって異なり「代償性」と「非代償性」の2つの段階に分けられます。
代償性肝硬変
代償性肝硬変とは、肝臓が硬くなっていても、まだ十分な機能を保っている状態です。
この段階ではほとんど自覚症状がないため、健康診断や他の病気の検査で偶然見つかることがほとんどです。
代償性肝硬変の治療方針は「これ以上悪化させない」ことです。
残念ながら、硬くなった肝臓を元に戻す薬はまだありませんが、原因に対する治療で進行を抑えることができます。
B型やC型肝炎ウイルスが原因なら、抗ウイルス薬でウイルスの活動を抑え込むことが有効です。
非代償性肝硬変
非代償性肝硬変は、肝臓の機能が著しく低下し、さまざまな症状が現れる肝硬変が進行した状態です。
この段階では、患者さまの生活の質を維持するために、合併症への適切な対処が重要となります。
非代償性肝硬変の症状と治療のポイントは、以下のとおりです。
- 黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)の出現
- 腹水に対する塩分制限(1日5〜7g)と利尿剤療法
- 重度の腹水には「腹水穿刺(ふくすいせんし)」による直接排液
非代償性肝硬変では、上記の症状が患者さまの日常生活に大きな影響を与えるため、家族の理解とサポートも大切です。
合併症の初期症状(意識の変化や腹部膨満感の増加など)に気づいたら、すぐに医療機関を受診しましょう。
肝硬変の原因
肝硬変は突然発症するものではなく、肝臓の慢性的な障害が徐々に進行して引き起こされます。
主な原因となるのは、B型・C型肝炎ウイルス感染や、脂肪性肝疾患です。
上記のような肝疾患により肝臓に持続的な炎症が起こると、その修復過程で線維(瘢痕組織)が形成され、肝臓全体が硬く小さくなっていきます。
そのため、肝硬変に進行する前に、原因となる肝疾患を治療することが重要です。
肝硬変を治すにはどんな治療がある?
ここからは、肝硬変に対する治療法を3つ解説します。
肝硬変の従来の治療方法は、根本的な治癒よりも「進行抑制」と「症状緩和」を主な目的としています。
薬物療法
肝硬変の治療には、主に以下のような薬が使われます。
| 薬剤 | 作用 |
|---|---|
| ウルソデオキシコール酸 | 以下のような作用により、肝臓の働きを助ける ・胆汁の分泌を促進する ・コレステロールの吸収を抑える ・胆石を溶かす |
| ・スピロノラクトン ・フロセミド |
尿の量を増やして体内の水分を減らす薬で、むくみや腹水を抑える |
上記のほか、B型・C型肝炎ウイルス感染のように原因となる疾患がある場合は、原因疾患に対する治療も行います。
食事療法・生活指導
肝硬変の症状を改善するには、食事療法・生活指導が非常に大切です。
食事のバランスはアンモニア濃度に影響することが確認されています。
また、以下のような疾患・症状がある場合は、カロリー制限や塩分制限なども行います。
| 疾患・症状 | 内容 |
|---|---|
| 糖尿病、肥満 | ・カロリー制限を行う ・食事回数を増やし、1回あたりの食事量を減らす ・就寝前に軽食を摂取して、就寝中に血糖値が下がらないようにする |
| むくみ、腹水 | ・塩分制限を行う |
適切な栄養バランスは人によって異なるため、医師や栄養士の指示を受けながらバランスの良い食事を摂るようにしましょう。
肝移植
非代償性肝硬変のように、肝臓が非常に硬く機能が低下している場合には、肝移植を検討します。
具体的には、以下のような病気が肝移植の対象です。
- ウイルス性肝硬変
- 肝がん
- 自己免疫性肝炎
- 非アルコール性脂肪肝炎
- 急性肝不全(B型肝炎、薬剤性など)
肝移植は根本的な治療につながる治療法ですが、他人の肝臓を移植するため、非常に大掛かりな手術となる点がデメリットです。
肝硬変の根治を目指せる「再生医療」という選択肢
肝硬変は従来の治療法では根本的な改善が難しかったり、大掛かりな手術が必要になったりするというデメリットがありました。
しかし、近年では肝硬変の根治を目指せる「再生医療」という新しい治療法が注目されています。
肝硬変を根本的に治したい方は、ぜひ参考にしてください。
再生医療(幹細胞療法)とは
再生医療は、患者さま自身の細胞を利用することで、入院や手術をせずに肝硬変の根治が期待できる治療法です。
患者さまの脂肪から幹細胞を採取・培養し、数を増やした後に体内に戻します。
幹細胞には、傷ついた血管や損傷した組織に変化する「分化能」という能力があり、肝硬変も根治できる可能性があるというわけです。
再生医療を用いた肝硬変治療は、主に以下のような流れで行います。
- 患者さまの脂肪組織を採取する
- 脂肪組織から幹細胞を取り出す
- 専門の施設で幹細胞を培養し、数を増やす
- 幹細胞を点滴によって患者さまの体内に戻す
点滴により投与した幹細胞は、血流にのって肝臓に到達し、損傷した肝臓組織の修復を促します。
再生医療が肝硬変治療に注目されている理由
再生医療が肝硬変治療に注目されている理由は、以下の3点です。
- 従来の治療法では難しかった「肝臓組織の改善」が期待できる
- 患者さま自身の細胞を用いるため副作用リスクが少ない
- 入院や手術不要で肝硬変の治療ができる
従来の治療法である薬物療法や食事療法は症状を緩和させるだけで、肝臓の組織を修復するという根本的な治療はできません。
また、肝移植は他人の肝臓を使用するため、拒絶反応やアレルギーなどの副作用が起こる可能性がありました。
近年注目されている「再生医療」は、患者さまの細胞を活用することで、リスクを抑えて肝硬変を根本的に改善できる可能性を秘めています。
肝硬変に悩まされていた多くの患者さまに希望をもたらす新たな選択といえるでしょう。
当院リペアセルクリニックの公式LINEでは、再生医療に関する情報を無料で配信しています。
「肝硬変を根本的に治療したい」という方は、ぜひ公式LINEをチェックしてみてください。
肝硬変の予防・進行を遅らせるための対処法
肝硬変は一度進行してしまうと完全に元に戻すことは難しい病気ですが、早い段階から適切な対策を取ることで進行を遅らせたり、発症そのものを予防できます。
近年の日本では、ウイルス性肝炎の治療薬が進歩したことで、ウイルスが原因の肝硬変は減少傾向にある一方、アルコールや脂肪肝など生活習慣に起因する肝硬変の割合が増加しています。
そのため、肝硬変の予防・進行を遅らせるには日々の生活習慣の見直しが重要です。
食生活を改善する
肝臓は「体の化学工場」とも呼ばれ、食事内容が直接肝機能に影響します。
そのため、肝硬変の予防や進行抑制には、日々の食習慣の見直しが欠かせません。
肝臓に優しい食生活を送るために、何を食べるべきか、何を控えるべきかを理解しましょう。
| 積極的に摂りたい食品 | ・野菜、海藻、きのこ類(ビタミン・食物繊維が豊富) ・魚(DHA・EPAが豊富) ・脂肪の少ない肉(鶏むね肉など) ・大豆製品(豆腐・納豆など) ・オリーブオイル、ナッツ類(良質な脂質) ・コーヒー(適量) |
|
控えるべき食品 |
・揚げ物、スナック菓子(高脂肪・高カロリー) ・インスタント食品、ファストフード ・清涼飲料水、甘い菓子類(高糖分) ・塩分の多い食品(漬物・加工肉など) ・生の魚介類、加熱不十分な肉(感染リスク) ・アルコール飲料 |
食事の取り方も重要で、一度に大量に食べるより少量ずつ規則正しく摂ることで、肝臓への負担を減らせます。
特に肝硬変の方は腹水悪化を防ぐため、塩分制限(1日5〜7g)を心がけましょう。
肝機能が低下している方は食中毒リスクが高まるため、生ものは避けた方が良いです。
禁酒・減酒する
アルコールは肝臓で分解される過程で、肝細胞にダメージを与えるため、禁酒・減酒が肝硬変の進行を防ぐポイントです。
お酒を飲む量が多く、期間が長いほど肝臓の線維化(硬くなること)が進行します。
肝硬変や肝がんを予防するためには、「肝硬変になる前にお酒をやめること」が効果的です。
すでに肝硬変と診断された方は、それ以上の悪化を防ぐために禁酒が強くすすめられます。
原因となる肝疾患を治療する
肝硬変の多くは、肝機能障害や肝疾患が長期間進行した結果として発症します。
そのため、前段階である肝炎や脂肪肝などの早期発見と適切な治療が非常に重要です。
例えば、B型・C型肝炎ウイルスに感染している方は、自覚症状がなくても放置すると肝硬変や肝がんへ進行する恐れがあります。
早期に適切な治療を行えば、肝硬変への進行を防げる可能性が高まります。
肝炎ウイルスは自覚症状がないまま肝臓を傷めることが多いため、過去に輸血を受けた経験がある方や感染リスクがある方は一度検査を受けることをおすすめします。
肝硬変を根本的に治すには再生医療をご検討ください
肝硬変は一度発症すると完全な治癒は難しいものの、早期発見と適切な治療により進行を抑えることが可能です。
肝臓の健康は日々の生活習慣に大きく左右されますので、この記事の情報を参考に、ご自身やご家族の肝臓を守る取り組みを始めてみてください。
なお、従来の治療法は進行抑制と症状緩和が中心でしたが、近年では再生医療という新たな選択肢が注目されています。
再生医療は、損傷した肝臓組織の修復・再生を促し、従来では不可能といわれていた「肝臓組織の改善」が期待できる治療法です。
再生医療について詳しく知りたい方は、再生医療を専門とする当院リペアセルクリニックにご相談ください。
また、当院リペアセルクリニックの公式LINEでは、「再生医療ではどのような治療を行うのか」「再生医療で治療した症例」を無料で配信しています。
「肝硬変を手術や入院なしで治したい」という方は、ぜひ公式LINEをチェックしてみてください。

監修者
渡久地 政尚
Masanao Toguchi
医師
略歴
1991年3月琉球大学 医学部 卒業
1991年4月医師免許取得
1992年沖縄協同病院 研修医
2000年癌研究会附属病院 消化器外科 勤務
2008年沖縄協同病院 内科 勤務
2012年老健施設 かりゆしの里 勤務
2013年6月医療法人美喜有会 ふたこクリニック 院長
2014年9月医療法人美喜有会 こまがわホームクリニック 院長
2017年8月医療法人美喜有会 訪問診療部 医局長
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 院長