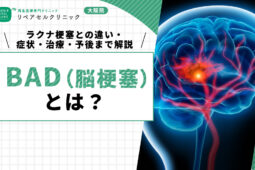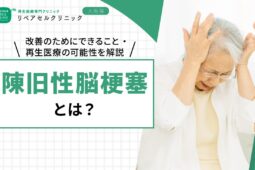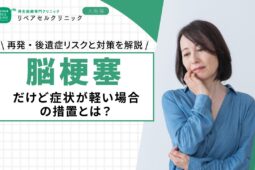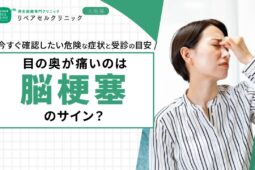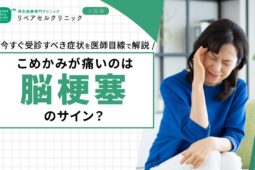- 脳梗塞
脳梗塞は発症から一週間が山?早期対応の重要性とよくある初期症状について解説
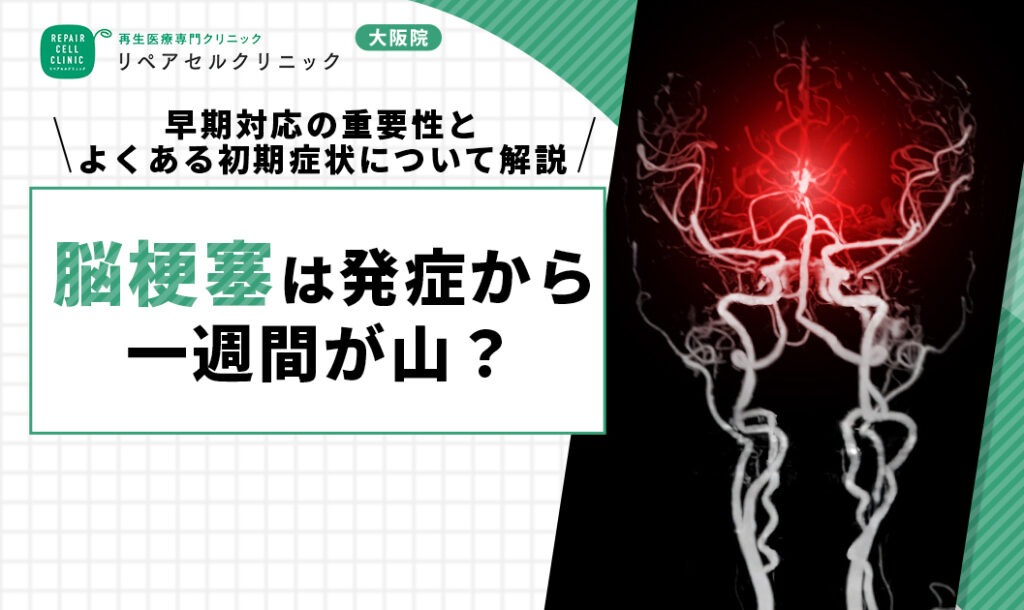
身近な方が脳梗塞で倒れ、「最初の一週間が山場だ」と耳にして、予断を許さない状況に不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
結論、脳梗塞の発症から一週間は、症状が急変しやすい時期にあたります。
本記事では、脳梗塞は「発症から一週間が山」といわれる医学的な理由や、発症後の経過について詳しく解説します。
正しい知識を持つことが、焦る気持ちを落ち着かせ、患者さまを支えるための力となりますので、ぜひ参考にしてください。
また、脳梗塞の後遺症治療や再発予防には、先端医療である再生医療が選択肢の一つです。
再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて損傷した脳細胞の再生・修復を促すことで、後遺症の改善や再発予防につながる治療法です。
以下の動画では、当院の再生医療によって、脳梗塞後の半身麻痺が改善した症例を紹介していますので、併せて参考にしてください。
目次
脳梗塞は「発症から一週間が山」といわれる理由とは
脳梗塞は「発症から一週間が山」といわれる理由は、症状が急変する可能性や脳のむくみ(脳浮腫)といった生命に関わるリスクがこの期間に集中して発生するためです。
一度治療が始まっても、症状が急変する可能性が高く、容体が安定するまでには一定の時間を要します。
本章では、症状の急変が一週間の間に起こりやすいのはなぜか、そのメカニズムと注意点について詳しく解説します。
ご家族としては心配な時期が続きますが、医療チームはこのリスクを予測し、24時間体制で管理を行っているため、信じて見守ることが大切です。
症状が急変する可能性があるのはなぜか
脳梗塞発症直後に入院して治療を開始した場合であっても、最初の数日間は症状が進行したり、悪化したりする可能性が残されています。
脳梗塞の症状が急変する可能性がある理由は、以下のとおりです。
- 血栓の拡大:詰まった血栓がさらに大きくなり、血流が途絶える範囲が広がる。
- 脳浮腫のピーク:発症から3〜5日後には脳浮腫のピーク※により脳が圧迫される。
- 側副血行路の不全:詰まった血管の代わりに働いていた「迂回ルートの血管」の血流が悪くなる。
- 血圧の変動:脳の血流を維持するために必要な血圧が下がってしまう。
- 再発:不安定なプラーク(血管のコブ)が剥がれ、新たな梗塞を作る。
脳梗塞のタイプ(脳血栓症・脳塞栓症)によって症状の進行パターンは異なりますが、いずれの場合も最初の一週間は特に注意が必要です。
そのため、医師や看護師は頻繁に声をかけたり、手足の動きを確認したりして、わずかな変化も見逃さないよう厳重な監視を行っています。
脳梗塞の発症から一週間に行われる対応・治療
脳梗塞の発症から一週間は、時間経過とともに治療の目的が「救命」から「機能回復」へとスピーディーに変化していく期間です。
本章では、発症から時間経過ごとに行われる主な対応・治療について解説します。
この一週間の流れを大まかに把握しておくことで、医師からの説明も理解しやすくなり、ご家族としての心構えも整いやすくなります。
変化する病状に対し、どのような医療介入が行われるのか、具体的に見ていきましょう。
24時間以内の対応
脳梗塞の発症から24時間以内は、「いかに早く血流を再開させ、脳細胞の死滅を食い止めるか」が重要です。
具体的には、病院到着までの時間に応じて、以下のような治療が検討されます。
| 治療法 | 詳細 |
|---|---|
| t-PA静注療法(発症から4.5時間以内) | 血栓を溶かす強力な薬剤を点滴で投与します。 劇的な回復が期待できる反面、出血のリスクもあるため慎重に適応が判断されます。 |
| 脳血管内治療(血栓回収療法) | カテーテルという細い管を太ももの付け根などから入れ、脳の太い血管に詰まった血栓を直接絡め取ったり、吸い出したりします。 t-PAが使えない場合や、効果が不十分な場合に行われます。 |
| 抗血栓療法・脳保護療法 | 血液をサラサラにする点滴を行い、これ以上血栓が大きくならないようにすると同時に、脳細胞を保護する薬剤を使用します。 |
上記の治療は、集中治療室(ICU)や脳卒中ケアユニット(SCU)に入室し、24時間体制での厳重な管理が行われるのが一般的です。
発症直後はどれだけ早く治療を開始できるかで予後に大きな影響を与えるため、脳梗塞が疑われる症状が現れたら迷わずに救急車を呼びましょう。
48〜72時間の対応
脳梗塞の発症から48〜72時間は、脳の「むくみ(脳浮腫)」がピークに向かう時期のため、症状が急変しやすいタイミングです。
血流が戻ったとしても、ダメージを受けた脳細胞が水分を含んで膨らむことで、正常な脳組織まで圧迫してしまうリスクがあります。
この時期は、脳の圧力をコントロールするための治療と、早期回復へ向けた取り組みが並行して行われます。
| 脳浮腫への対策 | 詳細 |
|---|---|
| 抗脳浮腫薬の投与 | グリセロールなどの薬剤を使用し、脳の水分を減らして圧力を下げます。 |
| 開頭減圧術 | 薬の効果が不十分で、脳の腫れが生命を脅かすほど強い場合には、一時的に頭蓋骨を外して脳の逃げ場を作る手術を行うことがあります。 |
また、容体が安定していれば、全身状態に注意しながら発症翌日ごろからリハビリを開始することが一般的です。
ベッド上で手足を動かしたり、座る練習をしたりすることで、寝たきりによる筋力低下(廃用症候群)を防ぐ狙いがあります。
一週間経過後の評価とその後の対応
脳梗塞の発症から一週間が経過すると、脳浮腫が徐々に落ち着き、急性期の危機的な状況を脱するケースが増えてきます。
この段階になると、治療の主軸は急性期治療から「再発予防」および「機能回復のための本格的なリハビリテーション」へと移行します。
具体的には、以下のような評価と方針決定が行われます。
| 評価項目 | 詳細 |
|---|---|
| 神経症状の再評価 | 麻痺の程度、言語障害、飲み込みの機能(嚥下機能)などがどの程度残っているかを詳しく評価します。 |
| 再発予防策の確立 | 脳梗塞の原因(不整脈、動脈硬化など)を突き止め、それに合わせた内服薬の調整や、食事・生活指導を開始します。 |
| 転院の検討 | 急性期病院での治療が終了した後は、リハビリ専門の「回復期リハビリテーション病棟」を持つ病院へ転院し、社会復帰へ向けた集中的なトレーニングを行う流れが一般的です。 |
脳梗塞の発症から一週間を乗り越えることは、回復への道のりのスタートラインに立ったことを意味します。
焦らず長期的な目線で、患者さまご本人の「治したい」という意欲を支えていくことが大切になるでしょう。
脳梗塞の回復には早期対応が重要!よく見られる症状に注意
「一週間が山」と言われる脳梗塞の急性期を乗り越え、その後の回復をスムーズにするためには、「発症時の初期症状にいち早く気づき、救急要請する」ことが重要です。
脳の細胞は血流が止まると短時間で壊死してしまいますが、発症直後であれば、特効薬やカテーテル治療によって改善する余地が残されているためです。
本章では、見逃してはいけない脳梗塞によくある症状について詳しく解説します。
以下で、それぞれの症状について確認していきましょう。
顔や手足の麻痺、しびれ
脳梗塞の初期症状として代表的なものが、身体の片側だけに力が入りにくくなる「片麻痺」です。
麻痺によって、「食事中に箸を落とす」「歩行時に片足を引きずる」「片方の口角が下がる」といった変化が突然現れます。
また、「腕がしびれる」といった感覚の異常も、右半身か左半身の「片側だけ」に現れるのが特徴です。
特定の動作などの原因がなく突然発症するため、顔や手足の片側で麻痺やしびれ症状が見られた場合は、早期に医療機関を受診しましょう。
呂律が回りにくいなどの言語障害
呂律がまわりにくいなどの言葉の異常も、本人や周囲が気づきやすい脳梗塞の重要なサインです。
舌や唇が麻痺して「呂律が回らない」だけでなく、言いたい言葉が出てこなくなる「失語症」が見られるケースもあります。
「話している内容が支離滅裂になる」「相手の言葉が理解できず会話が成立しない」といった場合も、脳の言語中枢がダメージを受けている疑いがあります。
言語障害を自覚したら、早期に医療機関に連絡・受診して診断を受けましょう。
平衡感覚障害によるめまい、吐き気
小脳や脳幹の血流が悪くなり、平衡感覚機能(バランス機能)が損なわれることで、めまいや吐き気が生じることがあります。
「自分や天井がぐるぐると回るような激しいめまい」や、それに伴う「強い吐き気・嘔吐」が特徴です。
まっすぐ歩けずにふらついたり、同時に手足のしびれを伴ったりする場合は、単なる体調不良ではなく脳梗塞の可能性を疑いましょう。
立ち上がれないほどの強いめまいは、脳からの危険信号である可能性があるため、早期に医療機関を受診することが重要です。
目がぼやけ、かすみ
視力を司る脳細胞が影響を受けると、目そのものは健康でも見え方に異常が生じる可能性があります。
「物が二重に見える(複視)」や、「片方の視野が半分だけ欠ける(半盲)」といった症状が特徴的です。
症状を自覚したら片目を隠して見え方を確認し、視野の一部がカーテンを引いたように暗くなっている場合は注意しましょう。
上記のようなケースでは、眼科ではなく脳神経外科への受診が急務となります。
脳梗塞発症から一週間の山を超えても後遺症の可能性あり
脳梗塞の発症から一週間という急性期の「山」を越えれば、命に関わる緊急事態は脱したといえます。
しかし、一週間の山を超えた後は、麻痺や言語障害といった「脳梗塞の後遺症」や「再発リスク」と向き合うことが重要です。
本章では、脳梗塞の後遺症に対するリハビリテーションやご家族ができるサポート内容について解説します。
一度壊死してしまった脳細胞は元に戻りませんが、リハビリによって残された脳の回路を活発に働かせることで、失われた機能を取り戻したり、補ったりできます。
以下でそれぞれの内容について確認していきましょう。
時期ごとのリハビリテーションが重要
脳梗塞のリハビリテーションは、発症からの経過期間によって「急性期」「回復期」「生活期(維持期)」の3つのステージに分けられます。
それぞれの時期で優先すべき目的は異なりますが、一貫して「早期からの開始」と「切れ目のない継続」が適切な機能回復を促すための鉄則です。
各ステージでどのようなリハビリが行われるのか、具体的な内容を見ていきましょう。
急性期のリハビリ
脳梗塞の急性期(発症直後から2週間程度)のリハビリは、全身状態に注意したうえでベッド周辺でできることから開始されます。
「治療中に動かしてよいのか」と不安に思うかもしれませんが、早期のリハビリは、筋力が衰えて体が固まる「廃用症候群」を防ぐために不可欠です。
手足の関節を動かしたり、ベッドの上で寝返りを打ったり、端に座ったりすることから始め、早期の離床を目指します。
回復期のリハビリ
病状が安定した発症後数週間〜6ヶ月程度の回復期に行われるリハビリは、機能回復のための「ゴールデンタイム」です。
回復期は脳の神経可逆性(神経構造や機能を変化させる能力)が最も高く、この期間で集中的なリハビリを行うことで、新しい神経経路が形成され、後遺症の軽減や再発予防につながります。
多くの場合はリハビリテーション専門の病院へ転院し、一日平均2時間から最大3時間の集中的なトレーニングに取り組みます。
麻痺した手足の機能訓練に加え、歩行、食事、着替え、入浴といった「日常生活動作(ADL)」を自力で行えるようにし、自宅復帰や社会復帰を目指すことが目標です。
生活期(維持期)のリハビリ
生活期(維持期)は、退院後に自宅や施設での生活が始まってからのリハビリ期間を指します。
回復期で取り戻した機能が再び低下しないよう維持し、実際の生活や仕事の中で活かしていくことが目的となります。
病院での訓練とは異なり、デイケアや訪問リハビリを活用しながら、家事や趣味、散歩などを通じて「生活そのものをリハビリにする」という意識で継続することが大切です。
家族ができるサポート
脳梗塞を発症し、後遺症のリハビリを励む患者さまに対して、専門的な介護をすべて背負う必要はありません。
ご家族だからこそできるサポートとして、以下のポイントを意識してみましょう。
| 家族ができること | 詳細 |
|---|---|
| 精神的なケア | 小さな変化や回復を一緒に喜び、孤独感を和らげる声かけをする。 |
| 環境の整備 | 手すりの設置や段差の解消など、安全に暮らせる住環境を整える。 |
| 情報の共有 | 医師やリハビリスタッフと密にコミュニケーションを取り、本人の状態や家での注意点を把握する。 |
| 制度の手続き | 介護保険や身体障害者手帳の申請など、公的支援を受けるための手続きを進める。 |
突然の脳梗塞や後遺症に戸惑い、リハビリに励む患者さまにとって、一番近くにいるご家族の存在は何よりの支えになります。
しかし、負担が大きいと感じる場合は、公的サービスを利用できるため、上手く活用することも重要です。
脳梗塞の一週間の山を超えた後の治療には再生医療をご検討ください
脳梗塞は、症状が急変する可能性や脳のむくみ(脳浮腫)といった生命に関わるリスクが集中する「発症から一週間が山」といわれています。
早期発見・早期治療によって山を超えた後も、麻痺・しびれや言語障害などの後遺症や再発リスクと向き合う必要があります。
しかし、いつまで続くかわからない長期間のリハビリテーションや再発予防に疲れてしまい、治療に前向きになれない患者さまも少なくありません。
そこで、近年の脳梗塞治療では、患者さまの細胞や血液を用いて損傷した脳細胞の再生・修復を促す再生医療が注目されています。
これまでの医学では「一度死んだ脳細胞は戻らない」とされてきましたが、再生医療はその考えを覆す可能性を秘めている治療法として研究が進んできました。
当院リペアセルクリニックでも、再生医療によって長年悩まされていた脳梗塞の後遺症が改善した患者さまの症例もあります。
>10年前の脳梗塞による半身麻痺の後遺症が改善した症例(40代男性)はこちら
「再生医療について詳しく知りたい」という方は、ぜひ当院の無料カウンセリングにてご相談ください。

監修者
圓尾 知之
Tomoyuki Maruo
医師
略歴
2002年3月京都府立医科大学 医学部 医学科 卒業
2002年4月医師免許取得
2002年4月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2002年6月関西労災病院 脳神経外科 勤務
2003年6月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2003年12月大阪母子医療センター 脳神経外科 勤務
2004年6月大阪労災病院 脳神経外科 勤務
2005年11月大手前病院 脳神経外科 勤務
2007年12月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2012年3月大阪大学大学院 医学系研究科 修了(医学博士)
2012年4月大阪大学医学部 脳神経外科 特任助教
2014年4月大手前病院 脳神経外科 部長