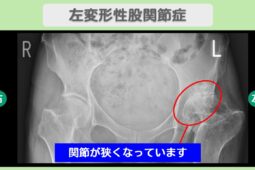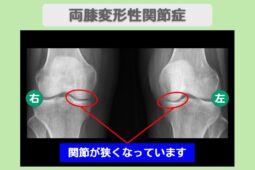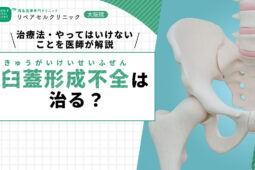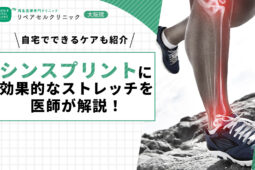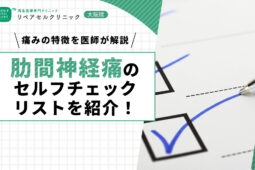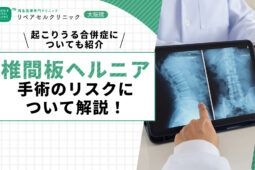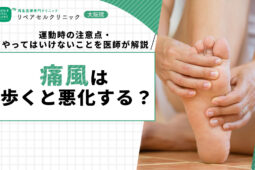- 免疫細胞療法
- 再生治療
膀胱炎の治し方|自力で治す方法と治療中にやってはいけないことを解説【医師監修】
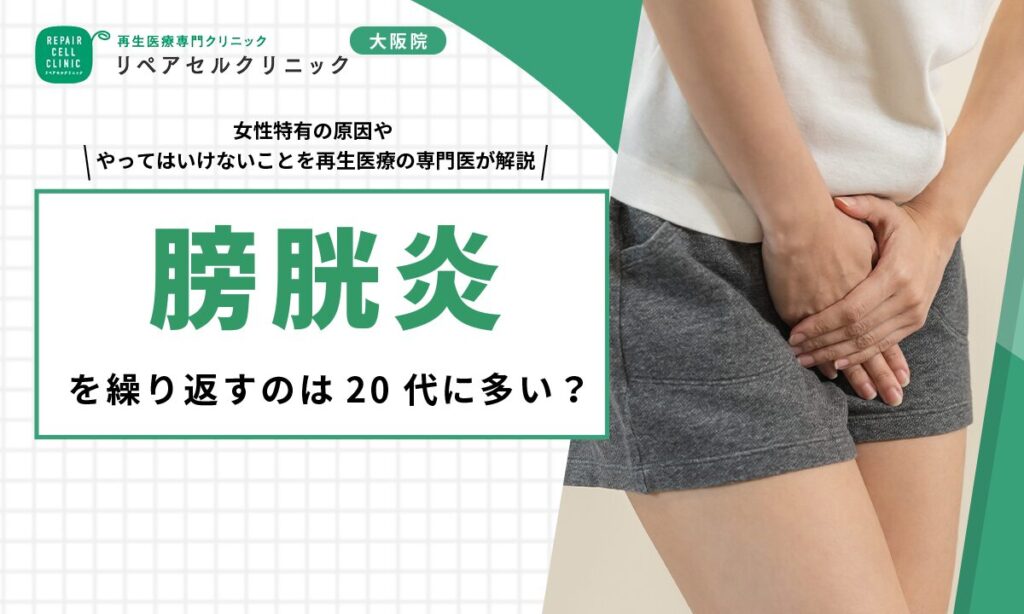
膀胱炎(ぼうこうえん)は、細菌感染が原因で膀胱に炎症が起こる病気で、排尿痛や残尿感などの症状がみられます。
「膀胱炎は自力で治せるのか」「医療機関を受診すべきかどうか」不安な方も多いのではないでしょうか。
本記事では、膀胱炎の症状改善が期待できるセルフケアと治療法について解説します。
また、膀胱炎に関するお悩みを今すぐ解消したい方は、再生医療による治療も選択肢の一つです。
\膀胱炎に有効な再生医療とは/
再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて自然治癒力を向上させることで、繰り返す膀胱炎の改善が期待できます。
【こんな方は再生医療をご検討ください】
- 繰り返す膀胱炎を早く治したい
- 現在の治療では目立った効果が出ていない
具体的な治療法については、当院リペアセルクリニックで無料カウンセリングを行っておりますので、ぜひご相談ください。
▼まずは膀胱炎の治療について無料相談!
>>(こちらをクリック)今すぐ電話相談してみる
目次
膀胱炎の治し方|自力で治すためのセルフケア
軽度・初期症状の段階の膀胱炎であれば、以下で紹介するセルフケアで改善が期待できます。
しかし、発熱や血尿、強い痛みや症状の悪化が見られた場合は医療機関を受診してください。
膀胱炎になった際のセルフケア方法について、詳しく解説します。
水分を多く摂る
膀胱炎にかかったら、意識的に水分を多く摂ることが重要です。
水分摂取によって排尿の回数が多くなり、膀胱内にある雑菌が排出されます。
1日に1.5リットルから2リットルほど飲むと良いでしょう。
カフェインやアルコールは利尿作用がありますが、膀胱に刺激を与える可能性があるので、カフェインが含まれていない水が推奨されます。
トイレを我慢しない
尿意を感じたら我慢せずにトイレに行きましょう。
日常的に排尿を我慢する習慣があると膀胱の機能が低下して、排尿後に尿が残ってしまう「残尿」が増える恐れがあります。
残尿が増えると、雑菌を多く含んだ尿が長時間溜まることになり、細菌が繁殖しやすい環境を作り出し、膀胱炎のリスクを高める原因となります。
尿意がない場合でも、トイレに行く時間を決める、あるいはトイレの前を通った際に立ち寄るなど、こまめな排尿を習慣づける工夫をしましょう。
デリケートゾーンを清潔に保つ
膀胱炎にかかったときは、症状の悪化を防ぐためにデリケートゾーンを清潔に保つことが重要です。
デリケートゾーンを清潔に保つために、以下の点に注意してください。
- おりものシートやナプキンをこまめに替える
- シャワーや入浴で身体を綺麗に保つ
- 性行為を控える
とくに女性は、ナプキンなどとデリケートゾーンが密着しているため、菌が繁殖しやすい状態にあります。こまめに取り換え、雑菌が繁殖しないようにしましょう。
性行為は尿道から雑菌が入るリスクがあるので、膀胱炎にかかった場合は控えてください。
シャワーや入浴で身体を清潔に保つと、膀胱炎の改善に効果が期待できます。
下腹部を温める
効果に個人差がありますが、下腹部を温めると膀胱の圧迫感や不快感を緩和する効果が期待されます。
痛みや違和感がある部位にカイロやパッドを当てるほか、入浴で下腹部を温めることでも同様の効果が得られます。
しかし、温めることで血行促進による症状緩和効果は期待できますが、対症療法となるため、根本的な治療にはつながりません。
また、方法によっては長時間温めていると火傷する可能性があるので、温度や温める時間に注意して利用しましょう。
膀胱炎の治し方|医療機関で受けられる治療
医療機関で受けられる治療は、基本的に薬物療法です。
膀胱炎の種類別に治療法を解説します。
それぞれの膀胱炎で、発症の原因や治療法が異なりますので、ご自身の症状に合わせた治療法をご確認ください。
急性単純性膀胱炎
急性単純性膀胱炎で処方される代表的な薬剤は4種類あります。
| 対象 | 薬剤 | 服用期間 |
| 閉経前の女性 | レポフロキサシン | 3日 |
| シプロフロキサシン | 3日 | |
| セファレキシン | 7日 | |
| アモキシシリン/クラブラン酸配合剤 | 7日 | |
| 閉経後の女性 | セファレキシン | 7日 |
| アモキシシリン/クラブラン酸配合剤 | 7日 |
急性単純性膀胱炎は、女性が発症しやすい膀胱炎です。
尿道から侵入した細菌が膀胱内で増殖することで起こる、比較的軽度な膀胱炎です。主な症状は、排尿時の痛み・頻尿・残尿感・尿の濁り・血尿が挙げられます。
閉経前・閉経後の女性で処方される薬が異なるのは、閉経後の女性はキノロン系薬剤への耐性を持つ菌が多い傾向にあるためです。
急性単純性膀胱炎は抗菌薬の服用によって、数日から1週間程度で改善する可能性があります。
複雑性膀胱炎
複雑性膀胱炎の場合、処方される薬剤は主に2種類ですが、効果によって変更されるケースがあります。
| 種類 | 薬剤 | 服用期間 |
| 第一選択 | レポフロキサシン | 7~14日間 |
| シプロフロキサシン | 7~14日間 | |
| 難治例 | カルバペネム系注射薬 | 3〜14日間 |
| 第4世代セファロスポリン系注射薬 | 3~14日間 |
複雑性膀胱炎は、前立腺肥大症・尿路結石・糖尿病などの基礎疾患がある場合に起こる膀胱炎です。
単純性膀胱炎と異なり、基礎疾患の治療も同時に行わないと治りにくく、再発しやすいのが特徴です。
第一選択薬を投与して効果が見られない場合は、難治例に投与される薬が処方されます。これらの治療は検査結果に基づいて医師が判断します。
自己判断での服薬中止は、症状悪化や耐性菌発生のリスクを高めるため、必ず医師の指示に従いましょう。
ESBL産生菌による膀胱炎
ESBL産生菌による膀胱炎は、2種類の代表的な薬剤があります。
- ホスホマイシン
- ファロペネム
ESBL産生菌は、多くの種類の抗菌薬を分解する酵素を作り出す菌です。この菌は膀胱炎の治療に用いられる抗菌薬が効きにくく、治療が難しくなります。
ESBL産生菌による膀胱炎は再発しやすい傾向にあるため、治療が終わった後も油断はできません。
膀胱炎中にやってはいけないこと
膀胱炎にかかっているときには、症状の悪化を防ぐためにも以下の行動は避けましょう。
- トイレを我慢する
- ストレスを溜める
- 刺激物を摂取する
- 下腹部を冷やす
- 自己判断での治療
ストレスを溜めると免疫力が低下して、膀胱の機能の低下や症状の悪化を招く可能性があります。
刺激物を摂取すると膀胱の粘膜を刺激して症状を悪化させるケースがあるので、辛い物や酸味が強い食べ物の摂取は控えましょう。
自己判断で市販薬を使用せず、医療機関を受診したうえで医師の指導に従って治療をしてください。
膀胱炎の再発を防ぐ予防法
膀胱炎の再発を防ぐために気を付けることを紹介します。
| 予防法 | 内容 |
| 生理ナプキンをこまめに替える | 汚物が付いたナプキンを長時間付けていると雑菌が繁殖する可能性がある |
| トイレを我慢しすぎない | トイレを長時間我慢すると、膀胱内で菌が繁殖するケースがあるため、3~4時間に1度を目安にトイレに行く |
| 性行為の後にトイレに行く | 性交時に菌が入ってしまう可能性があるため、性行為の後にトイレに行く習慣をつける |
| 疲労をためこまないようにする | 疲れがたまることにより、免疫力が低下して膀胱炎にかかりやすくなるため、睡眠・休息をとる |
| 温水便座を使い過ぎない | 温水便座を過度に利用すると粘膜のバリア機能が弱くなり、膀胱に菌が入りやすくなるため、洗いすぎないよう注意する。 |
| 排便後に前から後ろに拭くようにする | 後ろから前に拭くと肛門の菌が尿道などに付着し、膀胱に入ってしまう可能性がある |
上記のように、膀胱炎の再発を防ぐにはデリケートゾーンを清潔に保つことが重要です。
温水便座はデリケートゾーンを清潔にするのに便利で多くのトイレで使用できますが、使用しすぎると粘膜のバリア機能が弱くなる可能性があるため、洗いすぎには注意が必要です。
膀胱炎の治し方についてよくある質問
膀胱炎の治し方についてのよくある質問に回答します。
以下では、それぞれの質問について詳しく解説していきます。
膀胱炎は市販薬で治せる?
膀胱炎の市販薬を使用することで症状の緩和は期待できますが、根本治療にはなりません。
市販薬には抗生物質が含まれていないためです。
2~3日で改善しない場合や、発熱・血尿・強い痛みがある場合は医療機関を受診してください。
膀胱炎は温めると治る?
温めると血行が促進され膀胱の不快感などが改善されますが、膀胱炎を治療する効果はありません。
あくまで対症療法となるため、適切な治療を受ける必要があります。
もし違和感のある部位を温める場合は、火傷のリスクを回避するため、カイロや湯たんぽの温度に注意しながら利用してください。
また、入浴するのも同様の効果が期待できます。
膀胱炎の原因は?
膀胱炎の主な原因は、細菌が膀胱粘膜に感染することです。
以下のような方は膀胱炎になりやすいため、注意しましょう。
- トイレを我慢しすぎる
- 生理ナプキンなどの長時間使用
- 過度なストレス
- 水分不足
- 基礎疾患がある
尿を膀胱に長時間ためず、雑菌が繁殖する環境を作らないことが重要です。
トイレや性行為の後もデリケートゾーン周辺を清潔に保つようにしましょう。
膀胱炎の治し方|適切な対処で早期回復を目指そう
軽度・初期の膀胱炎であれば、セルフケアで膀胱炎の改善が期待できます。
しかし、症状が長引いている場合や、発熱・血尿・強い痛みがある場合は医療機関を受診して、適切な治療を受ける必要があります。
当院リペアセルクリニックでは、膀胱炎に対して再生医療による治療を行っています。
再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて自然治癒力を向上させることで、繰り返す膀胱炎の改善が期待できます。
\こんな方は再生医療をご検討ください/
- 繰り返す膀胱炎を早く治したい
- 現在の治療では目立った効果が出ていない
繰り返す膀胱炎でお悩みの方は、ぜひ当院リペアセルクリニックまでご相談ください。
▼まずは膀胱炎の治療について無料相談!
>>(こちらをクリック)今すぐ電話相談してみる

監修者
岩井 俊賢
Toshinobu Iwai
医師