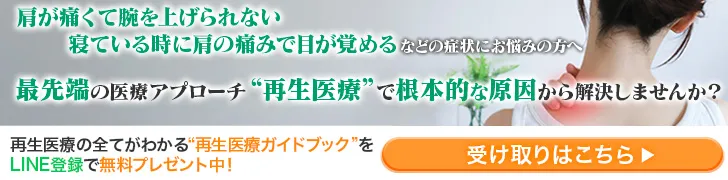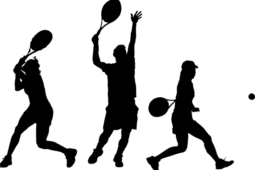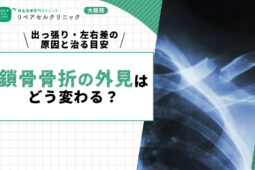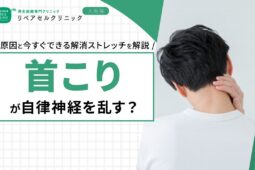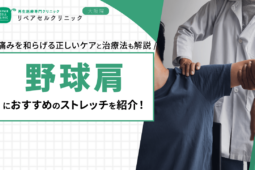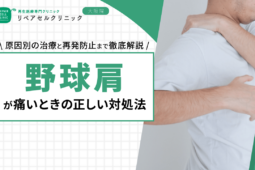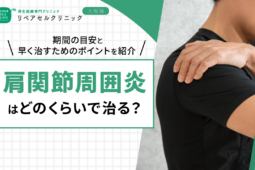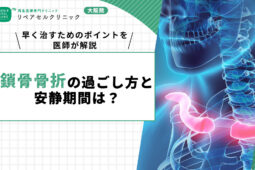- 肩
フローズンショルダー(凍結肩)とは?原因や治療法、リハビリについて解説

五十肩とも呼ばれる「フローズンショルダー(凍結肩)」は、ある日突然始まる肩の激しい痛みや腕が上がらないといった動きの制限によって、日常生活に大きな影響を与えます。
本記事では、フローズンショルダーとは一体どのような病気なのか、その主な原因、そして具体的な治療法について解説します。
- フローズンショルダー(凍結肩)の症状と主な原因
- 保存療法、手術療法、サイレントマニピュレーションといった主な治療法
- 症状の段階(炎症期・拘縮期・回復期)に応じた適切なリハビリ方法
肩の痛みや動きの制限でお悩みの方、フローズンショルダーについて詳しく知りたい方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
また、当院リペアセルクリニックの公式LINEでは、つらい肩の痛み症状の改善を目指せる再生医療に関する情報を配信中です。
「肩の痛みを早く治したい」という方は、ぜひ再生医療がどのような治療を行うか知っておきましょう。
目次
フローズンショルダー(凍結肩)とは
フローズンショルダー(凍結肩)は、肩関節を包んでいる関節包が炎症を起こして硬くなることで、痛みと可動域の制限が起きる疾患です。
じっとしていても痛むことがあり、特に夜間に痛みが強くなって目が覚めてしまう「夜間痛」に悩まされる方も少なくありません。
腕を上げようとしても一定の角度以上は上がらず、後ろに手を回そうとしても背中の途中までしか届かないなど、まるで肩が凍りついたかのように動きが固まってしまいます。
ただし、肩が痛くて上がらないという症状は、「石灰沈着性腱板炎」や「肩腱板断裂」などの病気でも起こりえます。
症状が続く場合は、必ず整形外科などの専門医を受診し、正確な診断を受けましょう。
以下の記事では「肩腱板断裂と五十肩の違い」について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
フローズンショルダー(凍結肩)の主な原因
フローズンショルダー(凍結肩)の明確な原因はまだ特定されていませんが、以下のような原因が関与しているとされています。
フローズンショルダー(凍結肩)の主な原因
- 加齢
- 肩の酷使
- 肩の外傷
- 姿勢の悪さ
- 運動不足
- 糖尿病
- ホルモンバランスの変化
- 慢性的なストレス
上記の要因が複数重なり合うことで、フローズンショルダーは発症すると考えられています。
フローズンショルダー(凍結肩)の治療法
本章では、フローズンショルダーに対して行われる主な治療法について解説していきます。
フローズンショルダー(凍結肩)の治療では、まず手術などのメスを使用しない保存療法から始めるのが基本です。
しかし、症状が長引く場合にはより積極的な治療法が検討されることもあります。
以下の動画では、四十肩・五十肩の治療について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
保存療法
フローズンショルダー(凍結肩)の治療は、まず手術以外の「保存療法」から始めるのが基本です。
痛みや炎症を抑えながら、硬くなった肩関節の動きを改善させることを目的に、以下の方法を組み合わせて行います。
| 治療法 | 詳細 |
| 薬物療法 | 痛みや炎症を和らげるための消炎鎮痛薬(NSAIDsなど)や筋肉の緊張をほぐす筋弛緩薬の内服、湿布の使用。 |
| 理学療法(リハビリ) | 肩周りの筋肉をほぐし、関節の動く範囲を広げるためのストレッチや運動療法。 温熱療法や超音波療法といった物理療法を併用することも。 |
| 注射療法 | 肩関節の周りへのステロイド注射による強力な抗炎症作用で、つらい痛みの軽減を図る。 関節の潤滑を良くする目的でヒアルロン酸注射を行う場合もある。 |
保存療法による治療を6カ月以上継続しても痛みが改善しない場合は、次に紹介する手術療法やサイレントマニピュレーションが検討されます。
手術療法
フローズンショルダー(凍結肩)の症状が、長期間にわたる保存療法を続けても一向に改善しない重度なケースでは、手術療法が検討されることがあります。
| 主な手術法 | 関節鏡下関節包解離術 |
| 詳細 | 肩に1cm程度の小さな穴を数カ所開け、そこから内視鏡(関節鏡)と細い手術器具を挿入し、硬く癒着した関節包を直接切開して、肩の動きを広げる |
| メリット | 従来の大きく切開する手術に比べて出血量が少なく、体への負担も少ない。 術後の回復が比較的早い。 |
ただし、手術にはわずかながら神経麻痺、感染症といったリスクも伴います。
手術を行うかどうかはメリットとリスクを総合的に考慮し、医師と患者さまが十分に話し合ったうえで、慎重に決定しましょう。
サイレントマニピュレーション
サイレントマニピュレーションは、保存療法では改善が難しい、固まってしまった重度のフローズンショルダー(凍結肩)に対して検討されるメスを使わない治療法です。
| ポイント | 詳細 |
| 治療方法 | 肩に局所麻酔を効かせた状態で、医師が患者様の力を借りずに肩関節を動かし、癒着して硬くなった関節包を剥がして可動域を改善させる |
| メリット | 麻酔下で行うため、施術中に痛みを感じることはほとんどない。 入院の必要がなく日帰りで受けられる場合もある。 |
施術後は、再び関節が固まってしまわないようにリハビリをする必要があります。
せっかく動くようになった肩もリハビリを怠ると、また元の固まった状態に戻ってしまう可能性があります。
以下の記事では、サイレントマニピュレーションについて詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
フローズンショルダー(凍結肩)に有効なリハビリテーション
フローズンショルダー(凍結肩)の改善や再発を予防するために大切なのはリハビリです。
本章では、凍結肩の病期ごとのリハビリについて解説します。
フローズンショルダー(凍結肩)の病期を大きく分けると炎症期、拘縮期、回復期の3つに分けることができますが、リハビリは、それぞれの病期に合わせておこなうことが大切です。
以下では、病期ごとのリハビリテーション内容について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
炎症期のリハビリテーション
フローズンショルダー(凍結肩)の炎症期は、明確なきっかけもなく痛みや違和感が生じ、関節が急速に硬くなっていく時期です。
肩を動かしたときに痛みが生じるだけでなく、安静にしているときや、寝ているときにも痛みが生じるのが特徴です。
進行期は痛みがあるときは局所を固定して安静にするべきですが、痛みの状態を見てストレッチや肩甲骨の動きを広げるエクササイズを少しずつ行なっていきます。
拘縮期のリハビリテーション
フローズンショルダー(凍結肩)の炎症期を過ぎると、拘縮期に入ります。
拘縮期は、炎症機ほどの強い痛みは治まるものの、肩の動きが悪くなって思うような動作ができなくなったり、動かす時に痛みが生じたりする時期です。
拘縮期には、運動療法によって動きにくくなった肩関節を動かせる範囲を広げていきます。
また、スポーツや仕事で肩をよく動かす必要がある場合は、その動作ができるようにするためのトレーニングも行います。
回復期のリハビリテーション
拘縮期を過ぎて回復期に入ると、肩を動かすときも痛みが出なくなってきたり、動かせる範囲も広くなってきます。
回復期になると「もう大丈夫だろう」とリハビリを止めてしまいがちですが、回復期こそしっかりとリハビリをして、継続的に症状改善を目指していくことが大切です。
回復期のリハビリは、肩関節の動かせる範囲を広げる運動や、普段よくおこなう動作の練習をし、肩周辺の筋肉も鍛えていきます。
以下の記事では、フローズンショルダー(凍結肩)を改善するためのストレッチを紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
フローズンショルダーによるつらい肩の痛みは早めに対処しよう
フローズンショルダーは、「関節包」という組織が炎症を起こして硬くなることで、激しい痛みと腕が上がらないといった動きの制限を引き起こす病気です。
しかし、肩の痛みの原因は「石灰沈着性腱板炎」や「肩腱板断裂」といった治療法が異なる類似の疾患である可能性も考えられます。
そのため、肩の痛みが長引いているのであれば自己判断で放置したりせず、まずは整形外科などの専門医療機関を早めに受診し、医師による正確な診断を受けることが重要です。
痛みが長引く方や損傷した組織の修復を促したいと考える方に対しては、ご自身の細胞や血液を活用して治療を行う「再生医療」も選択肢の一つです。
「肩の痛みを早く治したい」という方は、ぜひ当院リペアセルクリニックへご相談ください。

監修者
坂本 貞範
Sadanori Sakamoto
医療法人美喜有会 理事長
「できなくなったことを、再びできるように。」
人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの
お手伝いができれば幸甚の至りでございます。
略歴
1997年3月関西医科大学 医学部卒
1997年4月医師免許取得
1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務
1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務
1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務
1999年2月国立大阪南病院 勤務
2000年3月野上病院 勤務
2003年3月大野記念病院 勤務
2005年5月さかもとクリニック 開設
2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任
2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設
2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設