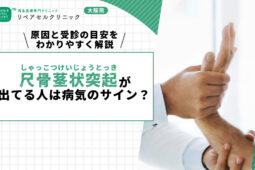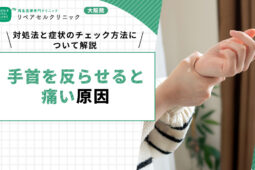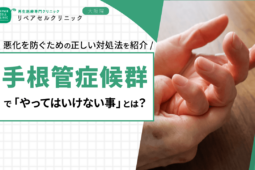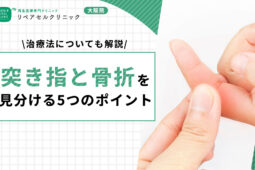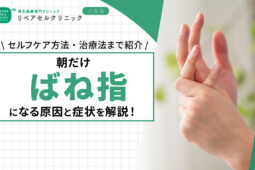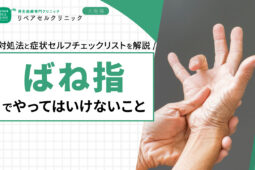- 手
- 再生治療
TFCC損傷を放置するとどうなる?悪化リスクや治療法を紹介
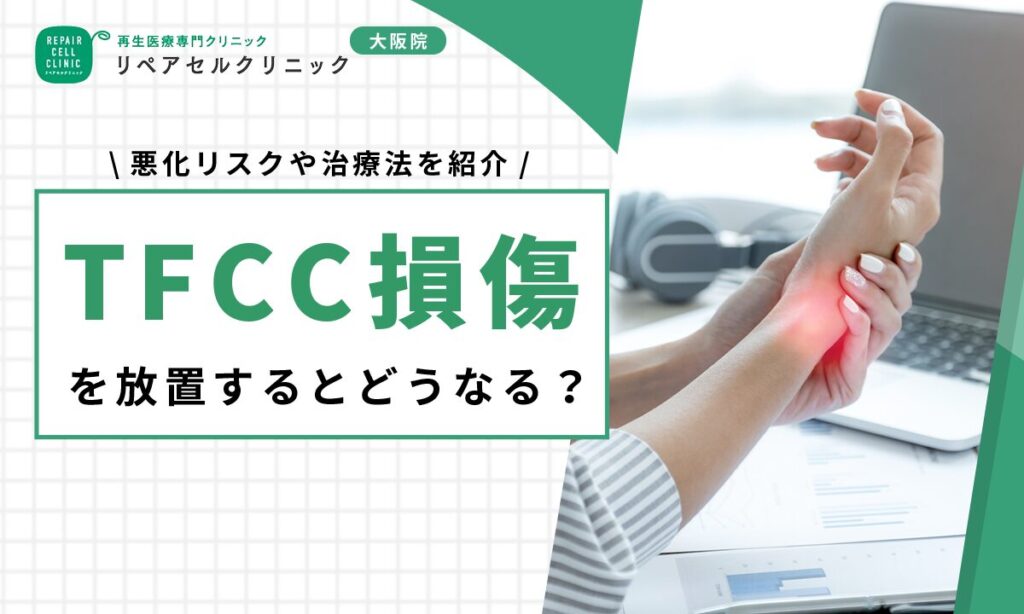
ドアノブを回す・重い物を持つ・パソコンを使うなど、普段何気なく行っている動作で手首に痛みがあるけど、「少しの痛みだから大丈夫」「そのうち治るだろう」と放置していませんか?
その痛みはTFCC損傷(三角線維軟骨複合体)と呼ばれる症状の可能性があり、放置すると日常生活での動作において痛みの慢性化や可動域の制限といった症状に進行するリスクも。
TFCC損傷は日常生活の動作で悪化する可能性もあるため、早期発見・早期治療が重要です。
この記事では、TFCC損傷を放置するリスクや原因、幅広い治療選択肢について詳しく解説します。
「この手首の痛みは放っておいて大丈夫?」と不安を抱えている方は、ぜひ参考にして早期治療に努めましょう。
目次
TFCC損傷を放置するリスク
TFCC損傷を放置すると、以下のようなさまざまなリスクを引き起こす可能性があります。
日常生活で安静にせず症状が進行した場合、手術が必要になる可能性があるため注意が必要です。
ただし手首を使う動作は日常生活で頻繁に行うため、安静にしていても症状が悪化する可能性があるので、少しでも痛みを感じた場合は医療機関を受診してください。
痛みの慢性化・悪化
TFCC損傷は軽い場合は自然に回復することもありますが、症状の程度によっては悪化するリスクがあります。
放置してしまうと、痛みの慢性化や手首の不安定感、動きの制限などの症状が現れることがあります。
とくに野球やテニスなどのスポーツをされている方は、手首に繰り返しかかる負荷が悪化の原因となるため、一時的な運動制限の検討が必要な場合も。
また、長時間のスマホ使用でも同じ動作を続けることで症状が悪化する可能性があります。
少しでも痛みを感じたら、無理な運動や長時間のスマホ使用は控えるようにしましょう。
可動域の制限
TFCC損傷は手首に繰り返し負荷がかかることで、以下のように動作の可動域が制限される可能性があります。
- ドアノブを回す、ペットボトルのフタを開ける動作など
- マウス操作などのパソコン作業
- フライパンを持つ、荷物を運ぶなど
このような状態を放置すると痛みだけでなく、手首の柔軟性や機能が低下し、日常生活に影響を及ぼす可能性があるので注意しましょう。
少しでも痛みや動かしづらさを感じた場合は手首に負担がかからないようにし、早めに医療機関で受診してください。
手首の不安定感
TFCC損傷が悪化すると、以下のような手首の不安定感を伴う症状が現れることがあります。
- 手首の力が抜ける
- グラグラする
- 安定しない
具体的には物を持ち上げる際に手首がぐらつく、動作中に抜けるような感覚があるといった症状になります。
放置すると、周囲の靱帯や腱にも負担がかかり、痛みや炎症が広がる恐れも。
このような不安定感を感じた場合は、無理に動かさず、手首にテーピングやサポーターをして安静に保つことが重要です。
変形性関節症への進行リスク
TFCC損傷を放置したまま手首に負荷をかけ続けると、関節内の軟骨や周辺組織に慢性的なストレスが加わり、手関節の変形性関節症(変形性手関節症)へと進行する可能性があります。
ただし、これは全ての患者さんに必ず起こるわけではなく、個人差や損傷の程度によって異なります。
また、保存療法を行っても症状が改善しない場合は、手術が必要なケースもあるので注意が必要です。
そのため初期の段階で治療を行い、症状が進行するリスクを減らすことが大切です。
TFCC損傷を放置すると保存治療が難しくなる可能性がある
TFCC損傷は、軽症であれば日常生活で安静にしておくことや、サポーターの装着といった保存療法で悪化するリスクを軽減することが可能です。
しかし、放置すると症状が慢性化し、難治性のTFCC損傷へと進行する可能性があります。
難治性のTFCC損傷となってしまった場合、保存療法のみでは改善が難しく、手術が必要となることもあります。
TFCC損傷は症状が悪化する前に、早期治療を行うことが重要です。
TFCC損傷の原因は外傷と加齢
TFCC損傷は主に「外傷」と「加齢」という2つの要因で発生します。
| 外傷 |
・転倒時に手をついた衝撃 ・自転車・交通事故での手首のひねりなど |
| 加齢 | 時間の経過とともにTFCC組織が徐々に摩耗 |
外傷性の原因としては、転倒時に手をついた衝撃や、自転車・交通事故での手首のひねりなどが挙げられます。
とくに手首を強く捻ったり、手のひらを地面に強く打ち付けたりする動作が損傷を引き起こすことも。
年齢を重ねると組織の弾力性が低下し、修復能力も衰えるため、日常的な使用でも損傷リスクが高まります。
また、野球やテニス、ゴルフなど手首に繰り返し負担がかかるスポーツをしている方は、慢性的な使用による微細な損傷が蓄積して症状が現れることもあります。
TFCC損傷の症状
TFCC損傷の症状は手首の小指側の痛みで、腫れや可動域の制限、不安定感などがみられます。
痛みはドアノブや重い物を持ち上げるなどの動作痛があり、腫れの原因は損傷により炎症が起こるためです。
このように日常生活における動作や、腫れなどによる痛みがありますが、悪化した場合は安静にしていても痛みや不安定感が出ます。
TFCC損傷の治療方法
TFCC損傷の治療法として以下のようなものがあります。
保存療法やリハビリテーションを行っても症状が改善しない場合は、損傷の種類や程度、患者さまの活動レベルなどを考慮して手術療法が検討されます。
保存療法
TFCC損傷の保存療法では、テーピングやサポーターの装着や、炎症を起こして腫れている場合などはアイシングを行います。
関節可動域訓練などもありますが、痛みや症状がさらに悪化する可能性があるため、医療機関の指導の下行うことが重要です。
まずは装具などで手首にかかる負担を軽減することを、保存療法では目的としています。
リハビリテーション
TFCC損傷のリハビリテーションでは、理学療法士が患者の状態に合わせてプログラムを作成し、手首の機能回復を目指します。
手首の安定性を高めるトレーニングや関節可動域を回復させる運動などもあり、スポーツへの復帰や職場への復帰、日常生活に支障が出ないようなサポートが中心です。
また、自宅でも続けられるリハビリなども指導するため、長期的な回復や再発防止にもつながります。
手術療法
保存療法やリハビリテーションを行っても、TFCC損傷が治らず悪化してしまった場合や、TFCC損傷が深刻な状態の場合、手術療法を行います。
手術療法には、TFCC縫合術、尺骨短縮術があり、必要となるケースは損傷が重度の靭帯損傷や完全断裂、慢性的な痛みが続いている場合です。
手術後では理学療法士の指導の下、手首の腫れの抑制や可動域を徐々に広げていくなどのリハビリテーションが行われます。
再生医療
TFCC損傷の治療法として再生医療という選択肢があります。
人間の体には、損傷したり弱ったりしている部分を修復する働きがある幹細胞というものがあります。
再生医療は、幹細胞を体から取り出し培養、損傷部分に注入するという治療法です。
手術療法では身体への負担や回復までに時間がかかることがありますが、再生医療では手術を行わずに治療することが可能です。
以下のページでは、TFCC損傷に対する再生医療の症例を公開しているため、併せて参考にしてください。
>TFCC損傷に対する再生医療の症例はこちら
【まとめ】TFCC損傷は放置せず早期治療を!まずは医療機関へ相談しよう
TFCC損傷を放置すると、痛みの慢性化や手首の不安定感の進行に加えて、変形性関節症へと進行するリスクがあります。
日常生活のドアノブを回す動作やスマホ操作でさえ症状が悪化することも。
軽症なら保存療法で改善できますが、放置すると難治性となり手術が必要になることもあるため、早期治療を行うことが大切です。
治療としては、保存療法や手術療法の他に再生医療という選択肢もあります。
再生医療には、主に幹細胞治療とPRP療法があり、どちらも患者さま自身の幹細胞・血液を用いるため、副作用のリスクが少ないのが特徴です。
手術や入院を必要としない再生医療について、詳しく知りたい方は当院「リペアセルクリニック」で紹介している症例をご確認ください。

監修者
坂本 貞範
Sadanori Sakamoto
医療法人美喜有会 理事長
「できなくなったことを、再びできるように。」
人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの
お手伝いができれば幸甚の至りでございます。
略歴
1997年3月関西医科大学 医学部卒
1997年4月医師免許取得
1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務
1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務
1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務
1999年2月国立大阪南病院 勤務
2000年3月野上病院 勤務
2003年3月大野記念病院 勤務
2005年5月さかもとクリニック 開設
2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任
2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設
2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設