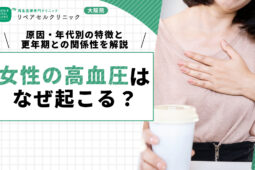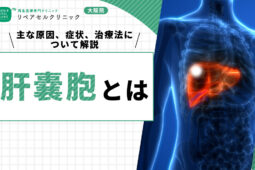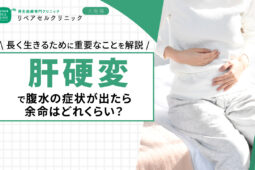- 肝疾患
肝血管腫とは|主な原因や症状は?治療が必要なケースと治療法について解説【医師監修】
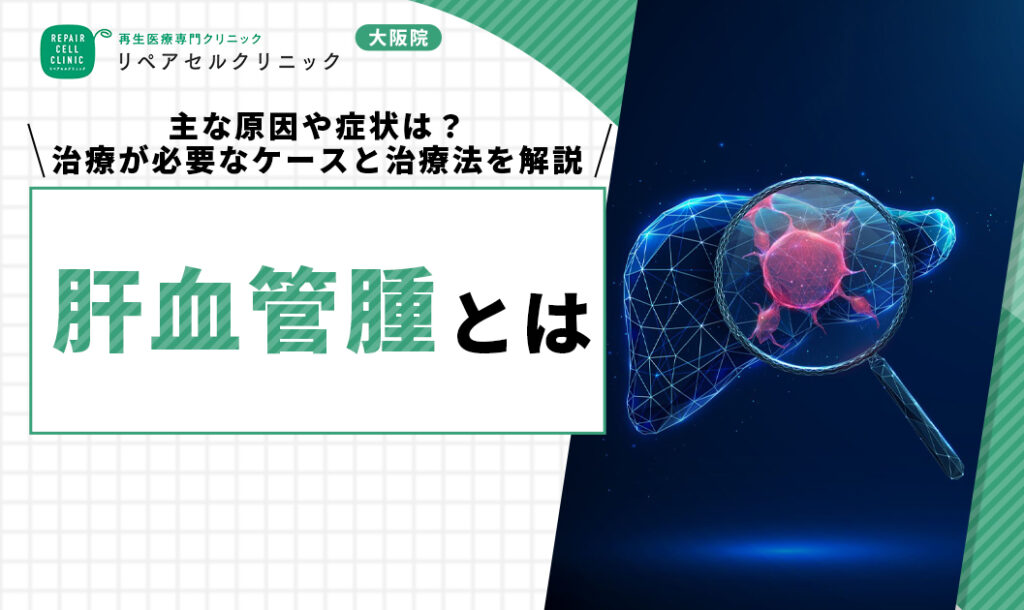
自覚症状がないにも関わらず、健康診断や人間ドックで「肝血管腫の疑いがある」と指摘され、突然のことに不安を感じていませんか。
肝血管腫は肝臓にできる良性の腫瘍であり、多くの場合は治療の必要がなく、そのまま経過観察となるケースがほとんどですので、過度に心配する必要はありません。
しかし、ごく稀に腫瘍が大きくなり、腹痛などの症状を引き起こしたり、治療が必要になったりすることもあります。
本記事では、肝血管腫ができる原因や主な症状、そして「どのような場合に治療が必要になるのか」について詳しく解説します。
病気の正体を正しく理解することが、漠然とした不安を解消するための第一歩となるため、ぜひ最後までご覧ください。
目次
肝血管腫とは|主な症状と原因
肝血管腫とは、肝臓内部の毛細血管が異常に増殖することでできる良性腫瘍のことです。
本章では、肝血管腫の主な症状や原因について解説します。
自覚症状がないのに、健康診断などで肝血管腫といわれて不安な方も多いでしょう。
主な症状や原因についてご覧いただき、少しでも不安を解消する材料にしてくださいね。
肝血管腫の症状
肝血管腫はほとんどの場合において無症状であり、自覚症状を感じることは滅多にありません。
そのため、健康診断や他の病気の検査で超音波(エコー)検査を受けた際に、偶然発見されるケースが大半を占めています。
しかし、腫瘍が大きくなった場合には、肝臓の表面が引き伸ばされたり、周囲の臓器を圧迫したりすることで、腹部の圧迫感や痛みが生じることがあります。
一般的には無症状ですが、4cmを超える大きさになると、腹部の圧迫感や痛みなどの症状が出やすくなります。
肝血管腫の原因
肝血管腫は、肝臓内の血管の異常増殖によってできることはわかっていますが、血管が異常増殖する根本的な原因はまだ完全には解明されていません。
現在の医学では、「先天性の血管奇形」や「女性ホルモン」が深く関わっているのではないかと考えられています。
一部の症例で妊娠中やピル使用中に腫瘍が増大する報告はありますが、明確な因果関係はありません。
先述のとおり肝血管腫は良性の腫瘍で、基本は無症状のため、定期的に検査を受けて大きさの変化を見守ることが現実的で効果的な向き合い方といえます。
肝血管腫ができやすい人は?
肝血管腫は30〜50代の女性に多く発見される傾向があります。
明確な発生原因は解明されていませんが、女性ホルモン(エストロゲン)が肝血管腫の発生に関与している可能性が示唆されています。
医学的に証明されていないものの、男女比を見てみると「1:1.2~6」と女性に多い※ことがわかっています。
※出典:日本医事新報社「肝良性腫瘍」
一方で、アルコールの過剰摂取や肥満といった生活習慣との直接的な関連は薄いとされています。
あくまで体質的な要因が強い可能性があるため、該当する年代の方やホルモンバランスが変化する時期の方は、定期検診でチェックすることが重要です。
肝血管腫の検査・診断方法
肝血管腫が無症状のうちは、血液検査でも異常が見られないため、基本的には以下の画像検査が行われます。
| 検査方法 | 詳細 |
|---|---|
| 腹部超音波検査(エコー検査) | ・超音波の出る機械を当て、跳ね返ってきた超音波を画像化する検査。 ・肝血管腫がある場合、白く円形の病変が映る。 |
| 腹部CT検査 | ・人体の断面を撮影後、コンピューターで再構成し、断面像・血管像を作成する検査。 ・造影剤を用いたCT検査では、肝血管腫の部分に造影剤が滞留して見える。 |
| MRI検査 | ・強力な磁場とラジオ波によって、体内の断層画像を撮影できる検査。 ・造影剤を用いたMRI検査は、確定診断において信憑性が高いとされている。 |
上記のような精密検査は、肝血管腫の有無の確認だけでなく、「良性・悪性の判断」のためにも行われます。
造影剤を用いる場合、アレルギーや服用中の薬などによっては検査できないこともあるため、医師の指示に従って検査を受けましょう。
肝血管腫の主な治療法
肝血管腫は良性腫瘍であるため、見つかったからといって必ずしもすぐに治療を始めなければならないわけではありません。
本章では、どのようなケースで治療が必要なのか、どのような治療法が選ばれるのかを解説します。
ご自身の状態がどの段階にあるのか、医師と相談する際の参考にしてください。
経過観察するケース
肝血管腫は良性腫瘍のため、無症状であるうちはほとんどのケースで経過観察が推奨※されています。
※出典:日本医学放射線学会「肝海綿状血管腫の画像診断ガイドライン」
がん化や日常生活での自然破裂のリスクは低いので、積極的に治療する必要はありません。
半年から1年に1回程度のペースで超音波検査(エコー)を受け、大きさや形に変化がないかを見守るだけで十分とされています。
肝血管腫と診断されたからといって、過度に不安になる必要はなく、医師の指示通りに通院していれば、普段と変わらない生活を送ることができます。
カテーテル手術が適応されるケース
カテーテル手術とは、カテーテルと呼ばれる細い管を挿入し、肝血管腫に流れる血流を止める「肝動脈塞栓術(TAE)」のことです。
主にカサバッハ・メリット症候群を合併した方や、肝血管腫が破裂した際の緊急応急処置として適応されます。
カテーテルを足の付け根から挿入するため、体への負担が少なく、入院期間も比較的短くて済むのが特徴です。
外科的手術と異なり、根治よりも痛みの緩和や破裂予防といった「症状のコントロール」を主目的として行われます。
外科的手術が適応されるケース
手術によって肝血管腫を切除する治療で、腹部を切開して行う「開腹手術」と数ミリの穴を複数開け、腹腔鏡というカメラや器具を用いて行う「腹腔鏡手術」があります。
腫瘍が10cmを超える大きさで満腹感や食欲不振がある場合や、破裂しそうな状態、合併症が出ている場合に適応されます。
手術によって腫瘍を肝臓ごと取り除くため、体への負担はありますが、破裂のリスクや症状を根本から解消できる点が大きなメリットです。
肝血管腫の位置や過去の腹部手術の有無によって、適した術式が異なるため、医師の話をよく聞いて判断しましょう。
肝血管腫に関するよくある質問
「肝血管腫」と診断された直後は、将来的な変化やリスクについてさまざまな不安がよぎるものです。
本章では、肝血管腫についてよくある疑問について回答します。
以下で、それぞれの疑問について解消していきましょう。
肝血管腫は自然になくなる?
一度できた肝血管腫が自然になくなる可能性もゼロではありません。
少数ながら、肝血管腫が縮小・消失するケースも報告されていますが、それを期待して放置するのは推奨されません。 実際に大部分(約8割)の症例で腫瘍の大きさに変化がない※ことが報告されています。
※出典:J-STAGE「肝血管腫の自然経過の追跡検討」
半年から1年に一度の定期検査を続け、大きさの変化を経過観察していくことが確実な管理方法です。
肝血管腫が癌になる可能性はある?
結論として、良性の肝血管腫が途中で悪性の「がん」に変化することはありません。
肝血管腫と肝がんは、細胞の成り立ちが全く異なる病気だからです。
後から「がんの疑いがある」といわれた場合は、血管腫が変化したのではなく、「画像検査で血管腫に見えていたものが、実は最初からがんだった(または区別がつきにくい)」というケースが考えられます。
だからこそ、最初の段階でCTやMRIなどの精密検査を行い、良性であることを確認しておくことが重要です。
肝血管腫は無症状でも経過観察が大切
本記事では、肝血管腫の原因や症状、治療方針について解説してきました。
肝血管腫は良性の腫瘍であり、ほとんどのケースで無症状のため、基本的には積極的に治療を受ける必要はなく、経過観察が重要となります。
また、悪性の腫瘍(がん)に変化するリスクなどもないので、医師の指示に従って定期的な経過観察を続けていれば、過度に恐れる必要はありません。
自己判断で通院を辞めてしまうことだけは避け、定期的に専門医に診てもらいながら、日々の生活を過ごしましょう。

監修者
渡久地 政尚
Masanao Toguchi
医師
略歴
1991年3月琉球大学 医学部 卒業
1991年4月医師免許取得
1992年沖縄協同病院 研修医
2000年癌研究会附属病院 消化器外科 勤務
2008年沖縄協同病院 内科 勤務
2012年老健施設 かりゆしの里 勤務
2013年6月医療法人美喜有会 ふたこクリニック 院長
2014年9月医療法人美喜有会 こまがわホームクリニック 院長
2017年8月医療法人美喜有会 訪問診療部 医局長
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 院長