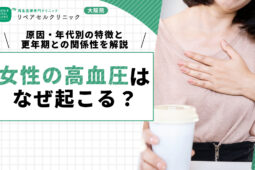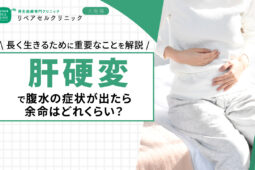- 肝疾患
- その他
肝嚢胞とは|主な原因、症状、治療法について解説【医師監修】
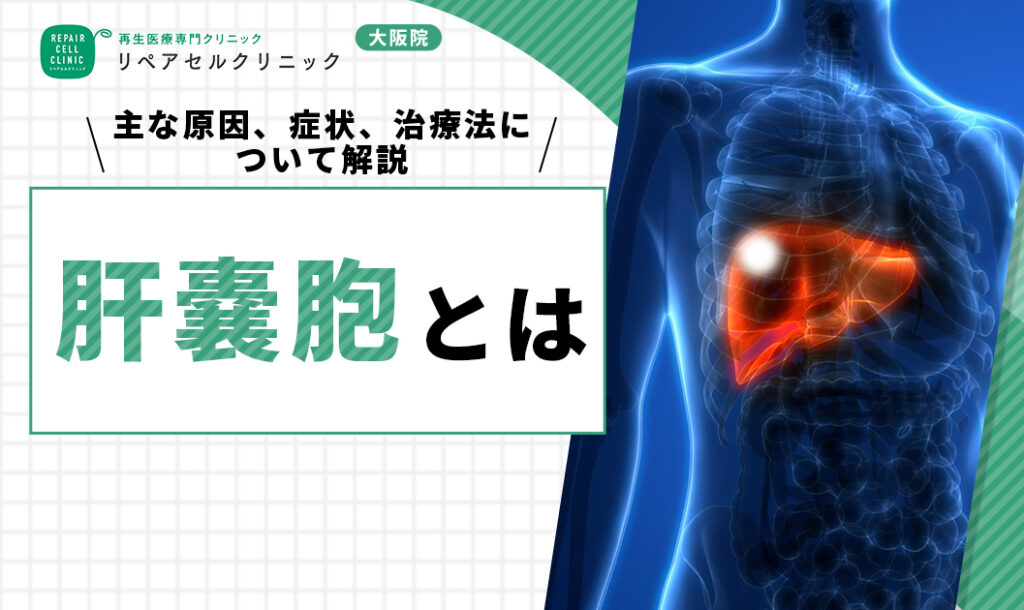
肝嚢胞とは、肝臓の中に液体が溜まった袋状のものができる状態で、多くは健康診断などで偶然発見されます。
放置しても問題ない場合がほとんどですが、大きくなると周囲の臓器を圧迫して症状が現れることがあります。
この記事では、肝嚢胞の症状や原因、治療法、放置した場合のリスクまで詳しく解説します。
肝嚢胞で悩まれている方は、ぜひ最後まで読んで適切な対処法を見つけましょう。
また、現在リペアセルクリニックでは手術せずに肝疾患・肝臓機能の改善が期待できる再生医療に関する情報をLINEで発信しております。
「肝疾患・肝機能に不安がある」「再生医療について詳しく知りたい」という方は、当院リペアセルクリニックへご相談ください。
目次
肝嚢胞とは
肝嚢胞(かんのうほう)とは、肝臓の内部に液体が溜まった袋状の病変のことで、その多くは良性のものです。
自覚症状はほぼなく、健康診断などで指摘されて発見されることが多いですが、直ちに治療が必要となるケースは稀ですので、過度に心配する必要はありません。
本章では、肝嚢胞について知っておくべき基本的な情報を、以下の3点に分けて解説します。
これらの正しい知識を身につけて、適切な検査と経過観察を行いましょう。
症状
肝嚢胞は、ほとんどの場合で無症状であり、日常生活の中で自覚症状が現れることはほとんどありません。
袋のサイズが小さいうちは体に影響を与えないため、自分では気づかず、検診や他の病気の検査中に偶然発見されるケースが大半を占めます。
しかし、嚢胞が巨大化(10cm以上)した場合、周囲の臓器を圧迫して以下のような症状が現れることがあります。
- お腹が張って重く感じる
- 右脇腹や右上腹部に鈍い痛みがある
- お腹が膨らんで見える
- 食欲が落ちる
- 吐き気がする
また、稀ですが、嚢胞内で出血や感染が起きたり破裂したりすると、急激な激痛や発熱を伴うことがあります。
上記のような症状が現れた場合は、医療機関で詳しい検査を受けましょう。
原因
肝嚢胞の原因は、特定の遺伝子の異常が関係していると考えられていますが、詳しい仕組みはまだ完全には解明されていません。
多くの場合が先天性で、生まれつき肝臓の中に小さな袋状のものがあり、年齢を重ねるにつれて徐々に大きくなることがあります。
また、肝臓の手術後や外傷後に、二次的に嚢胞ができることもあります。
肝嚢胞は年齢とともに有病率が高くなり、2022年に発表された大規模研究※では、50代では23.9%、60代では28.7%、70代以降は30%以上の方に肝嚢胞が見つかりました。
※出典:Nature
生活習慣の乱れが直接的な原因ではないため、食事制限などで予防できるものではないと理解しておきましょう。
検査方法
肝嚢胞の診断や状態確認には、腹部超音波検査(エコー)やCT、MRIといった画像検査が用いられます。
| 検査方法 | 内容 |
|---|---|
| 腹部超音波検査 | ・お腹の表面から超音波を当てて肝臓の状態を調べます。 ・痛みを伴わない基本的な検査です。 |
| CTスキャン | ・超音波検査より詳しく嚢胞の大きさや位置を確認できます。 ・複数の嚢胞がある場合にも有効です。 |
| MRI検査 | ・嚢胞の内容物を詳しく調べるときに使用します。 ・腫瘍との区別が必要な場合に行います。 |
| 穿刺吸引(せんしきゅういん) | ・細い針を刺して嚢胞の中の液体を採取し、性質を調べます。 ・悪性の可能性が疑われる場合に実施します。 |
なお、肝嚢胞があっても血液検査の数値(肝機能など)には異常が現れないことが多いため、肝臓疾患でよく行われる血液検査は適していません。
そのため、上記のような画像検査を中心に診断が進められます。
肝嚢胞の治療法
肝嚢胞と診断されても、その多くは良性で無症状であるため、直ちに治療を行う必要はありません。
基本的には定期的な検査で様子を見る「経過観察」となりますが、嚢胞の状態によっては以下の治療法が検討されることもあります。
- 経過観察
- 穿刺吸引硬化療法
- 開窓術(外科手術)
- 肝切除術
比較的小さな嚢胞の場合は、針を刺して嚢胞の中の液体を抜き取り、エタノールなどの硬化剤を注入して再発を防ぐ穿刺吸引硬化療法が行われます。
巨大化し、症状がある嚢胞に対しては、嚢胞の壁の一部を切り取る開窓術、悪性が疑われる場合や嚢胞が大きい場合は、嚢胞とともに肝臓の一部を切除する肝切除術を行います。
肝嚢胞があるとどうなる?放置するリスク
基本的には肝嚢胞を放置しても健康に影響しないケースが大半ですが、定期検診を受けずに完全に放置してしまうと、稀に起こる変化を見逃すリスクがあります。
以下のような変化を見逃さないためにも、定期的な検査を受け、完全放置ではなく「経過観察」することが大切です。
【肝嚢胞の病態の変化について】
- 嚢胞が急に大きくなる
- 嚢胞の中に出血が起こる
- 嚢胞に細菌が入って感染を起こす
- 嚢胞が破裂する
上記のようなケースになるのは稀ですが、起こると強い腹痛や発熱、吐き気などの症状が現れます。このような症状が出た場合は、すぐに医療機関を受診してください。
また、多発性嚢胞肝という病気の場合は、肝臓全体に多数の嚢胞ができて、肝臓が大きく腫れることがあります。
さらに、腎臓にも嚢胞ができる多発性嚢胞腎を合併していることがあり、腎臓の機能低下につながる場合もあるため、定期的な検査が重要です。
肝嚢胞ができたときの注意点
肝嚢胞ができたときの注意点について、以下の2つを解説します。
これらのポイントを押さえて、安心して生活を送りましょう。
定期的に検査を受ける
肝嚢胞が発覚した場合、無症状でも定期的な検査で経過観察することが大切です。
多くは大きさが変わらずに経過しますが、一部のケースでは数年かけて徐々に大きくなることがあります
そのため、年に1回程度の腹部超音波検査やCT検査で、嚢胞の大きさや状態に変化が起きていないかチェックしましょう。
とくに複数の嚢胞がある方や、家族に多発性嚢胞肝の方がいる場合は、より注意深い観察が必要です。
他の肝臓疾患が見つかることもあるため、健康診断は欠かさず受けてください。
医療機関を受診する
以下のような症状が現れた場合は、すぐに医療機関を受診してください。
- 急に右脇腹や右上腹部が痛くなった
- お腹が急に張って苦しくなった
- 発熱がある
- 吐き気や嘔吐が続く
- お腹を触ると硬いしこりを感じる
これらの症状は、嚢胞の出血や感染、破裂などのサインかもしれません。
放置すると重症化する可能性があるため、早めの受診が重要です。
肝嚢胞ができた方からよくある質問
肝嚢胞に関してよくある質問にお答えします。
医師との相談や経過観察の参考に役立てましょう。
肝嚢胞は自然に消える?
基本的に、一度形成された肝嚢胞が自然になくなることはほとんどありません。
多くの場合は大きさが変わらないか、長い年月をかけてわずかに大きくなる傾向があります。
ただし、31mmを超える肝嚢胞の観察結果では、まれに小さくなったり、成長が止まったりするというデータ※もあります。
※出典:Nature
自然に消えることを期待するのではなく、定期的な検査で経過を見守ることが大切です。
肝嚢胞は何センチで手術が必要?
肝嚢胞の手術が必要になるのは、一般的に10cm以上の大きさで症状がある場合です。
ただし、大きさだけで判断するのではなく、以下の要素も複合的に見て判断されます。
- 腹痛やお腹の張りなどの症状があるかどうか
- 嚢胞の位置や数
- 日常生活への影響の程度
- 患者さんの年齢や全身状態
10cm以下でも、症状が強い場合や急速に大きくなっている場合は、手術を検討することがあります。
逆に、10cm以上でも無症状であれば、経過観察を続けることもあるため、まずは医療機関の指示に従いましょう。
肝疾患・肝臓の機能改善には再生医療をご検討ください
肝嚢胞は多くの場合、無症状で治療が必要ないことがほとんどです。
しかし、定期的な検査で経過を確認し、症状が現れた場合は適切な治療を受けることが大切です。
また、肝疾患・肝臓の機能が気になる方には、再生医療という選択肢があります。
再生医療は肝嚢胞の直接的な治療法ではありませんが、脂肪肝や肝硬変などの肝疾患に対して損傷した肝臓の修復や機能改善を目指す治療法です。
以下のページでは、当院の再生医療によって肝疾患が改善した症例を紹介しているため、併せてご覧ください。
>再生医療によって肝疾患が改善した症例はこちら
「肝疾患・肝機能に不安がある」「再生医療について詳しく知りたい」という方は、当院リペアセルクリニックへご相談ください。

監修者
渡久地 政尚
Masanao Toguchi
医師
略歴
1991年3月琉球大学 医学部 卒業
1991年4月医師免許取得
1992年沖縄協同病院 研修医
2000年癌研究会附属病院 消化器外科 勤務
2008年沖縄協同病院 内科 勤務
2012年老健施設 かりゆしの里 勤務
2013年6月医療法人美喜有会 ふたこクリニック 院長
2014年9月医療法人美喜有会 こまがわホームクリニック 院長
2017年8月医療法人美喜有会 訪問診療部 医局長
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 院長