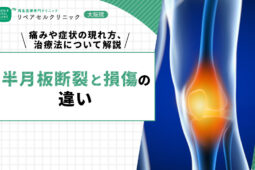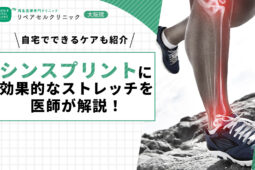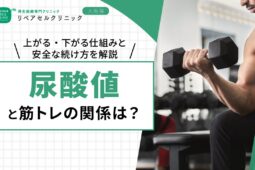- ひざ関節
- スポーツ医療
ランナー膝の治し方は?やってはいけないことや膝の外側の痛みのチェック方法も解説

「朝のランニングで、膝の外側にズキッとした痛みが走る」
「走り始めは大丈夫なのに、距離を重ねると膝の外側が痛くなってくる」
このような症状でお悩みの場合、その痛みはランナー膝の可能性があります。
ランナー膝はランナーの多くが経験するスポーツ障害で、放置すると慢性化し、最悪の場合は大会への参加を諦めざるを得なくなることもあります。
本記事では、ご自身でできるランナー膝のセルフチェック方法をはじめとして、症状の原因や治療法を詳しく解説します。
ご自身の状態を正しく理解し、つらい痛みから解放されるための第一歩として、ぜひお役立てください。
また、現在リペアセルクリニックでは、スポーツ障害の根本的な改善が期待できる「再生医療」に関する情報をLINEにて配信中です。
\慢性的な膝の痛みの改善を目指せる再生医療とは/
【こんな方は再生医療をご検討ください】
- 慢性化した痛みで、ランニングへの復帰を諦めている
- 従来の治療方法では、十分な効果が得られていない
- 手術はできるだけ避けたいと考えている
慢性化した痛みへ、従来の治療方法とは異なる選択肢に興味がある方は、以下からご登録ください。
目次
その膝の痛みはランナー膝かも?3つのセルフチェック方法
ランニング中の膝の外側に痛みを感じる場合、いくつかの特徴的な症状を確認することで、ご自身でランナー膝(腸脛靭帯炎)の可能性をある程度判断が可能です。
以下のポイントに一つでも当てはまるものがあれば、ランナー膝の可能性があります。
ご自身の症状と照らし合わせながら、一つずつ確認していきましょう。
膝の外側(骨の出っ張り周辺)を押すと痛い
膝の外側にある骨の出っ張りを指で押したときに、はっきりとした痛みを感じる場合、ランナー膝の典型的なサインと考えられます。
この場所は、専門的には大腿骨外側上顆(だいたいこつがいそくじょうか)と呼ばれ、腸脛靭帯(ちょうけいじんたい)が付着する部分です。
ランニング動作によって、この部分で腸脛靭帯の圧迫や摩擦が繰り返されることで、炎症が起きて痛みが生じます。
膝のお皿のやや外側にある、骨が出っ張っている部分を指で優しく押してみて、痛みを感じるかどうかを確認してみてください。
膝を30度ほど曲げた状態で痛みが出る
膝を軽く曲げ伸ばしした際、特定の角度(約30度)で痛みが誘発されるのも、ランナー膝にみられる特徴の一つです。
この角度は、腸脛靭帯が大腿骨外側上顆の上を通過するタイミングにあたり、靭帯の緊張が最も高まることで痛みが出やすくなります。
特に「階段を下りる」「坂道を下る」といった動作で、この痛みを感じやすいかもしれません。ご自宅で簡単に確認できる「グラスピングテスト」という方法もあります。
- 仰向けに寝て、痛い方の脚をまっすぐ伸ばす
- 膝の外側にある、押すと痛みを感じる部分を指でしっかりと押さえる
- その部分を押さえたまま、かかとを床から離さずにゆっくりと膝を90度まで曲げていく
- このとき、膝が30度ほど曲がったあたりで痛みが出たり、強くなったりすればランナー膝の可能性
これらのテストで痛みが誘発される場合、症状を悪化させないよう注意深く対処を進めると良いでしょう。
安静時は痛くないが、走り出すと痛みが再発する
安静にしていると痛みが和らぐのに、走り始めると再び痛み出すという症状の出方も、ランナー膝を判断するうえでの重要なポイントです。
この症状は、進行度によって現れ方が少しずつ変化します。
| 症状 | 状態 |
| 初期症状 | ランニングの開始直後は痛むものの、身体が温まってくると痛みが軽くなる、あるいは消える。しかし、走り終わって身体が冷えると再び痛み出す。 |
| 進行した症状 | ランニング中、常に痛みが続くようになる。さらに悪化すると、歩行や階段の上り下りといった日常生活の動作でも痛みを感じるようになる。 |
初期症状の段階で「温まれば大丈夫」と走り続けてしまうと、症状が進行し、回復が長引く原因にもなりかねません。
早めに気づいて対処することが、早期復帰への近道です。
ランナー膝でやってはいけないこと
ランナー膝を一日でも早く治すためには、回復を妨げる可能性のある行動を避けることが欠かせません。
良かれと思って続けている習慣が、実は症状を悪化させているケースも少なくないのです。
特に上記の3つの行動は回復を遅らせる代表的な例と考えられますが、なぜこれらの行動を避けるべきなのか、その理由を一つずつ解説していきます。
痛みを我慢して走り続ける
痛みを我慢して走り続けることは症状を悪化させ、回復を長引せる最も避けるべき行動です。
「これくらいの痛みなら大丈夫」という判断が、結果的にランニングから遠ざかることになりかねません。
痛みを無視して走り続けることには、以下のような複数のリスクが伴います。
- 症状の慢性化: 炎症を起こしている部分に繰り返し負担がかかり、痛みが長引き、治りにくい状態になる
- フォームの崩壊: 痛い脚を無意識にかばうことで、本来の効率的なランニングフォームが崩れてしまう
- 二次障害の誘発: 崩れたフォームのまま走り続けることで、反対側の脚や腰、股関節など、別の部位に新たな痛みや怪我を引き起こす
走りたいという気持ちを抑え、休む選択をすることが最終的に早期復帰への一番の近道となるでしょう。
痛い部分をフォームローラーなどで強く圧迫する
痛んでいる膝の外側をフォームローラーなどで直接強く圧迫することは、かえって回復を妨げる可能性があります。
セルフケアを行う際は、圧迫する「場所」と「強さ」を意識することが、回復を後押しします。
近年の研究では、ランナー膝の痛みは、靭帯と骨の間にある組織が圧迫されて炎症を起こす「圧迫説」も有力です。
そのため、ケアの対象とアプローチ方法を次のように整理すると良いでしょう。
| ケアする部位 | アプローチのポイント |
| 膝の外側(痛む場所) | 炎症を起こしている可能性があるため、直接の強い圧迫は避ける。アイシング(冷却)が中心。 |
| 周辺の筋肉(臀部・太もも) | 痛みの根本原因となっている筋肉の緊張をほぐすことが目的。こちらを優しくマッサージする。 |
このように、痛む場所そのものではなく、その原因となっているお尻や太ももの筋肉を優しくほぐすことを意識してみてください。
完全に動かない「絶対安静」
痛みが強い時期の安静はもちろん必要ですが、長期間にわたって全く動かない「絶対安静」はかえって筋力低下を招き、スムーズな復帰を妨げる要因になり得ます。
回復を促すには、痛みのない範囲で動くことも大切です。
「絶対安静」と、推奨される「相対的安静」には、以下のような違いがあります。
| 絶対安静 | 相対的安静 | |
| 主な目的 | 痛みの即時的な鎮静 | 筋力や機能を維持しながら回復を促す |
| 身体への影響 | 筋力低下や関節の硬化を招きやすい | 血行が促進され、回復を早める効果が期待できる |
| デメリット | 回復後の再発リスクが高まる | 痛みを悪化させない注意深い運動選択が求められる |
| 具体例 | 全く運動しない | ウォーキング、水泳、痛みのない範囲でのストレッチ |
痛みの様子を見ながら、膝への負担が少ない運動から少しずつ取り入れていくと良いでしょう。
ランナー膝の治し方|自宅でできる4つのステップ
ランナー膝の回復には、痛みの段階に応じたアプローチを順序立てて行うことが効果的です。
| ステップ | 時期 | 主な目的 |
| ステップ1 | 急性期(痛み始め) | 炎症を鎮め、痛みを最小限に抑える |
| ステップ2 | 回復期(痛みが軽減) | 痛みの根本原因となっている筋肉をほぐす |
| ステップ3 | 強化期(痛みが消失) | 再発しないための筋力をつけ、身体を根本から改善する |
| ステップ4 | 復帰期(トレーニング再開) | 焦らず安全にランニングへ戻る |
それぞれの段階で何をすべきか、具体的に解説していきます。
まずは炎症を抑える
痛みが出始めた急性期は、なによりもまず炎症を鎮めることに専念します。
この段階では、スポーツ障害の応急処置の基本である「RICE処置」が有効です。
| 処置 | 内容 |
| Rest (安静) | 痛みを感じるランニングやジャンプなどの運動を中止する。 |
| Ice (冷却) | 氷のうなどを使い、痛む部分を15〜20分ほど冷やす。1日に数回繰り返す。 |
| Compression (圧迫) | 弾性包帯やサポーターで軽く圧迫し、腫れを抑える。 |
| Elevation (挙上) | 患部を心臓より高い位置に保ち、腫れを軽減させる。 |
特にアイシングは自宅で簡単にできる効果的な処置ですが、冷やしすぎると凍傷のリスクもあるため、1回の冷却は20分以内を目安にしましょう。
痛みが軽減してきたら無理のない範囲でマッサージをする
痛みのピークが過ぎてきたら、ランナー膝の根本原因となっている筋肉の緊張をほぐすようにしましょう。
ただし、痛む膝の外側を直接強くマッサージするのは避けてください。
お尻や太ももの外側の筋肉が硬くなることで、腸脛靭帯が引っ張られて痛みが生じるため、これらの部位をほぐすのもおすすめです。
テニスボールやフォームローラーを使い、お尻の横や太ももの外側を優しくほぐしてみてください。
あくまで「気持ち良い」と感じる程度の強さで行うことが、回復を促すポイントです。
痛みがほぼなくなったら段階的にトレーニングを再開する
痛みが日常生活で気にならなくなったら、再発予防の鍵となる筋力トレーニングを開始します。
ランナー膝は、膝そのものではなく、股関節周りの筋力不足が原因であることが非常に多いのです。
特に、お尻の横にある「中殿筋」を鍛えることが、ランニング中の膝のブレを安定させ、腸脛靭帯への負担を軽減します。
- クラムシェル:横向きに寝て膝を曲げ、かかとをつけたまま上の膝を開閉する運動
- サイドレッグレイズ:横向きに寝て、上の脚をまっすぐ伸ばしたままゆっくりと上げ下げする運動
- ヒップブリッジ: 仰向けで膝を立て、お尻を持ち上げて身体を一直線に保つ運動
これらのトレーニングを無理のない範囲で継続することが、より強く、怪我をしにくい身体作りにつながります。
少しずつ走行距離を増やす
トレーニングを続けても痛みが出なくなったら、いよいよランニングを再開しますが、ここで焦りは禁物です。
身体がランニングの負荷に再び慣れるまで、段階的に距離を伸ばしていく必要があります。
安全な復帰プログラムとして、以下の手順を参考にすると良いでしょう。
- まずは15〜20分程度のウォーキングから始め、痛みが出ないことを確認する
- 「ウォーク&ラン」で少しずつ走りを取り入れる(例:ウォーク4分+ラン1分を5セット)
- 徐々にランニングの時間を増やし、ウォーキングの時間を減らしていく
- 痛みなく連続で走れるようになったら、走行距離を少しずつ伸ばす
走行距離を増やす際は、前週の総走行距離の10%以内にとどめる「10%ルール」を意識することが、再発を防ぐための安全な目安となります。
ランナー膝の完治までにかかる期間は?何日で治る?
ランナー膝が完治するまでの期間は、症状の重症度や対処法の適切さによって大きく変わります。
まずはご自身の症状と照らし合わせながら、どのくらいの期間が必要か、そしてどのような場合に専門医を頼るべきかを確認していきましょう。
軽症なら数週間〜1ヶ月・重症化すると数ヶ月かかる場合も
ランナー膝の回復期間は一概には言えませんが、症状のレベルに応じておおよその目安を立てることが可能です。
| 症状のレベル | 症状の特徴 | 回復期間の目安 |
| 軽症 | ウォーミングアップ中に痛みがあるが、走っていると痛みが消える。走り終わると再び痛む。 | 2週間〜1ヶ月程度 |
| 中等症 | ランニング中、常に痛みを感じる。日常生活では大きな支障はない。 | 1ヶ月〜3ヶ月程度 |
| 重症 | 歩行や階段の上り下りなど、日常生活の動作でも痛みを感じる。 | 3ヶ月以上かかる場合も |
適切なセルフケアを早期に開始することで、回復期間を短縮する効果も期待できます。
一方でこの期間はあくまで一般的な目安のため、無理をしてトレーニングを再開すると、症状がぶり返してさらに長い期間を要することになりかねません。
焦らず、身体の状態と向き合う姿勢が回復への鍵となります。
治らない・長引く場合は専門医へ相談する
セルフケアを続けてもなかなか改善しない場合や、痛みが悪化している場合は他の疾患が隠れている可能性も考えられます。
以下のような状況に当てはまる場合は、一度整形外科を受診することをおすすめします。
- 2週間以上セルフケアを続けても、痛みが全く改善しない
- 日に日に痛みが強くなっている
- 安静にしていても膝がズキズキと痛む
- 膝の曲げ伸ばしが明らかに困難になっている
- 膝が腫れていたり、熱を持っていたりする
当院(リペアセルクリニック)でも、膝の症状でお困りの方を対象に最先端の医療技術である再生医療を提供しています。
電話でのご相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
膝の痛みは⼿術しなくても治療できる時代です。
ランナー膝になってしまう原因
ランナー膝の痛みは、単に「走りすぎ」という理由だけで起こるわけではありません。
走りすぎ(オーバーユース)を前提としつつも、身体の使い方やトレーニング内容、そしてランニング環境といった複数の要因が複雑に絡み合っています。
一般的にランナー膝を引き起こす主な原因は、以下のように3つのカテゴリーに分けて整理されます。
| カテゴリー | 具体的な原因の例 |
| 身体的な要因 | 股関節周りの筋力不足、臀部や太ももの筋肉の柔軟性低下、O脚などの骨格的な特徴 |
| トレーニング内容 | 急激な走行距離やスピードの増加、坂道や不整地でのトレーニングの多用 |
| 環境的な要因 | 硬いアスファルトでのランニング、クッション性が失われた古いシューズの使用、傾いた路面の走行 |
これらの要因が一つ、あるいは複数重なることで膝の外側にある腸脛靭帯への負担が増大し、痛みとなって現れます。
ご自身のランニング習慣や身体の状態を振り返り、当てはまる点がないか確認してみてください。
セルフケアでランナー膝が改善しない場合の治療方法
セルフケアを続けても痛みが改善しない、あるいは悪化する場合には、医療機関の受診を検討してください。
それぞれの治療法がどのようなものか、具体的に見ていきましょう。
整形外科で行う一般的な保存療法
整形外科におけるランナー膝の治療は、手術を伴わない「保存療法」が中心となります。
これは、身体に備わっている治癒能力を最大限に引き出すことを目的としたアプローチです。
保存療法には、様々な選択肢があります。
- 理学療法: 理学療法士の指導のもと、原因となっている筋肉の柔軟性を高めるストレッチや、股関節周りを中心とした筋力強化トレーニングを行う。
- 物理療法: 超音波や低周波といった物理的な刺激を利用して、痛みの緩和や血行促進を図る。
- 薬物療法: 炎症を抑えるための消炎鎮痛剤(内服薬)や湿布薬が処方される。
- 注射療法: 痛みが非常に強い場合に、炎症を強力に抑えるステロイド注射を行うことがある。ただし、腱への影響を考慮し、繰り返し行うことは慎重に判断される。
これらの治療を組み合わせて痛みの根本原因にアプローチしていくことで、症状の改善を目指します。
難治性の場合に検討される外科的治療
非常に稀なケースですが、長期間にわたって保存療法を続けても全く効果が見られない場合には、外科的治療が検討されることもあります。
ただしこれは、あくまで最終的な手段と位置づけられています。
一般的には、少なくとも6ヶ月以上の保存療法を行っても日常生活に大きな支障をきたすほどの痛みが続く場合に、医師と相談の上で判断されることになるでしょう。
手術では、緊張が強くなっている腸脛靭帯の一部を切離し、骨との圧迫を軽減させる処置が行われます。
しかし、ほとんどのランナー膝は保存療法で改善が見込めるため、まずは根気強くリハビリに取り組むことが大切です。
新たな選択肢である「再生医療」
従来の治療法で改善が見られなかったり、手術を避けたいと考えたりする方にとって、 ご自身の細胞の力を活用して損傷した組織の根本的な修復を目指す「再生医療」が、新たな希望となる可能性があります。
痛み止めやステロイド注射は症状を一時的に和らげる対症療法であり、痛みの根本原因が解決されない限り、症状を繰り返してしまうケースは少なくありません。
当院で提供している再生医療は、そのような慢性的なランナー膝に対して、患者さまご自身の脂肪から採取した「幹細胞」を患部に注射することで、腸脛靭帯自体の治癒能力を高める根本的なアプローチです。
| 従来の保存療法 | 幹細胞治療 | |
| アプローチ | 薬の力で「一時的に」炎症を抑える。 | 自身の細胞の力で組織修復を促し、「根本から」炎症を鎮める。 |
| 身体への影響 | 腱を脆くするなどの副作用リスクがあり、使用回数に制限がある。 | 自身の細胞を用いるため、アレルギーや副作用のリスクが極めて低い。 |
| 期待できる効果 | 短期的な痛みの緩和。慢性化した場合、効果が限定的になることも。 | 長期的な痛みの改善と、諦めていたスポーツへの復帰。 |
これまで完治が難しいとされてきた慢性的な靭帯の炎症に対しても、再生医療は靭帯自体に悪影響を与えることなく、痛みの軽減と組織の再生を促すことが可能です。
活動的な毎日を取り戻すための選択肢として、ぜひご検討ください。
ランナー膝でお悩みなら、ぜひ当院へご相談ください
リペアセルクリニックでは、膝の症状への新たな選択肢として再生医療を提供しています。
手術をせずに根本的な改善を目指したい方、従来の治療で満足のいく効果が得られなかった方は、ぜひ一度お問い合わせください。
膝の痛みは⼿術しなくても治療できる時代です。
ランナー膝の再発予防|見直すべき3つのポイント
痛みがなくなり、無事にランニングを再開できたとしても、根本的な原因が解決されていなければランナー膝は再発を繰り返してしまいます。
二度と辛い痛みに悩まされないためには、以下のポイントが大切です。
以下で詳しく解説していきます。
テーピングの活用で走行時の負担を軽減する
ランニングを再開する初期段階や、長距離を走る際には、テーピングを活用することで膝への負担や再発の不安を軽減する効果が期待できます。
テーピングは腸脛靭帯の動きをサポートし、膝関節の安定性を高める役割を果たします。
ここでは、ご自身で簡単にできる基本的な貼り方の一例を紹介します。
- テープの準備: 幅5cm程度の伸縮性テープを、膝を伸ばした状態で太ももの付け根の外側から膝下の外側までの長さに合わせてカットします。テープの角は丸く切っておくと、剥がれにくくなります
- 貼る姿勢: 膝を約90度に曲げた姿勢をとります
- 貼り始め: 太ももの付け根の外側からテープを貼り始めます
- メイン部分: 腸脛靭帯に沿って、膝の外側を通り、膝下の外側(脛骨)に向かって、テープを少し引っ張りながら貼っていきます
- 貼り終わり: 最後の数cmは引っ張らずに、優しく肌にのせるように貼ります
正しく貼ることで、走行中の膝のスムーズな動きを助けてくれるでしょう。
ただし、皮膚がかぶれやすい方は、長時間の使用を避けるなどの注意が必要です。
ランニングフォームを改善する
ランナー膝の根本原因として、膝に負担をかけるランニングフォームが挙げられます。
特に、着地時に膝が内側に入ってしまう「ニーイン」や、着地のたびに骨盤が左右に大きく揺れる動きは、腸脛靭帯に過剰なストレスを与えます。
これらのフォームを改善するためには、以下のポイントを意識すると良いでしょう。
| 改善ポイント | 具体的なアクション | 期待できる効果 |
| ピッチを上げる | 1分あたりの歩数を少しだけ増やしてみる。(例:170歩/分 → 180歩/分) | 上下動が少なくなり、着地衝撃が緩和される。 |
| 着地点を意識する | 足を身体の真下(重心の近く)に着地させるように意識する。 | 膝へのブレーキが減り、スムーズな重心移動が可能になる。 |
| 体幹を安定させる | お腹に軽く力を入れ、骨盤が左右にブレないように走る。 | 股関節や膝の動きが安定し、エネルギー効率も向上する。 |
最初は意識するのが難しいかもしれませんが、短い距離から少しずつ試してみてください。
スマートフォンで自分のフォームを撮影し、客観的に確認することも有効な方法です。
シューズや練習環境を見直す
自分では気づきにくいシューズの劣化や、いつも走っているコースの特性も、ランナー膝の引き金になることがあります。
定期的に練習環境を見直すことで、未然に再発を防ぐことが可能です。
以下のチェックリストを参考に、ご自身の環境を確認してみましょう。
-
シューズの寿命は大丈夫?
□ ランニングシューズの総走行距離は500kmを超えていませんか?
□ 靴底のかかと部分が、内外どちらかだけ極端にすり減っていませんか?
□ シューズを履いたときに、以前のようなクッション性を感じられますか?
-
練習コースに偏りはない?
□ いつも同じ方向に傾いた路肩ばかりを走っていませんか?(たまに走る側を変える)
□ 陸上トラックで練習する場合、いつも同じ左回りばかりではありませんか?(たまに右回りも行う)
□ 下り坂が続くコースを、スピードを出しすぎて走っていませんか?
これらの小さな心がけが、長期的に見てあなたの膝を守ることにつながります。
慢性的なランナー膝の改善に再生医療もご検討ください
ランナー膝のセルフチェックを正しく行うことで、早期発見・早期治療が可能となり、慢性化や重症化を防ぐことができます。
一方で、「温まれば痛みが消えるから」と自己判断で放置することは、結果的に治療期間を長引かせることになりかねません。
セルフチェックで一つでも該当項目があった方は、早めの対処を心がけてください。
また、保存療法で改善しない慢性的な痛みに対しては、手術だけでなく、ご自身の細胞の力を活用して組織の修復を目指す「再生医療」という新たな選択肢もあります。
長引く膝の痛みでお悩みでしたら、自己判断で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。
膝の痛みは⼿術しなくても治療できる時代です。

監修者
坂本 貞範
Sadanori Sakamoto
医療法人美喜有会 理事長
「できなくなったことを、再びできるように。」
人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの
お手伝いができれば幸甚の至りでございます。
略歴
1997年3月関西医科大学 医学部卒
1997年4月医師免許取得
1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務
1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務
1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務
1999年2月国立大阪南病院 勤務
2000年3月野上病院 勤務
2003年3月大野記念病院 勤務
2005年5月さかもとクリニック 開設
2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任
2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設
2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設