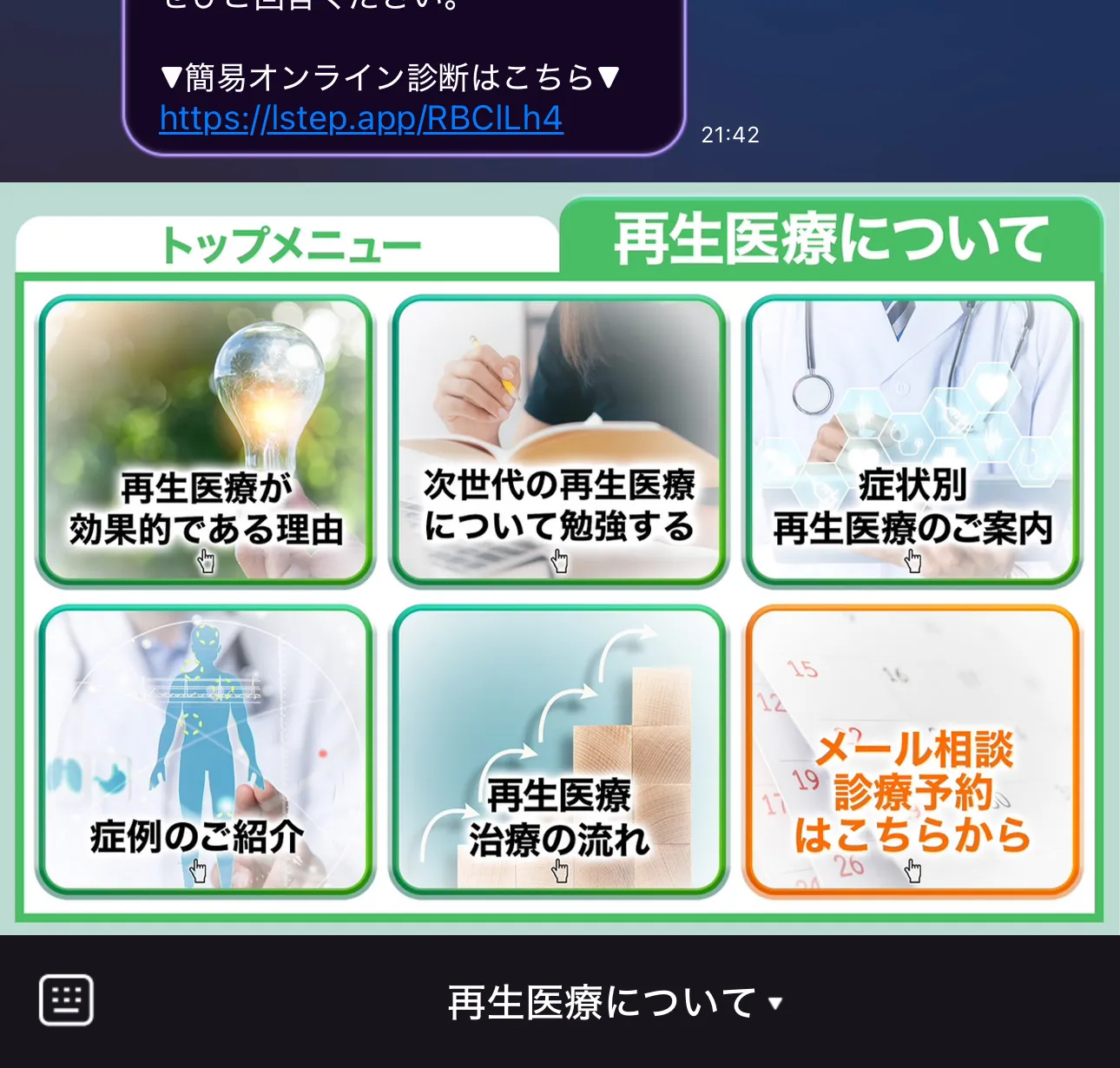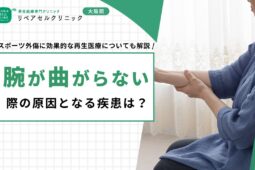肘頭滑液包炎におすすめのサポーターを紹介!痛みの軽減に役立つ活用方法も解説
公開日: 2019.10.04更新日: 2025.06.30
肘の痛みや腫れで病院を受診し、「肘頭滑液包炎」と診断されたものの軽症のためサポータの活用などの安静指示のみで終わるケースは少なくありません。
しかし、日常生活や仕事では肘を動かさないのは難しく、自分に適したサポーターを選びたいと考えている方も多くいらっしゃるかと思います。
そこで本記事では、自分の症状や生活環境に合ったサポーターの選び方や、正しい使い方を詳しく紹介していきます。
サポーターは単なる補助具ではなく、症状を悪化させずに「普段通りの生活」を取り戻すための大切なツールです。
ぜひこの記事を参考に、自分に合った対処法を見つけてください。
また当院リペアセルクリニックの公式LINEでは、肘頭滑液包炎の症状に不安を持つ方に向けて、再生医療の症例や治療内容を紹介しています。
手術を回避し、より早く日常生活へ復帰したい方はぜひご確認ください。
目次
肘頭滑液包炎におすすめのサポーターの選び方
肘頭滑液包炎に適したサポーターを選ぶ際は、「固定力」と「快適性」のバランスを重視することが重要です。
症状の悪化を防ぎ、回復を促すためには、自身の状態や生活環境に合ったサポーターを選定する必要があります。
下記ではサポーターのおすすめの選び方を解説していくので、ぜひ参考にしてみてください。
固定力と可動域のバランスを重視する
肘頭滑液包炎に対応したサポーターを選ぶ際には、患部を安定させる固定力が重要です。
過度な固定は日常生活に支障をきたし、逆に固定力が弱すぎると炎症が悪化する恐れがあります。
肘頭滑液包炎は、肘を過度に使うことで滑液包(関節の滑らかな動きを助ける液体が入った袋)が炎症を起こす疾患です。
そのため、安静が最優先の対処法とされており、以下を参考にサポーターによって動きを制限することが症状の進行を抑えるカギとなります。
- 高い固定力を持つサポーターがおすすめの人
↳腫れが強く、動かすだけで痛みが出る人
↳炎症が慢性化しやすく、再発を繰り返している人 - 可動性が高いサポーターがおすすめの人
↳軽度の炎症で、日常生活や仕事を続けたい人
↳家事やデスクワークなど、ある程度肘を使う必要がある人
上記のように、症状の段階や日常生活での使い方に応じて、サポーターの「固定力と可動域」を適切に見極めることが、肘頭滑液包炎の悪化防止と回復促進のために欠かせないポイントです。
素材・通気性・装着感などを比較する
肘頭滑液包炎に使用するサポーターは、固定力だけでなく、「素材・通気性・装着感」といった使用時の快適さも重要です。
これらの要素が不足していると、かえって皮膚トラブルや長時間装着による不快感を引き起こし、継続使用が困難になる場合があります。
チェックしたい素材・通気性・装着感のポイントは以下の通りです。
| 項目 | 特徴・ポイント |
|---|---|
| ネオプレン素材 | 高い固定力・保温性あり。蒸れやすく夏は不向き |
| ナイロン+ポリウレタン素材 | 伸縮性と通気性に優れ、快適なフィット感 |
| 綿混素材 | 肌にやさしく吸湿性も高いが、固定力は弱め |
| 通気性 | 蒸れを防ぎ、長時間の装着でも快適。特に夏場に重要 |
| スリーブタイプ | 肘全体を包み、軽度の症状に適した装着感 |
| ベルト・バンドタイプ | 一点集中の圧迫が可能。部分的なサポートに有効 |
| その他の工夫 | 滑り止めや肌にやさしい縫製で快適性アップ |
快適に使えるサポーターを選ぶことは、肘頭滑液包炎の継続的な対処と症状の回復に大きく影響します。
素材や通気性、装着感にも注目し、自分に合った製品を選びましょう。
肘頭滑液包炎の治療中は肘を動かさないようにすることが重要
肘頭滑液包炎は、肘関節の滑液包にたくさんの滑液がたまり、炎症を起こしている状態です。
滑液の過剰分泌の原因の1つは、肘への刺激です。
そのため、治療中は肘を動かさないようにすることが重要です。
滑液包は関節の中の緩衝材とも呼べる組織で、関節を動かすことによって刺激を受けます。
滑液を注射で抜き取るという治療を行った後も、動かしてしまうと肘頭滑液包炎を再発させてしまいます。
再発を予防するためにも、治療の後は患部を安静にするようにしましょう。
肘頭滑液包炎に効果的なサポーター・テーピングの活用方法
肘関節のサポートをするサポーターやテーピングは、肘の曲げ伸ばしの負担を軽減してくれます。
以下では、具体的なテーピング方法とサポーターの活用方法をご紹介します。
【サポーターの活用方法】
- サポーターは「肘頭(肘の突起部)」をしっかり覆うように装着し、ずれないよう固定しましょう。
- 圧迫が強すぎると血行障害を引き起こすため、「心地よい締めつけ感」を意識することが大切です。
- 使用前に必ず製品付属の説明書を確認することが重要です。
テーピングの活用方法は以下の通りです。
【テーピングの方法】
- 巻く順番は腕 → 二の腕に向かって巻き上げるイメージです。
- テープの幅1本分の隙間を作り腕にテープを巻き始めます。
- 2~3周かけて肘の内側まで巻き上げたら、肘の内側を斜めに横断するように二の腕側に移ります。
- 二の腕側でも2~3周巻き、巻き上げたときのテープとXになるようにクロスし、腕側へ戻りましょう。
- 腕側で1周、二の腕側でさらに1周巻いた後、テープをしっかり密着させれば完成です。
- ※ポイントは肘の外側にテープを巻かないように気を付けることです。
正しく選んで、正しく使えば、サポーターは肘頭滑液包炎のセルフケアにおいて心強いパートナーになります。
自身の症状や生活スタイルに合った使い方を意識し、無理なく改善を目指しましょう。
肘頭滑液包炎の治療方法について
肘頭滑液包炎の治療は、症状の程度や発症原因に応じて「保存療法」と「医療的処置」が基本となります。
保存療法が第一選択とされており、安静・冷却・圧迫といった日常的な対処が症状の改善に有効です
ただし、痛みや腫れが強く、日常生活に支障をきたす場合には医師の診断を受け、必要に応じて穿刺(せんし)や注射といった医療処置が行われます。
症状が軽度であれば、自己管理とサポーターの併用によって多くのケースで改善可能です。
ただし、痛みが強くなる、腫れが引かない、熱感が続くといった症状があれば、早めに整形外科を受診しましょう。
早期の適切な対処が、肘頭滑液包炎の早期回復と再発予防につながります。
自己治癒力を高める再生医療という選択肢
肘頭滑液包炎の症状が慢性化していたり、保存療法や薬物治療で改善が見られない場合には、「自己治癒力」に着目した再生医療という選択肢も注目されています。
肘頭滑液包炎は基本的に保存療法で回復が見込まれる疾患ですが、症状が長引くケースや再発を繰り返すケースでは、治癒力そのものが低下している可能性があります。
そんなとき、有効な選択肢の一つとして挙げられるのが、幹細胞(かんさいぼう)治療などの再生医療です。
「自己由来の幹細胞」を活用した治療は、自分の脂肪組織や骨髄などから採取した細胞を使うため、拒絶反応が起きにくいという特徴があります。
肘関節は日常的に使用頻度が高いため、安静を保つのが難しい部位です。
そのため、再発防止や根本的な組織修復を目指す再生医療は、肘頭滑液包炎の長期的な改善を求める方にとって魅力的な選択肢となり得ます。
従来の治療で満足な効果が得られなかった方や、できる限り自然な形で症状を改善したいと考える方にとって、再生医療は新たな希望となる選択肢といえるでしょう。
手術をしない新しい治療「再生医療」を提供しております。
自分に合ったサポーターで肘頭滑液包炎を悪化させない対策を行おう
肘頭滑液包炎は、初期の対応と継続的なセルフケアによって、症状の悪化を防ぎながら日常生活を維持できる疾患です。
そのためには、「自分に合ったサポーター」を選び、正しく活用することが非常に重要です。
症状が軽度のうちからサポーターを正しく使用することで、悪化の予防や再発防止にもつながります
逆に、自己判断で合わない製品を使い続けたり、無理に動かしてしまうと、炎症の長期化や慢性化を招くおそれもあるため注意が必要です。
サポーターや保存療法で十分な改善が得られない場合には、リペアセルクリニックが提供する「再生医療」という新しい選択肢も検討してみるのがおすすめです。
リペアセルクリニックでは、自己由来の幹細胞を用いた治療によって、滑液包の慢性的な炎症を内側から抑制し、自己治癒力を高めながら回復を促す治療を行っています。
サポーターという手軽な対処から始めつつ、必要に応じて再生医療のような専門的ケアも視野に入れることで、改善の道が広がります。
最適な方法で、肘の痛みに悩まされない生活を取り戻しましょう。

監修者
坂本 貞範
Sadanori Sakamoto
医療法人美喜有会 理事長
「できなくなったことを、再びできるように。」
人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの
お手伝いができれば幸甚の至りでございます。
略歴
1997年3月関西医科大学 医学部卒
1997年4月医師免許取得
1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務
1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務
1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務
1999年2月国立大阪南病院 勤務
2000年3月野上病院 勤務
2003年3月大野記念病院 勤務
2005年5月さかもとクリニック 開設
2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任
2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設
2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設