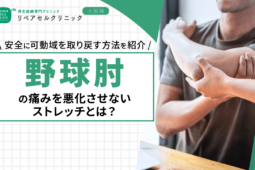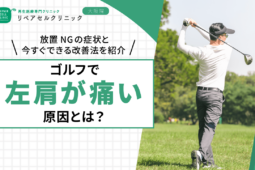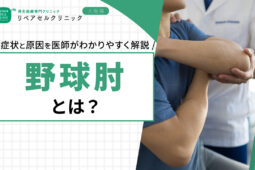- 肘
【症状別】野球肘の治療期間を医師が解説|早く治す方法もあわせて紹介
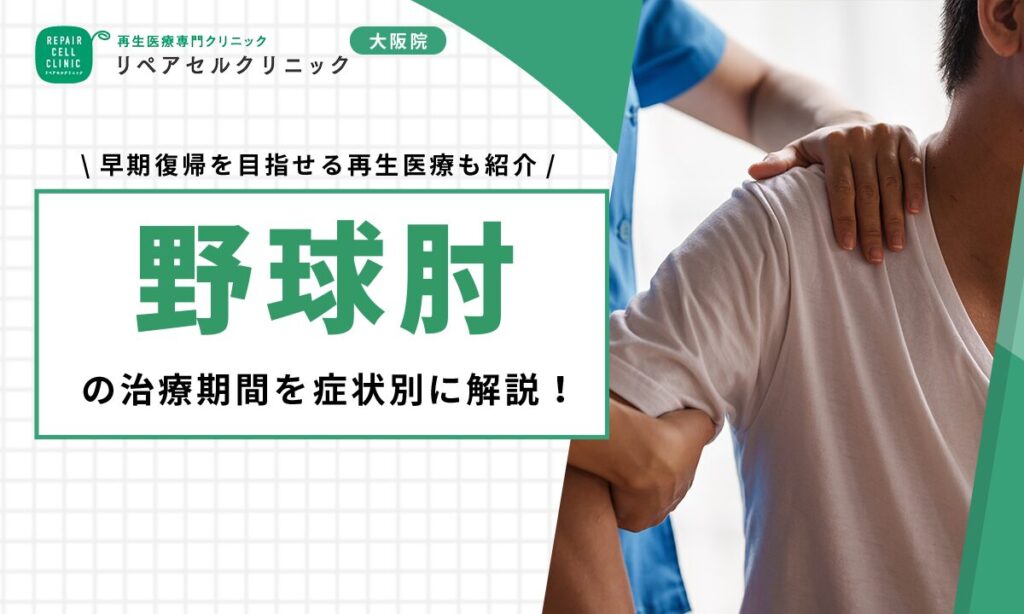
「野球肘」と診断されたとき、「いつになったら、また野球ができるようになるのか」と不安になる方も多いでしょう。
本記事では、野球肘の治療期間の目安を症状別に解説します。
- 【症状別】野球肘の治療期間の目安
- 野球肘を早く治すための具体的な方法
- 野球肘の回復を妨げないために避けるべきこと
野球肘の痛みにお悩みの方、治療期間や復帰までの道のりについて知りたい方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
また、当院リペアセルクリニックの公式LINEでは、野球肘をはじめとする肘関節の治療法として注目されている再生医療に関する情報を配信中です。
「野球肘を早く治したい」「治療期間を短くしたい」という方は、ぜひ再生医療がどのような治療を行うか知っておきましょう。
目次
野球肘の治療期間【症状別】
「野球肘」は投球動作によって起こる肘関節のスポーツ外傷の総称で、痛む場所や損傷している組織によっていくつかの種類に分けられます。
そして、種類や重症度によって、治療にかかる期間や再びボールを投げられるようになるまでの道のりは異なります。
本章では、野球肘の代表的な症状別に、それぞれの治療期間の目安について解説していきます。
ご自身の症状と照らし合わせ、治療期間の目安を把握しましょう。
内側上顆裂離(リトルリーグ肘)
内側上顆裂離(リトルリーグ肘)の治療期間は、1ヶ月~2ヶ月程度の投球中止と安静を中心とした保存療法で、良好な回復が期待できます。
| 項目 | 詳細 |
| 症状 | 肘の内側にある骨の出っ張り(内側上顆)の成長軟骨が、投球時の牽引力によって剥がれてしまう裂離骨折。 骨の成長がまだ完了していない、主に小中学生のピッチャーに多く見られる。 |
| 治療 | 基本的には1~2ヶ月の投球中止と安静。 痛みが強い場合は、2~4週間ほどギプスなどで肘を固定することもある。 |
軽症であれば短期間の休養で回復しますが、骨片の転位が大きい重症例では、長期の休養やまれに手術が検討されることもあります。
以下の記事では、野球少年が野球肘を発症した場合のリハビリや再発予防策について解説しているので、ぜひ参考にしてください。
肘内側側副靭帯損傷
肘内側側副靭帯損傷の治療期間は、部分的な断裂であれば1~3ヶ月の保存療法で回復が期待できます。
| 項目 | 詳細 |
| 症状 | 投球動作の繰り返しによって、肘の内側で関節を安定させている靭帯(内側側副靭帯:UCL)に過度な負荷がかかり、損傷したり、断裂したりするケガ。 肘関節のぐらつき(不安定感)や投球時の痛みが主な症状。 |
| 治療 | まずは投球を中止し、アイシングやストレッチ、リハビリといった保存療法が行われる。 |
ただし、完全に断裂してしまい靭帯を再建する手術が必要な場合は、競技復帰までに約1年という長い時間が必要になります。
以下の記事では、靭帯を再建するトミージョン手術について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
肘部管症候群
「肘部管症候群」の治療期間は、保存療法で改善しない場合に行われる手術(肘部管解放術)を受けたとしても、術後約3ヶ月での競技復帰が目標となります。
| 項目 | 詳細 |
| 症状 | 肘内側の尺骨神経が圧迫される障害。 肘の内側の痛みや、小指と薬指にしびれが現れる。 |
| 治療 | まずは投球を休止し、ストレッチなどの保存療法が行われる。 改善しない場合や麻痺が重い場合には、手術療法を行う。 |
重症化すると、手の小指側の筋力が低下する恐れもあります。
上腕骨小頭離断性骨軟骨炎
上腕骨小頭離断性骨軟骨炎の治療期間は、保存療法でも少なくとも6ヶ月以上の投球禁止が必要で、手術を行うと競技復帰まで8~9ヶ月程度かかることもあります。
| 項目 | 詳細 |
| 症状 | 肘の外側にある腕の骨(上腕骨小頭)の軟骨とその下の骨が、血流障害などによって部分的に壊死し、剥がれてしまう病気。 主に10歳前後の、骨がまだ成長段階にあるピッチャーに多く見られる。 |
| 治療 | 早期に発見できれば投球禁止などの保存療法で治癒可能。 進行すると、関節鏡視下での損傷組織の除去や骨軟骨移植など外科的治療が検討される。 |
注意すべき点は、初期の段階では痛みなどの自覚症状がほとんどないことです。
「沈黙の障害」とも呼ばれ、選手自身も指導者も気づかないうちに、水面下で病状が進行してしまうことが少なくありません。
壊死した骨軟骨が進行して、ついには「ポロッ」と剥がれ落ちてしまうと、そのかけらが関節の中を動き回る「関節ねずみ」という状態になります。
関節ねずみについては以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
肘頭骨端線離開
「肘頭骨端線離開」の治療期間は、軽症であれば2週間~4週間程度の投球中止と安静で症状が改善することが多いです。
| 項目 | 詳細 |
| 症状 | 肘の後方の出っ張った骨である肘頭にある、骨が成長するための部分(骨端線)が、投球の繰り返しによって負担がかかり、剥がれてしまう障害。 投球時の肘の後方に痛みが生じる。 |
| 治療 | 多くの場合、投球を中止し、安静にすることで自然に治癒する。 骨端線のズレが大きい場合や保存療法で改善しない場合には、剥がれた骨片をボルトなどで固定する手術が検討される。 |
手術を行った場合はその後のリハビリも含め、競技に復帰するまでには3ヶ月程度の期間を見込む必要があります。
野球肘を早く治す方法
本章では、野球肘を早く治すための方法について解説します。
野球肘と診断された選手やご家族にとって「どうすれば一日でも早く治せるのか」が気になることでしょう。
焦りは禁物ですが、着実に回復するための参考にしてください。
投球を休止して安静にする
野球肘を早く治すためには、痛みの原因となっている投球動作を中止し、肘を十分に休ませることが大切です。
【投球休止と安静の重要性】
- 痛みや違和感があるのに投げ続けると炎症や損傷が悪化する
- 結果として回復が長引き、復帰が遅れる恐れがある
- 軽症の野球肘なら、数週間から数ヶ月の投球休止で改善することも多い
- 肘の違和感が完全になくなるまで、投球練習や負担のかかる動作は避ける
痛みは、身体が発している「これ以上無理をしないでほしい」という警告のサインです。
身体のサインに耳を傾け、勇気をもって休養を優先することが、結果的に早くグラウンドへ復帰するための近道になります。
ストレッチや筋トレによるリハビリテーション
痛みが治まったら、医師の指示のもとでリハビリテーションを開始しましょう。
【野球肘のリハビリのポイント】
- 必ず医師の指示のもとでリハビリを開始する
- 肘周りのストレッチで、硬くなった関節の柔軟性を取り戻す
- 手首の運動などで前腕の筋肉を鍛え、肘の安定性を高める
リハビリは自己流ではなく専門家の指導を受け、無理のない範囲で段階的に強度を上げていくことが大切です。
再生医療
野球肘の治療には、先端医療である再生医療という選択肢があります。
再生医療で行われる「幹細胞治療」や「PRP療法」は、スポーツへの早期復帰が目指せる治療法です。
それぞれの治療方法には、以下の特徴があります。
-
幹細胞治療
患者さま自身の脂肪組織や骨髄から採取・培養した幹細胞を損傷部位に投与する治療法。
幹細胞は損傷した組織や失われた機能の修復・再生を促す。 -
PRP療法
患者さま自身の血液から抽出した血小板を高濃度に濃縮し、損傷部位に注射する治療法。
血小板に含まれる成長因子が組織の修復を促進する。
当院「リペアセルクリニック」では、野球肘を含むスポーツ外傷に対する再生医療を行っています。
「野球肘を早く治して競技復帰したい方」は、手術や入院をせずに野球肘の改善を目指せる再生医療について知っておきましょう。
次の動画では、野球肘の再生治療について解説しているので、ぜひ参考にしてください。
野球肘を早く治すためにやってはいけないこと
野球肘を早く治すためにも、肘を悪化させてしまう以下の行動は避けましょう。
【野球肘を早く治すためにやってはいけないこと】
- 痛みを我慢して投げ続けること
- 自己流のフォーム修正を試みること
- 十分な休養を取らないこと
- 肘に負担をかける活動を続けること
- 早すぎる復帰をすること
野球肘は投球制限・休息により回復可能な障害ですが、無理をすると症状が悪化するリスクがあります。
痛みは身体からの警告信号なので、無理に投げ続けるのは避けて、医師の指示に従って十分な休養をとりましょう。
野球肘の治療期間に関するよくある質問
本章では、野球肘の治療期間についてよくある質問に回答していきます。
野球肘はどのくらいで回復する?
野球肘が回復するまでの期間は症状の程度によって大きく異なり、軽い場合は2週間~4週間程度の投球休止で改善します。
重症で手術が必要な場合には、競技復帰まで約1年かかることもあります。
大切なのは、肘に違和感を覚えたらできるだけ早い段階で医療機関を受診し、重症化する前に対処を始めることです。
痛みを我慢して投げ続けることは、結果的に回復を長引かせてしまうということを覚えておきましょう。
野球肘かチェックする方法は?
「もしかして野球肘かも?」と感じたときに、ご自身で確認できるセルフチェックのポイントをご紹介します。
以下のサインに一つでも当てはまる場合は、野球肘の可能性が考えられるため注意が必要です。
- ボールを投げる瞬間に肘の内側や外側に痛みが走る
- 投げ終えた直後は痛むが、休んでいると痛みが消える
- 肘の曲げ伸ばしが、どこかぎこちなくスムーズに動かない
- 投げ込みの日など、球数が増えるにつれて痛みが強くなる
- キャッチボールをしていないときでも、肘に痛みが残っている
- 思い切り腕を振っているつもりでも、ボールのスピードやキレが明らかに落ちた
野球肘の初期段階でよく見られる落とし穴は、練習をやめると痛みが引いてしまうことです。
「初めて痛みを感じた」「いつもと違う違和感がある」と感じたら投球を中止し、できるだけ早く整形外科などの専門医療機関を受診しましょう。
野球肘を自分で治す方法は?
野球肘を自己判断だけで完全に治すことはできませんが、セルフケアを行うことで症状を和らげることは可能です。
【野球肘に対するセルフケア】
- アイシングで炎症と痛みを抑える
- 投球を休み、肘を安静に保つ
- 痛みが引いたら、医師の指導のもとでストレッチや軽い筋トレを行う
ただし、セルフケアは、あくまで回復を「サポートする」ためのものです。
痛みが長引く場合や、どのようなケアをすれば良いか不安な場合は、自己判断で無理をせず、必ず整形外科などの医療機関を受診し、専門家の診断と指導を受けるようにしてください。
野球肘はストレッチで治る?
残念ながら、ストレッチだけで野球肘を完全に治すことはできません。
しかし、ストレッチは野球肘の予防や、治療後のリハビリの一環として痛みを軽減させるためには有効な手段です。
野球肘は骨や軟骨・靭帯といった組織に炎症が起きている状態です。
そのため、まずは原因となっている投球動作を休止し、患部を安静にすることが重要です。
野球肘の治療期間を短くするには休養と適切な治療が重要
野球肘の治療期間は症状によって大きく異なり、軽症であれば数週間から1〜2ヶ月、重症で手術が必要な場合には競技復帰まで1年近くかかることもあります。
早く治すためには、肘に痛みや違和感を覚えたらすぐに投球を中止し、専門の医療機関を受診して、適切な治療と十分な休養をとることが重要です。
痛みを我慢して投げ続けることは回復を遅らせるだけでなく、選手生命に関わる深刻な事態を招く恐れもあります。
従来の治療法でなかなか改善しない、一日でも早く競技に復帰したい方には、「再生医療」という選択肢もあります。
手術や入院をせずに治療が可能で、早期の回復が期待できます。
つらい肘の痛みを諦める前に、ぜひ当院リペアセルクリニックにご相談ください。

監修者
坂本 貞範
Sadanori Sakamoto
医療法人美喜有会 理事長
「できなくなったことを、再びできるように。」
人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの
お手伝いができれば幸甚の至りでございます。
略歴
1997年3月関西医科大学 医学部卒
1997年4月医師免許取得
1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務
1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務
1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務
1999年2月国立大阪南病院 勤務
2000年3月野上病院 勤務
2003年3月大野記念病院 勤務
2005年5月さかもとクリニック 開設
2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任
2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設
2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設