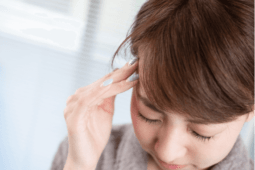- 脳梗塞
- 脳卒中
- 頭部
高齢者の脳梗塞に回復見込みはある?後遺症が改善した症例を解説【医師監修】

脳梗塞を発症した場合、高齢者でも回復する見込みがあるのか不安を抱える方も多いでしょう。
脳梗塞は発症後の対応が重要であり、適切な治療やリハビリ次第で日常生活を送れるまで回復する見込みはあります。
とはいえ、脳梗塞は脳細胞の損傷による障害のため、従来の治療では継続的な治療で症状をコントロールすることが目的となり、完治するのは難しい領域です。
近年の治療では「高齢者でも脳梗塞を治したい」「後遺症に悩まされたくない」という方向けに、損傷した脳細胞の改善が期待でき、脳梗塞の根本的な改善につながる再生医療が注目されています。
当院リペアセルクリニックでは、高齢者の脳梗塞でも症状の改善が期待できる再生医療をご提供・ご案内しています。
いきなり新しい治療を試すのは不安という方に対しても、当院では無料のカウンセリングも実施しており、治療内容について丁寧にご説明いたしますので、ぜひ一度ご相談ください。
また、公式LINEでも再生医療に関する情報や脳梗塞治療の症例を配信しているので、この機会に再生医療について知っておきましょう。
▼脳梗塞の後遺症治療に注目
>>公式LINE限定の再生医療に関する情報を見てみる
目次
高齢者の脳梗塞でも回復する見込みがある
一般的に年齢が高くなるほど、若年層と比較して高齢者の脳梗塞の回復には時間がかかる傾向があります。
しかし、高齢者であっても適切な治療を受け、計画的にリハビリを進めることで、日常生活動作(ADL)の向上が十分に期待できます。
回復見込みに影響を与える要素
高齢者が脳梗塞を発症した場合の回復の見込みは、以下のようなさまざまな要因が影響を与えています。
- 患者さまの年齢と体力
- 発症から治療開始までの時間
- 脳の損傷部位と程度
- リハビリテーションの質と継続性
- 基礎疾患(高血圧、糖尿病など)の管理状態
- 患者さま自身の回復力や意欲
上記のようなさまざまな要因が影響し、高齢者が脳梗塞を発症しても回復する見込みはあります。
とくに、脳梗塞の発症後4.5時間以内に初期治療を受けることが重要となり、発症後の迅速な対応が回復に影響します。
早期回復には適切なタイミングのリハビリが重要
脳梗塞の早期回復には、適切なタイミングで適切なリハビリテーションを行うことが重要です。
脳には「神経可塑性」という特性があり、適切なリハビリを継続することで、損傷した機能の一部を他の部位が補うことができます
ただし、回復の程度や速度には個人差が大きく、同じような症状であっても、改善の度合いは患者によって異なることに留意が必要です。
回復のステージと必要な対応について、以下の通りです。
|
回復段階 |
重要なポイント |
期待される効果 |
具体的なリハビリ例 |
|---|---|---|---|
|
発症直後 |
t-PA治療の実施(4.5時間以内) |
脳細胞の損傷を最小限に抑制 |
早期離床訓練 |
|
急性期 |
早期リハビリの開始 |
二次障害の予防、基本機能の維持 |
関節可動域訓練、嚥下訓練 |
|
回復期 |
計画的なリハビリの継続 |
日常生活動作(ADL)の改善 |
麻痺した手足の運動訓練、言語訓練、生活動作訓練 |
|
維持期 |
生活習慣の改善と基礎疾患の管理 |
機能維持と再発予防 |
自主トレーニング |
リハビリの成果は継続性や頻度に依存するため、専門家の指導のもとで計画的かつ段階的なアプローチを行うことが重要です。
たとえば、麻痺が残った手足の運動訓練では関節の動きを維持することから始めたり、失語症に対する言語訓練などによってコミュニケーション能力の回復を目指します。
日常生活動作(ADL)の改善については個人差があるものの、高齢者の場合でも比較的軽い脳梗塞であれば、早期治療とリハビリの組み合わせにより機能改善が期待できます。
ただし重度の場合は介助を必要とする場面が残る可能性もあり、さらに脳梗塞は再発リスクが高い疾患であり、とくに高齢者ではその傾向が顕著です。
脳梗塞による後遺症の回復見込み
高齢者が脳梗塞を発症した後、後遺症が出る可能性は若年層より高く、回復にも時間がかかる傾向があります。
とくに80歳以上や90歳以上では、その傾向が顕著です。高齢者が脳梗塞を発症した際に現れやすい後遺症は、以下の通りです。
| 脳梗塞の主な後遺症 | 症状 |
|---|---|
| 運動麻痺 | 手足が動きにくくなる、片側が麻痺する |
| 言語障害 | 言葉が出にくい、会話が難しくなる(失語症) |
| 嚥下障害 | 食べ物や飲み物が飲み込みにくくなり、誤嚥性肺炎のリスクが高まる |
| 認知機能の低下 | 記憶力や判断力が低下し、日常生活に支障をきたす |
後遺症が残った場合でも、回復見込みはありますので、以下のリハビリを継続的に行い、症状の緩和や生活の質の向上を目指しましょう。
高齢者の脳梗塞を回復させるために重要なリハビリテーション
脳梗塞後の後遺症からの回復を助けるリハビリとして、段階に応じたリハビリテーションを行います。
リハビリは大きく急性期、回復期、維持期の3つの期間に分けられ、それぞれ異なる目的とリハビリ内容を設定します。
| リハビリの期間 | 発症からの期間 | 目的 | 主なリハビリ内容 |
|---|---|---|---|
| 急性期 | 発症から1~2カ月以内 | 合併症の予防と身体機能の維持 |
|
| 回復期 | 発症から6カ月以内 | 身体機能・日常生活動作(ADL)の回復 |
|
| 維持期(生活期) | 発症から6カ月以降 | 機能の維持と生活の質向上 |
|
急性期には合併症の予防、回復期には機能の回復、維持期にはその維持と生活の質の向上を目指します。
脳梗塞後の高齢者の回復には、継続的なリハビリが欠かせません。医療スタッフや家族と協力しながら、その人の状態に合ったリハビリを進めていきましょう。
脳梗塞後の高齢者に対してご家族ができるサポート
脳梗塞後の高齢者を支えるには、ご家族の心理的な支援や日常生活のサポートによって、患者さまがリハビリを積極的に行えるようにすることが重要です。
サポートは重要ですが、家族だけですべてを抱え込むのは困難な場合も多いため、外部の介護サービスなどの活用も検討しましょう。
心理的なサポート
高齢の脳梗塞の患者さまには、以下のようなご家族からの心理的なサポートが欠かせません。
- 不安を軽減するために本人の気持ちに寄り添った声かけを行う
- 小さな進歩を褒めるなどの意欲を高める環境を作る
患者さまは、脳梗塞の症状や後遺症が治るのか不安を感じている場合がほとんどですので、不安を取り除いてあげるようなコミュニケーションが重要です。
また、リハビリを積極的に取り組めるように小さな進歩も褒めましょう。
日常生活を送りやすい環境づくり
脳梗塞を発症すると、今まで普通にできていたことができなくなることが多いです。
以下のような患者さまが日常生活を送りやすい環境づくりをしましょう。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 住環境の整備 | 手すりの設置や段差の解消、滑りにくい床材の導入を行い、転倒リスクを軽減する |
| 食事の工夫 | 栄養バランスを意識しつつ、飲み込みやすい形態(刻み食やゼリー状の食品)の食事を取り入れる |
| 外部サービスの活用 | 訪問リハビリやデイサービスの利用を検討し、必要に応じて保険外サービスも活用する |
脳梗塞の後遺症によって思ったように動けなくなると、小さな段差でも転倒してしまうケースも少なくありません。
階段や段差があるとこには手すりの設置や段差を解消して転倒リスクを軽減することが重要です。
高齢者の脳梗塞による後遺症が改善した症例
高齢者の脳梗塞による後遺症が改善した症例を紹介します。
上記の患者さまは、脳梗塞後の高次脳機能障害に悩まされていましたが、再生医療によって症状の改善がみられた症例です。
※効果には個人差があります。
その他にも当院リペアセルクリニックの症例ページでは、以下のような実際の症例と治療後の経過について解説しています。
| 症例 | 治療後の経過 |
|---|---|
| 急性期脳梗塞の後遺症 (60代男性) |
左手のしびれが消失し、不整脈の症状も改善がみられた。 呂律も回復し、スムーズに発語できるようになった。 |
| 脳梗塞後の右上肢の機能低下 (60代男性) |
右肩の可動域と筋力が改善し、ボールを投げる動作が可能になった。 脳の血管造影検査で損傷した脳細胞が改善した確認も得られる。 |
| 急性期脳梗塞の後遺症 (70代男性) |
初回投与後1週間で左口周りと左手のしびれが軽減し、夜間頻尿の症状改善がみられた。 4か月後にはふらつき、めまいがなくなり、小走りも可能になった。 |
それぞれの詳しい紹介は以下にて紹介していますので、詳細が気になる方はぜひご確認ください。
>>脳梗塞(脳卒中)の症例ページはこちら
脳卒中のお悩みに対する新しい治療法があります。
高齢者の脳梗塞と回復についてよくある質問
高齢者の脳梗塞と回復についてよくある質問は以下の通りです。
以下では上記の質問に回答しながら、高齢者でも可能な回復の道筋や治療の選択肢について解説します。
高齢者が脳梗塞になったら余命はどのくらい?
脳梗塞を発症すると命に関わる場合があるのは事実ですが、それが必ずしも長寿を妨げる要因ではありません。
適切な治療やリハビリ、再発予防の取り組みによって、発症後も生活の質を維持しながら長生きできる可能性があります。
-
再発リスクを抑える生活習慣の見直し
-
リハビリと心理的サポート
-
支援サービスの活用
まずは高血圧や糖尿病などの基礎疾患の管理が重要です。塩分を控えた食事や適度な運動を日常生活に取り入れることで、再発リスクを低減できます。
定期的な健康診断を受け、高血圧などの脳梗塞の要因を早期に発見することも大切です。
また、リハビリを通じて身体機能や日常生活動作の改善が可能です。歩行訓練や失語症の改善に向けた言語訓練などが効果を発揮します。
家族や介護者による心理的な支えが本人の意欲を高める鍵となるので、長い目で見ると結果的に負担が軽くなることも期待できるでしょう。
リハビリには家族のサポートは大切ですが、負担が大きくならないように支援サービスの活用も検討してみてください。
訪問リハビリやデイサービスといった外部の支援を取り入れることで、家庭での介護負担を軽減しながら、適切なケアを継続できます。
高齢者の脳梗塞は治療できない?
高齢者が脳梗塞を発症した場合、治療が難しいケースは確かに存在します。
これにはいくつかの要因が関係しています。
- 年齢と回復力
- 早期治療が不可能な場合
- 後遺症の重篤さ
- 合併症のリスク
高齢になるほど身体の回復力が低下し、外科的処置や薬物治療が適さない場合があります。
また、発症からの時間が遅れたためにt-PA治療(血栓を溶かす治療)などの早期治療が適用できないケースも少なくありません。
さらに、麻痺や言語障害が深刻でリハビリを行うことが難しい状況や、基礎疾患(心臓病や糖尿病など)が治療の妨げとなることもあります。
このような場合、従来の治療法が行えないため、代替策として以下の対応が考えられます。
- 緩和的ケアによる痛みや不快感の軽減
- 移動や日常生活を支えるための住環境の調整
- 専門家の指導を受けながらの家族や介護者の支援
治療が行えない場合でも、症状の進行を防いで生活の質を保つための工夫や支援を行うことが重要です。
家族や介護者が連携し、患者ができる限り快適な生活を送るためのサポートが大切です。
脳梗塞の再発を予防する方法は?
脳梗塞の再発を予防する方法は、以下の通りです。
- 定期的な健康診断の受診(血圧、血糖値、コレステロール値のチェック)
- 基礎疾患の適切な管理(高血圧、糖尿病、心房細動など)
- バランスの取れた食事(減塩、適切な栄養摂取)
- 適度な運動の継続(主治医と相談の上で)
- 十分な休息の確保(過度な疲労を避ける)
早期かつ適切な治療とリハビリを行うことで、高齢者であっても脳梗塞後の生活の質を向上させることが可能です。
焦らず、専門家のサポートを受けながら、段階的に回復を目指すことが大切と言えるでしょう。
脳梗塞の後遺症にお悩みの高齢者の方は再生医療をご検討ください
脳梗塞は高齢者にとって深刻な疾患ですが、適切な治療とリハビリを行うことで、回復への道が開ける場合があります。
ただし、若い世代と比較すると、加齢による回復力の低下や後遺症が出る可能性が高く、回復が難しいケースもあります。
これらの要因を踏まえつつ、再発を防ぎながら生活の質を向上させることが重要です。
近年の治療では、幹細胞治療をはじめとする再生医療が、高齢者の脳梗塞後の後遺症改善において注目されています。
当院リペアセルクリニックでは、高齢者の脳梗塞でも症状の改善が期待できる再生医療をご案内可能です。
いきなり新しい治療を試すのは不安という方に対しても、当院では無料のカウンセリングも実施しており、治療内容について丁寧にご説明いたしますので、ぜひ一度ご相談ください。
また、公式LINEでも再生医療に関する情報や脳梗塞治療の症例を配信しているので、この機会に再生医療について知っておきましょう。
▼脳梗塞の後遺症治療に注目
>>公式LINE限定の再生医療に関する情報を見てみる

監修者
圓尾 知之
Tomoyuki Maruo
医師
略歴
2002年3月京都府立医科大学 医学部 医学科 卒業
2002年4月医師免許取得
2002年4月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2002年6月関西労災病院 脳神経外科 勤務
2003年6月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2003年12月大阪母子医療センター 脳神経外科 勤務
2004年6月大阪労災病院 脳神経外科 勤務
2005年11月大手前病院 脳神経外科 勤務
2007年12月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2012年3月大阪大学大学院 医学系研究科 修了(医学博士)
2012年4月大阪大学医学部 脳神経外科 特任助教
2014年4月大手前病院 脳神経外科 部長
あわせて読みたいトピックス
-

脳卒中における二木の予後予測とは|回復期リハビリテーションの重要性と注意点を解説
-
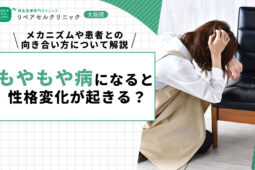
もやもや病になると性格変化が起きる?メカニズムや患者との向き合い方について解説
-

くも膜下出血は後遺症がなくても再発するリスクがある!注意点を解説
-

橋梗塞の症状とリハビリの進め方|具体的なプログラムとポイントについて解説
-

脳出血の看護ケア|在宅でも家族ができることや注意点・ポイントについて解説
-

脳出血の入院期間|年齢別・重症度別の違い、入院費用について解説【医師監修】
-

高次脳機能障害の回復事例を紹介!経過や治療・リハビリが大切な理由も解説
-

高次脳機能障害患者の家族が抱えるストレスとは?つらさの理由と無理をしない接し方を紹介