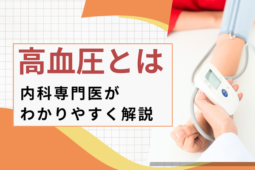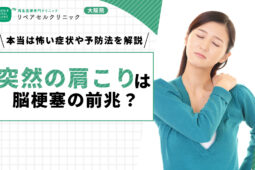- 脳梗塞
- 脳卒中
- 頭部
脳梗塞になりやすい人の特徴8選|予防法や前兆を解説【医師監修】

脳梗塞は脳血管に血栓が詰まり血流が途絶えることで、脳の神経細胞が死んでしまう病気です。
生活習慣病を持つ人や過度の飲酒や喫煙習慣がある人は、脳梗塞になりやすい傾向があります。
本記事では、脳梗塞になりやすい人の特徴や予防方法について解説します。
脳梗塞の発症リスクを確認し、脳梗塞を予防しましょう。
また、現在リペアセルクリニックでは脳梗塞の後遺症や再発予防に対する治療法として、再生医療を行っています。
\脳梗塞に有効な再生医療とは/
再生医療は、損傷した脳細胞にアプローチする治療によって、従来の治療では難しい脳細胞の改善が期待できます。
【こんな方は再生医療をご検討ください】
- 脳梗塞が治るか不安を抱えて生活している
- 治療後にも後遺症に悩まされている
- 現在の治療では目立った効果が出ていない
脳梗塞治療の新たな選択肢として、注目されている治療法です。
以下の動画では、実際に当院リペアセルクリニックで再生医療を受け、脳梗塞の後遺症が改善された患者さまの症例を紹介しています。
再生医療の治療法や症例については、当院リペアセルクリニックの公式LINEで発信しているので、併せて参考にしてください。
目次
脳梗塞になりやすい人の特徴8選
脳梗塞になりやすい人には、以下の8つの特徴があります。
乱れた食生活や運動不足によって発症した生活習慣病は、脳梗塞の原因にもなりうるため注意が必要です。
以下の動画では脳梗塞の初期症状についてわかりやすく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
脳梗塞になりやすい人の特徴について、それぞれ詳しく解説します。
高血圧
慢性的な高血圧は血管の壁が硬くなり、動脈硬化を引き起こすことで脳梗塞を発症する可能性があります。
一般的に最高血圧が140mmHg以上、あるいは最低血圧が90mmHg以上の状態が慢性的に続くと高血圧と診断されます。
高血圧にならないために、以下の特徴を持つ人は注意しましょう。
- 肥満である
- 過剰にアルコールを摂取している
- 喫煙している
- ストレスを溜めやすい
- 親族に高血圧の人がいる
高血圧の状態が続くと血管壁がもろくなり血栓ができやすいため、日常的な血圧管理が大切です。
脂質異常症
脂質異常症は、血液中の悪玉コレステロールや中性脂肪が異常に高い状態で、脳梗塞の原因となる動脈硬化を引き起こします。
脂質異常症の診断基準※は以下のとおりです。
| 疾患名 | 診断基準 |
| 高LDLコレステロール血症 | LDLコレステロール140mg/dL以上 |
| 境界域高LDLコレステロール血症 | LDLコレステロール120~139mg/dL |
| 低HDLコレステロール血症 | HDLコレステロール 40mg/dL未満 |
| 高トリグリセライド血症 |
中性脂肪(トリグリセライド:TG) 150mg/dL以上(空腹時採血) 中性脂肪(トリグリセライド:TG) 175mg/dL以上(随時採血) |
過食・肥満傾向、運動習慣のない人は、脂質異常症になりやすいため注意が必要です。
血液中に過剰に存在するコレステロールや中性脂肪は、プラーク(粥種)となり血管壁に沈着します。プラークが血管壁に沈着すると、血管壁が肥厚して硬くなり、動脈硬化のリスクが高まります。
心房細動(不整脈)
心房細動(不整脈)は、心臓の中の血流が滞ることで血栓ができやすい状態となり、この血栓が脳に運ばれて脳梗塞を引き起こす可能性があります。
加齢や高血圧などが原因で起こる不整脈のことで、心房細動になると血液循環機能が正常に働かず、心房内に古い血液が溜まり血栓ができやすくなります。
心房細動による脳梗塞は重症化しやすく、麻痺や言語障害など重い後遺症が残ることが多いため、生活習慣の見直しが必要です。
糖尿病
糖尿病は血糖値が高い状態が続く病気で、血液がドロドロになることで血液が詰まりやすくなり、脳梗塞のリスクが高まります。
糖尿病は、血糖値を下げるホルモンのインスリンが正常に機能しない病気で、診断基準※は以下のとおりです。
| 血糖値 |
空腹時血糖≧126mg/dL 75g経口ブドウ糖負荷試験2時間後の血糖値≧200mg/dL 任意の時間の血糖値≧200mg/dL |
| HbA1c |
HbA1c(JDS値)≧6.1% HbA1c(NGSP)≧6.5% |
※参照:糖尿病の新しい診断基準|国立国際医療研究センター糖尿病情報センター
インスリンの機能低下により高血糖状態になった場合は、動脈硬化が進行します。血管の状態が悪化し血液循環が滞ると血栓が作られ、脳梗塞になるリスクが高まります。
動脈硬化
動脈硬化は加齢や高血圧、糖尿病などが要因となり、血管壁がもろくなる疾患で、脳梗塞のリスクが高いです。
もろくなった血管壁を修復するために、血小板が凝集し血栓ができやすくなります。
動脈硬化が進行し、体のどこかで作られた血栓が脳血管まで到達したり、脳内で血栓ができた場合は、脳梗塞を発症する可能性があります。
生活習慣が乱れている
塩分や脂肪分の過剰摂取や運動不足など、生活習慣が乱れていると高血圧や糖尿病を発症し、脳梗塞を引き起こす可能性があります。
また、過度な飲酒や喫煙、ストレス、睡眠不足などにも注意する必要があります。
血液循環が正しく行われるよう、塩分を控えて適度な運動を行い、血液をきれいな状態に保つことが大切です。
過度の飲酒・喫煙習慣
過度の飲酒は血圧が上昇し、喫煙は血管を収縮させて血流を悪くなるため、脳梗塞のリスクが高まります。
また、アルコールには利尿作用があるため、脱水状態になりやすく、血液の粘度が高まることで血栓ができやすくなるため注意が必要です。
過度な飲酒は避けて適量を心がけることや、禁煙をするなど生活習慣を見直すようにしましょう。
遺伝的要因
家族に脳梗塞の発症歴がある場合、遺伝的要因により脳梗塞の発症リスクが高くなる可能性があります。
アテローム血栓性脳梗塞の感受性遺伝子として知られているRNF213遺伝子の多型の保有者は、脳梗塞を発症しやすいとされています。
脳梗塞や脳出血などの脳血管疾患は、生活習慣病などの環境的要因と遺伝的要因が組み合わさることでも、発症リスクが高まるため、生活習慣の見直しが重要です。
家族に脳梗塞の人がいる場合や、もともと血圧が高い人は、脳梗塞の発症リスクが高いため注意しましょう。
脳梗塞になりやすい食べ物
脳梗塞になりやすい食べ物の例は、以下のとおりです。
| 理由 | 食品例 | |
| 乳製品 | 飽和脂肪酸が多く、LDLコレステロール値が上がりやすい | バター、マーガリン、チーズ |
| 加工肉 | 飽和脂肪酸が多く、LDLコレステロール値が上がりやすい | ハム、ベーコン、ソーセージ |
| お菓子・スイーツ | トランス脂肪酸が多く含まれるため | スナック菓子、ケーキ、クッキー |
| 漬物・干物 | 塩分が多く含まれており、生活習慣病のリスクが高まるため | 梅干し、漬物、干物 |
| アルコール類 | 過剰なアルコール摂取は、生活習慣病のリスクを高めるため | ビール、ワイン、日本酒 |
動物性脂肪やトランス脂肪酸を含む食品や、加工食品の多量摂取は、動脈硬化のリスクを高めます。アルコールの過剰摂取も脳梗塞の発症リスクを高めるため、過度な飲酒には注意が必要です。
脳梗塞を予防する食べ物を日常の食事に取り入れ、健康的な食事習慣をつくりましょう。
脳梗塞にならないための予防法
脳梗塞にならないためには、以下の3つの行動を心がけることが大切です。
乱れた食生活や運動不足が続くと、生活習慣病の発症リスクが高まり脳梗塞になりやすくなります。生活習慣を見直し、脳梗塞のリスク因子を減らしましょう。
生活習慣の改善
脳梗塞にならないために、生活習慣の改善が大切です。生活習慣を改善すると、高血圧や糖尿病などの生活習慣病の発症リスクを低減できます。
生活習慣を見直す際は、以下のポイントを確認しましょう。
- 栄養バランスが良い食事にする
- 過剰なアルコール摂取を控える
- 禁煙する・喫煙本数を減らす
- 適度に運動する
- ストレスを溜めない
ストレスや疲労を溜めずに、規則正しい生活を送れば、脳梗塞のリスク因子の生活習慣病を防げます。改善できる生活習慣から見直していくことが大切です。
食生活の改善
脳梗塞を予防するために、食生活を改善しましょう。食生活を改善すると、高血圧や動脈硬化の予防につながり、脳梗塞になりにくくなります。
脳梗塞の予防に効果的な食品は、以下のとおりです。
| 脳梗塞の予防に効果的な食品 | 理由 |
| トマト・トマトジュース | トマトに含まれるリコピンは、悪玉コレステロールの値を下げる働きがある |
| 魚類 | 魚類に含まれるEPAは、コレステロールや中性脂肪を減らす働きがある |
| オリーブオイル | オリーブオイルに含まれる一価不飽和脂肪酸は、コレステロールや中性脂肪を下げる働きがある |
| 緑黄色野菜・果物類 |
ミネラルやビタミンは、体の酸化を予防できる 食物繊維はコレステロールの排出を促す働きを持つ |
| ナッツ類 | ナッツに豊富に含まれるビタミンEは、抗酸化作用があり、悪玉コレステロールを減らす働きを持つ |
悪玉コレステロールや中性脂肪の値が下がると血圧も下がるため、脳梗塞の予防に効果的です。以下の動画では、脳梗塞の予防に効果的な食品について詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
過剰摂取を避け、栄養バランスを考えて日々の食事に上記の食品を取り入れましょう。
運動不足の解消
脳梗塞を発症しないためには、運動不足を解消することが重要です。運動不足を解消すると血行が促進され、生活習慣病のリスクを低減できたり、ストレスを発散できたりします。
脳梗塞の予防には、有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせて行うのが効果的です。以下の具体例を参考に、日々の生活に運動を取り入れましょう。
| 有酸素運動 |
|
| 筋力トレーニング |
|
厚生労働省は「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」※で、息が弾み汗をかく程度以上の運動を週60分以上、筋力トレーニングは週2~3日行うことを推奨しています。
参照:健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023|厚生労働省
運動する時間がない人は、家事や仕事などで積極的に体を動かしましょう。
脳梗塞になりやすい人に関するよくある質問
脳梗塞になりやすい人に関するよくある質問をまとめています。
性格や前兆を知ることで、脳梗塞のリスクを軽減できる可能性があるため、参考にしてください。
脳梗塞になりやすい性格は?
脳梗塞になりやすい性格は、ストレスを溜め込みやすい人です。
過度なストレスは自律神経の乱れを招き、高血圧や高血糖になることで動脈硬化を引き起こし、結果的に脳梗塞のリスクが高まります。
性格が脳梗塞の直接的な原因となることはありませんが、運動や趣味などストレス解消法を見つけることが大切です。
脳梗塞の前兆は?
脳梗塞の前兆は主に以下の症状が見受けられたとき、注意が必要です。
- 手足のしびれ
- 物が二重に見えるなど視野異常
- ろれつが回らない
- 言葉が出てこない
- めまいやふらつき
上記の症状は一時的なものであっても、脳へのダメージを受けている可能性があるため、医療機関を受診しましょう。
脳梗塞になりやすい人は再生医療をご検討ください
脳梗塞になりやすい人は、生活習慣病だけでなく遺伝的要因も関係するため、家族に脳梗塞の人がいる場合は注意が必要です。
該当する方は、食生活や運動などの生活習慣を見直すことが脳梗塞の予防につながります。
万が一脳梗塞を発症した場合の治療法として、再生医療という選択肢があります。
再生医療は、患者さまの幹細胞を採取・培養して数を増やし、投与することで脳細胞を再生・修復させる医療技術です。
損傷した脳細胞の改善によって、言語障害や麻痺などの後遺症の改善や、リハビリ効果を高める効果も期待できます。
再生医療について詳しく知りたい方は、当院リペアセルクリニックにご相談ください。

監修者
圓尾 知之
Tomoyuki Maruo
医師
略歴
2002年3月京都府立医科大学 医学部 医学科 卒業
2002年4月医師免許取得
2002年4月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2002年6月関西労災病院 脳神経外科 勤務
2003年6月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2003年12月大阪母子医療センター 脳神経外科 勤務
2004年6月大阪労災病院 脳神経外科 勤務
2005年11月大手前病院 脳神経外科 勤務
2007年12月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2012年3月大阪大学大学院 医学系研究科 修了(医学博士)
2012年4月大阪大学医学部 脳神経外科 特任助教
2014年4月大手前病院 脳神経外科 部長
キーワード検索
カテゴリ
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116