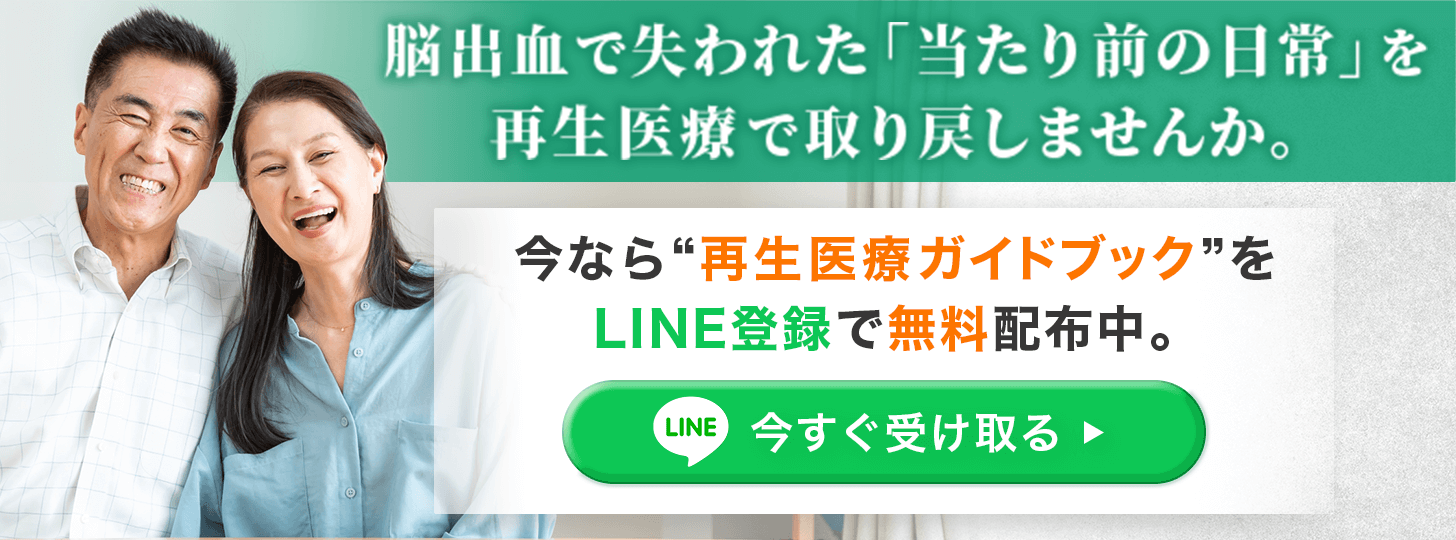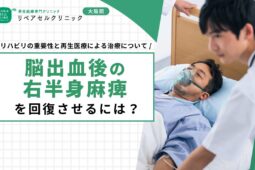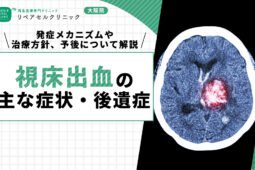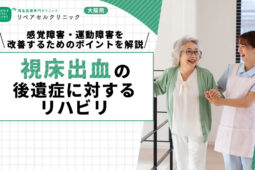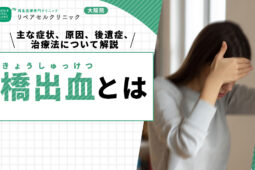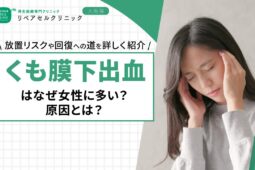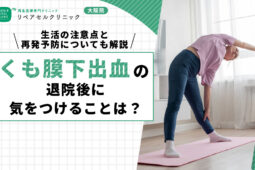- 頭部、その他疾患
- 脳出血
- くも膜下出血
もやもや病の初期症状|大人と子供で前兆は違う?注意すべき症状について解説
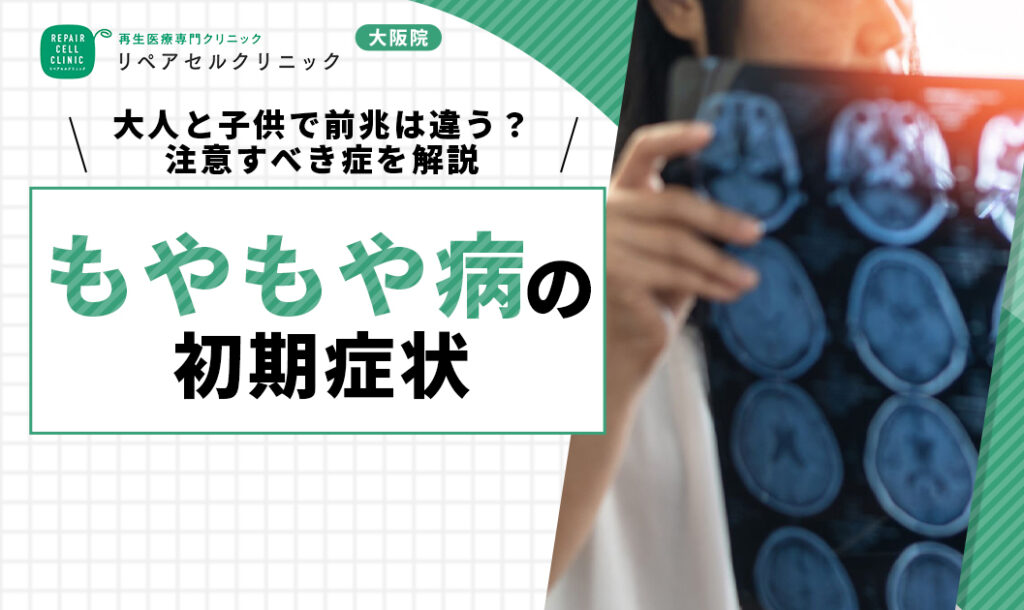
「ズキズキとした頭痛はもやもや病の初期症状?」
「手足のしびれを感じることがあり、重い病気か不安」
一時的な頭痛や手足のしびれなどの症状があり、すぐに治まるものの重い病気ではないか不安を感じる方も多いでしょう。
本記事では、もやもや病の見逃してはいけない初期症状や、大人と子供の症状の現れ方について解説します。
ご自身やご家族の症状と照らし合わせ、受診を検討する際の判断材料としてお役立てください。
目次
もやもや病の初期症状をタイプ別にチェック
もやもや病には、脳の血流が不足する「虚血型」と血管が破れる「出血型」の2つのタイプに分かれ、初期症状の現れ方が異なります。
本章では、もやもや病の2つのタイプとそれぞれの初期症状の特徴を解説します。
それぞれの特徴や、どのようなサインに注意を向けるべきかについて詳しく見ていきましょう。
もやもや病の種類とは
もやもや病は、症状の現れ方によって「虚血型」と「出血型」に分類され、それぞれ発症しやすい年代やメカニズムに違いがあります。
| タイプ | 発症メカニズム | 特徴・傾向 |
|---|---|---|
| 虚血型 | 血管が狭くなり、脳への血流が不足する | ・小児(特に5〜10歳)に多い ・一時的な麻痺や脱力感が主なサインとなる |
| 出血型 | 血管が破れることで脳内出血が起きる | ・成人(特に30〜50代)に多い ・突然の激しい頭痛や意識障害が起こるリスクがある |
もやもや病は、詰まった太い血管の代わりに細い血管(もやもや血管)が網目のように発達するのがこの病気の特徴です。
この細い血管が血液不足を補おうとして詰まるのが「虚血型」、耐えきれずに破れてしまうのが「出血型」とイメージすると分かりやすいでしょう。
また、もやもや病の有病率は男性に比べて女性が2倍多い※ため、女性に発症しやすい疾患といえます。
※出典:難病情報センター「もやもや病(指定難病22)」
虚血型もやもや病の初期症状
虚血型もやもや病の初期症状は、脳への血液供給が一時的に滞ることで起こる「一過性脳虚血発作(TIA)」が代表的です。
- ズキズキとした頭痛
- 手足のしびれや麻痺
- 言語障害
- 意識障害
- 痙攣発作
- 視覚障害
など
上記のような初期症状は一時的なものであることが多いため、見過ごしてしまう方も少なくありません。
運動後や入浴後など特定の状況下で繰り返し起こる場合や、徐々に持続時間が長くなったり、頻度が増えたりする場合は注意が必要です。
また、複数の初期症状が同時に現れる場合は、もやもや病の可能性を疑い、早期に医療機関を受診しましょう。
出血型もやもや病の初期症状
出血型もやもや病は、脳の血管が破裂して脳出血やくも膜下出血を起こすタイプで、緊急度の高い初期症状が見られます。
主な初期症状は、以下のとおりです。
- 突然の激しい頭痛
- 吐き気・嘔吐
- 意識レベルの変化
- 手足の麻痺
- 感覚障害
など
虚血型の初期症状を経て出血型に至るケースや、最初から出血型として発症するケースなどさまざまです。
激しい頭痛と同時に嘔吐や意識レベルの変化が見られる場合は、脳出血の可能性があるため、すぐに救急車を呼びましょう。
「いつもと違う頭痛」や「急激な体調変化」を感じた際は、ためらわずに医療機関に連絡することが予後に大きく影響します。
もやもや病の初期症状は大人と子供で違う?
もやもや病の初期症状は、大人と子供(発症する年代)で、現れやすい症状のタイプやリスクの傾向が異なります。
年代ごとの違いは、以下のとおりです。
| 比較項目 | 子供 | 大人 |
|---|---|---|
| 主なタイプ | 虚血型がほとんどで、出血型は稀 | 約30〜50%が出血型、残りが虚血型 |
| 主な初期症状 | ・過換気に見られる手足の麻痺 ・痙攣発作を繰り返す ・勉強中の集中力低下 ・軽度な頭痛 など |
・突然の激しい頭痛 ・吐き気、嘔吐 ・片側どちらかの手足の麻痺 ・言語障害 ・意識障害 など |
| 進行リスク | 脳の発達への影響、学習障害などにつながる可能性 | 脳出血による重篤な後遺症、生命に関わるリスク |
子供は脳の血流不足による虚血型の症状が中心ですが、大人は血管が破れる出血型の可能性も考慮しなければなりません。
子供の場合は「脳の成長を守るための早期発見」、大人の場合は「命を守るための出血予防」が、それぞれの治療や対応における大きなテーマとなります。
年齢に合わせたリスクを把握しておくことが、適切な対応への近道となるでしょう。
もやもや病の初期症状をチェックするポイント
もやもや病の早期発見のためには、初期症状そのものだけでなく、「どのような状況で症状が出たか」を観察することが大きな手がかりになります。
本章では、「日常生活」と「特定の状況下」の2つの場面で注意すべき症状について解説します。
日々の生活の中で見逃したくないサインを場面ごとに整理して確認していきましょう。
日常生活で注意すべき症状
まずは、特別な動作をしていない時でも現れる可能性のある、日常生活で注意すべき症状について解説します。
具体的には、以下のようなサインに注目しましょう。
| 注意すべき症状 | 具体的な症状の例 |
|---|---|
| 手足の動作異常 | ・食事中に突然お箸やスプーンを落とす ・字を書いている時にペンをうまく握れなくなる ・歩いている時に足を引きずる、カクンと力が抜ける |
| 感覚の異常 | ・手足がピリピリとしびれる感覚を訴える ・顔の片側に違和感がある |
| 言葉の異常 | ・急にろれつが回らなくなる ・言いたい言葉が出てこない、言葉が理解できていない様子がある |
脳の特定部位の血流が低下することで、上記のような身体の片側や言葉の機能に一時的なトラブルが生じることがあります。
これらの症状は「一過性脳虚血発作(TIA)」と呼ばれ、数分から数十分で消えてしまうことが多いため、疲れや気分の問題と誤解されがちです。
しかし、短時間でも「明らかに普段と違う」と感じた場合は、症状が出た時刻や持続時間をメモしておきましょう。
特定の状況下で起こる症状
もやもや病の初期症状は、特定の状況下で起こりやすい特徴があります。
主に以下のような状況下で初期症状が現れるか注目しましょう。
- マラソンなどの激しいスポーツ後
- 暑いお湯に浸かった後
- 深呼吸をした後
- 激しく泣いたり、笑った後
もやもや病(特に虚血型)には、呼吸が激しくなる動作が引き金となって症状が現れやすいという大きな特徴があります。
過呼吸によって血液中の二酸化炭素濃度が下がり、脳の血管が収縮して血流がさらに悪くなるためです。
上記のような「息を深く吸う、または吐く」ときに見られる症状は、単なる疲れではなく、もやもや病特有のサインである可能性があります。
こうした特定の動作と初期症状がセットで起こる場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
もやもや病の初期症状が疑われたら注意すべきこと
もやもや病の初期症状は、一時的なものが多いため、「疲れのせいだろう」と自己判断して様子を見てしまいがちです。
本章では、もやもや病が疑われる際に注意すべきポイントを解説します。
疑わしいサインに気づいた時点で、冷静かつ迅速に行動を起こすことが、将来的な脳梗塞や脳出血といった重篤なリスクを防ぐ大きな分かれ道となります。
ご自身やご家族の健康を守るために、これら2つのポイントを確認しましょう。
一過性の症状を見逃さない
もやもや病の初期症状が一時的なものであっても、「治ったから大丈夫」と安心せず、その時の状況を詳細に記録することが重要です。
初期症状が消失しても、脳内の血流不足という根本的な問題が解決したわけではないからです。
医師に正確な情報を伝え、診断の精度を高めるために、以下の項目をメモしましょう。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 日時 | いつ起こったか |
| 状況 | 何をしていた時か (例:スポーツをしていた、お風呂に入っていた) |
| 具体的な症状 | 身体のどこに、どのような変化があったか (例:右手が痺れた、言葉が出なかった) |
| 持続時間 | 症状がどれくらい続いて、どのように治まったか |
可能であれば、症状が出ている様子をスマートフォンなどで動画撮影しておくと、言葉で説明する以上に医師へ正確な状態を共有できます。
「些細なことかも」と思わずに、気づいた変化を積み重ねて記録することが、早期発見への貴重な手がかりとなります。
早期に医療機関を受診する
もやもや病が疑われる初期症状が現れたときは、迷わず脳神経外科や神経内科などの専門機関を受診しましょう。
進行性の病気ですが、早期に発見し、適切な管理や外科手術(バイパス手術など)を行うことで、脳梗塞や脳出血のリスクを大幅に下げられることが分かっています。
受診を検討する際は、以下の診療科が窓口となります。
| 項目 | 診療科 |
|---|---|
| 子供の場合 | 小児神経科、小児脳神経外科 |
| 大人の場合 | 脳神経外科、神経内科 |
MRIやMRA(磁気共鳴血管画像)、脳血管撮影といった検査であれば、脳血管の状態を詳しく調べられます。
まずは検査を受けてみることが、未来の生活を守るための賢明な選択といえるでしょう。
もやもや病の初期症状に関してよくある質問
もやもや病の初期症状について、多くの患者さまやご家族が抱く代表的な疑問に対して回答していきます。
正しい知識を持つことが、過度な不安を和らげ、前向きに治療に取り組むための支えとなるでしょう。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
もやもや病の初期症状を放っておくとどうなる?
もやもや病の初期症状を放置することで、将来的に重篤な脳卒中(脳梗塞や脳出血)を引き起こすリスクを高めることにつながります。
進行性の病気であり、時間の経過とともに症状が深刻化する傾向にあるためです。
しかし、初期症状は一過性のため、数分から数十分で治まることが多いため、放置されやすいです。
また、無症状であっても、年間10%未満の頻度で脳卒中のリスクが存在するため、定期的な検査を受けましょう。
重篤なリスクを回避するために、「症状が治まったから」と放置せず、早期に検査を受けることが重要です。
もやもや病の寿命は?
「もやもや病=寿命が短い」というわけではなく、適切な管理と治療を受ければ寿命への影響を大幅に抑えられます。
かつては脳出血による突然死のリスクなどが強調されることもありましたが、現在は診断技術や外科手術(バイパス手術)の手法が確立され、予後は大幅に改善しています。
長期的な見通しを良くするためには、以下の点がポイントとなります。
- 適切な時期の手術:脳梗塞や脳出血を起こす前に、血流を改善する手術を行う。
- 定期的な検診:症状が落ち着いていても、血管の状態を定期的にチェックする。
- 生活習慣の管理:高血圧や喫煙など、血管に負担をかけるリスク因子を避ける。
もやもや病と正しく向き合い、適切なコントロールを続けることが重要です。
もやもや病の原因はストレス?
ストレス自体がもやもや病を「発症させる直接の原因」ではありません。
もやもや病の根本的な原因はまだ完全には解明されていませんが、現在では「RNF213」と呼ばれる特定の感受性遺伝子が関与していることが分かっており、遺伝的要因が大きい※と考えられています。
※出典:難病情報センター「もやもや病(指定難病22)」
ただし、症状を引き起こすきっかけとして、過度なストレスや激しい感情の起伏が関わっている点は理解しておく必要があります。
また、もやもや病の診断後は発作を避けるために、過度なストレスや疲労を溜めない生活を心がけることが大切です。
もやもや病の初期症状は見逃さずに医療機関を受診しよう
もやもや病の初期症状は、一過性で数分から数十分で治まることが多いため、見逃されやすい特徴があります。
主な初期症状は、以下にまとめました。
| 虚血型 | 出血型 |
|---|---|
| ・ズキズキとした頭痛 ・手足のしびれや麻痺 ・言語障害 ・意識障害 ・痙攣発作 ・視覚障害 など |
・突然の激しい頭痛 ・吐き気・嘔吐 ・意識レベルの変化 ・手足の麻痺 ・感覚障害 など |
とくに出血型もやもや病の初期症状は、緊急性が高く、治療開始が遅れるほど予後に大きな影響を与えてしまいます。
上記のような初期症状が現れた場合は、早期に医療機関を受診しましょう。
出血型もやもや病によって「脳出血」や「くも膜下出血」を発症すると、重篤な後遺症が見られるケースが多いです。
近年の治療では、患者さまの細胞や血液を用いて損傷した脳細胞の修復・再生を促す再生医療が注目されています。
以下のページでは、再生医療によって脳出血後の運動機能や言語機能障害が改善した症例を紹介しているため、併せて参考にしてください。
>再生医療によって脳出血後の後遺症が改善した症例(80代男性)はこちら
「再生医療について詳しく知りたい」という方は、ぜひ当院リペアセルクリニックにご相談ください。

監修者
圓尾 知之
Tomoyuki Maruo
医師
略歴
2002年3月京都府立医科大学 医学部 医学科 卒業
2002年4月医師免許取得
2002年4月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2002年6月関西労災病院 脳神経外科 勤務
2003年6月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2003年12月大阪母子医療センター 脳神経外科 勤務
2004年6月大阪労災病院 脳神経外科 勤務
2005年11月大手前病院 脳神経外科 勤務
2007年12月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2012年3月大阪大学大学院 医学系研究科 修了(医学博士)
2012年4月大阪大学医学部 脳神経外科 特任助教
2014年4月大手前病院 脳神経外科 部長