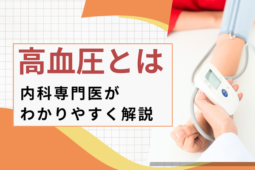- 脳梗塞
- 脳卒中
脳卒中のリスク管理方法は?急性期リハビリテーションにおける注意点を解説【医師監修】

「脳卒中の発症リスクをどうすれば管理できる?」
「再発を予防するためにできることは?」
上記のような疑問や不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
脳卒中は、ある日突然生活を一変させる可能性のある病気ですが、生活習慣の見直しと正しい知識でリスクを下げられます。
本記事では、脳卒中の主な危険因子である高血圧や糖尿病などのリスクを管理する方法を詳しく解説します。
- 脳卒中の主なリスクと管理方法
- 脳卒中の急性期リハビリのポイント
- 再発予防や後遺症改善の選択肢となる再生医療について
ご自身や大切なご家族の健康を守るため、ぜひ最後までご覧ください。
また、脳卒中のリスク管理・再発予防には、先端医療である再生医療による治療も選択肢の一つです。
当院リペアセルクリニックの公式LINEでは、損傷した脳細胞の改善にも期待できる再生医療に関する情報を配信しています。
「脳卒中の発症リスクを抑えたい」「将来的な不安がある」という方は、この機会に再生医療について確認してみてください。
目次
脳卒中の主なリスクと管理方法
脳卒中の発症や再発には、ご自身の努力で管理できる生活習慣病などの「危険因子」が隠れているケースがあります。
この章では、脳卒中を予防するうえで特に重要な危険因子と管理方法を取り上げます。
ご自身やご家族の健康を守るため、どのようなリスクがあり、どうすれば管理できるのかを確認していきましょう。
高血圧
高血圧は、脳卒中を引き起こす危険因子の1つです。
血圧が高い状態が続くと血管の壁に強い圧力がかかり、血管が弾力性を失って脆くなります。
この「動脈硬化」が、脳梗塞や脳出血の直接的な原因となります。
高血圧の主な対処法は、以下の通りです。
- 減塩を心がける(1日6g未満)
- 野菜や魚中心の食事に改善する
- ウォーキングなどの運動を習慣にする
- 飲酒量を控え、必ず禁煙する
- 医師から処方された薬を飲み続ける
高血圧は自覚症状がほとんどないため「サイレントキラー」とも呼ばれます。
そのため、家庭で血圧を測る習慣をつけ、ご自身の数値を把握することが管理の第一歩です。
脳卒中の治療ガイドラインでは、血圧を140/90mmHg未満、特定の条件に当てはまる方は130/80mmHg未満に抑えることが推奨※されています。
※出典:日本脳卒中学会「脳卒中治療ガイドライン2021〔改定2025〕」
また、以下の記事では、高血圧についてわかりやすく解説しているので、合わせてご覧ください。
糖尿病
糖尿病も脳卒中の重要な危険因子の一つです。
血糖値が高い状態が続き、全身の血管がダメージを受けることで動脈硬化が進行しやすくなるため、脳梗塞との関連が深いとされています。
糖尿病の主な対処法は、以下の通りです。
- 適切なカロリーと栄養バランスの食事
- 血糖コントロールを改善する運動療法
- 医師の処方に従った薬物療法
- 肥満を防ぐための体重管理
糖尿病の管理目標は、血糖値を安定させて合併症を防ぐことです。
初期段階では自覚症状が乏しいため、気づかないうちに病状が進行しているケースも少なくありません。
健康診断などで血糖値の異常を指摘された際は、放置せずに医療機関で相談しましょう。
脂質異常症
脂質異常症とは、血液中の悪玉(LDL)コレステロールや中性脂肪が多すぎる状態です。
自覚症状がないまま動脈硬化を進行させ、脳卒中の中でも「アテローム血栓性脳梗塞」のリスクを高める要因になります。
脂質異常症の主な対処法は、以下の通りです。
- 動物性脂肪やトランス脂肪酸の摂取を控える
- 食繊維や魚(EPA・DHA)を積極的に摂る
- コレステロール値を改善する有酸素運動
- 動脈硬化を悪化させる喫煙をやめる
- 必要に応じて脂質異常症治療薬を服用
血液中の悪玉コレステロールが過剰になると血管の壁にプラークという塊を作り、血管が狭くなることで血流が悪化します。
プラークが破れると血栓が脳の血管を詰まらせ、脳梗塞を引き起こす可能性につながります。
脂質異常症の管理には、健康診断などでの定期的な血液検査が欠かせません。
生活習慣の改善で数値が良くならない場合は、医師の判断で薬物療法が行われます。
心房細動(不整脈)
心房細動は、心臓が不規則にけいれんするように震える不整脈の一種です。
心臓の中に血の塊(血栓)ができやすくなるため、重症化しやすい「心原性脳塞栓症」の原因となります。
心房細動の主な対処法は、以下の通りです。
- 血栓を防ぐ抗凝固薬の服用
- 心拍数を整えるための薬物治療
- 不整脈の原因を焼くカテーテル治療
- 高血圧や飲酒など生活習慣の管理
心臓でできた血栓が血流に乗って脳の太い血管を詰まらせると、広範囲の脳組織がダメージを受け、深刻な後遺症につながる可能性があります。
動悸・息切れ・めまいといった症状は、心房細動のサインかもしれません。
上記のような症状を感じたら放置せずに医療機関を受診し、診断に基づいた適切な治療を開始することが重要です。
嗜好品の制限
喫煙と過度な飲酒は、それぞれが脳卒中の危険因子であるだけでなく、高血圧や脂質異常症といった他の生活習慣病を悪化させる要因にもなります。
脳卒中のリスク管理を考えるうえで、嗜好品の制限は避けて通れません。
| 要因 | メカニズム・作用 |
|---|---|
| タバコ (ニコチンなどの有害物質) |
・血管を収縮させ血圧が上昇する ・血液の粘度が増大する(血液がドロドロになる) ・血管内壁を傷つけ動脈硬化を促進する |
| 長期間の多量飲酒 | ・持続的に高血圧を引き起こす ・心房細動を誘発する可能性 |
脳卒中予防において、禁煙は効果的な対策の一つです。
ご自身の力で禁煙するのが難しい場合は、禁煙外来で専門家の支援を受けることをおすすめします。
飲酒は、1日あたりの純アルコール量で約20g(ビール中瓶1本程度)の適量※を守りましょう。
※出典:厚生労働省「アルコール」
脳卒中のリスク管理方法と合わせて確認したい予防十か条
脳卒中を予防するためには日々の生活を見直し、危険因子に関する正しい知識を持つことが大切です。
具体的な行動指針として、公益社団法人日本脳卒中協会では「脳卒中予防十か条」を提唱しています。
ご自身の生活習慣と照らし合わせながら、一つひとつ確認してみてください。
| 第1条 | 手始めに 高血圧から 治しましょう |
| 第2条 | 糖尿病 放っておいたら 悔い残る |
| 第3条 | 不整脈 見つかり次第 すぐ受診 |
| 第4条 | 予防には たばこを止める 意志を持て |
| 第5条 | 飲むならば なるべく少なく アルコール |
| 第6条 | 高すぎる コレステロールも 見逃すな |
| 第7条 | お食事の 塩分・脂肪 控えめに |
| 第8条 | 体力に 合った運動 続けよう |
| 第9条 | 万病の 引き金になる 太りすぎ |
| 第10条 | 脳卒中 起きたらすぐに 病院へ |
※出典:公益社団法人 日本脳卒中協会
上記の十か条は、脳卒中の主要な危険因子への対策から、万が一発症してしまった際の対応を分かりやすくまとめられています。
第1条から第3条は、脳卒中の3大危険因子である「高血圧」「糖尿病」「不整脈(心房細動)」の管理がいかに重要であるかを示しています。
中でも高血圧は大きな危険因子であり、血圧を適切にコントロールすることが脳卒中予防の重要なポイントです。
また、第5条のアルコールに関する標語は、「少量のお酒なら健康に良い」という考え方が新たな研究で否定されている背景から、2025年に内容が変更されました。
新たな飲酒は量に関わらずリスクを伴うため「飲むのであれば、できる限り少量に」とされています。
第10条では、脳卒中を疑う症状が現れた際は、躊躇せずに救急車を呼び、一刻も早く専門的な治療を受けることの重要性を伝えています。
脳卒中の急性期リハビリテーションにおけるリスク管理
万が一、脳卒中を発症してしまった場合、その直後の対応が回復を大きく左右します。
「急性期」とは、一般的に発症から病状が安定するまでの数週間から1ヶ月程度の期間のことです。
ここでは、脳卒中の急性期リハビリテーションにおけるリスク管理について解説します。
急性期は脳のダメージが広がりやすく、血圧や意識レベルといった全身状態も変動しやすいデリケートなタイミングです。
そのため、専門チームが密に連携し、患者様の全身状態を常に確認しながら、治療とリハビリを慎重に進めていく必要があります。
早期離床してリハビリを開始する
脳卒中のリハビリにおいて、徹底したリスク管理のもと、可能な限り早くリハビリを始める「早期離床」が推奨されています。
- 目的:寝たきりによる「廃用症候群」の予防
- 主な合併症:筋力低下や関節の拘縮、肺炎、血栓
- リハビリ内容:ベッド上の運動から始める段階的な訓練
早期から積極的に体を動かすことが障害を抑え、その後の回復を促すために重要です。
再発や合併症を予防する
脳卒中の急性期は、再発のリスクが高い時期でもあるため、リハビリは医学的な治療を妨げないように厳重な管理下で行う必要があります。
また、食べ物が気管に入ることで起こる「誤嚥性肺炎」や、足に血栓ができる「深部静脈血栓症」などの合併症にも注意が必要です。
これらの合併症は生命に関わるだけでなく、その後のリハビリの進行を大きく遅らせる原因となります。
急性期のリハビリは、機能回復を目指すだけでなく、上記のような危険な合併症を防ぐという意味でも大切です。
以下の記事では、脳梗塞の再発リスクについて詳しく解説しているので、合わせて参考にしてください。
脳卒中のリスク管理についてよくある質問
ここでは、脳卒中のリスク管理についてよくある質問に回答していきます。
それぞれ詳しく解説します。
脳卒中の危険因子を管理するにはどうすればいい?
脳卒中の危険因子の管理は「生活習慣の見直し」と「適切な治療の継続」が基本です。
塩分を控えた食事や定期的な運動、禁煙を心がけましょう。
それに加えて、定期健診でご自身の体の状態を把握し、異常があれば必ず医師に相談してください。
処方された薬を自己判断でやめないことも、脳卒中予防では重要なポイントです。
脳卒中を防ぐ方法はある?
高血圧をはじめとする生活習慣病を管理することで、多く脳卒中を防ぐことが可能とされます。
とくに脳卒中の大きなリスクとなる高血圧を防ぐためにも血圧管理を徹底することが重要です。
また、健康的な食事や適度な運動習慣といった生活習慣の改善は、複数の危険因子に同時に良い影響を与えます。
症状がないうちからリスクを早期発見し、対策を講じることが発症を防ぐためのポイントといえるでしょう。
脳卒中で早期離床を促すのはなぜ?
脳卒中で早期離床を促すのは、「二次的合併症」を防ぎ、「脳機能回復の促進」のためです。
寝たきりの状態は回復を妨げる多くの問題を引き起こし、筋力低下や肺炎、血栓などの二次的合併症の可能性が高くなります。
また、脳機能の回復を促進する目的でも早期離床は重要です。
早期からリハビリを始めることで脳や身体機能の改善が早まり、より良い状態で退院できる可能性が高まります。
脳卒中のリスク管理と合わせて再生医療をご検討ください
本記事では、脳卒中の発症および再発予防におけるリスク管理の重要性について解説しました。
高血圧や糖尿病といった危険因子を日々の生活で管理し、健康的な習慣を続けることが基本となります。
これらに加え、再発予防の新たな選択肢として「再生医療」をご検討ください。
再生医療は、患者さまの脂肪から幹細胞を採取・培養し、体内に戻すことで損傷した組織や身体機能の再生・修復を促す治療法です。
また、損傷した脳機能の改善を促し、後遺症である麻痺などの症状軽減が期待できる治療法として注目されています。
脳卒中のリスク管理や再発予防にお悩みの方は、ぜひ一度当院リペアセルクリニックへご相談ください。

監修者
圓尾 知之
Tomoyuki Maruo
医師
略歴
2002年3月京都府立医科大学 医学部 医学科 卒業
2002年4月医師免許取得
2002年4月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2002年6月関西労災病院 脳神経外科 勤務
2003年6月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2003年12月大阪母子医療センター 脳神経外科 勤務
2004年6月大阪労災病院 脳神経外科 勤務
2005年11月大手前病院 脳神経外科 勤務
2007年12月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2012年3月大阪大学大学院 医学系研究科 修了(医学博士)
2012年4月大阪大学医学部 脳神経外科 特任助教
2014年4月大手前病院 脳神経外科 部長