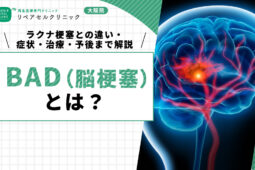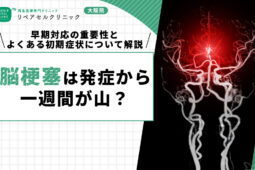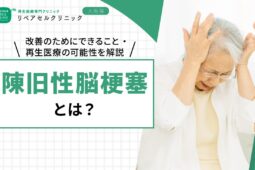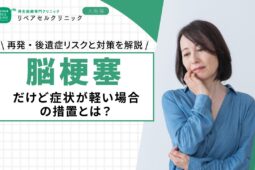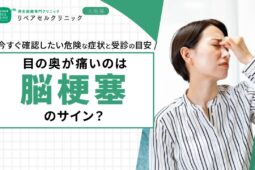- 脳梗塞
- 再生治療
閃輝暗点が脳梗塞である確率は?発症リスクを詳しく紹介

閃輝暗点(せんきあんてん)の症状があり脳梗塞の確率があると不安に思われていませんか?
「閃輝暗点」とは突然視界の端にギザギザした光が現れ、20〜30分ほどで消える症状です。
多くは片頭痛の前触れとして起こりますが、なかには「脳梗塞のサインでは?」と不安になる方もいるのではないでしょうか。
結論から言えば、閃輝暗点そのものが脳梗塞に直結する確率は極めて低いとされています。
しかし、ピルの内服や喫煙、家族の脳梗塞歴などがある場合は、注意が必要です。
この記事では、科学的根拠に基づく見分け方や受診の目安などを解説します。
目次
結論として閃輝暗点が脳梗塞である確率は条件次第
結論から言えば、閃輝暗点そのものが脳梗塞である確率は低いでしょう。
なぜなら、閃輝暗点は脳の機能変化として現れる一過性の神経現象で、脳組織の損傷や血流遮断は伴わないためです。
一方で脳梗塞では脳の血管が障害されることにより、脳や脳神経の損傷を伴います。
その結果として視野の欠けや閃輝暗点のような症状が見られることが特徴です。
とはいえ閃輝暗点=脳梗塞といえるだけの根拠はなく、閃輝暗点だけでは脳梗塞とは言えないでしょう。
ただし、閃輝暗点を伴う片頭痛を持つ人では、脳梗塞を起こすリスクが約2倍になると報告※されています。
※出典:British Medical Journal「Risk of ischemic stroke in people with migraine: systematic review and meta-analysis of observational studies」
これは「相対的な増加」を示すもので、たとえば一般の若年層で脳梗塞の確率が0.1%なら、2倍でも0.2%と依然として低い水準です。
つまり、「2倍=危険」ではなく、「もともと低い確率の中で一部条件に注意が必要」と言えます。
このように閃輝暗点=脳梗塞とは言えませんが、気になる場合は専門医に相談してください。
閃輝暗点と脳梗塞を見分けるポイント
閃輝暗点と脳梗塞を見分けるポイントとして、以下の観点から解説します。
この項ではそれぞれの違いがわかるように解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。
閃輝暗点の典型的な特徴
閃輝暗点の典型的な特徴※は、以下のとおりです。
| 閃輝暗点の典型的な特徴 | |
|---|---|
| 症状 |
・ジグザグ・ギザギザ(鋸歯状)の光や波打つような閃光が見える |
| 随伴症状 | ・拍動性の頭痛、吐き気、光過敏などの片頭痛症状が続くことが多い |
| 進行性・可塑性 |
・視野の一部から始まり、ゆっくりと広がっていく |
※出典:日本頭痛学会「国際頭痛分類第3版(ICHD-3)日本語版」
このように、閃輝暗点はゆっくりと進行する一過性の症状です。
少しずつ症状が進行する特徴があり、突然症状が強く出る脳梗塞とは違うことがわかります。
脳梗塞の特徴
一方で、脳梗塞には以下のような特徴※があります。
| 脳梗塞の特徴 | |
|---|---|
| 症状 |
・片側の手足や顔の麻痺 |
| 随伴症状 |
・意識障害や見当識障害 |
| 進行性・可塑性 |
・発症直後から最大の症状が出現することが多い |
※出典:日本脳卒中学会「脳卒中治療ガイドライン2021[改訂2025]」
このように、脳梗塞は発症直後から症状が強く、早く治療しないと症状の回復が見込めない特徴があります。
これらの症状が見られる場合には、可能な限り速やかに受診してください。
自分の発症リスクを把握する「年齢・性別・習慣」別の見方
閃輝暗点の発症リスクを把握するために、「年齢・性別・習慣」別の見方をまとめました。
もし自身の閃輝暗点リスクが気になるという方は、最後までご覧になられることをおすすめします。
若年層でも油断は禁物
若年層でも油断は禁物です。
健康に見えて実は一時的な血管のけいれんによって閃輝暗点が現れることがあります。
特に、睡眠不足・ストレス・ホルモンバランスの変化は、脳血流の一時的な変動を引き起こしやすい要因です。
これらが重なると、脳の視覚野が過敏に反応し、ギザギザした光や視野の欠けとして感じられることがあります。
若年層であっても、こうした誘因が繰り返される場合は放置せず、生活リズムの見直しや医療機関での相談が大切です。
女性特有のリスク要因
女性特有のリスク要因として、ホルモンの影響や避妊薬の使用が閃輝暗点のリスクに関係することがあります。
特に、月経前後や排卵期など女性ホルモンが急激に変化するタイミングでは注意が必要です。
さらに、低用量ピルの使用により、ホルモン変動が人工的に変化することで誘発される場合もあります。
加えて、喫煙者は血管の収縮反応が強まり、症状が出やすくなるため注意が必要です。
発作を繰り返す場合は、医師と相談してホルモンバランスや避妊薬の使用方法を相談した方が良いでしょう。
生活習慣と血管リスク
閃輝暗点は、生活習慣や血管リスクも考慮しなければいけません。
閃輝暗点は脳の血管が一時的にけいれんしたり、血流が変化することで起こることがあります。
そのため、禁煙・減塩・適度な運動といった生活習慣で血管環境を整えることが発症予防につながるでしょう。
特にストレスや睡眠不足、カフェインの過剰摂取は発症を助長するため、生活リズムの見直しも発症予防に期待できます。
もし「閃輝暗点の頻度が増えた」「発作が以前より重くなった」と感じる場合は、脳血流の変化が関与している可能性があるため、神経内科での脳血流検査を検討してみてください。
受診・専門機関への相談の目安
閃輝暗点の受診・専門機関への相談の目安は以下のとおりです。
- 初めての発作で強い不安を感じる
- 視覚異常が長引く・頻繁に繰り返す
- 神経症状(しびれ・言語障害など)が伴う
初めての発作で強い不安を感じた場合や、視覚異常が長引く・頻繁に繰り返すときには、脳血流の異常がないか確認することが重要です。
また、手足のしびれ・言葉が出にくい・力が入りにくいといった神経症状を伴う場合は、一過性脳虚血発作や脳梗塞の初期症状の可能性もあります。
こうした場合は自己判断せず、神経内科・脳神経外科・頭痛外来での検査を早めに受けましょう。
慢性的な血流不全や後遺症に対する新たな再生医療という可能性
閃輝暗点は前述のとおり、血流不全などによって生じることがあります。
血管の健康を保つためには、禁煙・減塩・適度な運動などの生活改善が基本です。
しかし、動脈硬化などが原因の場合には、これだけでは十分でないこともあります。
そのようなケースで注目されているのが、自己の細胞を用いて血管や神経の修復を促す「再生医療」です。
再生医療とは、脳梗塞や虚血性疾患による慢性的な血流障害や回復の遅れに対する新しい医療技術として研究が進んでいます。
当院リペアセルクリニック大阪院では、医学的根拠に基づき、安全性を最優先した評価と適応判断のもと、こうした再生医療の可能性を追求しています。
興味のある方は、ぜひ一度ご相談ください。
脳卒中のお悩みに対する新しい治療法があります。
閃輝暗点が突然・長時間続く場合は、早めの受診が重要
閃輝暗点が脳梗塞である確率について解説しました。
ポイントは以下のとおりです。
- 閃輝暗点が脳梗塞である確率は低い
- 閃輝暗点を伴う片頭痛は相対的に脳梗塞リスクが上がる
- 喫煙・運動・ピルなどの服薬・生活習慣を整えることが大切
閃輝暗点は多くの場合、良性の片頭痛の前兆として現れ、時間が経てば自然に消えることがほとんどです。
前述のとおり、閃輝暗点を伴う片頭痛の人は脳梗塞リスクが相対的に上昇すると報告されていますが、実際の発症率は条件次第で低いことも分かっています。
しかし、突然の発症・長時間の持続・手足のしびれや言葉のもつれなど神経症状を伴う場合は、脳梗塞ある可能性が否定できません。
だからこそこの記事で紹介したリスク要因を把握し、早めに受診することが発症予防につながるでしょう。
なお、当院リペアセルクリニック大阪院では脳梗塞に対する再生医療も実施しています。
過去には効果があった症例も経験していますので、興味がある方はお気軽にお問い合わせください。

監修者
圓尾 知之
Tomoyuki Maruo
医師
略歴
2002年3月京都府立医科大学 医学部 医学科 卒業
2002年4月医師免許取得
2002年4月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2002年6月関西労災病院 脳神経外科 勤務
2003年6月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2003年12月大阪母子医療センター 脳神経外科 勤務
2004年6月大阪労災病院 脳神経外科 勤務
2005年11月大手前病院 脳神経外科 勤務
2007年12月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2012年3月大阪大学大学院 医学系研究科 修了(医学博士)
2012年4月大阪大学医学部 脳神経外科 特任助教
2014年4月大手前病院 脳神経外科 部長