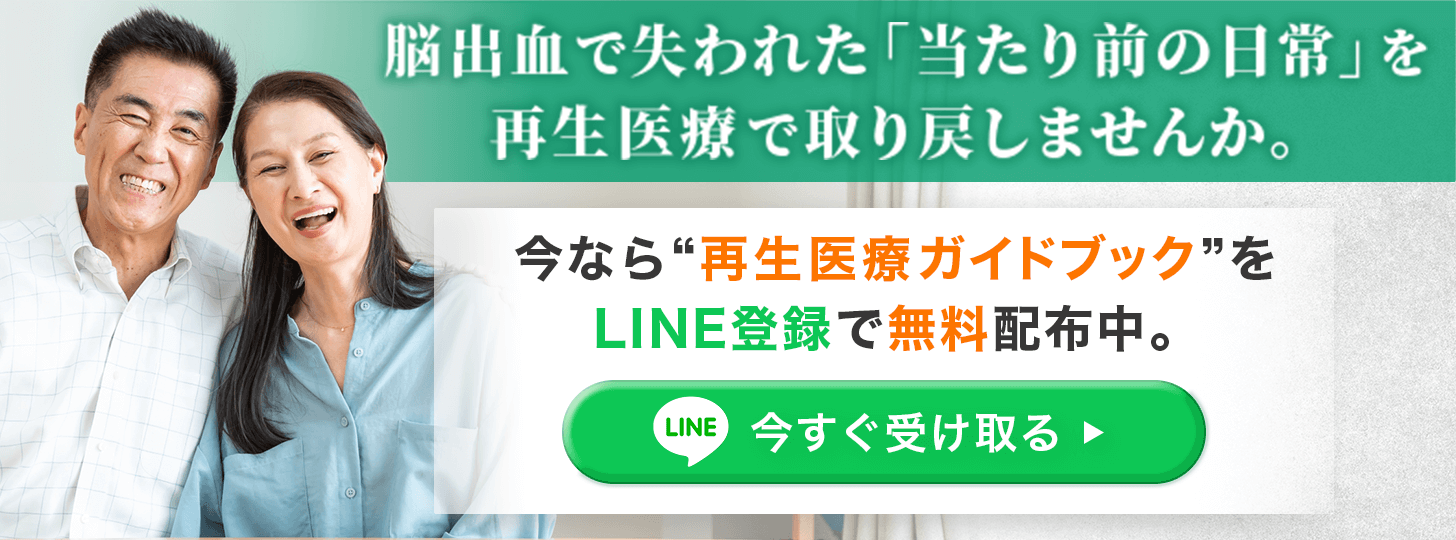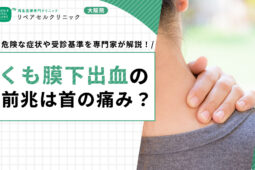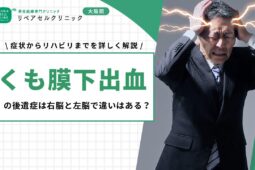- 脳卒中
- 頭部
- くも膜下出血
くも膜下出血の10年後の生存率は?再発率についても医師が解説
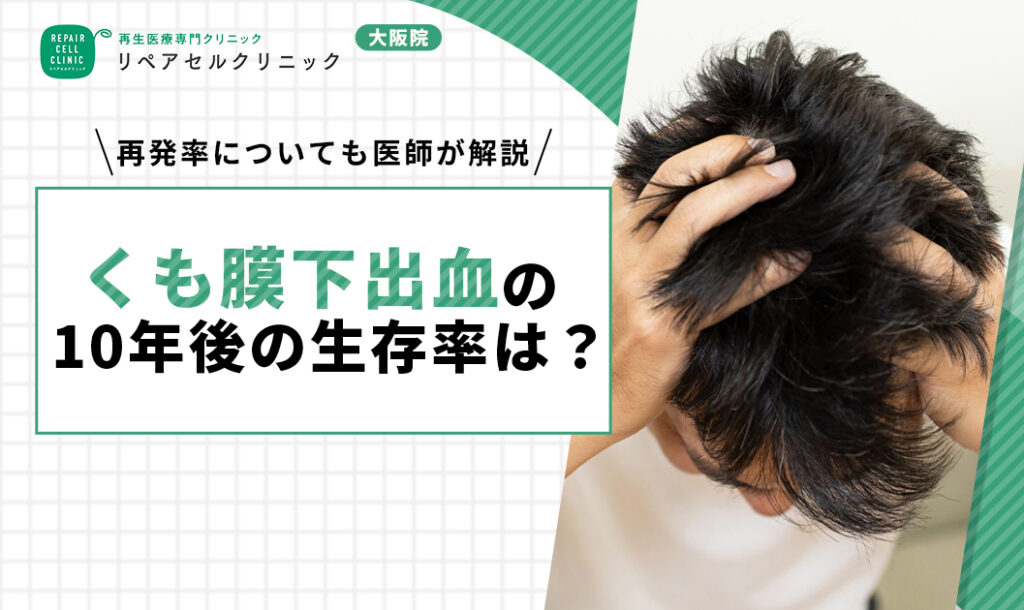
くも膜下出血とは、脳の表面を覆う膜(くも膜)の下で出血が起こる病気で、突然の激しい頭痛で発症します。
命に関わる危険性が高く、発症後の後遺症も心配される疾患です。
この記事では、くも膜下出血の10年後の生存率や、予後を左右する要因、再発リスクについて解説します。
くも膜下出血の予後について正しく理解することで、適切な治療選択や生活管理につなげられます。
また、現在当院(リペアセルクリニック)では「手術なしで根本的な改善が期待できる」再生医療に関する情報をLINEで発信しております。
くも膜下出血の後遺症に対する治療選択肢として、脳卒中に関する改善症例も紹介しておりますので、ぜひ登録してください。
目次
くも膜下出血の10年後の生存率は「重症度」と「治療の早さ」で変わる
くも膜下出血の10年後の生存率は、発症時の重症度と治療のタイミングによって大きく変わります。
発症直後の死亡率は約30%と非常に高く、医療機関到着前に亡くなるケースも少なくありません。
しかし、早期に適切な治療を受けた場合、10年後の生存率はおよそ50〜60%程度に改善するとされています。
生存率を左右する主な要素は以下の3つです。
- くも膜下出血の重症度(グレード1〜5で分類され、グレードが高いほど予後は厳しくなる)
- 搬送・手術のスピード(発症から治療開始までの時間が短いほど、脳へのダメージを最小限に抑えられる)
- 合併症の有無(脳血管攣縮や水頭症などが起こると予後に影響する)
これらの要素を総合的に判断し、患者さま一人ひとりの状態に応じた適切な治療を行うことが、長期的な予後の改善につながります。
くも膜下出血の予後を左右する要因【10年後の生活にも影響】
くも膜下出血の予後は、以下のさまざまな要因が複雑に関係しています。
これらの要因を理解することで、10年後の生活をより良くするための対策を立てられます。
発症時の年齢|高齢になるほど回復率が低下しやすい
発症時の年齢は、予後に大きく影響する要因の一つです。
一般的に、若い方ほど回復力が高く、リハビリの効果も出やすい傾向にあります。
高齢者の場合、以下のような理由で回復に時間がかかりやすくなります。
- 血管がもろくなっている
- 高血圧や糖尿病などの他の病気を抱えている
- 体力や筋力が低下している
- 神経の回復力が若年層に比べて弱い
ただし、高齢者でも適切な治療とリハビリを継続することで、日常生活に戻れる方もいらっしゃいます。
年齢だけで予後を判断するのではなく、総合的な健康状態を考慮することが大切です。
出血の場所と量|脳のどの部位で出血したかが予後を左右する
出血した部位や量は、その後の回復に大きく影響します。。
とくに注意が必要なのは、脳幹(呼吸や意識をコントロールする生命維持に不可欠な領域)周辺での出血です。
この部位で出血が起こると、重度の意識障害や深刻な神経後遺症が残るリスクが高まります。
また、出血が広範囲に広がるケースでは、脳全体が圧迫を受けるため、運動機能や言語機能など多岐にわたる障害が生じる可能性があります。
出血量が多いほど、こうしたダメージは深刻です。
発症から治療までの時間|早期手術が後遺症リスクを減らす
くも膜下出血は時間との勝負です。
発症から治療までの時間が長引くと、次のようなリスクが高まります。
- 再出血のリスク(最初の出血から数時間〜数日以内に起こりやすい)
- 脳へのダメージが拡大する
- 合併症が発生しやすくなる
- 後遺症が重くなる可能性が高まる
突然の激しい頭痛や、吐き気、意識障害などの症状が現れた場合は、すぐに救急車を呼びましょう。
一刻も早い治療開始が、命と予後を守ります。
合併症の有無|脳血管攣縮や水頭症の発生が回復に影響
くも膜下出血の後に起こる合併症は、予後に大きな影響を与えます。
代表的な合併症として、脳血管攣縮、水頭症、けいれん発作などがあります。
| 合併症 | 内容 |
|---|---|
| 脳血管攣縮 | 出血後3〜14日頃に起こりやすく、脳の血管が縮んで血流が悪くなります。脳梗塞を引き起こすリスクがあり、後遺症や再出血の可能性を高めます。 |
| 水頭症 | 脳の中を流れる髄液が正常に吸収されず、脳の中にたまってしまう状態です。頭痛や意識障害、歩行困難などの症状が現れます。 |
| けいれん発作 | 脳の損傷により、異常な電気信号が発生してけいれんが起こることがあります。薬でコントロールできるケースが多いです。 |
入院中だけでなく、退院後も定期的な受診を続けることで合併症の早期発見につながります。
くも膜下出血の再発率|後遺症なしでも再発するリスクがある
くも膜下出血を一度経験した方は、たとえ後遺症がなくても再発のリスクがあります。
再発を防ぐために、以下のポイントに注意しましょう。
- 血圧を適切にコントロールする(家庭で毎日測定し、記録する)
- 処方された薬は指示通りに服用する
- 定期的に脳の検査を受ける
- 禁煙する
- 過度な飲酒を避ける
- 塩分を控えた食事を心がける
- ストレスをためない生活を送る
- 激しい運動や力仕事は医師に相談してから行う
とくに高血圧は、くも膜下出血の大きな危険因子です。
退院後も血圧管理を継続し、主治医の指示に従って定期的に受診することが、再発予防につながります。
適切な治療と生活管理で、くも膜下出血の長期予後の改善を目指そう
くも膜下出血は重篤な疾患ですが、発見のタイミングと早期の治療によって、予後が大きく変わる可能性があります。
適切な治療を受け、退院後も生活習慣を見直すことで、長期的な予後の改善を目指せます。
現在、くも膜下出血の後遺症に悩まされている方には、再生医療も選択肢の一つです。
再生医療とは、患者さま自身の細胞を使って、傷ついた組織の再生を促す医療技術です。
当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療についての詳細や実際に治療を行った方の症例を紹介しているので、ぜひご覧ください。
くも膜下出血の生存率に関するよくある質問
くも膜下出血の生存率に関するよくある質問を紹介します。
退院後の生活や回復に関する不安を解消しましょう。
くも膜下出血の退院後はどんなことに気をつければいい?
くも膜下出血の退院後は、再発予防のため以下の点に気を付けましょう。
- 毎日血圧を測る
- 処方された薬を指示通りに服用する
- 禁煙する
- 飲酒は適量に抑える
- 塩分を控えた食事を心がける
- 規則正しい生活を送る
- ストレスをためない
体調に変化があった場合(激しい頭痛、手足のしびれ、ろれつが回らないなど)は、すぐに医師に相談してください。
早期発見・早期治療が、再発予防につながります。
くも膜下出血で意識不明の場合の回復時期は?
くも膜下出血で意識不明になった場合、回復時期は出血の重症度や脳のダメージの程度によって異なります。
軽度から中等度の場合は数日から数週間で意識が回復することがありますが、重度の意識障害(昏睡状態)の場合、回復までに数か月以上かかることもあります。
意識回復に影響する要因は次のとおりです。
| 要因 | 内容 |
|---|---|
| 重症度 | 発症時の意識レベルが低いほど、回復に時間がかかります。 |
| 治療のタイミング | 発症から手術までの時間が短いほど、回復の可能性が高まります。 |
| 合併症 | 脳血管攣縮や水頭症などの合併症が起こると、回復が遅れることがあります。 |
| 年齢 | 若い方ほど、神経の回復力が高い傾向にあります。 |
意識が戻った後も、リハビリを継続することが重要です。
言語療法、理学療法、作業療法など、さまざまなリハビリを組み合わせることで、日常生活への復帰を目指せます。

監修者
圓尾 知之
Tomoyuki Maruo
医師
略歴
2002年3月京都府立医科大学 医学部 医学科 卒業
2002年4月医師免許取得
2002年4月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2002年6月関西労災病院 脳神経外科 勤務
2003年6月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2003年12月大阪母子医療センター 脳神経外科 勤務
2004年6月大阪労災病院 脳神経外科 勤務
2005年11月大手前病院 脳神経外科 勤務
2007年12月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2012年3月大阪大学大学院 医学系研究科 修了(医学博士)
2012年4月大阪大学医学部 脳神経外科 特任助教
2014年4月大手前病院 脳神経外科 部長
あわせて読みたいトピックス
-

脳卒中における二木の予後予測とは|回復期リハビリテーションの重要性と注意点を解説
-
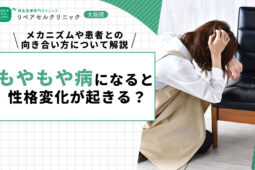
もやもや病になると性格変化が起きる?メカニズムや患者との向き合い方について解説
-

くも膜下出血は後遺症がなくても再発するリスクがある!注意点を解説
-

橋梗塞の症状とリハビリの進め方|具体的なプログラムとポイントについて解説
-

脳出血の看護ケア|在宅でも家族ができることや注意点・ポイントについて解説
-

脳出血の入院期間|年齢別・重症度別の違い、入院費用について解説【医師監修】
-

高次脳機能障害の回復事例を紹介!経過や治療・リハビリが大切な理由も解説
-

高次脳機能障害患者の家族が抱えるストレスとは?つらさの理由と無理をしない接し方を紹介