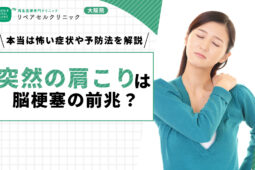- 脳梗塞
- 脳卒中
- 頭部
脳梗塞による記憶障害の種類と原因は?リハビリ内容についても解説

脳梗塞を経験した方やそのご家族にとって、記憶障害は日常生活に大きな影響を及ぼす深刻な問題です。
突然、大切な過去を思い出せなくなったり、日々の出来事を忘れてしまったりする状況に直面すると、困惑や不安を抱える方が多いでしょう。
「記憶障害はどうして起こるのか」「改善する方法はあるのか」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、脳梗塞により引き起こされる記憶障害の種類や症状、原因について詳しく解説します。
また、効果的なリハビリテーションの方法や社会的支援の活用方法についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
脳梗塞による記憶障害の種類と症状
脳梗塞によって脳への血流が遮断されると、記憶障害を引き起こします。その症状は、影響を受けた脳の部位や損傷の程度によってさまざまです。
ここでは5種類の記憶障害と症状について紹介します。
記憶障害の症状は、患者の日常生活や対人関係に影響を及ぼすため、それぞれの特徴を理解しておくのが大切です。
短期記憶障害
短期記憶障害とは、新しい情報を短期間だけ保持する能力が低下して、数秒から数分間の記憶を保持するのが難しい状態です。
- 今日の日付や曜日が思い出せない
- 食事をしたことや友人との会話を覚えていない
- 物の置き場所を頻繁に忘れる
- 簡単な計算を頭の中で行うのが難しくなる
- 簡単な指示や手順を覚えられない
短期記憶障害は、日常生活で必要な動作や作業に大きな影響を及ぼし、さまざまな支障を引き起こす原因となります。
長期記憶障害
長期記憶障害は、数日~数週間、数十年で覚えた情報や出来事を思い出すことが難しくなる状態です。
- 過去の記憶が思い出せなくなる
- 記憶していた内容が時系列で整理できなくなる
- 新しく得た情報を長期的に記憶するのが難しい
長期記憶障害は、過去の経験や知識を思い出すことが難しくなるため、日常生活や人間関係に影響を及ぼすことがあります。
エピソード記憶障害
エピソード記憶障害は、過去に体験したエピソードを思い出すのが難しくなる状態です。
- 家族や友人との旅行で体験した出来事が思い出せない
- 過去に働いていた職場での仕事内容を思い出せない
- 食事したことを忘れてしまう
自身が体験した内容に関しての記憶が一部、あるいはエピソードが全体的に思い出せなくなってしまいます。出来事がいつ、どこで、何が起こったのか、文脈的な情報を含む記憶が失われるのが特徴です。
手続き記憶障害
手続き記憶障害は、体で覚えた動作や技能を忘れてしまう状態です。
- 車や自転車の乗り方を思い出せない
- 料理で食材の切り方や包丁の使い方がわからない
- パソコンのキーボードが打てなくなる
主に頭でハッキリ考えずともできていた、習慣的な行動に支障をきたします。今まで意識せずに行っていた動作ができなくなり、日常生活で大きなストレスや不便さを感じる原因になります。
見当識障害
見当識障害は、時間や場所、自分自身に関する基本的な認識が混乱する状態です。
- 今が何月何日なのかわからない
- 自分が現在どこにいるのかわからない
- 自分が誰であるのがわからない
見当識障害は、記憶だけでなく、日常生活全般に深刻な影響を及ぼします。
とくに、自分がどこにいるかを認識できないため、道に迷ったり、家に帰れなくなるといった危険な状況が生じることもあります。
見当識障害は脳梗塞だけでなく、認知症の初期症状としても見られる症状です。
脳梗塞により記憶障害になる原因
脳梗塞は、脳への血流がなんらかの理由で遮断されることによって発生し、脳細胞が酸素や栄養を十分に受け取れなくなることでダメージを受けます。
記憶に関連する脳の部位にダメージが及ぶと引き起こされるのが記憶障害です。
とくに、重要な影響を受ける脳の部位と、それによって生じる記憶障害については以下の表にまとめました。
| 影響を受ける部位 | 主な機能 | 障害が起きた際の症状 |
|---|---|---|
|
海馬 |
短期記憶から長期記憶への変換、空間記憶の形成 |
新しい記憶の形成が困難、最近の出来事を覚えられない |
|
側頭葉 |
長期記憶の保存、視覚や聴覚の記憶処理 |
過去の記憶の想起が困難、物や人の認識に支障 |
|
前頭葉 |
作業記憶、記憶の整理と実行機能 |
複数の作業の同時進行が困難、計画立案の障害 |
とくに、海馬や側頭葉、前頭葉といった記憶の形成や保持に深く関わる領域が影響を受けると、短期記憶や長期記憶、さらにはエピソード記憶といった多様な記憶機能に障害が現れることがあります。
また、脳梗塞の影響で脳のネットワークが遮断されると、情報を効率的に処理したり記憶を引き出したりする能力も低下します。
これにより、日常生活における出来事や新しく学んだ知識を覚えることが難しくなるのです。さ
らに、記憶だけでなく、認識力や判断力などの認知機能全般に影響を及ぼす場合もあります。
脳梗塞による記憶障害は、発生した部位や範囲、血流が遮断されていた時間の長さによって症状の程度が異なるため、早期の診断と治療が不可欠です。
また、リハビリテーションによって残存する脳の機能を活用し、記憶障害の改善を目指すことができます。
他にも、もともと我々の身体にある幹細胞を活用した再生医療による治療という選択肢もあります。
脳卒中(脳梗塞、脳出血)再生医療の治療結果は、病状や体の具合によって個人差はあるものの、一度機能しなくなった脳細胞が復活し、脳卒中の後遺症を改善させる効果が期待できます。
再生医療による脳の再生を目指したい方やご興味がある方は、ぜひ当院へご相談ください。
脳卒中のお悩みに対する新しい治療法があります。
脳梗塞による記憶障害のリハビリテーションの種類
リハビリテーションでは、患者の記憶機能を補助したり代替したりするさまざまな方法が用いられます。
ここでは、脳梗塞による記憶障害に対して行われるリハビリテーションの種類を紹介します。
また、ご家族のサポートとリハビリ効果を高める再生医療についても解説しているので、ぜひご覧ください。
内的記憶戦略法
内的記憶戦略法※は、脳梗塞による記憶障害のリハビリにおいて、患者自身が意識的に記憶力を高めるための方法です。
※参照: 国立障害者リハビリテーションセンター「医学的リハビリテーションプログラム」
この方法では、記憶を活性化し情報を効果的に覚えるための具体的な工夫を取り入れます。
代表的な方法として、語呂合わせや情報をカテゴリーごとに整理する手法、視覚イメージ法などがあります。
内的記憶戦略法の主な手法とその実践例を以下の表にまとめました。
| 手法 | 概要 | 具体的な実践例 |
特徴・効果 |
|---|---|---|---|
|
カテゴリー分類法 |
情報を共通の特徴で分類して記憶する |
野菜(にんじん、キャベツ)、果物(りんご、みかん)のように分類 |
|
|
視覚イメージ法 |
記憶したい情報を具体的な映像として思い描く |
買い物リストに「牛乳とパン」がある場合、「巨大なパンで牛乳パックをサンドイッチ」とイメージ |
|
これらの内的記憶戦略法の利点は、患者自身が能動的に取り組むことで、記憶の回復を目指せる点です。
この方法は、日常生活に取り入れやすく、繰り返しの練習により効果が高まるとされています。
外的補助手段
外的補助手段※は、外部ツールを利用して記憶力の低下を補助する方法です。
※参照: 国立障害者リハビリテーションセンター「医学的リハビリテーションプログラム」
患者が記憶を頼りにせずとも日常生活を円滑に送るための方法で、実用性が高いのが特徴です。
外的補助手段の具体的な方法と実践のポイントを以下の表にまとめました。
記憶障害があるとスマートフォンなど外部ツールの使用を忘れてしまいますが、繰り返しにより習慣になる場合もあります。
外的戦略は習慣化するまでは患者本人だけで継続するのは難しく、ご家族や支援者が協力して環境を整えることで、より効果を発揮します。
課題指向型アプローチ
課題指向型アプローチは、患者が日常の生活で直面する具体的な問題に焦点を当て、その解決を目指す実践的なリハビリテーション方法です。
たとえば、以下のような具体的な課題設定と実践方法が挙げられます。
| 生活場面 | 具体的な課題例 | 実践方法 | 期待される効果 |
|---|---|---|---|
|
買い物 |
商品リストの記憶と購入 |
|
|
|
家事 |
段取りを考えた家事の実行 |
|
|
これらのリハビリにより、実際の生活で記憶を活用する能力を高められますが、課題の設定は患者ごとに異なり、その人の能力や生活環境に合わせて設定する必要があります。
必要に応じて外的補助手段も活用し、記憶力の向上を図りながらも、実際の生活場面での失敗を最小限に抑えるアプローチも可能です。
また、成功体験を重ねることで自信を回復させる効果も期待できます。
家族による環境のサポートも重要
脳梗塞による記憶障害に対しては、家族のサポートが患者の回復を支える重要な要素です。
家族は患者の生活環境を整えるだけでなく、心理的な支えにも大きな役割を果たします。
効果的な家族サポートの具体例として、以下のような環境づくりが挙げられます。
| サポートの種類 | 具体的な方法 | 期待される効果 | 実践する上での注意点 |
|---|---|---|---|
|
物理的環境整備 |
必要なものを見える位置に配置 |
日常生活の自立支援 |
配置場所の一貫性を保つ |
|
習慣形成支援 |
スマートフォンのアラーム設定を一緒に練習 |
自己管理能力の向上 |
段階的に習慣づける |
|
心理的サポート |
適切な距離感を保ちながらの見守り |
自尊心の維持 |
過度な干渉を避ける |
しかし、リハビリテーションによる回復には個人差があり、時には望むような改善が見られないこともあります。
家族とはいえ、すべてのサポートをするのは容易ではなく、負担が大きくなることで、ご家族の方が心身に疲れを感じることもあるでしょう。
また、記憶障害のある患者本人にとっても家族への依存を余儀なくされる状況は大きな精神的負担となるため、早期の機能回復により患者と家族双方の負担軽減が望まれます。
そこで、患者さまの回復をより早めつつご家族の負担を軽減する手段として、ぜひ再生医療もご検討ください。
- 再生医療は、患者の脳細胞の修復や再生を促進する先進的な治療法です。
- 脳梗塞をはじめとする脳卒中の後遺症改善効果が期待できます。
- リハビリと並行して再生医療を行うことで、リハビリ効果を高められます。
脳梗塞による記憶障害でお困りの方、あるいは家族のサポートに課題を感じている方は、ぜひ当院へご相談ください。
脳卒中のお悩みに対する新しい治療法があります。
脳梗塞による記憶障害への社会的支援
脳梗塞による記憶障害を抱える方が利用できる社会的支援について紹介します。
障害者手帳や各種支援制度、家族の相談窓口など、さまざまなサポートを受けることで、患者本人だけでなくご家族の負担も軽減できます。
障害者手帳
障害者手帳は、身体や精神に障害がある方が受けられる社会的支援の基盤となる制度です。
要件を満たせば手帳の交付を受けられる可能性があり、障害者手帳を取得すると、以下のような支援を受けられます。
- 医療費の助成
- 公共交通機関の割引
- 税制上の優遇措置
障害者手帳には、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の3つの種類があります。
記憶障害を含む高次脳機能障害が原因で日常生活や社会活動に支障が生じている場合、器質性精神障害として精神障害者保健福祉手帳の申請対象※となる可能性があります。
※参照:国立障害者リハビリテーションセンター「高次脳機能障害支援に関する制度」
自立支援給付や地域生活支援事業
自立支援給付や地域生活支援事業は、障害を抱える方が地域社会で自立して生活するための支援を提供する制度です。
- 自立支援給付:福祉サービスの利用料軽減、訪問介護やデイサービスの提供
- 地域生活支援事業::移動支援や相談支援など、地域ごとに設けられた支援プログラム
これらの支援は、記憶障害による日常生活の困難を補うために利用できます。
お住まいの市町村の福祉担当窓口で詳細の確認および申請が可能です。
ご家族が相談できるサービス
脳梗塞による記憶障害は、患者だけでなくそのご家族にも大きな負担がかかります。こうした状況に対応するため、各自治体では以下のような支援が受けられます。
| 窓口 | 受けられるサービス |
|---|---|
| 地域包括支援センター |
|
| 居宅介護支援事業所 |
|
| 市区町村の福祉課や障害者支援担当窓口 |
|
相談窓口は無料で利用できる場合が多く、まずは最寄りの自治体の福祉課や障害者支援担当窓口に問い合わせてみることをおすすめします。
脳梗塞による記憶障害についてのまとめ
脳梗塞による記憶障害は、短期記憶や長期記憶、エピソード記憶などさまざまな記憶機能に影響を及ぼします。
記憶障害への対応には、原因を理解し、適切なリハビリテーションを行うことが重要です。
記憶障害について正しく理解し、適切な対策を講じることで、患者とご家族が安心して生活を送る環境を整えられます。
金銭的な負担やご家族の負担を軽減できる社会支援サービスもありますので、これらを活用しながら、無理のない形で後遺症と向き合っていくことが大切です。
脳梗塞による後遺症のリハビリ効果を高める、あるいはご家族の負担を減らすための選択肢の1つとして、ぜひ再生医療もご検討ください。
当院(リペアセルクリニック)で提供している再生医療は厚生労働省に受理された治療方法で、脳梗塞においては再生医療で脳卒中の再発予防にも役立ちます。
>>当院で行っている脳梗塞を含むに脳卒中に対する再生医療の症例は、こちらから確認いただけます。
再生医療について気になる点は、お気軽に当院へお問い合わせください。
以下の動画では、実際に当院リペアセルクリニックで再生医療を受け、脳梗塞の後遺症が改善された患者様の症例を紹介していますので、併せて参考にしてください。

監修者
圓尾 知之
Tomoyuki Maruo
医師
略歴
2002年3月京都府立医科大学 医学部 医学科 卒業
2002年4月医師免許取得
2002年4月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2002年6月関西労災病院 脳神経外科 勤務
2003年6月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2003年12月大阪母子医療センター 脳神経外科 勤務
2004年6月大阪労災病院 脳神経外科 勤務
2005年11月大手前病院 脳神経外科 勤務
2007年12月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2012年3月大阪大学大学院 医学系研究科 修了(医学博士)
2012年4月大阪大学医学部 脳神経外科 特任助教
2014年4月大手前病院 脳神経外科 部長
キーワード検索
カテゴリ
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116
Warning: Undefined array key "use_desc_for_title" in /home/xb684686/africatime.com/public_html/wp/wp-includes/class-walker-category.php on line 116