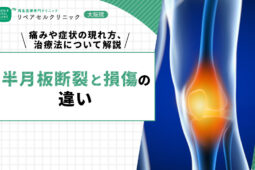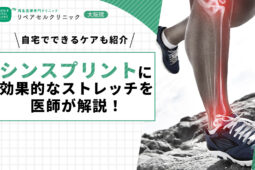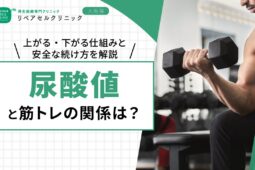- ひざ関節
- スポーツ医療
膝に水が溜まる原因|初期症状や水を抜く方法、治し方について解説【医師監修】
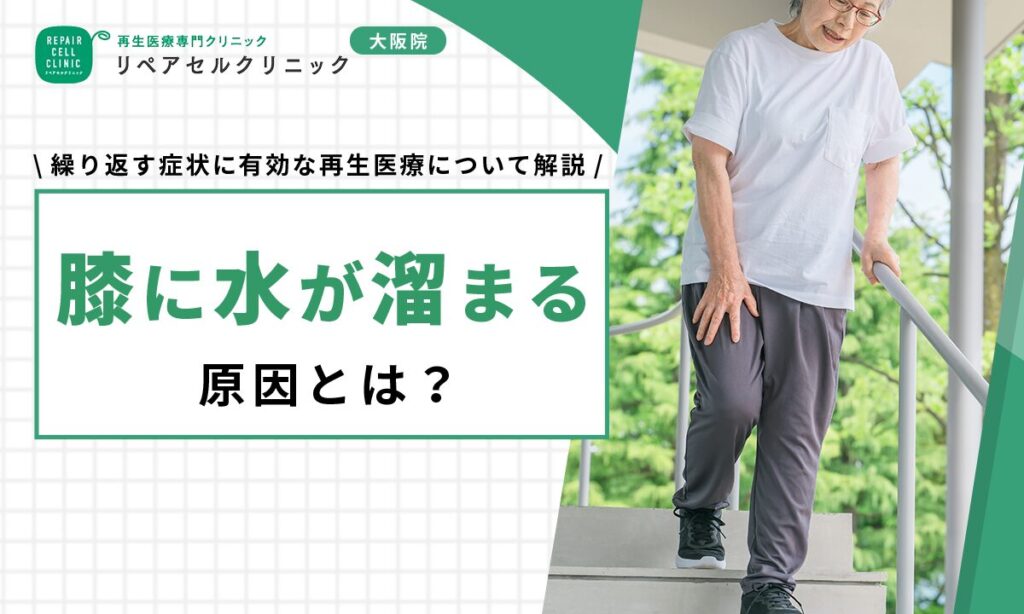
膝に水が溜まったような感覚や膝の腫れに悩まされている方も多いのではないでしょうか。
膝に水が溜まると歩行時の痛みや不快感が生じ、日常生活に大きな支障をきたします。
この記事では、膝に水が溜まる主な原因や初期症状、水を抜く方法から根本的な治し方まで詳しく解説します。
膝の水で悩まれている方は、ぜひ最後まで読んで適切な対処法を見つけましょう。
また、現在リペアセルクリニックでは手術を伴わない膝の疾患に対する治療法「再生医療」に関する情報をLINEで発信しております。
簡易オンライン診断も実施しているので、ぜひご登録ください。
目次
膝に水が溜まるとは?
膝に水が溜まるとは、怪我や体重の増加など様々な原因により、滑膜という組織から分泌されている関節液が過剰に分泌されている状態のことです。
痛みや腫れなどの初期症状が出る場合があります。
この関節液は、健康な人でも膝関節に通常1~3ml程度ありますが、炎症などを起こした場合、30ml以上溜まることもあります。
炎症が起こった場合、関節液の分泌と吸収のバランスが崩れることにより、膝に水が溜まる状態となります。
膝に水が溜まる原因
膝に水が溜まる原因は、膝関節にある軟骨や滑膜組織の損傷による炎症です。
原因となる主な疾患は、以下の通りです。
膝に水が溜まる原因を正しく理解して、適切な治療法を選択しましょう。
変形性膝関節症
変形性膝関節症は、膝関節の軟骨が徐々にすり減っていく疾患です。
変形性膝関節症による軟骨の摩耗によって骨同士の摩擦が生じ、炎症が発生することで膝に水が溜まる原因となります。
加齢によって軟骨が摩耗しやすくなる中高年に多く見られ、日常的な膝の痛みや腫れを引き起こします。
半月板損傷や靭帯損傷
膝に水が溜まる原因として、半月板損傷や靭帯損傷をきっかけとした炎症が考えられます。
半月板は膝関節にある軟骨で、クッションの役割を持つ部位です。半月板損傷や靭帯損傷は激しいスポーツや日常生活の急な動きなどによって起こる可能性があります。
半月板損傷が起こると膝が腫れて、過剰に分泌された関節液が膝に溜まることがあります。
関節リウマチや感染症
関節リウマチは自己免疫の異常によって関節が慢性的に炎症を起こし、滑膜が充血して腫れあがることで過剰に関節液が分泌されます。
進行すると関節の変形を伴うリスクがあります。
また、怪我や膝関節の注射などにより細菌やウイルスが関節内に侵入し、急性の痛みや腫れが発生する感染性関節炎も原因の一つです。
虫歯菌が血管に入って膝まで運ばれる血行性感染も含まれます。
膝に水が溜まるときの初期症状
これらの症状を早期に認識することで、適切な治療を受けることができます。
歩行時や曲げ伸ばしによる膝の痛み
膝に水が溜まると、歩行時や階段の上り下りなど膝を曲げ伸ばしする際に痛みを感じます。
- 歩行時の膝の痛み
- 階段の上り下りでの痛み
- 膝の曲げ伸ばし時の痛み
- 正座や立ち上がり時の痛み
炎症が起こると滑膜組織から過剰に関節液が分泌されるほか、サラサラした水のような関節液になります。
サラサラの関節液では膝関節の負荷を軽減できず、骨と骨がぶつかるため、歩行時や膝の曲げ伸ばしの際に痛みが生じるのです。
膝周辺の熱感や腫れ
炎症が起きている状態では、膝関節の周囲が熱を持ち腫れることがあります。
- 膝が熱っぽく感じる
- 膝周辺が腫れている
- 膝の周りがブヨブヨしている
- 見た目で膝の腫れが分かる
スポーツで怪我をした場合、傷や内出血だけでなく膝の腫れにも注意が必要です。
軟骨や滑膜組織が損傷し、膝に水が溜まっている可能性も視野に入れて早めに受診してください。
膝周辺の違和感
明確な症状がなくても、膝の周辺に違和感を感じるケースもあります。
- 膝が重たく感じる
- 膝に何かが入っているような感覚
- 膝を曲げ伸ばししづらい
- 膝がこわばる
これらの違和感が特徴的です。関節液が過剰に溜まることで、膝関節の正常な動きが制限されて引き起こされます。
膝に水が溜まったときの対処法と流れ
膝に水が溜まったときは、主に以下の対処法を行います。
自分で対処するのは難しいため、医療機関を受診して対応してもらいましょう。
①膝の水を抜く
膝に水が溜まった場合、まず注射器を使って関節液を抜く処置を行います。
これは関節穿刺(かんせつせんし)と呼ばれる処置で、膝の痛みや腫れを一時的に和らげることができます。
処置は比較的簡単で、局所麻酔をした後に注射器で関節液を吸引します。
処置時間は数分程度で、即座に膝の張りや痛みが軽減されます。
ただし、水を抜くだけでは根本的な解決にはならず、原因を治療しなければ再び水が溜まる可能性があります。
②検査で原因を特定する
膝の水を抜いた後は、なぜ水が溜まったのかを特定するための検査を行います。
主な検査方法は以下の通りです。
| 検査方法 | 検査内容 |
|---|---|
| レントゲン検査 | 骨の変形や関節の隙間を確認 |
| MRI検査 | 軟骨、半月板、靭帯の損傷を詳しく観察 |
| 関節液検査 | 抜いた関節液の性状や細菌の有無を調べる |
| 血液検査 | 炎症反応やリウマチ因子を確認 |
これらの検査により、変形性膝関節症、半月板損傷、関節リウマチ、感染症など、水が溜まる原因を特定できます。
③原因を改善する治療を行う
検査で原因が特定されたら、その原因に応じた根本的な治療を開始します。
原因によって治療法は大きく異なるため、適切な診断に基づいた治療選択が重要です。
軽度の場合は薬物療法やリハビリテーションなどの保存療法から開始し、症状が改善しない場合は手術療法や再生医療などの選択肢を検討します。
原因を治療せずに水抜きだけを繰り返すと、膝の状態がさらに悪化する可能性があるため、根本的な治療が不可欠です。
膝に水が溜まる原因の治し方
膝に水が溜まった場合の治療は、症状の原因や程度に応じて選択します。
| 治療法 | 内容 |
|---|---|
| 消炎鎮痛剤の投薬や膝周辺のリハビリ | |
| 関節の修復や人工関節置換 | |
| PRPや幹細胞を活用し、軟骨や組織の再生を促進 |
軽度の場合は保存的治療が基本となりますが、症状が改善しない場合は他の治療が必要です。
保存療法
膝に水が溜まった場合、まずは薬物療法やリハビリテーションなどの保存療法から開始することが一般的です。
| 治療法 | 内容 |
|---|---|
| 薬物療法 | 消炎鎮痛剤の内服、ヒアルロン酸注射、ステロイド注射 |
| 物理療法 | 安静、圧迫、挙上(RICE療法)、温熱療法 |
| リハビリテーション | 膝周辺の筋力強化、柔軟性向上、歩行訓練 |
専門の理学療法士による指導のもと、膝周辺の筋力や柔軟性を強化することにより、再発を防止することが目的です。
手術療法
重度の変形性膝関節症や半月板・靭帯の損傷、リウマチを発症している場合などは、手術療法を行う場合があります。
| 疾患 | 手術方法 |
|---|---|
| 変形性膝関節症 | 人工膝関節置換術、骨切り術、関節鏡視下手術 |
| 半月板損傷 | 半月板縫合術、半月板切除術 |
| 膝の靭帯損傷 | 靭帯再建術、靭帯縫合術 |
| リウマチ性関節炎 | 人工膝関節置換術、滑膜切除術 |
いずれも保存療法などによって改善が見られない場合に適用されるケースがほとんどです。手術を回避するためにも早めに医療機関を受診し、適切な治療を受けましょう。
再生医療
膝に水が溜まる症状では、PRPや幹細胞を利用した再生医療が治療の選択肢となります。
| 治療法 | 内容 |
|---|---|
| PRP療法 | 患者さまの血液から抽出した血小板の濃縮液を用いて行う治療 |
| 幹細胞療法 | 患者さまの脂肪から幹細胞を採取・培養し、患部に投与する治療 |
再生医療は患者さま自身の血液や細胞を利用するため、副作用のリスクが少ないのが特徴です。
以下のページでは、実際に当院で再生医療の治療を受け、改善した患者さまの症例を紹介しているため、併せて参考にしてください。
>再生医療による膝関節の症例はこちら
膝に水が溜まることについてよくある質問
膝に水が溜まる原因に関するよくある質問を5つ紹介します。
気になる疑問を解消して、症状の改善に向けた行動をとりましょう。
膝に水が溜まるのを自分で治す方法は?
軽度の腫れであれば、安静にして膝への負担を減らすと改善するケースがあります。
具体的には、膝を高く上げて横になる、冷却パックで冷やす、過度な運動を控えるなどの方法が有効です。
ただし、原因によっては医師の診断と治療が必要です。
とくに感染症やリウマチ、関節の損傷が疑われる場合は、薬物治療やリハビリが欠かせません。
症状が続く場合は、専門医に相談しましょう。
太り過ぎは膝に水が溜まる原因になる?
太り過ぎは体重過多によって膝への負担が大きくなるため、膝に水が溜まる原因になります。
体重が増えると膝関節にかかる負担が増し、軟骨や関節に過剰な圧力がかかるためです。
圧力がかかると軟骨の摩耗や炎症を引き起こし、膝に水が溜まる原因になります。
また、肥満は変形性膝関節症のリスクを高めます。体重管理を行い、膝への負担を減らしましょう。
膝に溜まった水は自然に消える?
軽度の炎症による一時的な水の蓄積であれば、安静にすることで自然に消えることがあります。
しかし、慢性的な疾患や重度の損傷が原因の場合は、自然治癒は期待できません。
水が溜まる原因を治療しなければ、水を抜いても再び溜まってしまいます。
症状が長期間続く場合や繰り返し水が溜まる場合は、必ず医療機関を受診して根本的な治療を受けることが重要です。
膝の水を抜くストレッチはある?
ストレッチで直接水を抜くことはできませんが、膝周辺の筋肉をほぐし血流を改善することで症状の緩和が期待できます。
- 太もも前面のストレッチ
- 太もも後面のストレッチ
- ふくらはぎのストレッチ
- 膝の軽い曲げ伸ばし運動
ただし、痛みが強い場合や腫れがひどい場合は、ストレッチを行わず医療機関を受診してください。
無理な運動は症状を悪化させる可能性があります。
膝に水が溜まるのを予防する方法は?
適正な体重維持と膝周辺の筋力強化が最も効果的な予防法です。
- 適正体重の維持
- 太ももの筋力強化
- 運動前の十分なウォーミングアップ
- 運動後のクールダウンとストレッチ
- 正しい姿勢の維持
- 膝に負担をかける動作の回避
また、長時間のデスクワークで同じ姿勢を保つと血行不良になり、膝関節に悪影響を及ぼすため、定期的に姿勢を変更することも大切です。
日常生活での膝への負担を意識し、予防に取り組みましょう。
膝に水が溜まる原因の治療には再生医療をご検討ください
膝に水が溜まる原因は膝への過剰な負担や変形性膝関節症、細菌やウイルス性の関節炎など多くの原因があります。
症状として歩行時の痛みや熱感、腫れなどが現れ、日常生活に大きな支障をきたします。
治療法は症状の原因や程度によって異なり、保存療法や手術療法に加えて、再生医療という選択肢もあります。
再生医療は、患者さま自身の血液や幹細胞を利用するため、副作用のリスクが少ないのが特徴です。
膝に水が溜まる症状でお悩みの方は、ぜひ当院「リペアセルクリニック」にご相談ください。

監修者
坂本 貞範
Sadanori Sakamoto
医療法人美喜有会 理事長
「できなくなったことを、再びできるように。」
人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの
お手伝いができれば幸甚の至りでございます。
略歴
1997年3月関西医科大学 医学部卒
1997年4月医師免許取得
1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務
1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務
1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務
1999年2月国立大阪南病院 勤務
2000年3月野上病院 勤務
2003年3月大野記念病院 勤務
2005年5月さかもとクリニック 開設
2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任
2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設
2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設