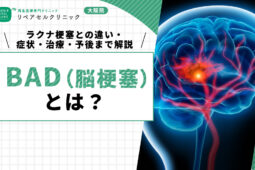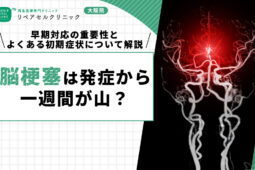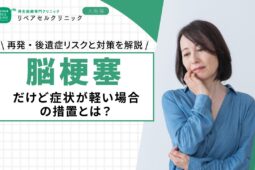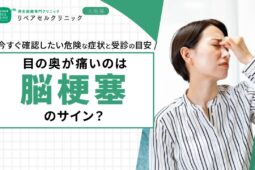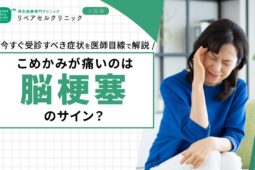- 脳梗塞
陳旧性脳梗塞とは?改善のためにできること・再生医療の可能性を解説
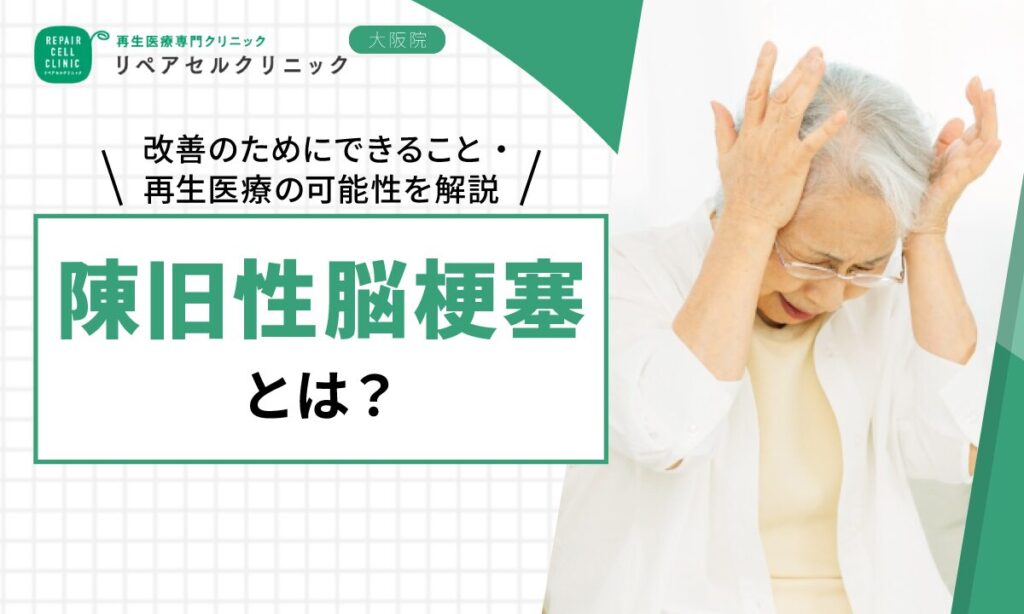
脳梗塞を経験された患者様の中には「発症から時間が経っているのに、症状がなかなか良くならない」「これ以上の回復は期待できないのだろうか…」と不安を抱えている方もいらっしゃいます。
発症後しばらく経過した脳梗塞は、一般的に陳旧性脳梗塞と呼ばれます。
この状態は回復が緩やかになる傾向があり、リハビリを続けていても「停滞しているように感じる」時期が出てくることもあります。
本記事では、陳旧性脳梗塞がどのような状態なのか、そのメカニズムや後遺症との付き合い方、日常生活でできる工夫、そして後半では新しい選択肢として注目されている再生医療についても分かりやすく解説していきます。
目次
陳旧性脳梗塞とはどんな状態?
陳旧性脳梗塞とは、脳梗塞の発症から一定期間が経過し、症状が慢性化した状態のことを指します。
一般的に脳梗塞は「急性期 → 回復期 → 生活期(慢性期)」と進行していきますが、発症から数か月〜数年が経ち、症状が安定してきた段階が陳旧期(慢性期)と呼ばれます。
この段階では、新たな炎症は落ち着いているものの、すでに損傷を受けた神経細胞が残っているため回復がゆっくりになることが特徴です。
「回復しにくい」と感じてしまう場合もありますが、生活の工夫、継続的なリハビリ、体の状態に合わせたケアを続けることで、日常生活の負担を減らすことは十分に目指すことができます。
- 発症から時間が経過している(数か月〜数年)
- 症状が安定しやすいが急激な変化は少ない
- 神経細胞の損傷が残るため回復がゆっくり
- 生活期(慢性期)とも呼ばれる時期
- リハビリの継続によって生活動作が向上しやすい
陳旧性脳梗塞は「治療の終わり」ではなく、「長期的な生活と向き合う段階」です。
この時期は患者様の不安やご家族の負担が大きくなりやすいため、必要に応じて専門医に相談しながらケア方法を見直していくことがとても大切です。
次の章では、陳旧性脳梗塞が「回復が難しい」と言われる理由について、回復メカニズムと従来の治療法の観点から詳しく解説していきます。
なぜ回復が難しいと言われるのか
陳旧性脳梗塞は「神経細胞の損傷が残りやすい」という特徴があるため、回復がゆっくりになることが多いとされています。
脳梗塞は発症直後の数週間〜数か月が最も回復しやすい時期といわれています。
しかしこの期間を過ぎて陳旧期(慢性期)へ移行すると、脳の自然な回復力が徐々に落ち着き、改善のスピードが緩やかになります。これが「回復が難しい」と言われる主な理由です。
ここからは、回復の仕組みと一般的な治療の役割・限界を詳しく解説し、陳旧期に入ってからの経過を理解しやすく整理していきます。
発症直後〜陳旧期までの回復メカニズム
脳は発症直後〜数か月が最も回復しやすく、その後ゆっくりとした改善へ移行します。
脳梗塞では脳の血管が詰まり、神経細胞の一部がダメージを受けます。発症直後は炎症が強いものの、脳が持つ回復力(可塑性)が最大限働くため、リハビリによる改善が比較的得られやすい時期です。
しかし、時間が経過して炎症が落ち着いた陳旧期では、損傷した神経細胞の再生が難しく、脳の代償機能(他の部分が助け合う仕組み)もゆっくり働くようになります。
そのため「改善しているけれどスピードが落ちている」と感じる患者様が多いのが特徴です。
- 急性期:炎症が強く、症状が不安定になりやすい
- 回復期:脳の可塑性が働き、リハビリ効果が出やすい
- 陳旧期:炎症が落ち着き、回復スピードがゆっくりになる
- 改善は可能だが長期的な視点が必要
- 脳の代償機能が少しずつ働くことで動作が安定しやすくなる
陳旧期は「もう改善しない」という意味ではなく、「改善のスピードがゆっくりになる」時期です。
継続的なリハビリや生活の工夫により、日常生活動作の安定を目指すことは十分可能です。
一般的な治療(薬・リハビリ・装具)の役割と限界
一般的な治療は後遺症への重要なサポートになりますが、改善には限界が出てくることがあります。
陳旧性脳梗塞では、薬物療法・リハビリ・装具を組み合わせて後遺症の軽減や生活動作の向上を目指すのが基本です。
それぞれ重要な役割を担っていますが、脳細胞の再生そのものを促すわけではないため、時間の経過とともに改善が停滞するケースもあります。
- 薬物療法:血流や血圧の管理、再発予防に重要
- リハビリ:筋力維持・動作の再獲得をサポート
- 装具:歩行の安定や転倒予防に役立つ
- 限界:損傷した神経細胞を元に戻す治療ではない
- 改善の停滞:陳旧期に入ると進展が緩やかになりやすい
こうした背景から「これ以上良くならないのだろうか…」と不安を抱く患者様は多くいらっしゃいます。
しかし、一般的な治療でカバーしきれない部分を補うための方法として、近年では再生医療が新たな選択肢として検討されるケースも増えています。
陳旧性脳梗塞の後遺症と付き合うためのポイント
陳旧性脳梗塞の後遺症と向き合うには、日常生活の工夫と継続的なケアを組み合わせて取り組むことが大切です。
陳旧期では回復のスピードが緩やかになるため、「あまり変化がない」と感じる患者様も多くいらっしゃいます。
しかし、日常生活の工夫や自主リハビリ、再発予防のための生活管理を続けることで、生活動作の安定につながるケースが多くあります。
ここからは、後遺症と共に日常生活を送るための具体的な工夫と、再発を防ぐために重要な生活習慣について詳しく解説します。
日常生活でできる工夫と自主リハビリのポイント
陳旧性脳梗塞では、日常の小さな工夫と自主リハビリを継続することで生活動作の安定を目指すことができます。
陳旧期は回復のスピードが緩やかな時期ですが、「ゆっくりでも続けること」が生活の質を維持するうえで非常に大切です。
手足の動かしにくさ、疲れやすさ、歩行の不安定など、後遺症の内容に応じてリハビリ方法を工夫することで、負担を減らしながら日常生活の動作をサポートできます。
- 動かしにくい部位の反復練習を行う(無理のない範囲で)
- 立つ・歩く動作は短時間でも毎日取り入れる
- ストレッチで筋肉のこわばりを防ぐ
- 姿勢の見直し(猫背・前傾姿勢を避ける)
- 休息と負荷のバランスを意識する
自主リハビリは“無理をしないこと”もとても大切です。
疲労が強い日は休息を優先し、できる日には少しだけ負荷をかけるように調整することで長く続けやすくなります。
ご家族がサポートする場合も「できている部分を認めながら励ますこと」が継続の力になります。
再発予防のための生活管理
陳旧性脳梗塞では、再発予防のための生活管理が非常に重要です。
脳梗塞は再発率が高い疾患とされており、陳旧期に入っても適切な生活管理を続けることで再発リスクを下げることが可能です。
特に血圧・血糖・コレステロールなど、血管の健康に関わる要素を整えることが予防の基本となります。
- 減塩を意識した食事(加工食品に注意)
- 適度な運動(散歩・軽い筋トレなど)
- 血圧・血糖・脂質の定期的なチェック
- 禁煙・節酒など血管に優しい習慣づくり
- 睡眠リズムを整える
再発予防では、「完璧にやらなければ」と思いすぎないことも大切です。
焦って生活を変えようとすると継続が難しくなるため、できることから少しずつ習慣を整えていくことで負担が少なく続けやすくなります。
また、気になる症状や不安がある場合は早めに専門医へ相談することで、安心感を持ちながら生活管理を進めやすくなります。
陳旧性脳梗塞に対する再生医療(幹細胞治療)という新しい選択肢
陳旧性脳梗塞の後遺症に悩む患者様の選択肢として、再生医療(幹細胞治療)が注目されるケースがあります。
従来のリハビリだけでは補いきれない部分をサポートする方法として、身体が本来持つ力を活かす再生医療が相談される場面が増えています。
再生医療は患者様自身の細胞を用いることで、負担を抑えながら身体づくりをサポートする可能性がある治療として関心が高まりつつあります。
- 手足の動かしにくさが続いている
- しびれ・歩行不安などが残っている
- リハビリだけでの進展がゆるやかと感じている
- 生活動作の負担を少しでも軽減したいと考えている
- 再発予防も含めて身体の状態を整えたい場合
- 新しい選択肢を知ったうえで検討したい患者様
再生医療は、患者様の状態によって適応の可否が異なるため、まずは専門医が丁寧に評価し、無理のない範囲で検討することが大切です。
また、従来の治療やリハビリと組み合わせて取り入れるケースもあり、「できることを広げたい」と考える患者様の支えになることがあります。
リペアセルクリニック大阪院では、再生医療に精通した医師が患者様一人ひとりの状態を詳しく確認し、必要なケア・生活習慣の改善アドバイスも含めて総合的な提案を行っています。
治療を押しつけることはせず、患者様の希望や生活背景を大切にしたサポートを行っているため、安心して相談しやすい環境が整っています。
- 再生医療に精通した医師が在籍し相談しやすい
- オーダーメイドの治療提案で一人ひとりに適した選択肢を提示
- 生活習慣・リハビリのアドバイスも含んだ総合的なケア
- 無理な治療の提案を行わない安心の方針
- 丁寧なカウンセリングで疑問や不安を相談しやすい
- プライバシーに配慮した空間で落ち着いて相談できる
- 完全予約制のため待ち時間のストレスが少ない
気になる症状がある場合や、将来のために治療の幅を広げておきたい場合には、一度専門医に相談することで安心感が得られやすくなります。
手術をしない新しい治療「再生医療」を提供しております。
陳旧性脳梗塞は日常生活でできる工夫と適切なケアが重要
陳旧性脳梗塞と向き合うためには、日常生活の工夫と適切な医療的サポートを組み合わせることが大切です。
発症から時間が経過した陳旧期は、回復のスピードがゆっくりになる時期ですが、生活の工夫・自主リハビリ・再発予防の管理を継続することで、日常の不安や負担を減らすことが期待できます。
焦らず続けることが、長期的な生活の質につながっていきます。
- 生活動作を工夫し負担を減らす
- 自主リハビリを無理のない範囲で継続する
- 再発予防のため血圧・血糖などを管理する
- できることを少しずつ積み重ねる姿勢が大切
- 不安や疑問は専門医へ相談し適切なケアを受ける
- 再生医療という選択肢を必要に応じて検討する
陳旧性脳梗塞は、改善のスピードが緩やかなぶん、不安を抱え込みやすい時期でもあります。
ご自身だけで頑張ろうとせず、家族や医療者と協力しながら取り組むことが、心身双方の負担を減らすことにつながります。
また、後遺症が続いている患者様や、今後の生活に不安を抱えている患者様にとって、身体の状態に合わせてサポートする再生医療が新しい選択肢となることもあります。
リペアセルクリニック大阪院では、陳旧性脳梗塞の患者様の状態を丁寧に確認したうえで、再生医療を含めた多角的なケア提案を行っています。
リハビリ・生活習慣のアドバイス・相談しやすいカウンセリング体制があり、患者様が不安を抱え込まずに進める環境を整えています。
「今後の過ごし方が不安」「何をどう進めればよいか迷っている」そんな方は、一度専門医に相談することで、より納得感のある選択肢を見つけやすくなります。
無理なく取り組める形で、これからの生活を整えていきましょう。

監修者
圓尾 知之
Tomoyuki Maruo
医師
略歴
2002年3月京都府立医科大学 医学部 医学科 卒業
2002年4月医師免許取得
2002年4月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2002年6月関西労災病院 脳神経外科 勤務
2003年6月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2003年12月大阪母子医療センター 脳神経外科 勤務
2004年6月大阪労災病院 脳神経外科 勤務
2005年11月大手前病院 脳神経外科 勤務
2007年12月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2012年3月大阪大学大学院 医学系研究科 修了(医学博士)
2012年4月大阪大学医学部 脳神経外科 特任助教
2014年4月大手前病院 脳神経外科 部長