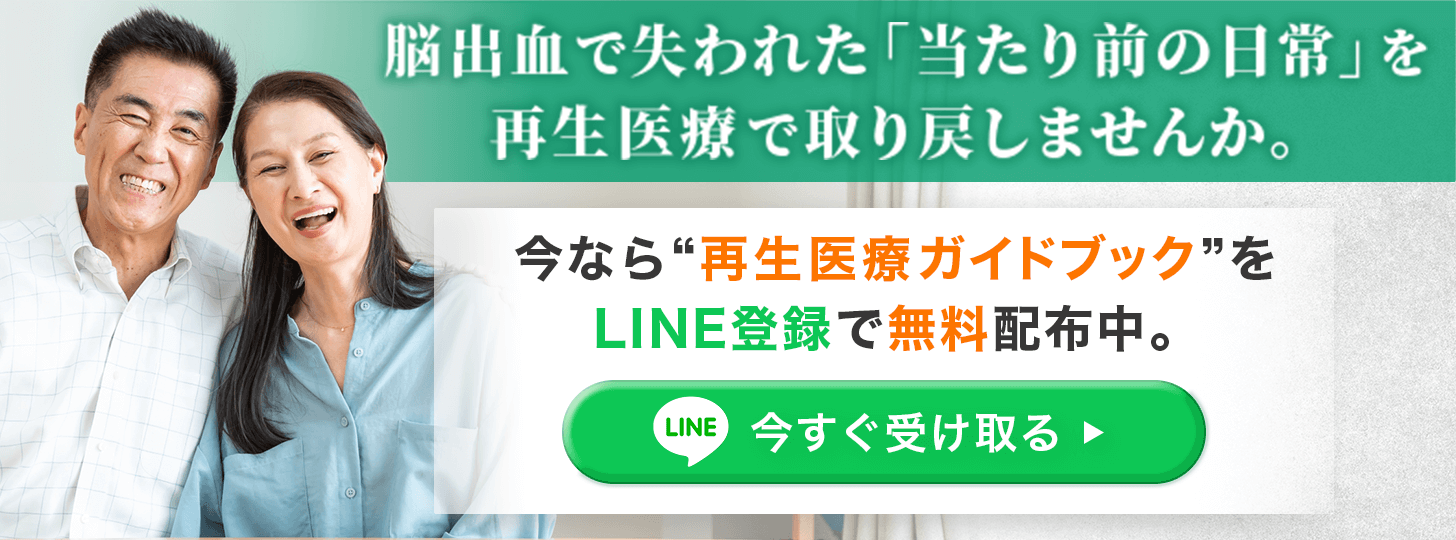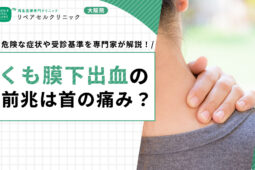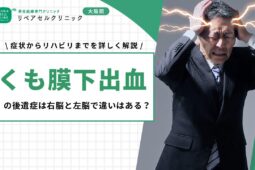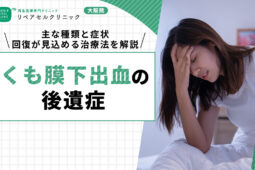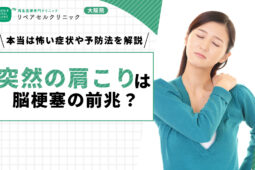- 脳卒中
- 頭部
- くも膜下出血
くも膜下出血の退院後に気をつけることは?生活の注意点と再発予防についても解説
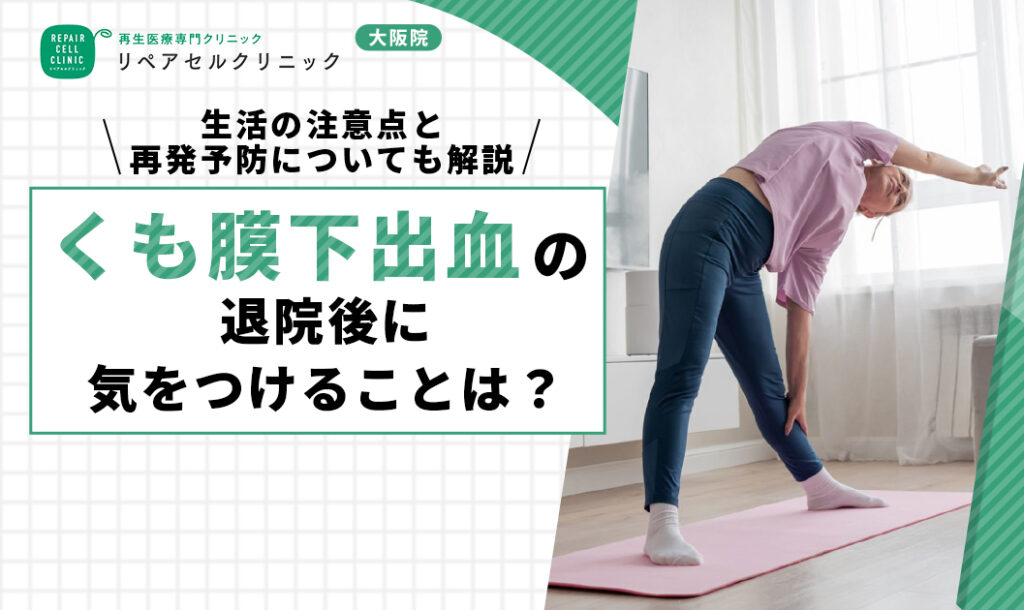
くも膜下出血を発症して入院し、やっとの思いで退院したにも関わらず、再発に対して不安を抱えている人もいるでしょう。
自宅での生活では病院とは違い、再発予防のために自分自身での体調管理が必要となります。
しかし、「無事退院できたけど、これから何を気を付ければよいの?」「また突然、発症したらどうしよう」という方も多いと思います。
この記事では、くも膜下出血の退院後に気をつけるべき「生活習慣」や、再発予防に効果的な「血圧の管理」について解説します。
くも膜下出血の「退院後の生活」における注意点を理解し、再発への不安を減らすために、ぜひ最後までお読みください。
また、くも膜下出血の再発率を下げたい方は、再生医療も選択肢の一つになります。
くも膜下出血を含む脳卒中は、以下のような特徴があり、再発予防が極めて重要です。
- 初回が軽症でも再発リスクが高い
- 治療中・リハビリ中でも血管の閉塞や破裂が起こりうる
- 高血圧や糖尿病などの生活習慣病があると再発リスクがさらに上昇する
また実際に当院の治療を受けられた症例動画は、以下で紹介しています。
【こんな方は再生医療をご検討ください】
- くも膜下出血の再発率を少しでも下げたい方
- 後遺症を改善したい方
- 将来的に寝たきりや再発のリスクを減らしたい方
早期の適切な管理が、再発予防にも、生活の質(QOL)の向上にもつながります。
当院(リペアセルクリニック)の公式LINEでは、再生医療の治療法や症例も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
目次
くも膜下出血の退院後に気をつけるべき生活習慣【再発予防が大切】
くも膜下出血の再発予防のために気をつけるべき習慣には、以下のようなものがあります。
くも膜下出血の再発を防ぐには、退院後の生活習慣や血圧の管理が深く関わりますので、ぜひ参考にしてください。
体調に変化があればすぐ主治医へ相談する
退院後にいつもと違う体の異変を感じた場合、すぐに病院を受診するか、もしくは救急要請をしてください。
くも膜下出血の再発や他の脳卒中は、突発的に起こる場合があります。
再発や脳卒中が疑われる症状は、以下の通りです。
| 部位 | 症状の例 |
|---|---|
| 頭・首 | ・突発的で激しい頭痛 ・頭痛に伴う噴射状の嘔吐 ・首の後ろが硬く痛む |
| 手足 | ・片方の手足に力が入らない ・箸を落とす ・シャツのボタンが留めにくい |
| 言葉 | ・ろれつが回らない ・言葉が出にくい ・相手の言葉が理解できない |
上記のような症状が見られる場合は、脳の中で再び出血が起きていたり、脳の別の部分に異常が起きている可能性があります。
処方薬は医師・薬剤師の指示通り正しく服用する
処方された薬の中で、特に血圧を下げる薬(降圧剤)は、医師や薬剤師の指示通りに飲み続ける必要があります。
体調が良いから大丈夫と感じても、ご自身の判断で薬の量を減らしたり、飲むのをやめたりしないでください。
薬で抑えられていた血圧は、服用をやめると以前より高く跳ね上がる現象(リバウンド現象)が起こる可能性があります。
リバウンド現象のような急激な血圧の変動が、弱っている血管に大きなダメージを与え、血管の再破裂の引き金になる可能性があるため、注意が必要です。
定期的に血圧を測定する
くも膜下出血の再発予防において、ご自身の判断で調整できる上に、血管への影響が大きいものが血圧です。
退院後は、毎日決まった時間に血圧を測り、記録する習慣をつけましょう。
血圧測定の具体的なタイミングの目安は、以下の表で確認しましょう。
| 測定のタイミング | 具体的な条件 |
|---|---|
| 朝・起床後1時間以内 | ・排尿後 ・薬を飲む前 ・朝食前 |
| 夜・寝る前 | ・入浴や食事の直後を避ける ・リラックスした状態 |
脳卒中を経験した方の血圧目標は、健常者の基準よりも厳しめに設定されており、家庭で測る血圧で「130/80 mmHg未満」とされています。
※参照:日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン」
測定した血圧の数値はすべて記録し、受診の際に主治医に確認してもらいましょう。
ストレスを溜めない・生活リズムを整える
ストレスや寝不足、不規則な生活は自律神経を乱して血圧を上げる原因になります。
緊張で「交感神経」が刺激されることで血管が収縮してしまうため、特にくも膜下出血後は通常より、血圧変動が大きくなりやすいです。
以下のポイントを意識して生活リズムを整えましょう。
生活リズムを整えるポイント
- 十分な睡眠時間をとる
- 日中は無理なく活動する
- 夜はリラックスして休む
- 趣味などでストレスを解消する
飲酒は控えめにし、喫煙は避ける
くも膜下出血の再発予防のため、飲酒は控えめにし、喫煙は避ける必要があります。
アルコールの摂取や喫煙は血圧の急な変動を招いたり、動脈硬化を進めたりする原因になるためです。
血管の健康を守るためにも、動脈硬化を招く飲酒・喫煙に対しては、今まで以上に注意しましょう。
塩分を抑え、バランスの良い食事を意識する
血圧を管理するために、減塩の徹底が効果的です。
高血圧の治療での目安として、1日の塩分摂取目標を6g未満と定められています。
※参照:日本高血圧学会「さあ、減塩!」
塩分を摂りすぎると、血液中の水分量が増え、血管への圧力が高まります。
以下の点に注意し、塩分を控えた食事を意識してください。
減塩のための工夫
- ラーメンやうどんの汁は残す
- 漬物や干物を控える
- 酸味や香辛料、ハーブを活用する
濃いめな味が好きな方には抵抗があるかもしれませんが、再発予防のためにも減塩を心がけましょう。
運動機能を低下させないように注意する
退院後は運動機能を低下させないよう、適度な運動を生活に取り入れましょう。
適度な運動は体力維持や血圧安定に効果的と考えられています。
推奨される運動は、以下の通りです。
推奨される運動
- ウォーキング
- 軽いジョギング
- 水中ウォーキング
上記のような軽く息が弾む程度の有酸素運動は、血管を広げて血圧を下げる働きが期待できます。
ただし、自己判断で運動を始めるのではなく、必ず医師に相談してから始めるようにしましょう。
くも膜下出血の退院後はリハビリが重要|体力回復と再発予防に役立つ
くも膜下出血の退院後に後遺症が残っている場合でも、リハビリテーションの継続が回復につながります。
リハビリには、機能の回復だけでなく体を使わないことで体力が衰えてしまう「廃用症候群(はいようしょうこうぐん)」を防ぐ目的があります。
また、脳の神経細胞の一部がダメージを受けても残った細胞が新しいネットワークを作り直し、失われた機能を代行する能力「可塑性(かそせい)」が脳には備わっています。
可塑性は発症してから長い期間続くと知られており、退院後も諦めずに適切なリハビリを続けると、ゆっくりとした改善が期待されます。
くも膜下出血の再発予防には退院後の継続的な治療が欠かせない!
くも膜下出血の退院後は、再発を防ぐための継続的な治療が必要です。
この記事で解説した内容は以下のとおりです。
まとめ
- いつもと違う症状が出たらすぐに主治医へ相談する
- 血圧の目標は「家庭血圧130/80 mmHg未満」とする
- 降圧剤はご自身の判断で中止しない
- 1日の塩分摂取量を6g未満に抑え、禁煙を徹底する
- ウォーキングなどの有酸素運動を無理のない範囲で続ける
くも膜下出血の後遺症による麻痺や機能障害が残り、リハビリを続けても改善が見られず悩んでいる場合は、再生医療も選択肢の一つになります。
当院(リペアセルクリニック)では、ご自身の脂肪から取り出した幹細胞を用いる「自己脂肪由来幹細胞治療」を行っています。
脳卒中後の慢性的な後遺症の改善を目指す治療ですので、ご自身の症状が対象となるか知りたい方は、当院の公式LINEよりご確認ください。
くも膜下出血の退院後の生活に関するよくある質問と回答
以下では、くも膜下出血の退院後の生活に関してよく寄せられる質問にお答えします。
仕事復帰や車の運転が可能な時期は?
仕事復帰や車の運転が可能な時期の目安は、以下のとおりです。
| 項目 | 注意点 |
|---|---|
| 仕事復帰 【目安】軽度:1〜3ヶ月 【目安】重度:半年〜 |
・負担の少ない業務から始める(短時間勤務やデスクワークなど) ・復帰時期は主治医や産業医と相談して決定する |
| 車の運転再開 【目安】発症後 3〜6ヶ月以降 |
・麻痺や注意力、判断力の客観的な評価が必要 ・運転免許センターでの適性相談や検査を受ける必要がある ・医師の診断書をもとに許可を得る |
ただし、上記期間はあくまで目安です。症状により許可が下りない場合もあります。
仕事復帰や車の運転再開はご自身の判断で行わず、必ず主治医の許可を得てください。
退院後に避けた方が良い食べ物は?
退院後は、血圧管理と動脈硬化の予防のため、塩分や脂質の多い食事を控える必要があります。
退院後に控えるべき食品の例は、以下の通りです。
塩分を多く含むもの
- ラーメンやうどんの汁
- 漬物、干物
- 練り物(ハムなど)
- スナック菓子
脂質(飽和脂肪酸・トランス脂肪酸)を多く含むもの
- 肉の脂身
- バター、生クリーム
- マーガリン
- ショートニング(菓子パンなどに使用)
これらの食品を完全に断つのではなく、まずは量を減らすよう意識してみましょう。

監修者
圓尾 知之
Tomoyuki Maruo
医師
略歴
2002年3月京都府立医科大学 医学部 医学科 卒業
2002年4月医師免許取得
2002年4月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2002年6月関西労災病院 脳神経外科 勤務
2003年6月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2003年12月大阪母子医療センター 脳神経外科 勤務
2004年6月大阪労災病院 脳神経外科 勤務
2005年11月大手前病院 脳神経外科 勤務
2007年12月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2012年3月大阪大学大学院 医学系研究科 修了(医学博士)
2012年4月大阪大学医学部 脳神経外科 特任助教
2014年4月大手前病院 脳神経外科 部長