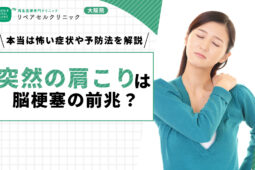- 脳梗塞
- 脳卒中
- 頭部
脳梗塞の合併症とは?急性期から慢性期まで注意すべき症状を解説
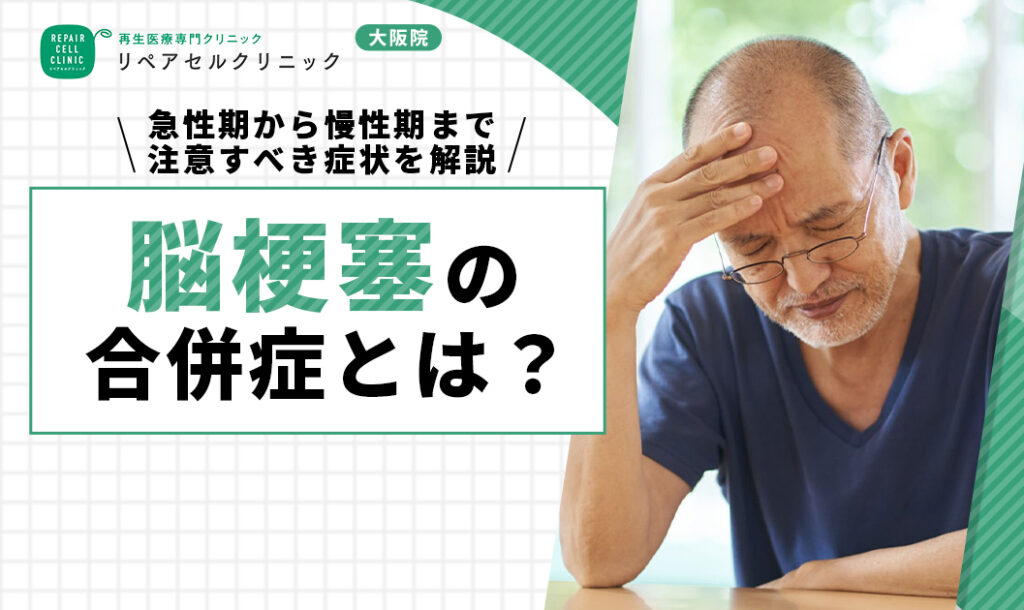
脳梗塞とは脳の血管が詰まって血流が途絶え、酸素や栄養が届かなくなった脳細胞がダメージを受ける病気です。
発症後は脳梗塞の後遺症に加えて、時間の経過とともにさまざまな合併症が起こることがあり、命に関わるリスクや生活の質を大きく低下させる可能性があります。
この記事では、脳梗塞で起きやすい主な合併症と、それぞれの対処法・治療法を詳しく解説します。
合併症からの回復には、早期発見と適切な対応が重要です。
脳梗塞やその合併症で悩まれている方は、ぜひ最後まで読んで適切な対処法を見つけましょう。
また近年は従来のリハビリや薬物療法だけで改善が難しい症状に対し、再生医療は新たな選択肢の一つになります。
症状にお悩みの方は
再生医療をご検討ください
【こんな方は再生医療をご検討ください】
- 合併症に悩まされている
- 麻痺やしびれが残り、日常生活に支障が出ている
- リハビリを続けているが改善が停滞している
- できるだけ手術は避けたい
実際に治療を受けた方の症例については、以下の動画でもご紹介しています。
再生医療の治療法や症例については、当院(リペアセルクリニック)公式LINEでも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
目次
脳梗塞の主な合併症
脳梗塞を発症すると、麻痺や言語障害だけでなく、さまざまな合併症が起こる可能性があります。
これらの合併症は急性期(発症直後から数日間)から慢性期(発症後数週間以降)にかけて現れることがあり、早期発見と適切な対応が重要です。
主な合併症として以下があります。
これらの合併症は命に関わるものから、日常生活に大きな影響を与えるものまでさまざまです。
それぞれの症状や特徴を正しく理解して、早期に対応できるよう備えましょう。
体温調節障害|発熱や高体温が続く場合は要注意
脳梗塞によって脳の中で体温をコントロールする部分が傷つくと、身体の熱を適切に調節できなくなります。
この状態を体温調節障害といい、発症後の数日間に起こりやすい合併症です。
主に以下の症状があります。
- 脳の体温調節中枢が損傷することで、体温をうまくコントロールできなくなる
- 38度以上の発熱が続く、または身体が異常に熱くなる
- 感染症がないのに高熱が出る場合は体温調節障害の可能性がある
- 脳のダメージを悪化させるため、早めの対応が必要
高熱が続くと脳へのダメージがさらに広がる可能性があるため、熱が下がらない場合は医療スタッフにすぐに伝えることが大切です。
誤嚥性肺炎
脳梗塞によって飲み込む力が弱くなると、食べ物や飲み物、唾液などが誤って気道に入ってしまうことがあります。
これを誤嚥(ごえん)といい、気道に入った細菌が肺で増えて炎症を起こす状態が誤嚥性肺炎です。
症状は以下のとおりです。
- 飲み込む機能が低下し、食べ物や唾液が誤って気道に入ってしまう
- 気道に入った細菌が原因で肺に炎症が起こる
- 咳、発熱、呼吸困難などの症状が現れる
- 脳梗塞の合併症の中でも命に関わる危険性が高い
高齢者や飲み込む機能が低下している方にとくに起こりやすく、発熱や咳、呼吸が苦しくなるなどの症状が見られます。
予防には口の中を清潔に保つことや、飲み込む力を高めるリハビリが効果的です。
食事の際は姿勢に注意し、ゆっくり食べるよう心がけましょう。
脳出血・消化管出血などの出血性合併症
脳梗塞の治療で血栓を防ぐために使用する、血液をサラサラにする薬の影響で出血しやすくなることがあります。
とくに注意が必要なのは脳内での出血と、胃や腸からの出血です。
以下の特徴があります。
- 血液をサラサラにする薬の影響で出血しやすくなる
- 脳内で出血が起こると、頭痛や意識障害などの症状が現れる
- 胃や腸から出血すると、黒い便や吐血が見られることがある
- 命に関わる重大な合併症のため、早急な対応が必要
脳内で出血が起こると、急激な頭痛や意識レベルの低下、新たな麻痺などの症状が現れます。
消化管から出血している場合は、便が黒くなる、吐血する、貧血症状が出るなどのサインがあります。
これらの症状に気づいたら、すぐに医療機関に連絡してください。定期的な検査で早期発見に努めることも大切です。
血管性認知症(記憶障害・判断力低下など)
脳梗塞が原因で脳の細胞が傷つくと、記憶や判断、思考などの認知機能が低下することがあります。
これを血管性認知症といい、脳梗塞の発症直後や、複数回の脳梗塞を経験した後に現れやすい症状です。
主な症状は以下のとおりです。
- 脳梗塞によって脳の細胞が損傷し、認知機能が低下する
- 記憶力の低下、判断力の低下、集中力の低下などが見られる
- 感情のコントロールが難しくなり、怒りっぽくなることもある
- 脳梗塞を繰り返すと症状が段階的に悪化する
完全に元に戻すことは難しいですが、脳梗塞の再発を防ぐことで進行を抑えられます。
血圧管理や生活習慣の改善、リハビリの継続が重要です。
サルコペニア(筋力低下・筋萎縮)
サルコペニアとは、筋肉の量が減り、筋力が低下する状態です。
脳梗塞によって身体を動かせない状態が続くと、筋肉が急速に衰えてしまいます。
サルコペニアの特徴は以下のとおりです。
- 麻痺や安静状態が続くことで筋肉が衰える
- 筋力が低下し、立つ、歩く、物を持つなどの動作が困難になる
- 転倒のリスクが高まり、日常生活の自立度が低下する
- 栄養状態の悪化も筋力低下を加速させる
サルコペニアが進むと、立ち上がる、歩く、階段を上るなどの基本的な動作が難しくなり、転倒や骨折のリスクも高まります。
予防には早期からのリハビリが最も効果的です。
褥瘡(床ずれ)
脳梗塞で寝たきりに近い状態が続くと、身体の同じ部分に圧力がかかり続けて、皮膚や皮下組織が傷んでしまいます。
これが褥瘡(じょくそう)、一般的には床ずれと呼ばれる状態です。
褥瘡の主な特徴は以下のとおりです。
- 同じ姿勢で長時間横になることで、皮膚に圧力がかかり続ける
- 血流が悪くなり、皮膚や組織が傷んで潰瘍ができる
- お尻、かかと、肩甲骨、腰などの骨が出ている部分に起こりやすい
- 悪化すると感染症を引き起こし、治療に時間がかかる
褥瘡は一度できると治りにくく、悪化すると皮膚が深くえぐれて感染症を起こすこともあります。
予防には定期的な体位変換(2時間ごとに身体の向きを変える)ことが大切です。
脳梗塞の合併症が起きた際の対処法・治療法
脳梗塞の合併症が起こったときは、それぞれの症状に応じた適切な対処が必要です。
以下に主な合併症の対処法と治療法をまとめました。
| 合併症の種類 | 対処法・治療法 |
|---|---|
| 体温調節障害 | ・通常は解熱鎮痛薬を使用して熱を下げる ・感染症など他の原因がないか確認しながら、慎重に体温管理を行う |
| 誤嚥性肺炎 | ・抗菌薬を投与して肺の炎症を抑える ・呼吸が苦しい場合は酸素を投与する ・口の中を清潔に保つケアを行う ・飲み込む力を高めるリハビリを継続して行う |
| 脳出血・消化管出血 | ・血液をサラサラにする薬を一時的に中止する ・必要に応じて血液製剤や血小板輸血を行う ・脳内出血の場合は血圧を下げる薬や、出血を止める薬を使用する |
| 血管性認知症 | ・血圧のコントロールや生活習慣の改善を行う ・脳の血流を良くする薬を使用することもある ・リハビリで身体機能の低下を防ぐ ・脳梗塞の再発予防が最も重要 |
| サルコペニア | ・リハビリを中心とした運動療法で筋力を維持・向上させる ・タンパク質やアミノ酸を多く含む食事で栄養状態を改善する ・早期からリハビリを開始することが予防につながる |
| 褥瘡(床ずれ) | ・2時間ごとに体位を変えて同じ部分に圧力がかからないようにする ・専用のマットレスやクッションを使用する ・皮膚を清潔に保つ ・すでに褥瘡ができている場合は、傷の処置と栄養管理を行う |
合併症は早期に発見して対応するほど、重症化を防げる可能性が高まります。
日頃から身体の変化に注意を払い、気になる症状があればためらわずに医療スタッフに伝えましょう。
脳梗塞の合併症が疑われたらすぐに受診しよう!再生医療という選択肢も
脳梗塞の合併症は、急性期から慢性期まで幅広い時期に現れる可能性があります。
体温調節障害や誤嚥性肺炎、出血性合併症などは命に関わることもあるため、少しでも異変を感じたらすぐに医療機関を受診してください。
脳梗塞をはじめとする脳卒中に対しては、再生医療も選択肢の一つです。
再生医療では、脳卒中の後遺症改善や再発予防を目的として、幹細胞を使用します。
当院「リペアセルクリニック」で行っている再生医療については、以下の動画をご覧ください。
実際に脳卒中の方に対する症例については、当院の公式LINEで紹介しているので、ぜひご覧ください。

監修者
圓尾 知之
Tomoyuki Maruo
医師
略歴
2002年3月京都府立医科大学 医学部 医学科 卒業
2002年4月医師免許取得
2002年4月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2002年6月関西労災病院 脳神経外科 勤務
2003年6月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2003年12月大阪母子医療センター 脳神経外科 勤務
2004年6月大阪労災病院 脳神経外科 勤務
2005年11月大手前病院 脳神経外科 勤務
2007年12月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2012年3月大阪大学大学院 医学系研究科 修了(医学博士)
2012年4月大阪大学医学部 脳神経外科 特任助教
2014年4月大手前病院 脳神経外科 部長