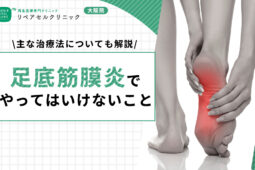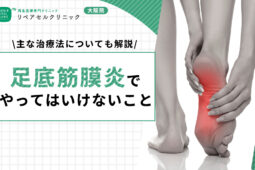- 足底腱膜炎
歩きすぎは足底筋膜炎(足底腱膜炎)の原因になる?足裏の痛みが続くときの治療法を医師が解説

歩きすぎた翌日や、朝起きて一歩踏み出した瞬間に「かかとがズキッと痛む」ことはありませんか?
その痛みは、もしかすると足底筋膜炎(足底腱膜炎)が原因かもしれません。
足底筋膜炎は、歩きすぎ以外にも立ち仕事・合わない靴、足のアーチの崩れなどによって足裏の組織に負担が蓄積し、炎症を起こすことで発症します。
しかし、「なぜ歩きすぎると足底筋膜炎になってしまうのか?」と、疑問や悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、歩きすぎが足底筋膜炎を引き起こすメカニズムや、その他の原因、対策について詳しく解説します。
「足裏の痛みがなかなか治らない」「また気兼ねなく歩けるようになりたい」という方は、ぜひ参考にしてください。
改善しない足底筋膜炎に
お悩みの方へ
従来の治療法(湿布やステロイド注射など)ではなかなか改善せず、痛みを繰り返しているという方は、再生医療も選択肢の一つになります。
再生医療は、患者さまご自身の血液や細胞が持つ自然治癒力を活用する治療法で、損傷した組織の修復そのものを促すことを目的としています。
【こんな方は再生医療をご検討ください】
- 歩くたびに痛みがあり、趣味の散歩やスポーツが楽しめない
- 既存の治療では改善が見られず、手術はできるだけ避けたい
また実際に治療を受けた方の症例については、以下の動画でもご確認いただけます。
治療法や症例については当院(リペアセルクリニック)の公式LINEでも紹介していますので、ご覧ください。
目次
なぜ歩きすぎで足底筋膜炎(足底腱膜炎)になるのか【症状を解説】
歩きすぎは足底筋膜に過度な負担を与えるため、炎症が起こりやすく足底筋膜炎の原因になります。
足底筋膜はかかとから足指の付け根まで伸びる強い線維組織で、土踏まずを支えて歩行時の衝撃を吸収するクッションの役割を果たし、歩くたびに「伸ばされる力」と「地面からの衝撃」が同時に加わります。
特に長時間歩くことや、急に運動量を増やすことでかかとの骨(踵骨)付近に負担が集中するため、その部位が傷つきやすくなり、炎症や痛みが生じやすくなるのです。
典型的な症状としては、以下のようなものがあります。
- 朝起きて最初の一歩でかかとに鋭い痛みが走る
- 歩き始めにズキッとした痛みが出る
- 長時間の立位や歩行で痛みが悪化する
これらは、安静時に縮んでいた足底筋膜が歩き出しの瞬間に急に伸ばされ、強い負荷がかかるために起こる現象です。
足底筋膜炎を放置すると慢性化し、治るまでに時間がかかるため、痛みが続く場合は整形外科を受診しましょう。
歩きすぎだけじゃない!足底筋膜炎の主な原因
以下では、歩きすぎ以外で考えられる足底筋膜炎の主な原因について解説します。
足裏の痛みを根本的に解決するためには、単に歩く量を減らすだけでなく、「なぜ負担がかかっているのか」を把握することが大切です。
ご自身に当てはまる要因がないか、以下のポイントをチェックしてみましょう。
足裏に繰り返し負担がかかる動作・環境(オーバーユース)
足底筋膜炎の代表的な原因の一つがオーバーユース(使いすぎ)であり、日常生活や仕事、運動習慣の中で足裏に強い負荷が継続することが発症につながります。
特に以下のような動作や環境では、足底筋膜に過剰な衝撃や伸張力が繰り返し加わることで負担が溜まり、痛みが出やすくなるため注意が必要です。
| 項目 | 詳細 |
| 負担のかかる運動 |
・マラソン |
| 負担のかかる仕事 | ・立ち仕事 ・硬い床での作業 ・重量物の持ち運び など |
回復が追いつかないまま負荷が重なると、痛みが慢性化し、日常生活にも支障が出ることがあります。
足裏に疲労を感じる場合はストレッチやマッサージを取り入れ、休息を確保するなど負荷を軽減しましょう。
簡単なストレッチ方法については、以下でも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
足のアーチバランスの乱れ(扁平足・ハイアーチ)
足のアーチバランスが乱れると足底筋膜に負担が集中しやすくなり、足底筋膜炎の発症につながります。
足のアーチとは土踏まずの部分にある弓状の構造で、歩行時の衝撃を吸収するクッションの役割を果たしています。
このアーチが崩れると衝撃をうまく分散できず、足底筋膜に負担が偏って炎症を起こしやすくなるのです。
代表的な足のアーチ崩れには、以下の2つがあります。
| 項目 | 詳細 |
| 扁平足 |
・土踏まずが低く、足底筋膜が過度に引き伸ばされやすい |
| ハイアーチ | ・土踏まずが高すぎる状態 ・衝撃吸収機能が弱く、地面からの衝撃がダイレクトに伝わる |
これらのアーチ異常は先天的な体質による場合もありますが、後天的な要因で悪化することも多いです。
- 足裏の筋力低下
- 長時間の立ち仕事
- 運動習慣の偏り
- タコやウオノメによる体重の偏り
アーチバランスが乱れた状態を放置すると、歩くたびに足底筋膜へ過剰な力が加わり、炎症や痛みが慢性化しやすくなります。
早期の段階でアーチを支えるインソールを使用したり、足裏の筋力を鍛えるトレーニングを取り入れることが予防と改善に有効です。
サイズに合わない靴を履いている
サイズに合わない靴を履くことは足底筋膜に余計な負担をかけ、足底筋膜炎を引き起こす原因になります。
| 項目 | 詳細 |
| 小さい靴を履くと起こる問題 |
・足が圧迫され、歩行時の重心が乱れる |
| 大きすぎる靴を履くと起こる問題 |
・靴の中で足が滑り、歩行が不安定になる |
また、クッション性の低い靴や底がすり減った靴は衝撃吸収が不十分になり、着地の負担がダイレクトに伝わるので注意しましょう。
症状を予防するためには、かかとがしっかり支えられ、つま先に適度な余裕がある靴を選ぶことが大切です。
さらにアーチサポートやクッション性のあるインソールを使用することで、歩行時の衝撃を軽減し、足底筋膜への負担を抑える効果が期待できます。
足裏のクッション性の低下や足の柔軟性低下・筋力不足
足裏のクッション性が弱くなったり、足やふくらはぎの柔軟性・筋力が不足すると、以下のように歩行時の衝撃が直接足底筋膜に伝わりやすくなり、足底筋膜炎を発症しやすくなります。
こうした状態を引き起こす主な原因には、以下のような変化が挙げられます。
- 加齢により足裏のクッション性を担う脂肪が薄くなり、衝撃を吸収しにくくなる
- ふくらはぎやアキレス腱の柔軟性が低下し、足底筋膜に負担がかかりやすくなる
- 足裏や足指の筋力低下でアーチが支えられず、衝撃が足底に集中しやすくなる
これらの変化が重なると、歩くたびに足底筋膜に負荷がかかり続け、炎症や痛みが起こりやすい状態になるのです。
特に若いころからの運動不足や、長年の立ち仕事で蓄積した疲労が、加齢とともに症状として表面化することも少なくありません。
足底筋膜炎を防ぐためには、足裏の筋力強化トレーニングやふくらはぎのストレッチを習慣的に行い、必要に応じて整形外科で相談しましょう。
体重増加・肥満による負荷
体重が増えると、以下のように歩行や立つたびに足裏へかかる圧力が大きくなるため、足底筋膜炎のリスクが高まります。
- 足底筋膜へ伝わる負荷が大きくなる
- 過剰な負荷で土踏まずのアーチが押しつぶされ、扁平足を助長しやすくなる
- アーチが崩れると衝撃が分散できず、足底筋膜に負担がかかりやすくなる
このような負担を軽減するためには、自分の適正体重を把握しておくことが大切です。
以下を目安に、自身の適正体重を確認しましょう。
| 適正体重 | 身長(m)× 身長(m)×22=適正体重(kg) |
| BMI(体格指数) | 体重(kg)÷[身長(m)×身長(m)]=BMI値 |
※参照:日本医師会「身長から、自分の適正体重を知る」
体重が増えるほど足裏に伝わる衝撃は大きくなり、足底筋膜の回復が追いつかず炎症が慢性化しやすくなります。
ただし普段運動習慣のない人が急にランニングを始めたり、運動量を急激に増やすと、足底筋膜にさらに過度な負荷がかかるため注意が必要です。
無理のない範囲で体重管理や運動習慣を見直しましょう。
足底筋膜炎の主な治療法
足底筋膜炎の主な治療法としては、以下のようなものがあります。
| 治療法 | 詳細 |
| 保存療法 | ・ストレッチ、ふくらはぎの柔軟性向上、足底筋膜の緊張緩和 ・温熱療法・超音波などの物理療法 ・消炎鎮痛薬の使用 ・アーチサポート付きインソールで負荷を軽減 ・痛みが強いときは体外衝撃波治療(ESWT)やステロイド注射を行う場合もある |
| 手術療法 |
・痛みの原因となる足底筋膜の一部を切除する足底筋膜切離術 ・かかとの骨の棘(骨棘)を削る骨棘切除術 |
| 再生医療 |
・幹細胞治療やPRP治療など、組織修復を促す治療 ・手術を避けたい人や早期の改善を希望する人の選択肢 |
足底筋膜炎の治療は、まず保存療法を中心に進めるのが一般的で、多くの場合は手術を行わずに改善が期待できます。
保存療法で改善する例が多い一方、長期化した場合はより専門的な治療が必要となるため、痛みが続く場合は整形外科で適切な治療方針を確認することが大切です。
足底筋膜炎にならないためには歩きすぎに注意!痛みを感じたら早期受診をしよう
足底筋膜炎を予防するためには、歩きすぎによる負担を避け、足裏にかかるストレスを日頃から減らすことが大切です。
特に、急に歩行量を増やしたり、クッション性の低い靴で長時間過ごすと足底筋膜に負荷がかかりやすくなるため注意が必要です。
また、ふくらはぎや足裏のストレッチ、体重管理、アーチを支えるインソールの活用は、発症予防に役立ちます。
しかし、セルフケアだけでは改善しにくい痛みや慢性的な炎症に悩まされることもあります。
こうした場合は、早めに整形外科を受診し、症状の程度に応じた治療を受けましょう。
また近年では、保存療法で改善しにくい慢性の足底筋膜炎に対し、「再生医療」という新しい選択肢も注目されています。
【当院の再生医療】
- 損傷した組織の修復・再生を促すため、治療期間の短縮が期待できる
- 手術が必要とされるケースでも避けられる可能性がある
- スポーツの早期復帰を目指せる
- 患者本人の細胞を利用するため、副作用が少ない
症例紹介・治療の流れや再生医療の基礎知識については、当院(リペアセルクリニック)の公式LINEでも紹介しています。
足底筋膜炎をはじめ足の痛みで悩んでいる方、スポーツ復帰を少しでも早めたい方は、一度チェックしてください。
足底筋膜炎に関するよくある質問と回答
足底筋膜炎に関するよくある質問と回答は以下のとおりです。
足底筋膜炎と足底腱膜炎の違いは?
足底筋膜炎と足底腱膜炎は、名称に違いがあるものの、多くの医療機関ではほぼ同じ疾患として扱われています。
ただし厳密には、以下のように痛みが生じるタイミングや症状の出方に違いが見られる場合があります。
| 足底筋膜炎 | 足裏の筋膜部分に炎症が起こり、歩き始め・立ち上がりの瞬間に鋭い痛みが出やすい |
| 足底腱膜炎 | 足底腱膜の付着部(かかと付近)の炎症が中心で、持続的な痛みや慢性的な鈍い痛みが起こりやすい |
両者は炎症が起きる部位が非常に近いため、症状・原因・治療法がほぼ同じです。
かかとや土踏まずに痛みを感じる場合、放置してしまうと慢性化し治りにくくなることがあります。
痛みが続く時は早めに医療機関を受診し、適切な治療を受けましょう。
足底筋膜炎になりやすい人の特徴は?
足底筋膜炎になりやすい人の特徴は、以下のとおりです。
- 中年以降の女性
- 長時間の立ち仕事をしている人
- スポーツをよくする人
- 扁平足・ハイアーチなど足の形に問題がある人
- 体重が増加している人・肥満傾向の人
- ふくらはぎの柔軟性が低い人、歩き方に癖がある人
- クッション性の低い靴を履いている人
足裏に大きな負担がかかりやすい生活習慣や体の特徴を持つ人に発症しやすい傾向があります。

監修者
坂本 貞範
Sadanori Sakamoto
医療法人美喜有会 理事長
「できなくなったことを、再びできるように。」
人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの
お手伝いができれば幸甚の至りでございます。
略歴
1997年3月関西医科大学 医学部卒
1997年4月医師免許取得
1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務
1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務
1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務
1999年2月国立大阪南病院 勤務
2000年3月野上病院 勤務
2003年3月大野記念病院 勤務
2005年5月さかもとクリニック 開設
2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任
2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設
2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設