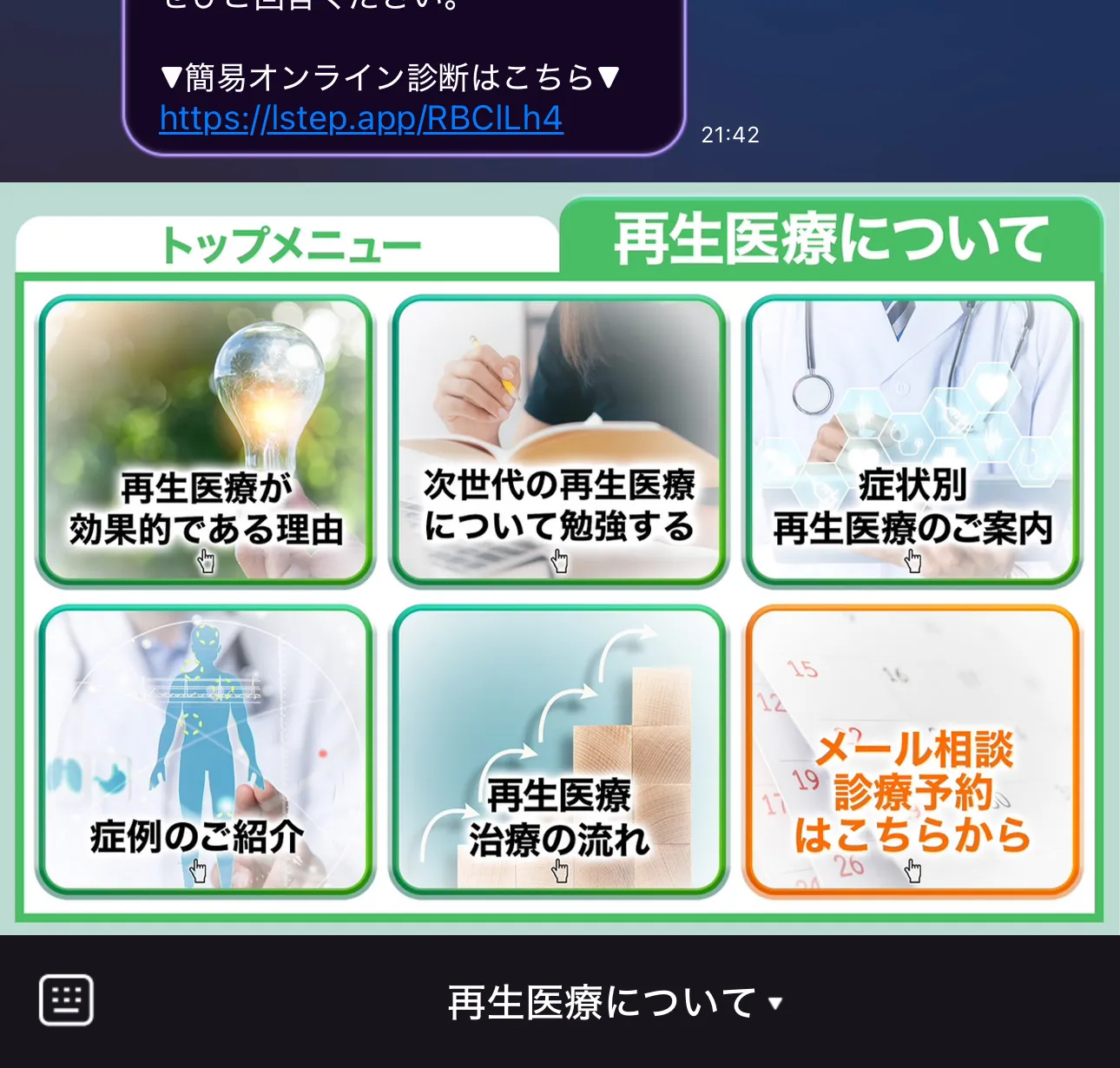サッカー選手が足底腱膜炎(足底筋膜炎)になりやすい理由とは?原因・対処法まで解説
公開日: 2019.12.20更新日: 2025.06.30
サッカーをしていると、足裏に痛みを感じることはありませんか?
特にかかとや土踏まずの痛みが慢性的に続く場合は、足底腱膜炎の可能性があります。
サッカーは長距離のランニング・急な方向転換・キック動作など足への負荷が大きく、実際に足底腱膜炎を発症する選手は少なくありません。
痛みを我慢してプレーを続ければ、悪化して長期離脱につながるケースもあるので注意が必要です。
この記事では、なぜサッカー選手が足底腱膜炎になりやすいのか・発症した場合の対処法について解説します。
ケガを未然に防ぎたい方や、すでに足裏の痛みに悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。
また手術は避けたいけれど、できるだけ早くサッカーに復帰したいという方は、再生医療という新たな治療の選択肢もあります。
治療法や症例については、当院(リペアセルクリニック)の公式LINEでも解説していますので、ぜひ参考にしてください。
目次
サッカー選手が足底腱膜炎(足底筋膜炎)になりやすい原因とは
サッカー選手に足底腱膜炎が多い主な原因は、足底腱膜への繰り返しの負荷にあります。
サッカーは、1試合あたり約10km以上を走るスポーツであり、以下のような動きも求められます。
- 長時間のランニング
- 急なターンやストップ
- 方向転換
- ジャンプ
これらの動作は、足裏のアーチを支えている足底腱膜に継続的なストレスを与えるため、負担が蓄積しやすいのです。
特に人工芝や硬いグラウンドでのプレーでは、足底に伝わる衝撃が大きくなり、足底腱膜の微細な損傷が進行・炎症 ・痛みという流れで足底腱膜炎を発症するケースにつながります。
さらに足底腱膜炎は、外見上の腫れや赤みが出にくいため、本人が炎症に気づかずプレーを続けてしまうことも少なくありません。
その結果、ある日突然、かかとや土踏まずに鋭い痛みを感じて発症に気づくというケースが多いのが特徴です。
足底腱膜炎の症状
足底腱膜炎の症状は以下の通りで、主にかかとや土踏まずの痛みが生じます。
- かかと~土踏まずにかけての鋭い痛み
- 歩き始めに強い痛みを感じるが、歩いているうちに軽減することがある
- 足裏を押すとピンポイントで痛みを感じる部位がある
- ランニングやジャンプ後に痛みが強くなる
- 朝の一歩目が特につらい
- 症状が進むと安静時にも痛むことがある
特に、朝起きて最初に足を着いたときや、長時間の座位の後に立ち上がった瞬間に強く痛みを感じるのが特徴です。
これは、安静時に縮こまった足底腱膜が、急に引き伸ばされることで炎症部に負担がかかるためです。
痛みは初期段階では運動後に出現する程度でも、放置すると慢性化し、日常生活に支障をきたすようになるので、早期の対処が重要です。
サッカー選手が足底腱膜炎を予防するための方法
サッカー選手が足底腱膜炎を予防するための方法として、以下のようなものがあります。
- スパイクを見直す
- 練習量を調整する・オーバーユースに注意する
- 足の筋肉・柔軟性を鍛える
- ゴルフボールを使ったマッサージをする
これらの対策は、足底腱膜炎の予防だけでなく、サッカーに伴う他の足のトラブルの防止にも役立ちますので、ぜひ参考にしてください。
スパイクを見直す
サッカー選手が足底腱膜炎にならないようにするための対策として、スパイクを見直してみるという方法があります。
スパイクは一般的な運動靴に比べて急加速や急停止、ターンや切り返しなどがしやすくなるなど、パフォーマンスが上がるというメリットがある一方で、足への負担が大きくなるというデメリットもあります。
最近では、衝撃吸収性に優れた高弾性のスパイクも登場しており、足への負担を軽減するうえで有効です。
また、足裏のサポート力を高めるためにインソール(中敷き)を併用するのも効果的です。
ただし、どんなに弾力性の高いスパイクでも、使用を重ねるうちにクッション性は徐々に低下していきます。
弾力が失われたスパイクを使い続けると、かえって足への負担が増える可能性があるため、適切なタイミングでの買い替えも忘れないようにしましょう。
練習量を調整する・オーバーユースに注意する
足底腱膜炎の原因の一つが、過剰な練習による足のオーバーユース(使いすぎ)で、以下のような状況では注意が必要です。
- 休養を十分に取らずに連日練習している
- 急激に練習強度や時間を増やした
- 疲労が残った状態でプレーを続けている
サッカーのように反復動作が多く、長時間にわたって足に負担をかける競技では、足底腱膜へのダメージが蓄積しやすくなります。
このような状態が続くと、足底腱膜が回復する時間を失い、炎症や痛みの原因となります。
違和感がある日は無理に練習せず、積極的に休養をとる・練習後のアイシングやマッサージを習慣化するなど、練習量と休息のバランスを意識しましょう。
足の筋肉・柔軟性を鍛える
足底腱膜炎の予防・再発防止には、足の筋力と柔軟性を高めることが重要です。
特に、足裏・ふくらはぎ・足首まわりの筋肉をバランスよく鍛えることで、足底への負担を軽減し、衝撃の吸収力が高まります。
無理のない範囲で、継続的にトレーニングやストレッチを取り入れ、足元から健康を整えていきましょう。
ゴルフボールを使ったマッサージをする
過度に使われた足底腱膜は徐々に柔軟性を失い、足底腱膜炎を引き起こしやすい状態になるため、足裏の筋膜や筋肉をマッサージでやさしくほぐしてあげることが大切です。
足裏マッサージの方法はさまざまありますが、自宅で簡単にできるセルフケアとしておすすめなのがゴルフボールを使ったマッサージです。
- 床にゴルフボールを置く
- 裸足または靴下のまま、足裏をボールの上に乗せる
- 足の裏全体を使って、前後にコロコロと転がす
この方法は、足底腱膜全体をまんべんなく刺激し、血行を促進するとともに、筋膜の緊張を和らげる効果が期待できます。
継続しやすいセルフケアとして、ぜひ取り入れてみてください。
足底腱膜炎に悩むサッカー選手は早期の治療が大切
サッカーの上達には日々の練習やトレーニングが不可欠ですが、無理を続けて足底腱膜炎が発症・悪化すると、プレーそのものに影響を及ぼす恐れがあります。
もし足裏に痛みを感じたら、まずは無理をせず安静にし、以下のようなセルフケアも取り入れましょう。
- 練習量を見直す
- 中敷きを交換して衝撃吸収性を高める
- 足裏のマッサージで筋膜の柔軟性を維持する
また、症状が重くなってしまった場合やなかなか改善しない場合には、再生医療という治療法も選択肢の一つになります。
再生医療は、患者自身の細胞を使って損傷組織の修復を促す新しい治療法で、近年はスポーツ障害の分野でも注目を集めています。
サッカーを長く楽しむためにも、早期対応と正しい知識を身につけて、ケガと上手に向き合っていきましょう。

監修者
坂本 貞範
Sadanori Sakamoto
医療法人美喜有会 理事長
「できなくなったことを、再びできるように。」
人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの
お手伝いができれば幸甚の至りでございます。
略歴
1997年3月関西医科大学 医学部卒
1997年4月医師免許取得
1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務
1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務
1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務
1999年2月国立大阪南病院 勤務
2000年3月野上病院 勤務
2003年3月大野記念病院 勤務
2005年5月さかもとクリニック 開設
2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任
2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設
2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設