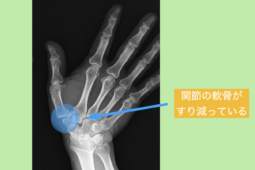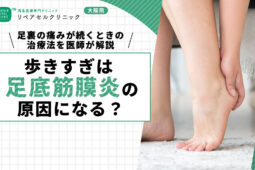- 足底腱膜炎
足底筋膜炎でやってはいけないこと|どのくらいで治る?主な治療法について解説

「足底筋膜炎でやってはいけないことは?」
「足底筋膜炎はどのくらいで治る?」
足底筋膜炎を早く治すために、上記のような疑問やお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
本記事では、足底筋膜炎の回復を妨げる「やってはいけないこと」を中心に、治るまでの期間の目安や主な治療法について詳しく解説します。
- 足底筋膜炎のときにやってはいけない5つのこと
- 足底筋膜炎の症状が治るまでの期間の目安
- 足底筋膜炎の主な治療法
手術以外の治療法として注目されている再生医療についても紹介しますので、つらい痛みを早く治したい方はぜひ参考にしてください。
また、当院リペアセルクリニックの公式LINEでは、足底筋膜炎の治療にも有効な再生医療の治療法や症例を配信中です。
「足底筋膜炎を早く治したい」「手術を避けて治療したい」という方は、ぜひこの機会に再生医療についてチェックしてみてください。
目次
足底筋膜炎でやってはいけないこと
足底筋膜炎と診断されたら、回復を早めるために日常生活での過ごし方が重要になります。
ここでは、足底筋膜炎のときに避けるべき5つの行動を解説します。
良かれと思って行った行動が、症状を悪化させてしまうケースも少なくありません。
上記のやってはいけないことを無意識に行っていないか、ご自身の生活を振り返りながら確認していきましょう。
激しい運動を継続する
激しい運動を継続することは、足底筋膜炎の症状を悪化させる原因の1つです。
足底筋膜炎は足裏への負担の蓄積によって起きるため、無理に運動を続けると炎症を起こした組織にさらに傷がつき、回復が遅れてしまいます。
とくに、以下のような運動は足裏への負担が大きいため、痛みがあるうちは休止しましょう。
- ランニングやジョギング
- 長時間のウォーキング
- サッカーやバスケットボールなど、ジャンプや急な方向転換が多いスポーツ
運動を再開する際は、痛みが完全になくなってから、医師や専門家と相談のうえで軽いメニューから慎重に始めましょう。
以下の記事では、サッカー選手が足底筋膜炎になりやすい理由について詳しく解説しているので、参考にしてください。
かかとへの衝撃が大きい動作を行う
かかとへの衝撃が大きい動作は、炎症を起こしている足底筋膜を刺激してしまうため、症状を悪化させる原因になります。
スポーツだけでなく、日常生活の中にもかかとに大きな衝撃を与える動作は潜んでいます。
日常生活でかかとに衝撃を与える動作
- アスファルトなど硬い地面での運動
- 階段を駆け足で下りる
- 高い場所から飛び降りる
上記の動作は無意識に行ってしまいがちですが、足底筋膜炎の回復を妨げる要因となります。
足裏に痛みがある時期は「エレベーターを使う」「段差はゆっくり降りる」など、かかとへの衝撃を避ける工夫をしましょう。
足に合わない靴を着用する
足に合わない靴を着用すると足裏への負担が増え、足底筋膜炎の回復を遅らせる原因となります。
靴は地面からの衝撃を吸収し、足のアーチを支える重要な役割を担っているため、適切な靴を選ばないと足底筋膜に絶えずストレスがかかり続けます。
以下のような特徴の靴は、できるだけ避けましょう。
- 靴底が薄く、硬い素材の靴(革靴やパンプスの一部)
- クッション性が低いスニーカー
- サイズが合っておらず、靴の中で足が動いてしまうもの
- かかとが固定されないサンダルやハイヒール
とくに、足底筋膜炎の治療中は、かかと部分がしっかりしていて、クッション性の高いスニーカーがおすすめです。
足のアーチを支えるインソール(中敷き)の活用も負担を軽減するうえで効果的な対策です。
自己判断で冷却・温めを行う
自己判断で冷却・温めを行うのは、足底筋膜炎の症状を悪化させるリスクがあるため注意が必要です。
足底筋膜炎は、症状の段階によって適した処置が異なります。
熱感や腫れがある「急性期」には患部を冷やすのが有効ですが、炎症が落ち着いた後の「慢性期」には温める方が効果的な場合があります。
間違ったケアを行うことで、逆効果になりかねません。
| 症状の段階 | 主な症状 | 間違った対処とリスク |
|---|---|---|
| 急性期 | ・運動後のズキズキする痛み ・熱感や腫れ |
温める:炎症がさらに悪化する可能性 |
| 慢性期 | ・歩き始めに痛みがある ・長引く痛み ・足のこわばり |
冷やす:血行不良になり回復が遅れる可能性 |
ご自身の症状を安易に判断するのは避け、必ず医師や理学療法士など専門家の指示に従いましょう。
自己流のストレッチを行う
自己流のストレッチは、足底筋膜炎による炎症を悪化させる危険があります。
正しいストレッチは足底筋膜炎の改善に有効ですが、誤った方法で行うと傷ついた筋膜をさらに傷つける可能性が高いです。
とくに、以下のようなセルフケアには注意しましょう。
避けるべきセルフケア
- 痛みを我慢して足裏を強く伸ばす
- ゴルフボールやテニスボールで足裏をゴリゴリと強く刺激する
ご自身の症状にはどのようなストレッチが適しているか、専門家の指導を受けてから行いましょう。
以下の動画では、足底筋膜炎に対するストレッチについて詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。
足底筋膜炎はどのくらいで治る?
足底筋膜炎の回復までにかかる期間は、症状の重さや治療を始めたタイミング、生活習慣などによって大きく異なります。
症状のレベル別の回復期間の目安は、以下のとおりです。
| 症状のレベル | 主な症状 | 回復期間の目安 |
|---|---|---|
| 軽度 | ・長時間歩いた後に痛む ・朝起きて最初の一歩が少し痛い |
数日〜数週間 |
| 中等度〜重度 | ・歩くのがつらいほどの強い痛み ・日常生活に支障が出ている |
数ヶ月〜1年程度 |
| 難治性 | ・適切な治療をしても6ヶ月以上痛みが続く | 1年以上 |
しかし、上記の期間はあくまで一般的な目安です。
早期回復を目指すためには、治療期間に影響を与える要因を理解し、正しい行動をとることが重要になります。
足底筋膜炎の治し方|主な治療法
足底筋膜炎の治療は、主に以下の3つの選択肢があります。
ご自身の病状と照らし合わせながら、どのような選択肢があるのかを1つずつ確認していきましょう。
保存療法
保存療法は、手術以外のすべての治療法を指し、足底筋膜炎の治療の基本となります。
具体的な治療法は多岐にわたり、以下を組み合わせて行います。
| 安静と活動調整 | 足に負担をかける運動や長時間の立ち仕事を制限する |
| ストレッチ | アキレス腱やふくらはぎを中心に、硬くなった筋肉や腱を伸ばす |
| 装具療法 | インソール(中敷き)やクッション性の高い靴で、足裏への衝撃を和らげる |
| 薬物療法 | 痛みや炎症を抑えるための飲み薬や湿布薬を使用する |
| 注射療法 | 痛みが非常に強い場合に、炎症を抑えるステロイド注射を行う |
| 体外衝撃波治療 | 長引く痛みに対して、特殊な衝撃波で組織の修復を促す |
治療の目的は、患部の炎症を抑え、硬くなった足底筋膜の柔軟性を取り戻すことです。
また、ストレッチや靴の見直しは、再発予防の観点からも重要です。
以下の記事では、足底筋膜炎に対するステロイド注射について詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。
手術療法
手術療法は、保存療法を続けても症状が改善しない「難治性足底筋膜炎」の場合に検討される最終的な選択肢の1つです。
足底筋膜炎と診断された方のうち、手術が必要になるケースはごく一部です。
手術療法のポイント
- 対象となる人:目安として6ヶ月以上、保存療法を試みても効果が見られない場合
- 手術の目的:硬くなってしまった足底筋膜の一部を切り、足裏の緊張を和らげる
- 手術の方法:近年では、内視鏡を使った傷口の小さい手術も実施される
手術療法には、感染症などのリスクや足のアーチのバランスが変わる可能性も伴います。
そのため、手術を受けるかどうかは、メリットとデメリットを十分に理解したうえで、専門医とよく相談して慎重に決定する必要があります。
再生医療
再生医療は、保存療法では十分な効果が得られず、手術には抵抗があるという方にとっての新しい治療選択肢です。
患者さまの細胞や血液を用いて「自己治癒能力」を高め、損傷した組織の再生・修復を促すことを目的としています。
具体的な治療法として、脂肪組織から採取・培養した細胞を用いた「幹細胞療法」や、血液に含まれる血小板を用いた「PRP療法」などがあります。
患者さまの細胞や血液のみを用いるため、拒絶反応やアレルギーのリスクが少ない治療法です。
また、手術や入院を必要とせず、通院のみで治療を受けられるため、日常生活を送りながら足底筋膜炎の改善を目指せます。
以下の記事では、再生医療による足底筋膜炎の治し方について詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。
足底筋膜炎でやってはいけないことに関するよくある質問
足底筋膜炎の治療を進めるうえで、多くの方が抱きやすい疑問についてお答えします。
正しい知識を身につけて、ご自身の症状に合った適切な対処ができるようになりましょう。
足底筋膜炎の簡単な治し方は?
足底筋膜炎には、残念ながらすぐに痛みが消えるような「簡単な治し方」はありません。
しかし、ご自宅で簡単に実践でき、回復への近道となる効果的なセルフケアは存在します。
セルフケアの方法
- 足裏だけでなく、アキレス腱やふくらはぎをゆっくり伸ばす
- 運動後やズキズキ痛むときに、1回10〜20分を目安に冷やす
- クッション性の高い靴や、アーチを支えるインソールで足への負担を減らす
すぐに効果が出なくても地道に毎日続けることが重要です。
セルフケアで痛みが改善しない場合は、医療機関で適切な治療を受けることが推奨されます。
足底筋膜炎は歩かない方がいい?
歩行制限は、足底筋膜炎の重症度によって変わります。
痛みのレベルに応じて歩行を制限すべきか、慎重に動くべきかを判断する必要があります。
| 痛みのレベル | 歩行の目安 |
|---|---|
| 痛みが非常に強い(急性期) | ・無理に歩くのは避け、できるだけ安静を優先する ・歩行は炎症を悪化させる可能性がある |
| 症状が落ち着いてきた時期 |
全く動かないと血行不良や筋力低下につながるため、痛みが出ない範囲の短時間から歩行を再開 |
最終的には、医師や理学療法士と相談しながら、ご自身の症状に合わせて活動のレベルを調整することが大切です。
足底筋膜炎でやってはいけないことを守って早期回復を目指そう
足底筋膜炎の回復への第一歩は、「やってはいけないこと」を避け、足裏への負担を減らすことです。
回復まで時間がかかることもありますが、正しい知識を持って、専門家のアドバイスのもとで根気強くケアを続けることが重要です。
痛みが長引く場合は自己判断で放置せず、必ず整形外科などの医療機関に相談しましょう。
また、「足底筋膜炎を早く治したい」「手術を避けて治療したい」という方は、再生医療による治療も選択肢の一つです。
痛みを抑えるだけでなく、損傷した組織の修復を促すことで症状の根本的な改善が期待できます。
以下の動画では、実際に当院リペアセルクリニックで再生医療を受け、足底筋膜炎(足底腱膜炎)の症状が改善された患者さまの症例を紹介しています。
再生医療による治療について詳しく知りたい方は、ぜひ当院リペアセルクリニックまでご相談ください。

監修者
坂本 貞範
Sadanori Sakamoto
医療法人美喜有会 理事長
「できなくなったことを、再びできるように。」
人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの
お手伝いができれば幸甚の至りでございます。
略歴
1997年3月関西医科大学 医学部卒
1997年4月医師免許取得
1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務
1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務
1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務
1999年2月国立大阪南病院 勤務
2000年3月野上病院 勤務
2003年3月大野記念病院 勤務
2005年5月さかもとクリニック 開設
2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任
2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設
2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設